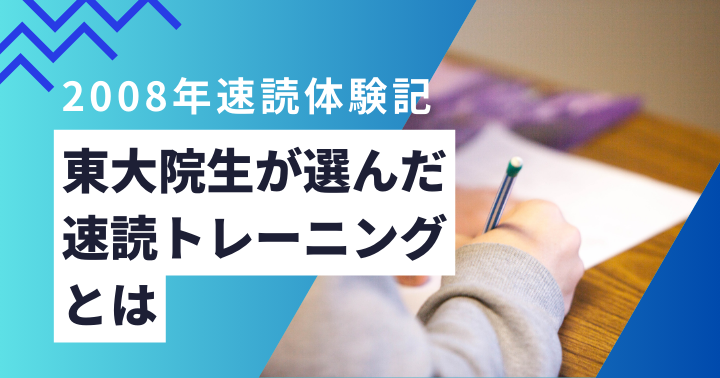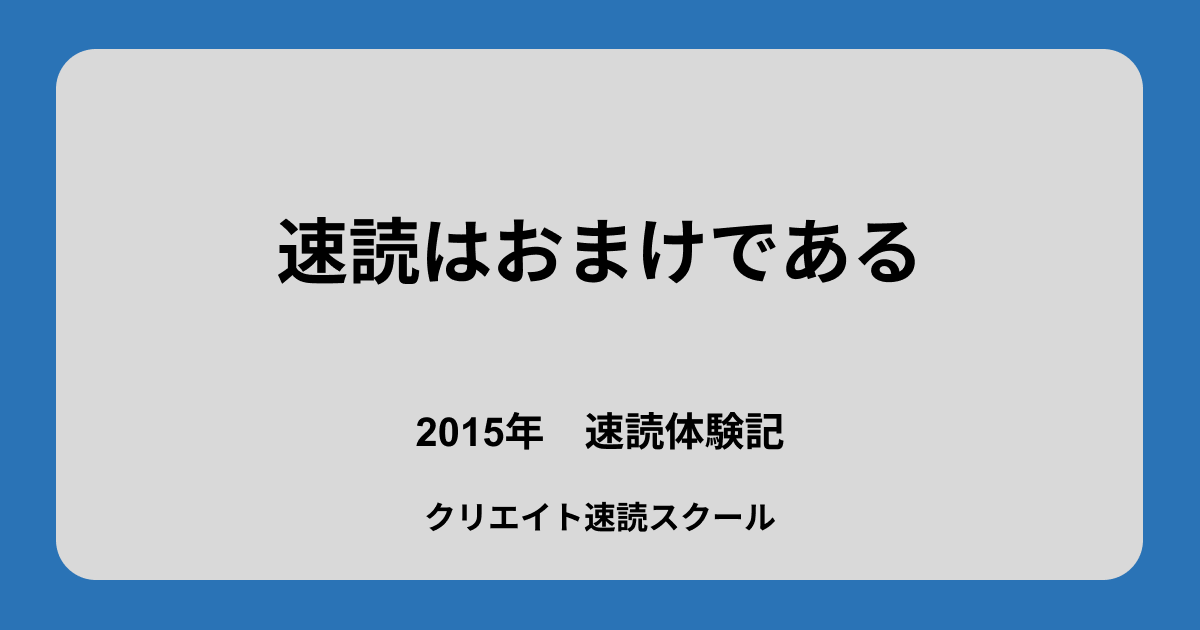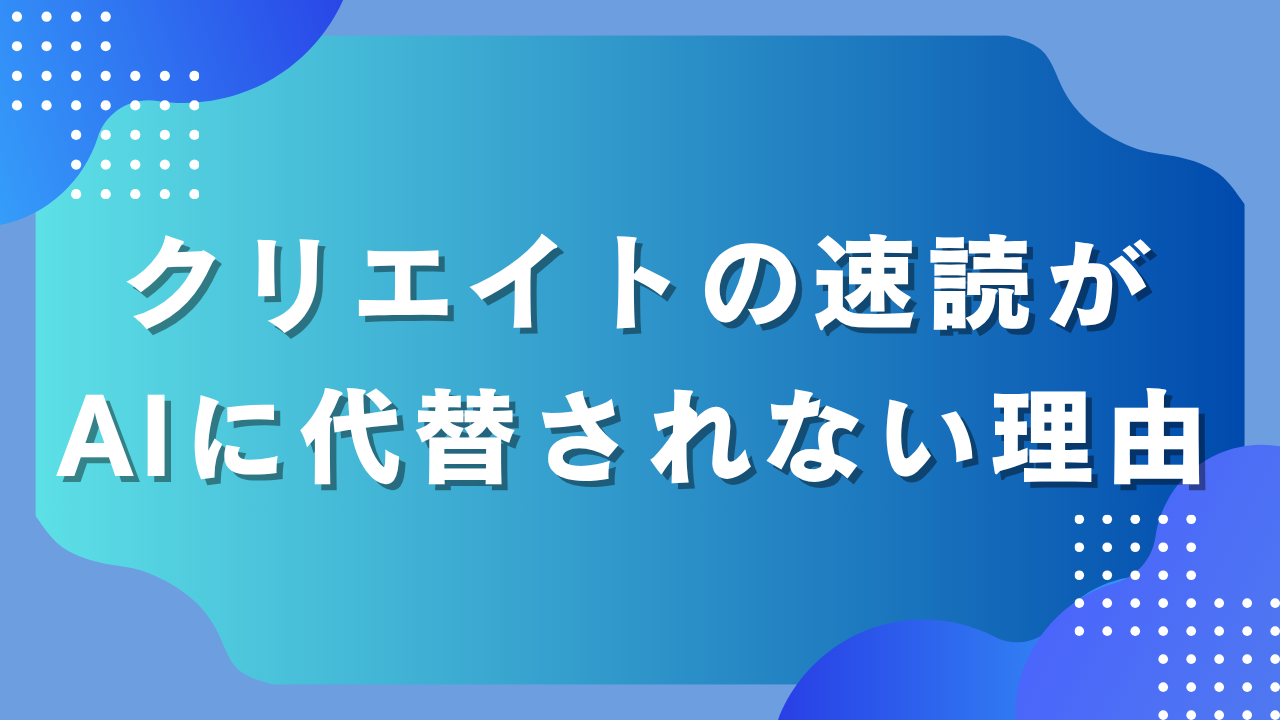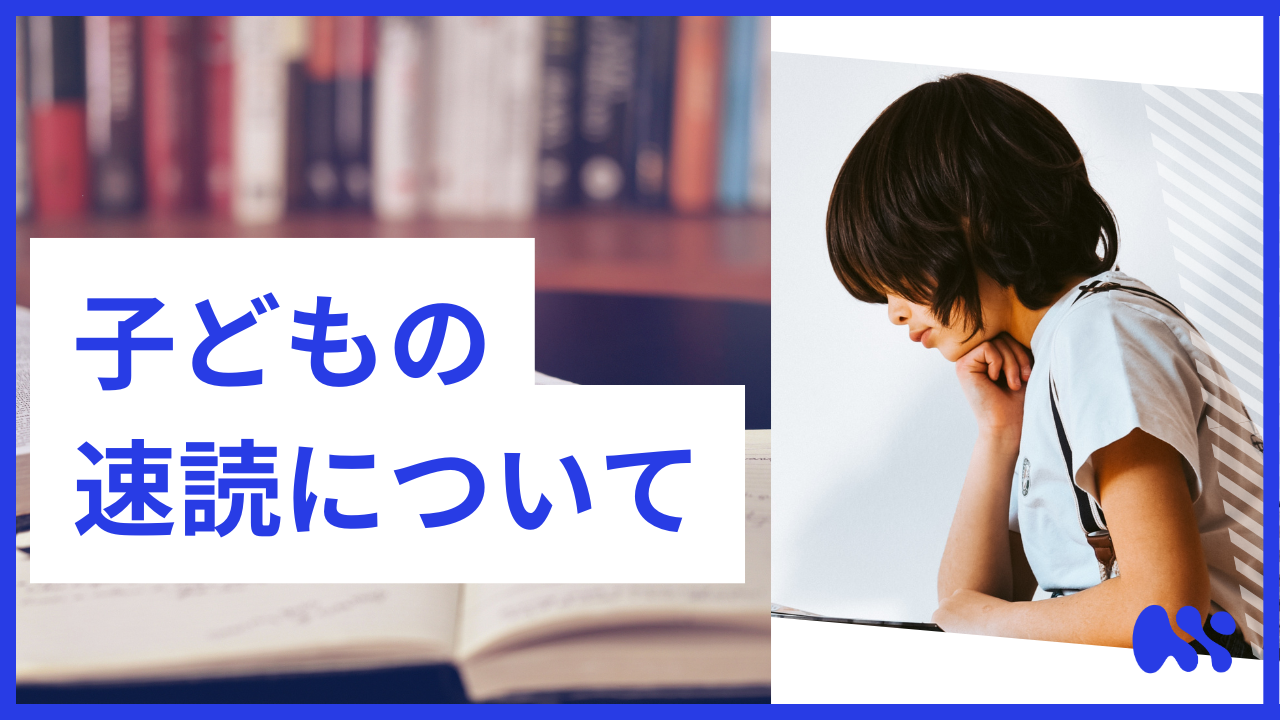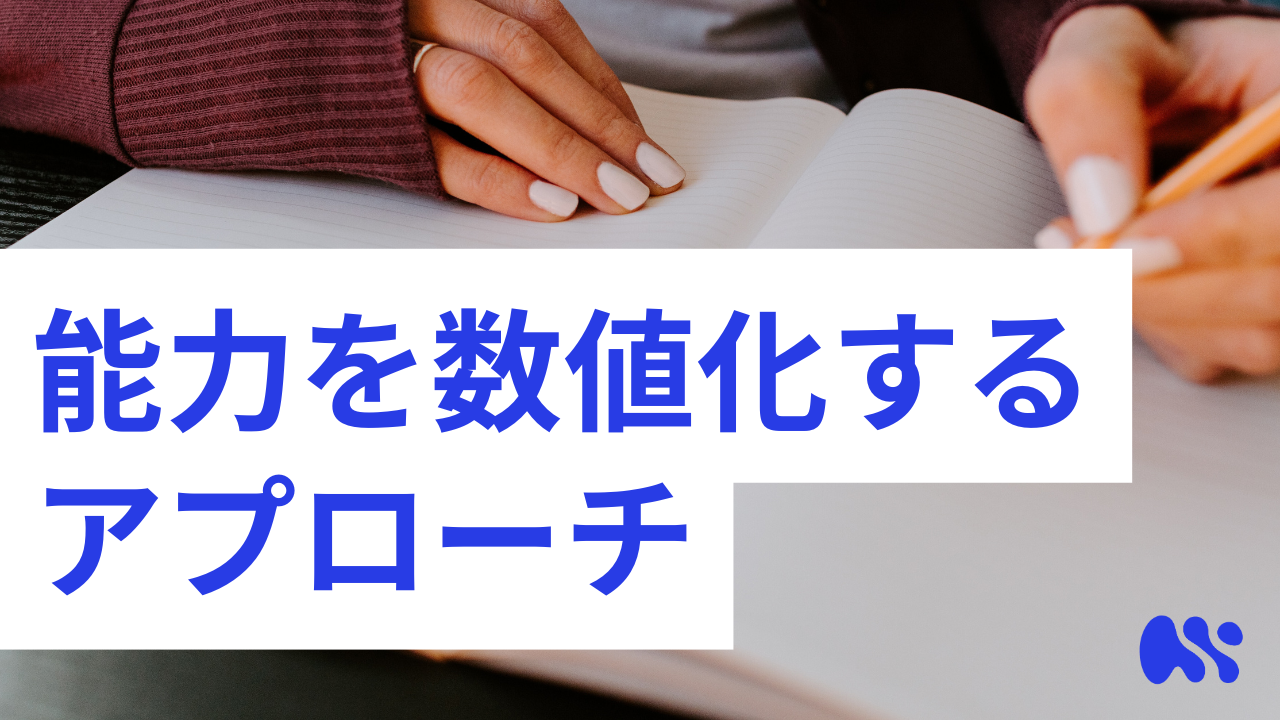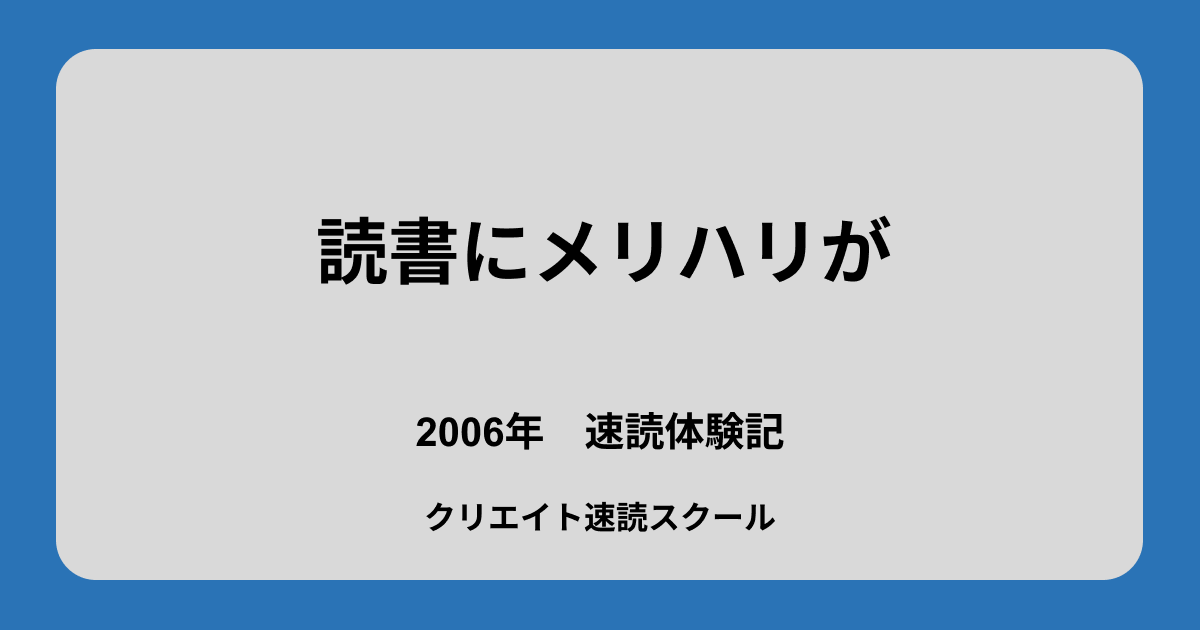
この記事は、高橋さんによる速読体験記です。
高橋 博明
速読教室に通う心がまえ
クリエイト速読スクールに通いはじめてから1年半になり、受講回数は90回を越えた。体験記の依頼を受けたのは2回目となる。
訓練の結果に一喜一憂していた最初の頃に比べると最近は落ち着いて受講できるようになった。40回目位までは訓練の結果が気になって仕方がなかった。個人差はあるのかもしれないが、90回となるとそう簡単に数値が上がらないとわかるので、今はあまり気にしていない。わりと順調に伸びてきた分だけ訓練も厳しくなっている。しかし、結果は気にしないが、目標の数値は決めて臨むようにしている。目標といっても前回より少しでも数値を越すように心掛けるだけ。たとえ下がったとしても気にならないので、気分的に余裕を持って受講できる。気がつくと少しずつではあるが、今でも着実に成果が表れている。
速読トレーニングの内容
1回の速読訓練90分は大きく3つに分けられる。序盤は視野を拡大する訓練、中盤は論理的思考力やイメージ力を高める訓練、終盤は読書訓練である。
序盤はシートを使った訓練が中心となる。シート訓練により、ページ全体が視界に入り、行単位で文章を捉えることができるようになる。訓練では大まかでもなるべく全体を意識することが大事である。ランダムシートやブロックパターンシートでは、文字の特徴をイメージしてページ全体を見るとイメージしている文字が浮かび上がるような感覚になる。文字によって難易度はあるが、私の場合は比較的見やすい漢字の「夏」やひらがなの「あ」でこの感覚をつかんだ。
中盤では、ペンをもって用紙に記入する訓練に入る。スピードチェックは前半で目の動きがスムーズになった後に行う訓練で、速さだけではなく正確に認識できているかどうかの確認になる。手で紙に記入しながら頭では次の問題に取り組み、同時に二つの作業を行う。資料から即座にキーワードを探し出す時や瞬時に概要を把握したい時などに役立っている。
中盤の訓練で後半につながる重要なものとしては、イメージ記憶訓練がある。これは時間内に全く関係のない二つの単語を関連づけ、記憶した単語を書き写す。単語のもつ様々なイメージを一瞬で引き出さなければならないため、感受性や好奇心の強い人が得意だと思う。行ごとに文章を読むと複数の単語が目に入ってくるので、これらを瞬間的にイメージで結びつける作業が必須となり、特に小説で情景やストーリーなどを頭に描きながら読むときに活きてくる訓練である。
終盤ではいよいよ読書の訓練に入り、読書スピードを上げるには欠かせない倍速読書訓練を行う。時々、同じ文演を受けた人たちや始めたばかりの受講生と速読の話をすることがある。訓練回数の浅い人たちはこの訓練を難しいと思っている人が割といて、他の訓練は伸びてきているが、なかなか読書スピードが上がらないといった話を耳にする。倍の速さで読むと内容を理解できなくなるので、そのことが不安になるという理由が多い。私の場合、訓練だと割り切り、内容の理解よりも、目標のページを決めて多少わからなくてもとにかく目を通すことにしている。現在の訓練時の読書スピードは理解度A―(理解はできるのだが、急いで読んでいるという感覚)で約20,000字/分であるので、倍速になると40,000字/分である。1秒間に約1ページ読んでいることになる。もちろん、内容は一部しか理解できなく、本によっては、ほとんど理解できないこともある。しかし、はじめて間もないころは倍速にして2,000字/分でも理解できなかったことを考えると、当初からは想像できなかった理解速度になってきている。
読書スピードを上げる感覚を実感する
たまたま教室で読んだ『上達の法則』(岡本浩一著、PHP新書P221)に下記のような記述がある。
水泳で最近用いられている練習法に、まずスピードの感覚だけ実感させるという方法がある。選手にロープをつけ、プールのコースにそって、クレーンで引っ張るような装置を作る。この装置を使って、その選手の目標タイムでまず引っ張るのである。そうして、自分が目標としているスピードで進んでいるときの水の抵抗の感覚など、さまざまなものを経験させるのである。 この訓練法の導入によって、水泳の訓練法は画期的に進んだということである。
まさに倍速読書訓練と同じ発想の訓練方法である。最大限の負荷をかけ、速読でいう倍速を体感することは重要なトレーニングである。ただ、速読において難しいところは、最も負荷をかけるべきところであるが、自分でブレーキをかけてスピードを調整できてしまうことである。私も日によって集中力の差があり、反省すべきところである。
文演を受けることで文章も鍛えられた
30回を過ぎた頃に文章演習講座(文演)を受講した。速読とは違い文章を何度も熟読し、筆者の意図を読み取ることを訓練する。初めのうちはどうしても自分の主観を入れて都合のいいように解釈をしていたのだが、文演が終わる頃には、論理的に文章を構成するための基本を身につけることができるようになった。しかし、受講するとわかるのだが、文章のみで自分の考えを的確に伝えることがいかに難しいか、また、文章を残す責任がいかに大きいかを身にしみて感じるようになった。読書だと一瞬で読まれてしまうのに、いざ自分が書こうとすると初めの一文を書くのになかなか手がつけられない。こういう感覚を今まで感じたことはなかった。
速読と文演を通して読書に緩急、メリハリをつけられるようになった。スピードを上げられる箇所、熟読を要する箇所を意識し、ただ漠然と読むだけということはしなくなった。今は高い理解度を維持しながら、いかに速度を上げていくかが課題である。
読書スピードを上げることは十分に達成できた
入会当初の目的であった、読書の方法を身につけてコンプレックスをなくすこと、読書スピードを3倍程度まで上げることは20回位で十分に達成できた。今までいかに本を読んでいなかったということかもしれないのだが、この1年半で読んだ本の数は生涯で読んだ数を軽く越えている。
いつまで続けていくのか。今までの訓練で身につけた技術、感覚はそう簡単には低下しないことはわかった。私の場合、通う目的ははっきりしている。もっと速く読めるようになることである。今はできるだけたくさんの本を読み、読書を通じて様々な作家の考え、価値観に触れたい。時間があればもっと読むことができるのだが、現在は余裕を持って読書する時間がほとんどない。限られた時間でいかに効率的に読むことができるか。そのためには、もっと速く読めるようになるほかない。この気持ちで今後もクリエイトを続けていくつもりである。それは、スポーツクラブで地道に基礎トレーニングを積むのと同じだと考えれば納得してもらいやすいかもしれない。