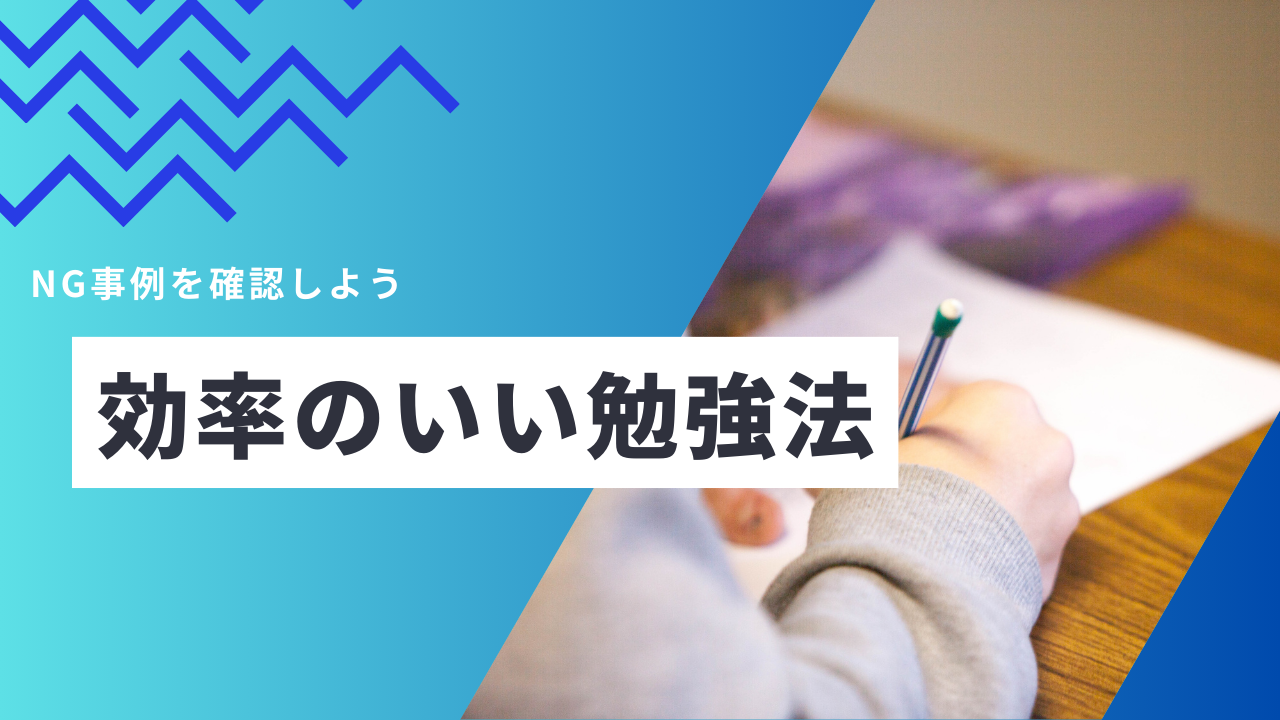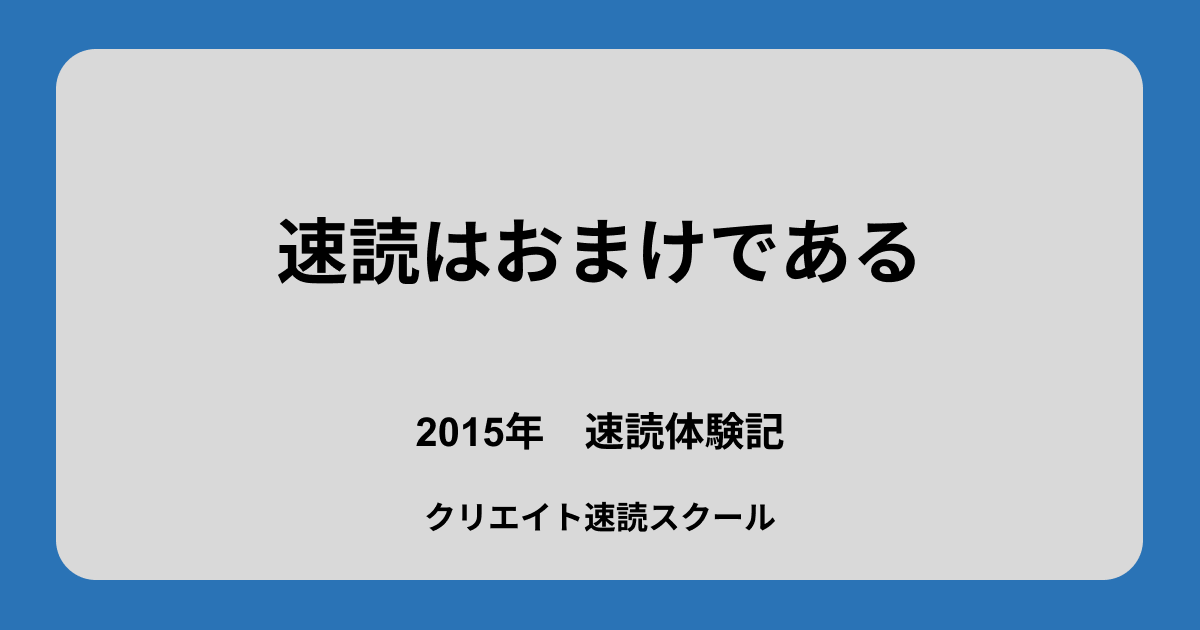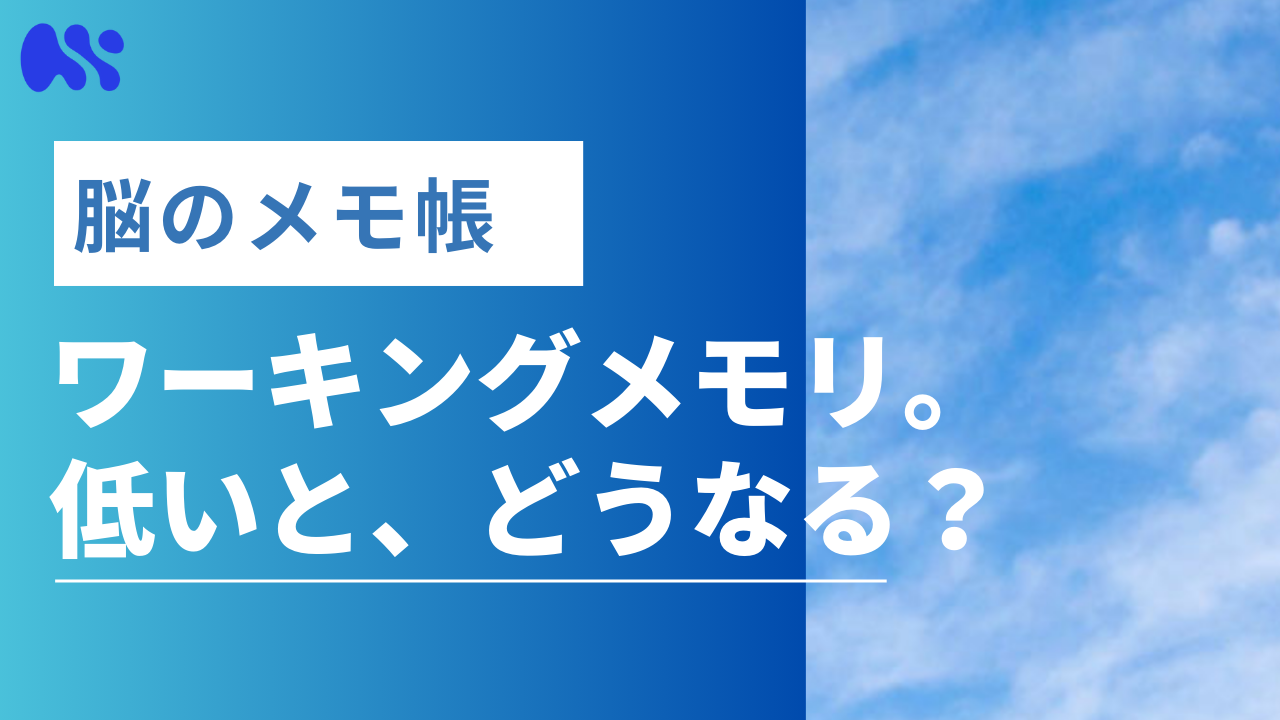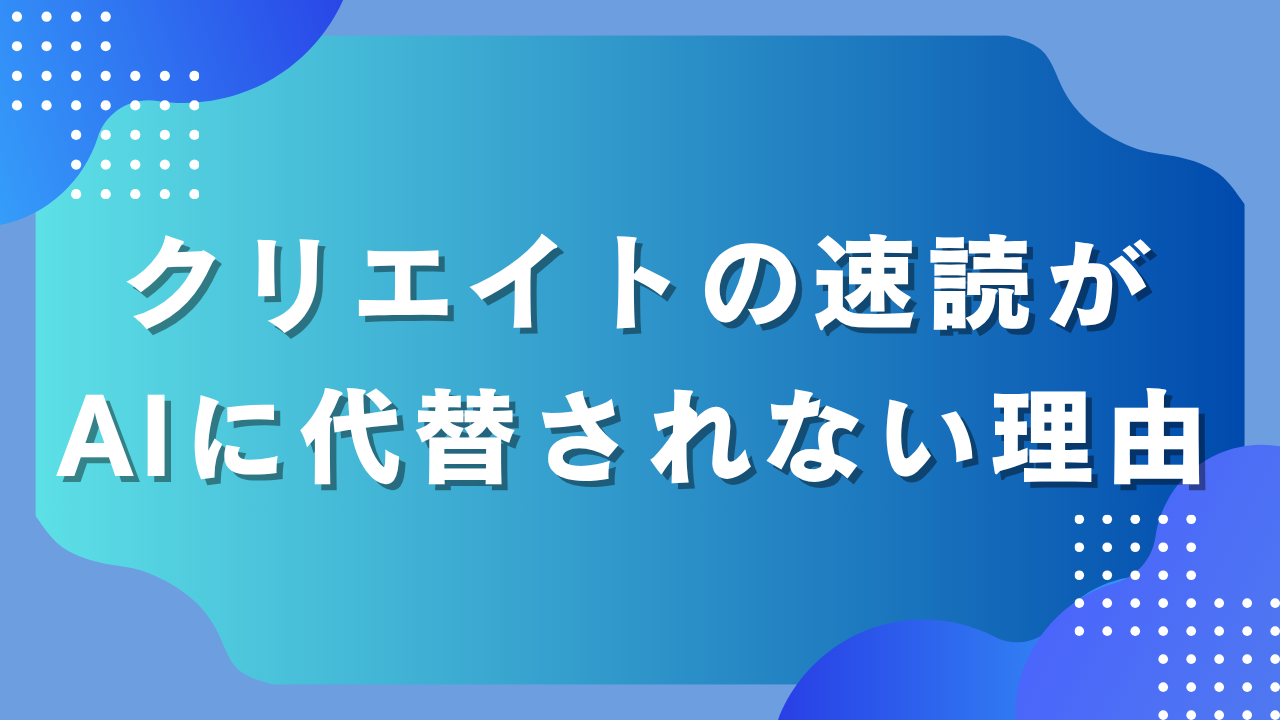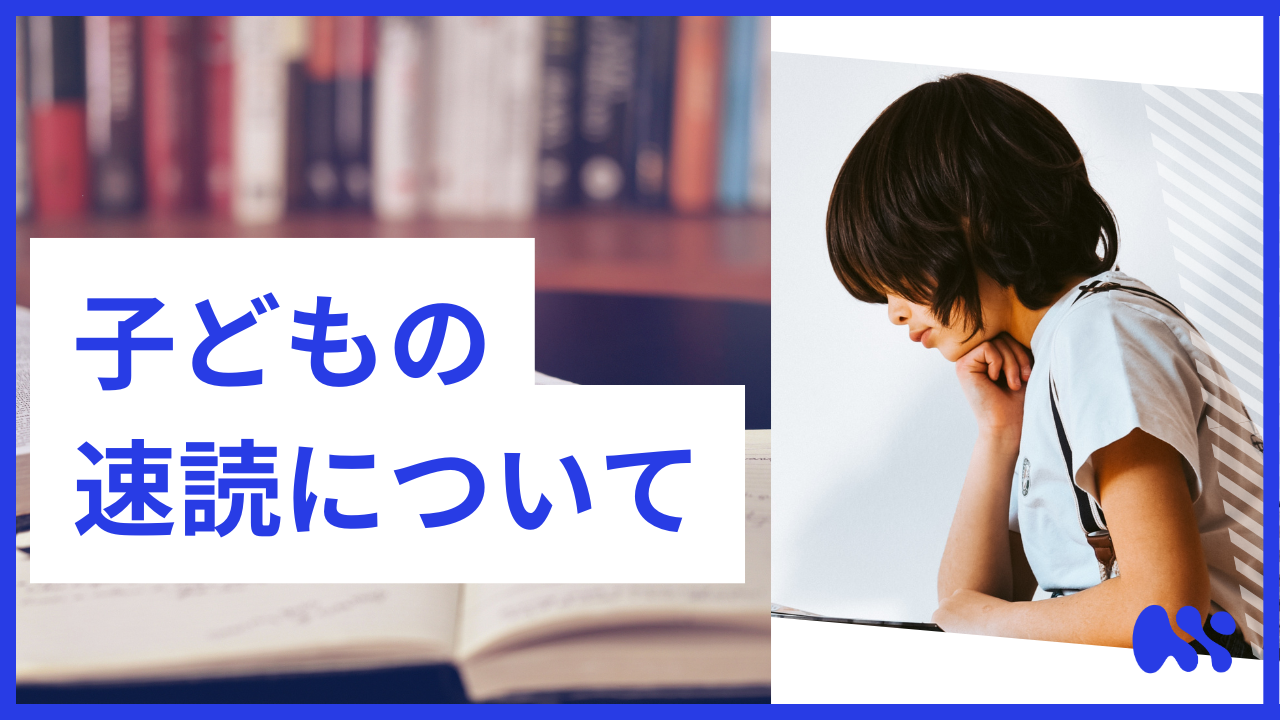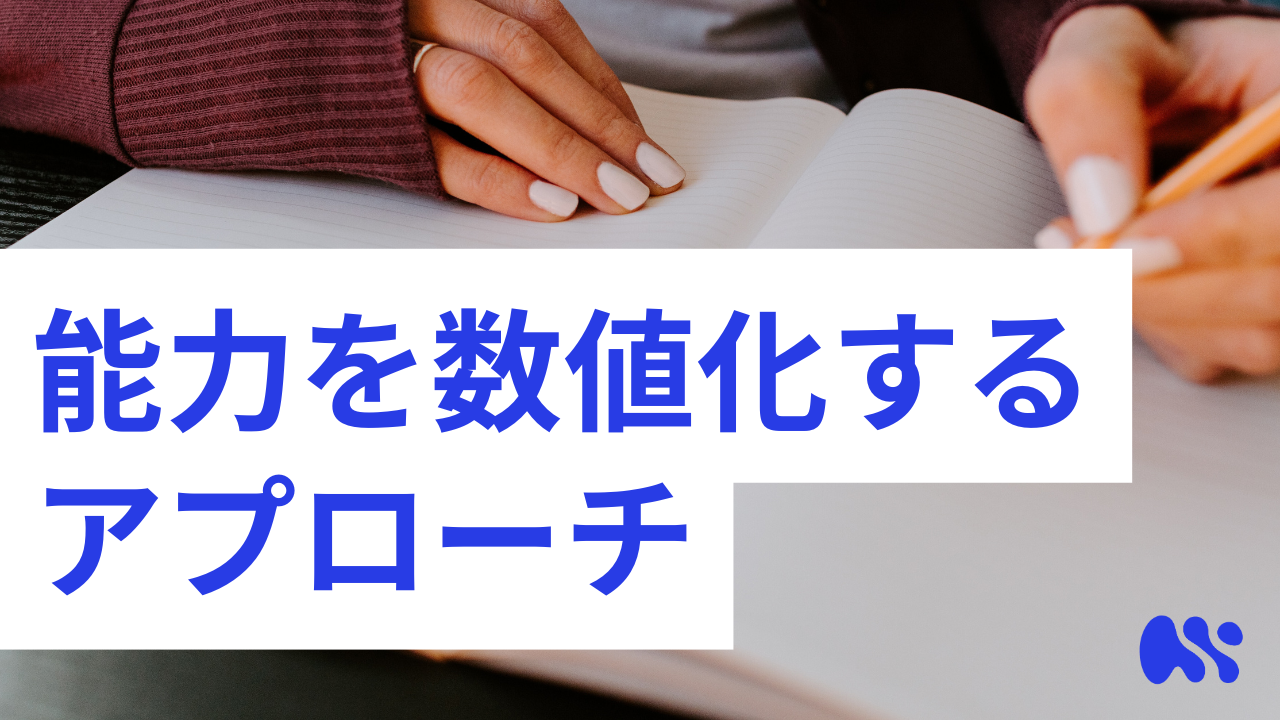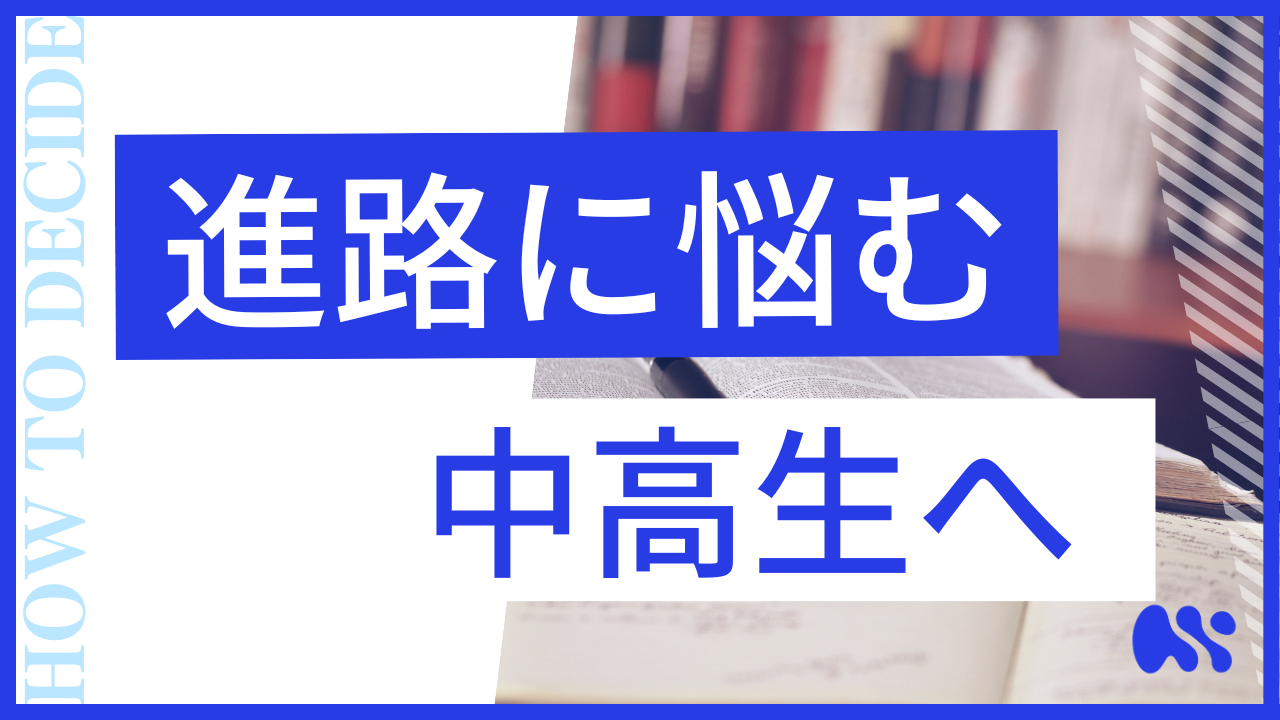
目次
意思決定とは
意思決定は、意思と決定、2つの要素から成り立ちます。
デジタル大辞泉
2つの単語の定義から考えると、意思決定とは「自分の心持ちに基づいて、物事を決めること」といえます。
意思決定の重要性
自ら意思決定ができないと、他人の意思決定に従わざるを得ません。
結果、自分にとって不利な状況になったとしても、状況を打開することが難しくなります。
たとえば、親の言いなりで、ある会社に就職したものの、入社後に合わない環境だとわかった場合を考えてみましょう。
自分の意思に基づいて判断し、状況を変える決断をしない限り、その状況から抜け出すことはできません。
意思決定と判断軸
意思決定には、判断軸が必要
周りに流されることなく、自ら意思決定をするには、判断軸が必要です。
判断軸なくして、意思決定は成り立ちません。
たとえば、
- したいこと/したくないことは何か
- 大切にしていることは何か
- 向き不向きは何か
といった判断軸に基づいて、意思決定は行われています。
判断軸は、意思決定を通じて明確になる
一方で、判断軸は、意思決定の数を重ねることで明確になるものです。
たとえば、「どのような仕事がしたいのかわからない」といった悩みは、アルバイト経験などを通じて自分の向き不向きを知ることで、解決することがあります。
一つひとつの意思決定を、あとに続く意思決定の参考として重ねていくことで、判断軸は明確になるのです。
意思決定能力の二極化を招く構造的問題
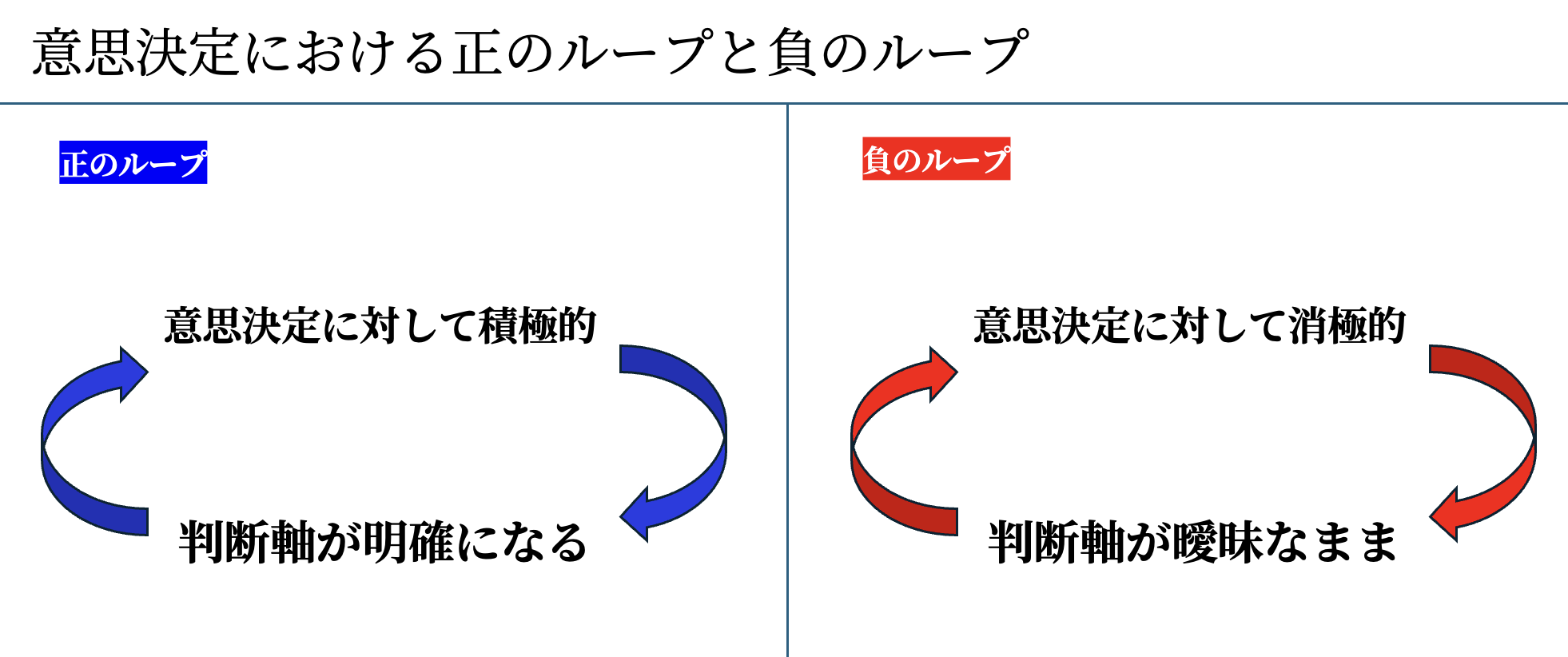
- 意思決定には判断軸が必要だが
- 判断軸は、意思決定を通じて明確になる
これらの事実が、「意思決定をする人ほど、意思決定に積極的になり、意思決定を避ける人ほど、意思決定に消極的になる」というループ構造を産んでいます。
では、負のループから抜け出すには、どうしたら良いのでしょうか。
意思決定の場としての日常
ひとたびきっかけを掴み、正のループにのることさえできれば、意思決定能力は自然と鍛えられていきます。
負のループから抜け出すきっかけ作りとして、オススメしたいのが「日常を活用すること」です。
日常は意思決定の連続です。日々直面する意思決定の機会に、敏感になってみましょう。
大きな問題を前にしたときの意思決定だけが、判断軸を形づくるわけではありません。
たとえ小さな意思決定であっても、数をこなすことで、判断軸は鍛えられます。
「小さな意思決定を通して経験を積むことで、大きな意思決定にも対処できるようになる」というのが、無理のない順序ではないでしょうか。
日常における意思決定の具体例
少し見方を変えてみると、「何を買うか」「何を食べるか」といった些細な事柄も、意思決定と捉えることができます。
広告の言いなりになるのではなく、「なぜこれなのか」「メリットは何か」「他との違いは何か」と、頭の体操をしてみましょう。
たとえ最終的な選択に違いがなくとも、意思決定のプロセスに自覚的になることが、判断軸の形成につながります。
中高生にとっての大きな意思決定
中高生が直面する大きな意思決定として、文理選択や志望校の選択など、進路に関わる問題があります。
「先のことなんかわからない」「どう考えればいいのかわからない」というのが本音だと思います。
結果、「数学が嫌いだから文系」「友達が目指しているから◯◯大学」と、受け身の選択を取ってしまいがちです。
中高生に大切にしてもらいたいこと
進路を決めるにあたり、「最終的にどんな選択をしたか」に意味はありません。
自分の選んだ道が正解になります。
大切なのは、真剣に悩むことです。
自分が大きな意思決定に直面していることを自覚し、誰よりも悩んでみてください。
自分の判断軸を形成する、決定的な機会になるはずです。
『武器としての決断思考』
意思決定には、正解がありません。
だからこそ、自分は何をもって解とするのか、その手法を確立する必要があります。
『武器としての決断思考』は、ディベートで用いられる考え方をもとに、意思決定のプロセスに光を当てる一冊です。
- なぜこれからの時代に意思決定が必要なのか
- 意思決定に必要な情報の集め方
- 与えられた情報を疑うことの重要さ
意思決定に活用できる、実践知が詰まった一冊です。ぜひご一読ください。
参考:瀧本 哲史, 2011年9月, 星海社新書, 『武器としての決断思考』
著者の瀧本哲史氏について知りたい方は、下記の記事をご覧ください。
参考:瀧本哲史さんインタビュー 2005 「投資リターンは、非常に高かった」大学3年の瀧本哲史さんが80回池袋に通った理由とその効果
この記事のタグ
劉 智秀 1999年東京都生まれ/栄東中学・高等学校/東京大学経済学部卒/クリエイト速読スクール二代目代表