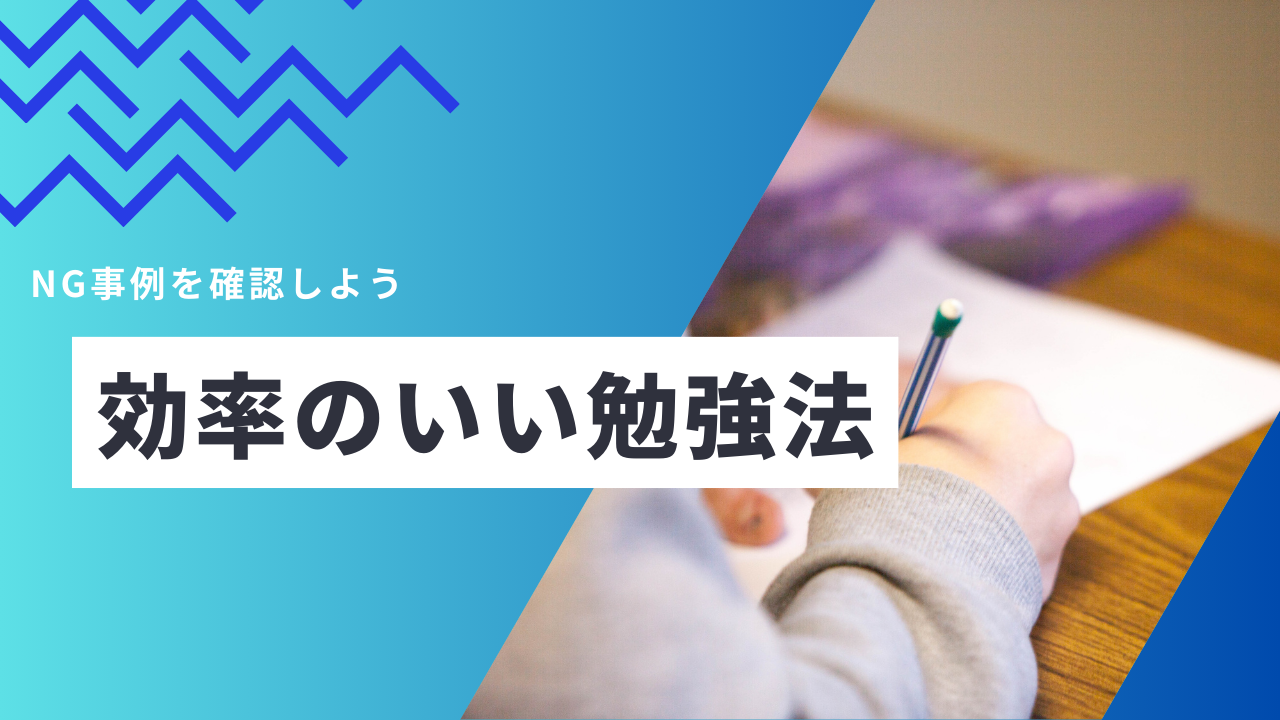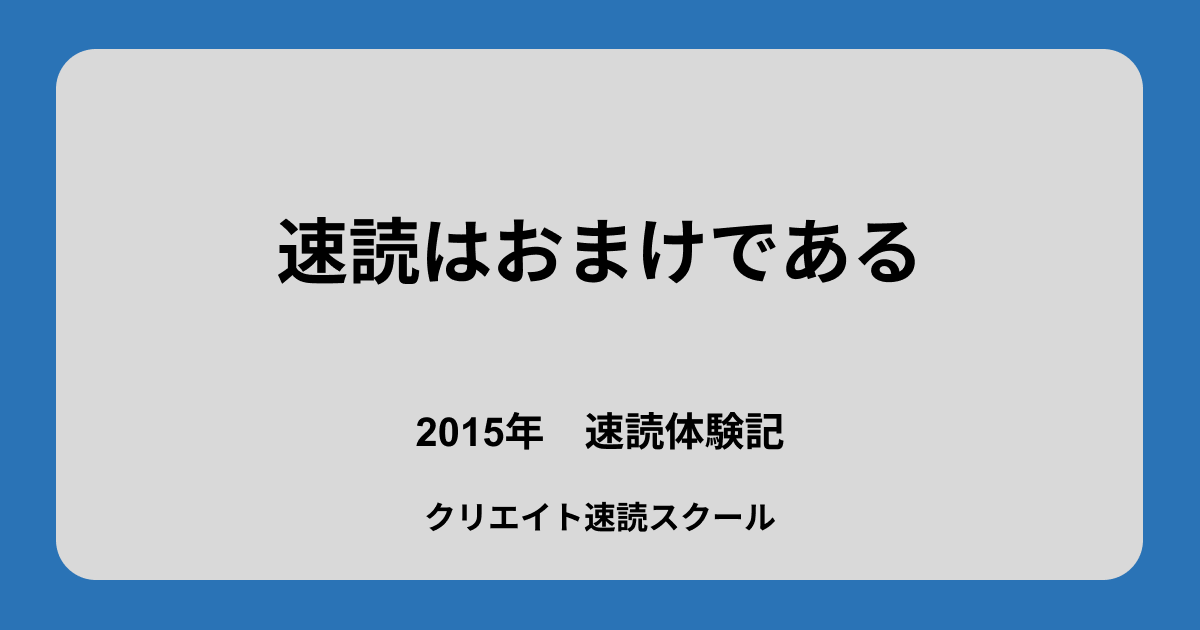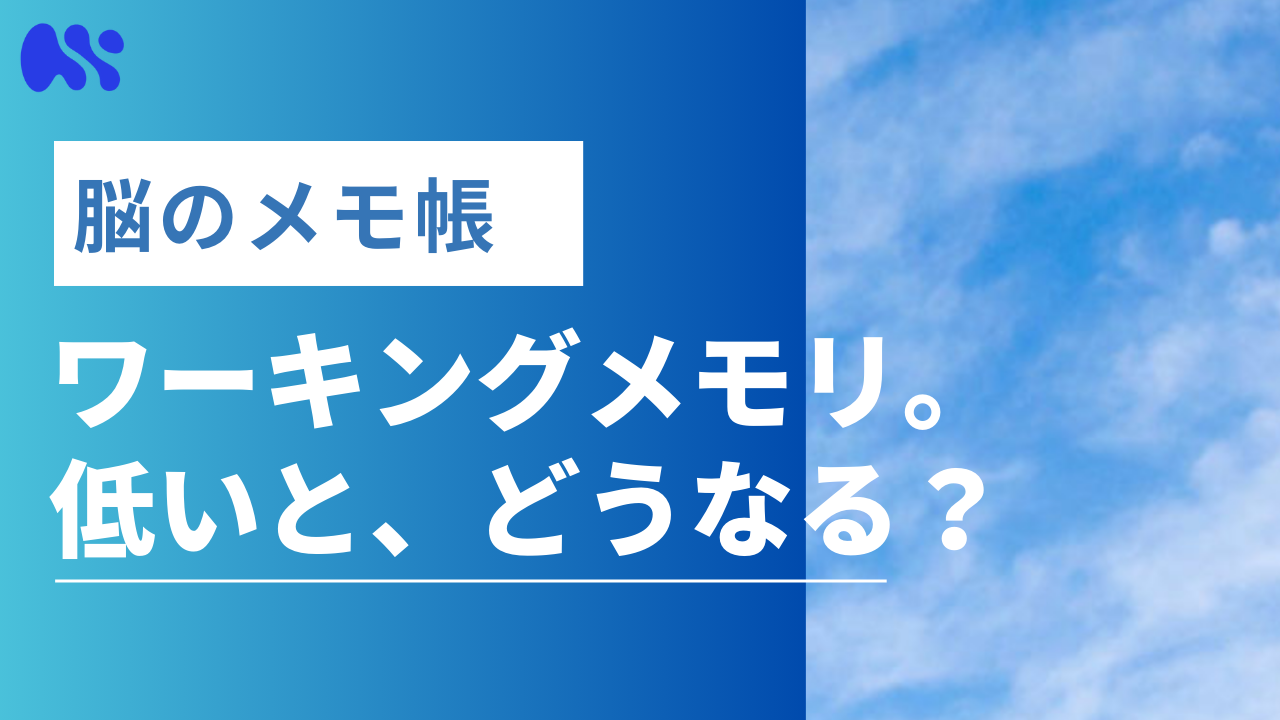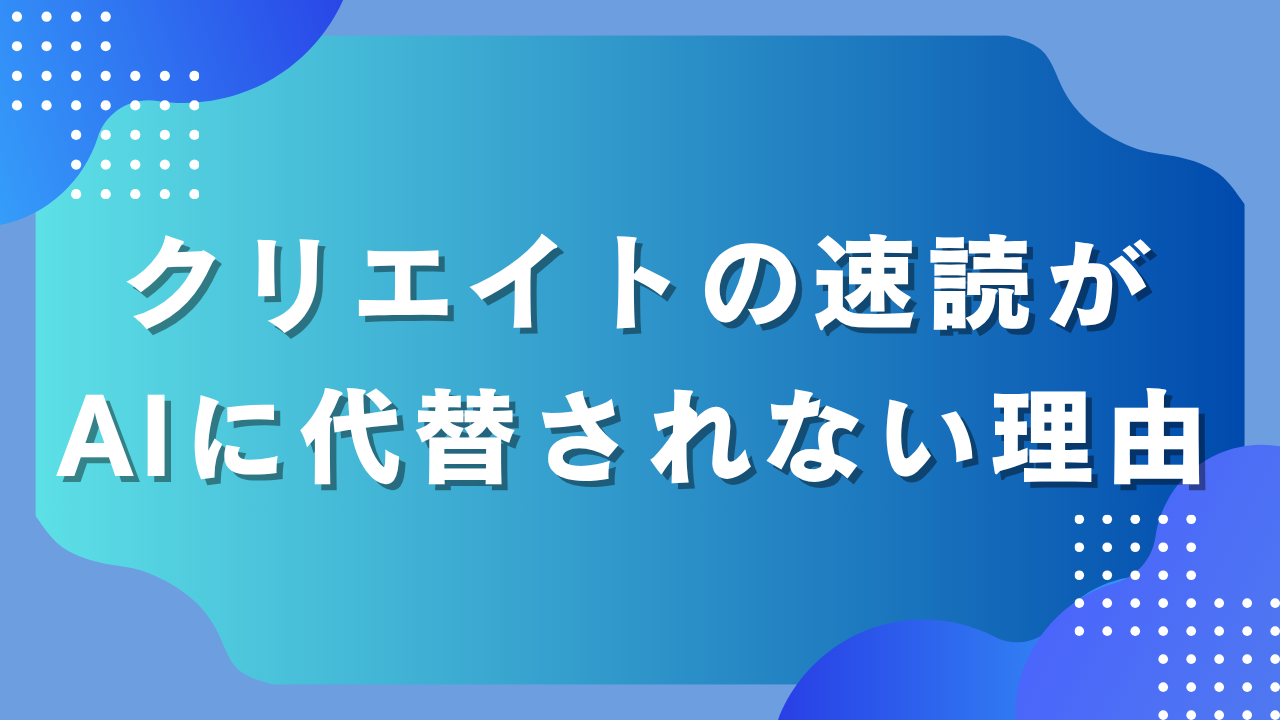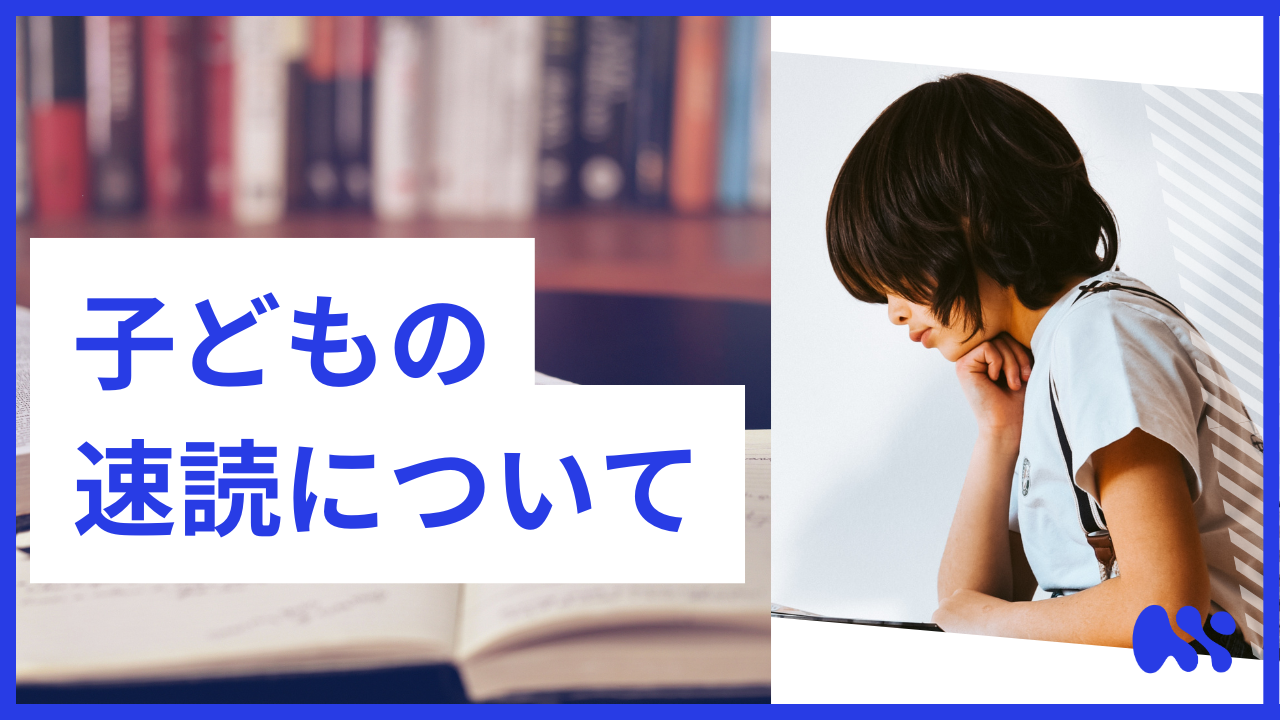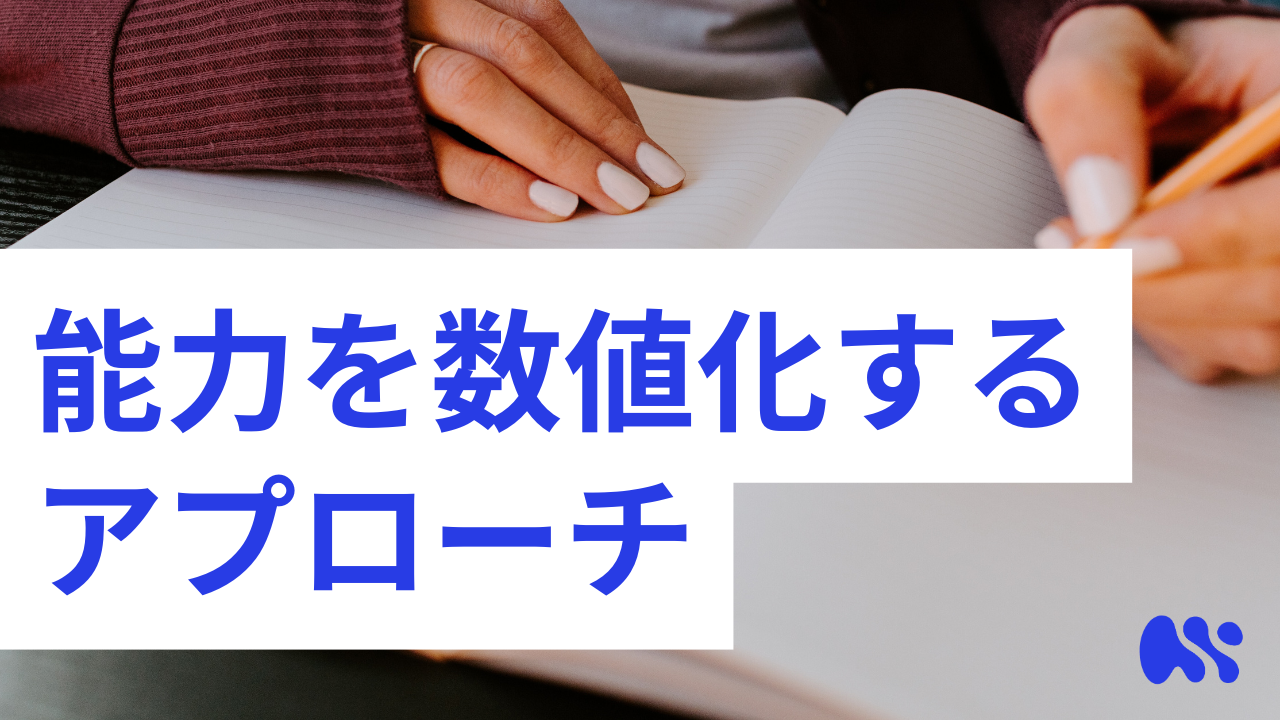目次
この記事では、読解力の定義・必要性・鍛える方法・お薦め書籍などをご紹介しています。
読解力とは
読解力とはどのような能力か。辞書では以下のように定義されています。
デジタル大辞泉
またOECD加盟国を対象にした国際学習到達度調査(PISA)では、以下のように定義されています。
(国立政策研究所 ホームページよりご紹介。2024年1月7日閲覧)
読解力がないとどうなる
誤解の元となる
読解力がないと、文章の意味を正しく把握することができず、誤解を生んでしまうことがあります。
たとえば、契約書の利用条件や解約条件を誤解したまま署名することで、不利な契約を結んでしまうことが考えられます。
学習効率の低下
読解力が乏しいと、文章の理解に時間がかかります。
学習の基本は読むことにあるため、文章の理解に時間がかかることは、学習効率の低下に直結します。
情報源が制限される
読解力が低いと、文章を理解するのに多くの時間と労力が必要になります。その結果、文章から情報を得ることに苦痛を感じ、動画や音声といったメディアに頼りがちになります。
複雑な知識や専門的な情報は、依然として文章で提供されることが多く、こうした習慣は知識の偏りを招きかねません。
読解力を鍛える方法
ここからは、読解力を鍛えるのに効果的な方法を、書籍から引用しご紹介します。
論理展開を意識する
文章を理解するには、論理展開を意識することが重要です。文章の主張、根拠、結論を正確に把握することで、内容を正しく理解できます。
具体的な方法論については、『大人に必要な読解力が正しく身に付く本』をご参照ください。
多読
多様なジャンルの本を読み、さまざまな考えに触れることは、読解力の向上に役立ちます。
『未来を生きるための読解力の強化書』では、特に古典文学を読むことと読解力の関係性について解説されています。
要約の練習
読んだ内容を自分の言葉で要約する練習は、重要なポイントを把握し、理解を深めるのに役立ちます。
『大人の読解力を鍛える』では、具体的な要約の方法について学べます。
読解力を鍛えるお薦めの本
『大人の読解力を鍛える』
読解力は文章理解のみならず、日々のコミュニケーションにおいても必要不可欠です。
日常での会話やプライベートなメール、SNSでのやり取りでは、簡潔な表現が多くなりがちです。その分、発言の真意を見失いやすく、誤解を招くリスクがあります。
『大人の読解力を鍛える』では、読解力不足が原因となって生じるトラブルを防ぐためのトレーニングが数多く紹介されています。
映画や歌の鑑賞を通じて読解力を鍛えるユニークな方法や、扇動的なニュースに惑わされないための方法など、実践的なトレーニングが解説されています。
日常のコミュニケーションを円滑にするためのガイドとして、ぜひご活用ください。
参考:齋藤孝, 2019年9月, 幻冬舎,『大人の読解力を鍛える』
『大人に必要な読解力が正しく身につく本』
書かれている内容を正確に理解する力は、無駄な処理プロセスを省き、効率的な情報収集を可能とします。
長年、大学受験生向けに国語を教えてきた著者による本書は、文章内容を速く正確に理解するための基本を、豊富な例題を交えて解説しています。
練習問題のテーマは多岐にわたり、接続語の使い方や論理展開など、文章を書く際にも役立つ内容になっています。
資料を読み込んでの報告書やプレゼンテーションの作成など、さまざまなビジネスシーンで役立つ一冊です。
参考:吉田裕子, 2022年5月, 大和書房, 『大人に必要な読解力が正しく身につく本』
『わかったつもり 読解力がつかない本当の原因』
なぜ文章を読み違えてしまうのか。答えの一つに「スキーマ」があります。
スキーマとは、心理学の専門用語で「経験をもとに構成された外界を理解するための枠組」のことをいいます。
サリーがアイロンをかけたので、シャツはきれいになった。
この一文だけを読んで、サリーの性格を断定することはできません。しかし、過去の経験に基づいて、サリーが几帳面な性格であると推測することには、一定の妥当性があります。
本書では、心理学の観点から、スキーマを無意識に当てはめることで文章を誤読し、「わかったつもり」に陥るプロセスを、豊富な例題を用いて解説しています。
参考:西村克彦, 2005年9月, 光文社, 『わかったつもり 読解力がつかない本当の原因』
『未来を生きるための読解力の強化書』
読解力は自分の考えを相対化するうえでも役立ちます。
読解力があれば、文章の中に含まれる偏見や誤った情報を見抜き、より客観的に情報を抽出することができます。
客観的な視点から情報を整理することで、多様な視点を把握し、自分自身の考えを相対化することが可能です。
このような観点のもと、本書が推奨しているのが、古典文学の読破です。
古典文学には、品行方正な人物だけではなく、悪人も多く登場します。文学作品を通して、多様な考えに触れることで自分とは異なる視点を受け入れられます。
本書には『塩狩峠』を題材とし、中学生を対象にした特別講義の章があります。この章では、作品に込められた意図を読み解く方法や、読者の視点で自由に読み解く方法が解説されています。
文学作品を読むことの大切さを深く理解できる一冊です。
参考:佐藤優, 2021年9月, クロスメディア・パブリッシング, 『未来を生きるための読解力の強化書』
この記事のタグ
劉 智秀 1999年東京都生まれ/栄東中学・高等学校/東京大学経済学部卒/クリエイト速読スクール二代目代表