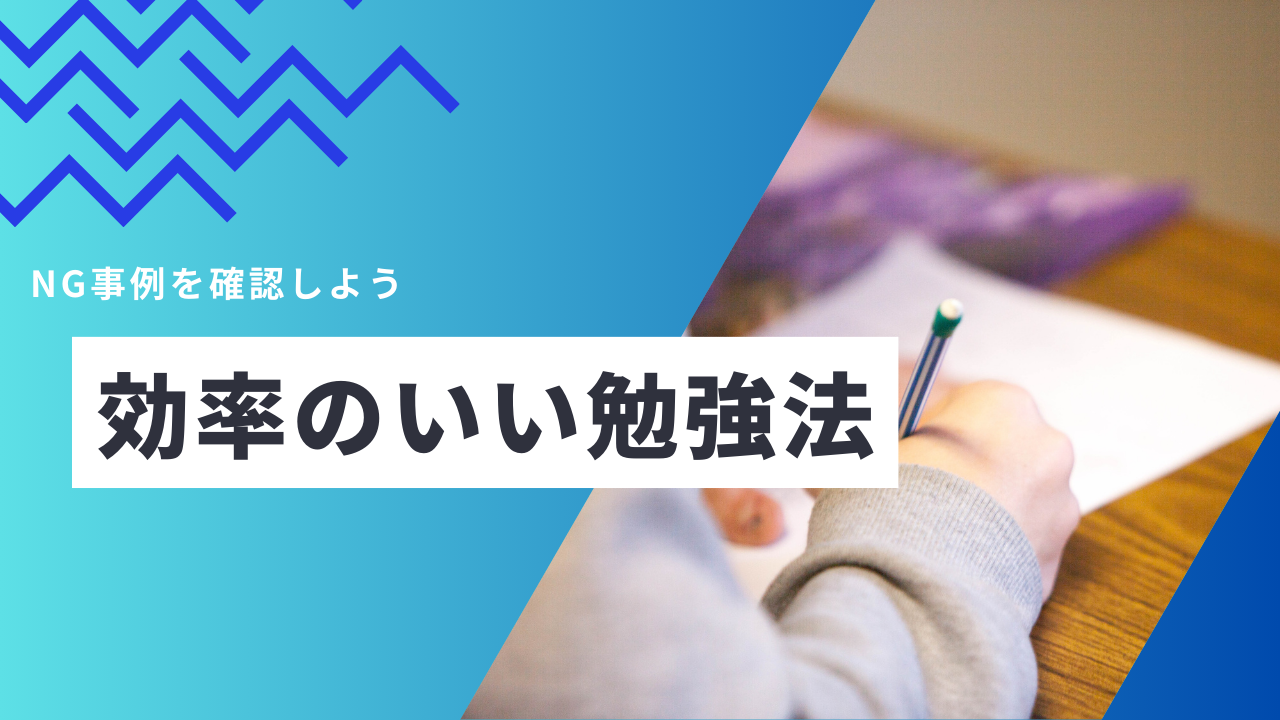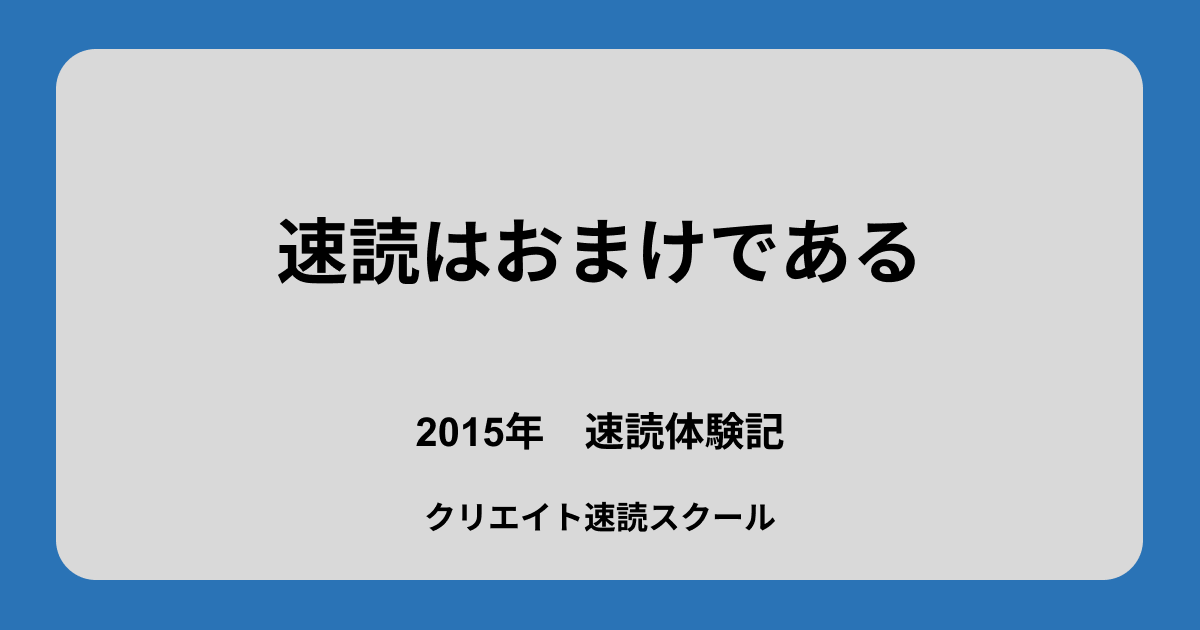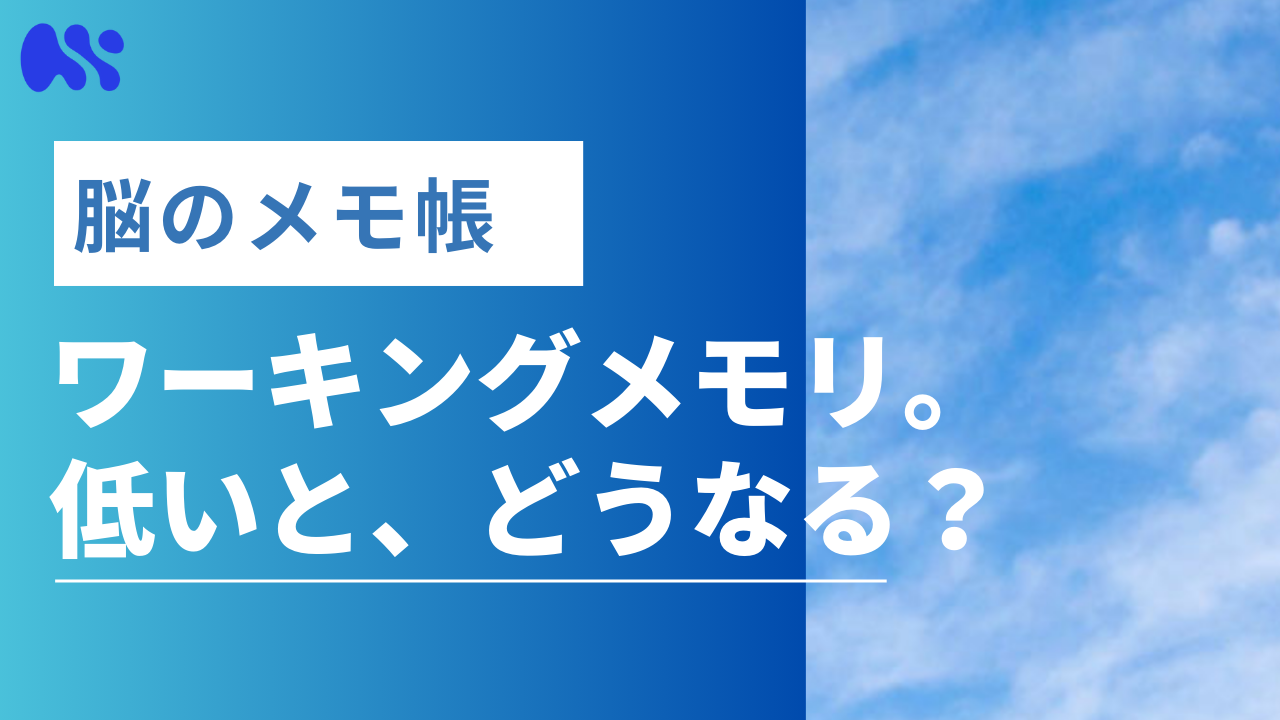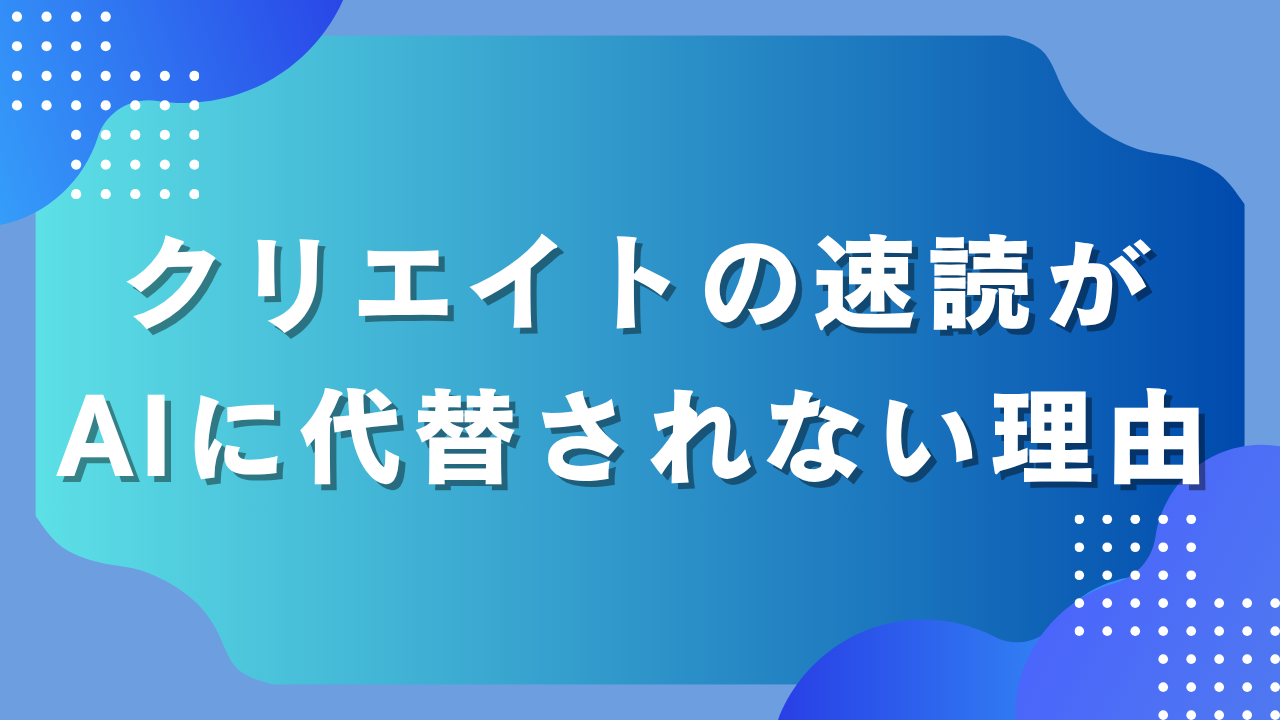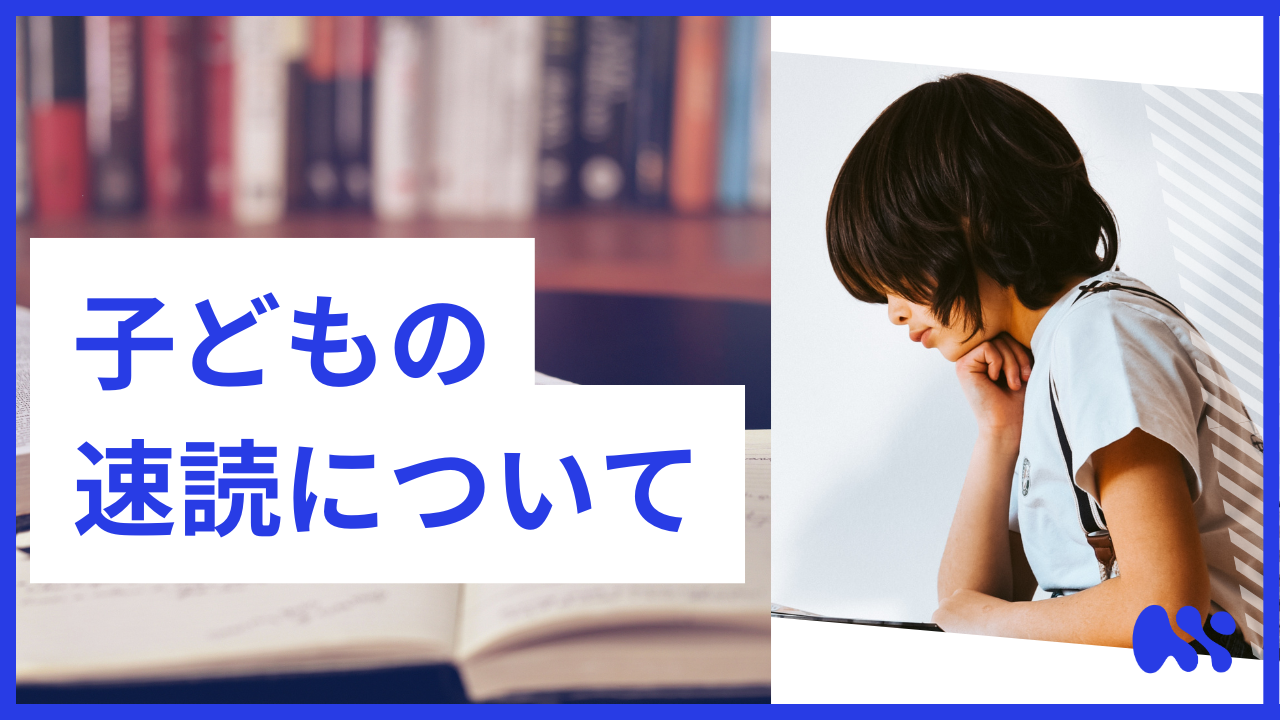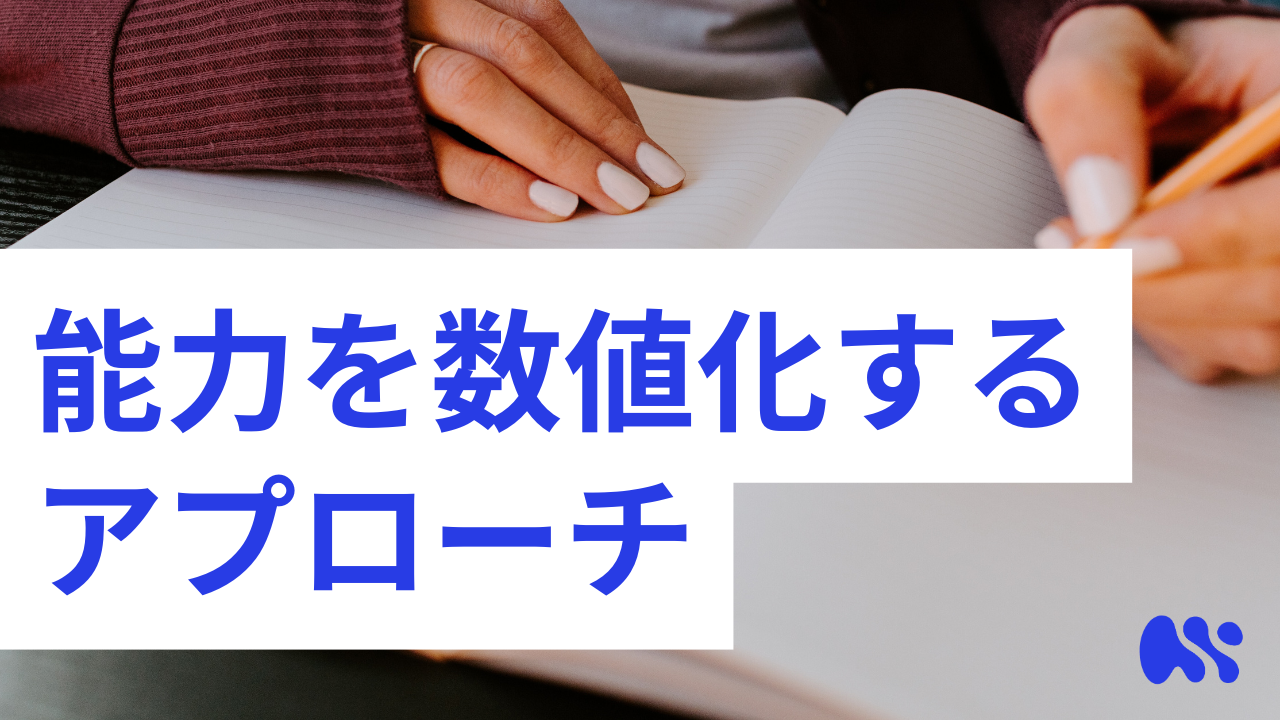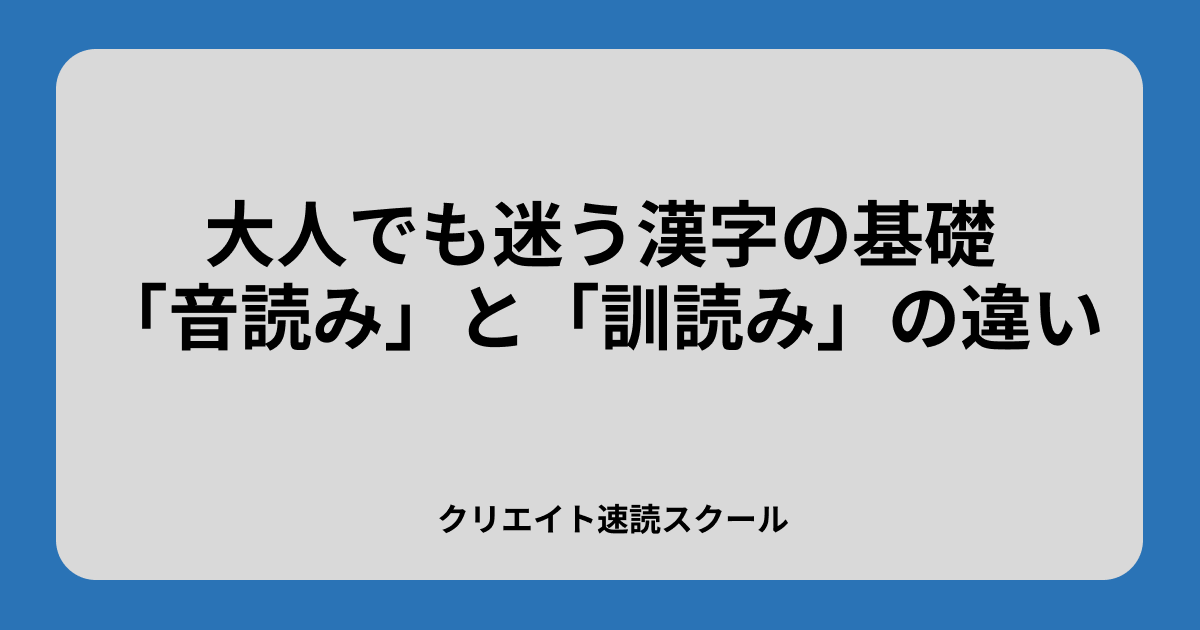
目次
日本の漢字には、「音読み」と「訓読み」という2つの異なる読み方が存在します。
大人の方でも2つの違いに混乱することが多く、漢字学習において、躓きやすいポイントとなっています。
この記事では、音読みと訓読みの違いや、見分け方についてご紹介します。
記事の後半には、見分け方を実践するための演習問題もご用意しています。
音読みと訓読み
音読みとは
ブリタニカ国際大百科事典より
漢字は、中国から日本に伝わってきた文字です。
音読みは、それぞれの漢字の中国語の発音を、そのまま利用した読み方です。
訓読みとは
ブリタニカ国際大百科事典より
訓読みは、漢字が意味しているものに、日本語の発音を対応させた読み方です。
音読みと訓読みの違い
音読みの特徴
音読みは、中国語の発音を基にした読み方で、主に四字熟語、複合語(例:学校、図書館)で使われます。
一つの漢字には複数の音読みが存在することもあります。
音だけで意味を把握することが難しいのが特徴です。
訓読みの特徴
訓読みは、漢字に日本独自の言葉を対応させて読む方法です。
特に、漢字一字で意味が成立するときに使用され、音だけで意味を把握しやすいのが特徴です。
違いを具体例で確認
たとえば、「山」の音読みは「サン」となります。
この「サン」という読み方だけでは、「山」が自然の山を指していることがわかりません。
訓読みでは「山」を「やま」と読みます。
この読み方は、漢字一字で日本語の意味を表現することが多く、発音だけで意味が把握できることが多いです。
音読みと訓読みの見分け方
①発音で意味がわかるかどうか
漢字の発音から意味を推測できるかどうか、で判断する方法です。
- 発音だけでは意味がわからない:音読み
- 発音だけで意味がわかる:訓読み
音読みは、漢字に中国語の発音をあてたものです。そのため、発音だけでは具体的な意味を把握しづらいのが特徴です。
訓読みは、漢字に日本語の意味を表す音をあてたものです。そのため、発音だけでも具体的な意味を把握しやすいのが特徴です。
たとえば「草」という漢字で考えてみましょう。
- 音読みの場合:ソウ
- 訓読みの場合:くさ
音読みの場合、「ソウ」と音だけ聞いても、何を指しているのかを特定できません。
訓読みの場合、迷うことなく、自然に生えている緑をイメージできます。
②送りがなが必要かどうか
漢字が送りがなを必要とするかどうか、で判断する方法です。
- 送りがなを必要としない:音読み
- 送りがなを必要とする:訓読み
送りがなとは、漢字で書いた語の読みを明らかにするために、漢字の下につけて表す仮名をさします。
日本語として意味がわかるように添えられている文字です。
そのため、送りがながついている漢字は、訓読みになることが多いです。
たとえば「走」という漢字で考えてみましょう。
- 「走(ソウ)」:音読み
- 「走る(はし・る)」:訓読み
訓読みの場合、送りがなの「る」がつくことで、日本語での意味が定まります。
なお、一部、送りがながついても訓読みにならない漢字があります。
「接する(セッ・する)」「屈する(クッ・する)」「生じる(ショウ・じる)」のように、「~する・~じる」の「~」部分は音読みになります。注意しましょう。
③読み方の文字数に着目する
読み方の文字数に着目する方法です。
- 読み方が3字以下:音読み
- 読み方が4字以上:訓読み
これは音読みが全て3文字以下であることを利用した方法です。
読み方が4字以上の漢字には「志(こころざし)」「公(おおやけ)」「私(わたくし)」などがあります。
これらの読み方は、すべて訓読みになります。
④2拍の読み方に着目する(難)
日本語の言葉は「拍」という単位で構成されます。
「拍」とは、言葉を読む際に一つの音として発音される単位を指します。
たとえば、「さくらんぼ」は「さ・く・ら・ん・ぼ」の5拍から成り立ち「今日」は「きょ・う」の2拍から成り立ちます。
特に2拍の読み方を持つ漢字は、以下のルールに基づいて、音読みと訓読みを見分けることができます。
漢字の読みが2拍で、拗音が含まれている:音読み
例:章(ショウ)曲(キョク)
拗音とは、「拗(ねじ)れた音」という意味で、小さい「や・ゆ・よ」を添えて書く音を指します。
拗音は、昔から日本語にあったわけではなく、中国から漢字とともに、もたらされた音といわれています。
そのため、拗音が含まれている場合、音読みと判断することができます。
漢字の読みが2拍で、末尾が「ウンチクキツイ」以外の場合:訓読み
これは、2拍の漢字の読みが音読みに分類されるときには、かならず末尾が「ウンチクキツイ」のいずれかになる、という法則を利用した判別方法です。
音読みと訓読みの見分け方を実践してみよう
漢字の読み方を完全に見分ける方法は存在しませんが、紹介した方法を使えば、ある程度音読みか訓読みかを判別することができます。
実際に判断するときは、一つの方法だけに頼らず、複数の方法を組み合わせて使うことがポイントです。
以下に示す漢字の読み方が、音読みなのか、訓読みなのかを判別してみましょう。
問題
- 愛する(あい・する)
- 食べる(た・べる)
- 町(まち)
- 妹(いもうと)
- 蝶(ちょう)
- 客(きゃく)
- 表す(あらわ・す)
解答と解説
-
答え:音読み
解説:1. 愛する(あい・する)」は、送りがながついていますが、「接する(セッ・する)」「屈する(クッ・する)」「生じる(ショウ・じる)」のように「~する・~じる」の「~」部分は音読みになります(方法2)。
-
答え:訓読み
解説:「食べる(た・べる)」の「食」は送りがな「べる」が必要なため、訓読みと判断できます。(方法2)。
-
答え:訓読み
解説:「町(まち)」は発音だけで具体的な意味がわかるため、訓読みと判断できます(方法1)。
-
答え:訓読み
解説:「妹(いもうと)」は発音だけで具体的な意味がわかること、そして読み方が4文字以上であるため、訓読みと判断できます(方法1, 3)。
-
答え:音読み
解説:「蝶(ちょう)」は2拍の読み方であり、拗音が含まれていることから、音読みと判断できます(方法4)。
-
答え:音読み
解説:6の蝶と同様に「客(きゃく)」は2拍の読み方であり、拗音が含まれていることから、音読みと判断できます(方法4)。
-
答え:訓読み
解説:「表す(あらわ・す)」は送りがな「す」が必要となることから、訓読みと判断できます。(方法 2)。
劉 智秀 1999年東京都生まれ/栄東中学・高等学校/東京大学経済学部卒/クリエイト速読スクール二代目代表