- ホーム
- 体験記&インタビュー
- 体験記 '03
- はまだりこ作品
クリエイト速読スクール体験記 '03
はまだりこ作品
表面張力
はまだ りこ
生茶、というペットボトルのお茶しか口にしなくなって、もう五日になる。
ぐうぐう鳴るわりに、空腹感はない。
会社帰り、今日も駅前のコンビニに立ち寄る。いい匂いをさせるレジ脇のおでんをチラリと見ただけで、五百ミリリットル入りの生茶を三本買う。
星がきれいだ。蚊に刺されながら見上げる花火より、鼻先を冷たくしながら見る、自分の白い息越しの星空のほうがずっと好きだ。後ろ手にハンドバックとコンビニの袋を両手であわせて持ち、歩くたびにブーツのふくらはぎにわざとあてて、わさわさと音を立てた。
駅から家まで五分のはずが、このところ十分近くかかる。星を見上げて歩くせいばかりではない。家に帰ればまた暫くはひとりになれない。それが少しだけ、足取りを重くするのだ。
家のドアを開けると、今日は私の大好きな肉じゃがの匂いがした。その美味しそうな匂いは、今日も決まった時間、食卓につくことを私に約束させるものだ。
「また、お茶?」
冷蔵庫の前で入らないペットボトルと格闘していると、不機嫌な母の声がした。「いいかげん、何か食べなさい。死んじゃうわよ」先にテーブルについている母を振り返らなくとも、どんな顔をしているか分かる。
「いいの、いいの。ダイエット、ダイエット」。冷蔵庫は、ここ数日の私が食べるはずだった夕飯で溢れ返っていた。なんとか二本のお茶を押し込むと、一本を手に、母の向かい側の席についた。父はまだ帰っていない様子だ。
私は嘘をついていた。会社では、夕飯しか食べないことにしたと言い、家では、昼食しか食べないことにした、と言った。友人も母も、それぞれにへぇと鼻で笑った。今まで流行のダイエットをあれもこれもと試していた三日坊主の私だから、また始まった、くらいに思ったのだろう。しかし、もう五日だ。このところの夕飯には、私の好きなものや、以前に美味しいと誉めたものばかりが並ぶ。私にダイエットを断念させようという、母のかわいらしい作戦だ。そろそろ、昼食も食べていないことに気づいているのかもしれないが、母は何も聞いてこない。せっせと夕飯をこしらえる。
食べる気の全く無い肉じゃがを挟んだ母とふたりの食卓。箸立てから、自分の箸さえ取らない私の顔を、美味しいわよ、と時々箸を止めては母が覗き込む。私は、そうね、美味しそうねと笑いながらペットボトルにまた口をつける。
我が家は、両親と私の三人家族だ。ごはんをいらないと言い放って、部屋に篭ってしまうのは簡単だが、私は決してそれをしない。母にとって、この時間が貴重であることを知っているからだ。母は、話したいのだ。たわいのない話に相槌を打つ才能のまるでない父に、今日あった出来事を話したところで壁に向かって話しているのと大差ない。私が高校生の頃から、夕飯の食卓は、食べることだけが目的ではなくなっている。日々の出来事をこうして言葉にするのは、単調な母の毎日をきちんと過去にしていく作業なのだと思う。私にはそれに付き合う義務があるように思うし、またそうしてあげたいと思ってもいる。
人付き合いの苦手な父が、今日はめずらしく友人と外食してくることや、今朝のゴミ出しが間に合わなくて、よその収集所までこっそり出しに行ったこと、一昨日盗まれた、我が家の自転車によく似たピンクの自転車を走って追いかけたことなんかを、母が面白おかしく話す。母はよくしゃべり、私は笑って相槌を打ちながら早くひとりになりたいと、ぼんやり思っていた。
六日前、私は振られた。正確には、距離を置こうと言われた。予感していたものではなく、あまりに唐突だったので、彼の言葉の意味が、すぐには分からなかった。
とても好きな人だった。つきあって一年半、毎日は彼と逢っている時間と、逢えない時間との二種類にしか分けることができなかった。仕事をしている私も、家で眠っている私も、ひとりの私は単に彼に逢えない私でしかなかった。
振られた理由はよく分からなかった。なんだか随分長く時間をかけて彼は話をしていたように思うけれど、振られた瞬間の記憶がどうも曖昧になってしまっている。小さい頃、両親が家の中で喧嘩を始めると、私はよく貧血を起こして倒れたらしい。起こって欲しくない現実を目の当たりにして消化しきれないと、私は自分でスイッチを切ってしまうらしいのだ。彼が別れ話をしたのは車の中だったので、倒れなかっただけで、私の機能は停止していたのかもしれない。
あの時から、生茶しか口にしていない。食べたいと思う欲がごっそり、消えてなくなってしまったみたいだった。胸のモヤモヤが胃袋にぎっしり詰まって、何も入らない。これから続くであろう孤独な週末を想像するだけで、満腹感さえあるように感じる。喉だけが、カラカラに渇いた。
私はこのことを誰にも話せずにいた。自分の味方ができてしまうことを恐れた。親も、友達も、みんな優しい。話したら慰めてもらえることは確実だった。けれど今、心配そうに目を覗き込まれたら、理性を保つ自信がなかった。どこでだって瞬間的に泣き崩れてしまいそうだった。
家庭で、職場で、私には課せられた役割というものがある。片付けねばならない仕事と、たくさんの約束がある。それを、泣き崩れてまっとうできなくなるわけにはいかない。私はもう、とうに三十を過ぎた大人なのだ。息を殺して、じっとしていれば、台風が過ぎ去るみたいにこの出来事は過ぎ去った思い出になるのだ。慰めてもらったって、事態は変わらない。彼が帰ってくるわけではないのだ。絶望の淵にいると告白しても、皆に心配をかけるだけだ。そして、周囲の暖かい励ましに、ありがとうと笑顔を向けるだけの余裕がないなら、なおさら人に言うべきではないように思えた。私は極力、この出来事を意識の奥底にしまいこんで日々を過ごすことに決めていた。
母の食事が済むと、テーブルを立ち、一緒に食器を下げた。よそられただけで手付かずの肉じゃがを鍋に戻し、私が大好きな子持ししゃもやアボガドのサラダに皿のままラップをかけた。母は、美味しいのにと口を尖らせながら、満杯の冷蔵庫に皿を押し込む努力をしていた。私は聞こえないふりで、一人前分しかない洗い物にさっさと取り掛かった。
母宛てに掛かってきた電話を合図に、私はそっと二階の自分の部屋へ上がった。掃除の行き届いた部屋。私はうっとりしながら、掃除し足りない部分はないかと見渡した。塵ひとつない。ここ数日、毎日、一晩中掃除をしているのだから当たり前の話だ。
食事を取らなくなったのと同時に、私は夜、眠れなくなった。全く眠くならなくなってしまった。最初の二晩は何とか眠りにつこうと、ひたすらベッドで寝返りをうった。しかし、三日目の晩、眠くならないものは仕方がないと開き直って、深夜番組を眺めていたら、テレビのブラウン管が汚れていることに気がついた。そっと拭いたら、ティッシュが真っ黒になった。よくよく近づいてみると、テレビの後ろのコードやら、コンセントに刺さった黒いプラグの四角い部分にもうっすらと埃が見えた。一度汚いと思ったら、なんだか我慢ならないもののように思えた。雑巾を持ち出すと、水音が両親の耳につくかもしれない。私はティッシュであちこち拭き始めた。掃除がまだ済まないうちに目覚ましが鳴り、夜が朝に変わっていた。ゴミ箱からティッシュが溢れていた。
眠らないことと、食べないことは、今までにない勢いでするすると体重を落としていった。体重計に乗ることが、日を追うごとにだんだん楽しくなってきていた。同僚の女の子に痩せたと羨ましがられると、少し鼻が高かった。痩せた私を見たら、彼はなんと言うだろう。多少なりとも同情や後悔をするのではないだろうか。私は、会社が同じでない彼と、道でばったり会うシーンを空想するようになっていた。
その晩、仕舞い湯に入っていると、先に休むからと磨りガラス越しに母が声を掛けてきた。おやすみを口にすれば、ここから先は朝まで私だけの時間だ。両親が起きている間は、部屋に戻ったところで、何くれとなく声を掛けられる。テレビが面白いから来てみろだの、新しい服を新調したんだけれどどう思うかとか、大した用ではないが、やはりその度に、私だけの時間からは引き離される。眠らなくなって、目の下のクマは気になるけれど、何といっても一日が、私だけの時間が、長くなったのがいい。一日が、真に二十四時間になったのだ。今日は、本棚の本を全部出して、棚を拭こう。本を整理するのもいいな。湯船につかりながらそんなことを考えた。
お風呂上り、ペットボトルを取ろうと冷蔵庫の扉をゆっくりと引いた。近ごろは慎重に開けないと、皿が転げ落ちてきたりする。すぐさま目的のものを見つけはしたものの、扉の中の異変に、私は何をするつもりだったのか忘れてしまった。冷蔵庫を占領していたはずの数日分のおかずが、全て跡形もなく消えていたのだ。バターや牛乳、漬物などはそのままで、カラッポではないものの、今日、母が苦労して押し込んだはずの、ししゃもさえいなかった。
冷蔵庫脇に二つ並ぶ、ペダル式で蓋の開く、色違いのゴミ箱に目を移した。生ゴミ用の方のペダルにゆっくりと足をかける。思ったより勢いよく赤色の蓋が上がった。
見覚えのあるおかずが重なり混ざり合ってそこにあった。さっき、食卓で私に横顔を見せていた子持ちししゃもが、一番上で正面からまっすぐに私を見上げていた。
変な気持ちだった。食卓にいるときはもちろん、冷蔵庫の中でさえ、そこに存在するだけで私に食べろと全身で命令していた食べ物たちが、今は全くその生命力を失ってしまっていた。食卓では、いい匂いをさせ、誇らしく皿を纏い、自信にあふれていた彼らが、みすぼらしい生ゴミになっていた。開いたゴミ箱の口から、嫌な臭いが漂った。それがますます、彼らがもう食べ物でないことを決定付けていた。母が捨てたに違いない。自分自身が母に見捨てられたような気がして、その食べ物の亡き骸をじっと見つめた。
彼らをゴミにしたのは私だ。
「ごめんね」ペダルにスリッパのつま先を掛けたまま、かつては私の晩ごはんだった生ゴミたちを見下ろしてつぶやいた。
ごめんね、彼もあの時そういった。
あの日、家のそばで車を降り、ふたりはいつものように私の家まで並んで歩いた。私は門の中から、門の外に立つ彼を振り返った。いつもならそこで、じゃあと背中を向ける彼が、開いたままの門をゆっくりと閉めた。観音開きの古い門は、ギィーがっしゃんと音を立て、もう遅い時間でひっそりとした住宅街に意外なほど響いて彼を驚かせていた。
二、三歩あとずさった後、彼は立ち止まって、私から視線を外した。低い声で「ごめんね」とつぶやくように言うと、身を翻して歩き出した。私はその背中が見えなくなった後も、閉まった門の中に立ち尽くした。手には、彼が最後に買ってくれたペットボトルの生茶を握っていた。
ゴミ箱のペダルからつま先を外すと、赤い蓋がゆっくりと閉まり、ギィーぱったんと音を立てた。私は胃の奥からせり上がってくるものを感じた。
ごめんね、の意味を理解してしまった。私がししゃもに告げたのと同じ、憐れみを込めた決別の言葉だ。ししゃもをゴミ箱から拾い上げて皿に盛ることはあり得ない。さよならよりも決定的で冷淡な、最後を意味する言葉だったのだ。
振られたときの、距離を置こう、というセリフに、私は無意識のうちに希望を見出していたのかもしれない。誰にも言わなかったのは、皆に心配を掛けたくないだけではなく、何事も無かったように戻れることを期待してのことではなかったか。
目眩がするのと同時に、血の気が引いていくのを感じた。私は本当にあの人を失ってしまっていた。へなへなとゴミ箱の前にしゃがみこむと、赤い蓋が鼻先にきた。この赤いプラスチックの向こうでししゃもが見上げていると思うと、吐き気がした。明日は金曜日だ。仕事がある。果たさなければならないたくさんの役割が私を待っている。スイッチを切っては駄目だ。ここで倒れたら大ごとになる。社会人として、大人として、私がそうあるべき枠から、恋人に振られたくらいで、はみ出すことはできない。例えコップの縁ギリギリだろうとも、流れ出るわけにはいかないのだ。
のろのろと立ち上がり、洗面所へ向かった。冷たく固いはずの床も廊下もなんだかふわふわしている。体重計に乗る。夕べよりもまた一キロ落ちていた。五日間の絶食で七キロ落ちたことになる。少なく表示されるデジタル数字にニタリとした自分に気づく。
私はまだ、コップの縁に留まっているのだろうか。
正面の鏡から、痩せこけた私が、ししゃものような顔でこっちを見ていた。



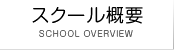




 Copyright© CREATE RAPID READING SCHOOL All Rights Reserved.
Copyright© CREATE RAPID READING SCHOOL All Rights Reserved.