高校生作品集
2001年度SEG文スキ受講アンケート
鈴木 めい
他の人の文章がなおされていくのを聞いた後でも、私は「一応文章が書ける」と思っていた。内容とくいちがったタイトルをつけるなんて、自分にはあり得ないことだと思っていた。だから先生のコメントがぎっしりと書き込まれた作文が返されたときは、本当にビックリした。自分の体験は、自分の頭の中にあるので、実際に原稿用紙に書いたこととそうでないことをごちゃまぜにして、それで全てを書いた気になっていたのだった。やはり、自分の文章をなおしてもらえると、癖というか、悪いところが次々と見えてきてよかった。
また、「文章表現スキルアップ」を受講して、素晴らしい作品にたくさん出会うことができた。クラスにも、とても文章が上手な人がいて、非常に刺激を受けた。私はいつも家でクラスの人たちの作文を読んで、「おもしろいんじゃない?」と言うにとどまっていたが、文章が上手な人たちは、他人の作品だけでなく、自分の作品をもじっくり読んで、自分の文章のどこに問題があるか授業中に指摘してくれた。文章が上手になるためには、良い作品も悪い作品も読んで、そこから学ぼうとすることが大切なんだな、と思った。
結局、私は二つしか文章を書けなかったが、一回提出して自分がいかに「舌っ足らず」かということを実感した。私はこの講習を受けるまで、自分の文章を他人に読まれるということに対して抵抗を持っていた(恥ずかしく思っていた)が、今では全くそんなことはなくなった。以前は、人の顔色をうかがうような文章を書いていたが、大切なのは「自分がどう思うか、そして感じるか」を書くことだと気付いた。とにかく、この講習を受けたことによって、「書くこと」が好きになった。
松田先生、本当にどうもありがとうございました!!!
第1作 アリアナ
鈴木 めい
私には、小学校三年生のとき以来の親友がいる。
父の転勤で小学一年生の終わりにサイパンという小さな南の島に引っ越した。日本人学校がなかったので、英語が一言もしゃべれないまま現地校に入った。しかし、そこでは人間関係がうまくいかず、とうとう学校に行くことを考えただけで気分が悪くなってしまうほどになり、転校した。
サイパンの人口は約六万人と少ないので学校も小規模だが、次に入った学校は小学校一年生から中学二年生全員を合わせても三十人足らずという小さなところだった。一年生から三年生を「ローワースクール」、四年生から六年生を「アッパースクール」、七、八年生を「ジュニアハイ」と区切って、三つの教室で授業するという状況だった。そこで私が出会ったのがアリアナだった。彼女も私が転校したのと同じ時にアメリカのデンバーからサイパンに越してきて、WPS (Whispering Palms School) に入ったのだった。その時私は三年生で、アリアナは一年生だった。私はまだあまり話せなかったが、アリアナはおかまいなしに私に話しかけてきてくれた。なぜ彼女が私とあんなに仲良くしてくれたのかは分からないが、とにかくすごく気が合った。アリアナは毎週末、お泊まりにさそってくれた。アリアナが一度私の家に泊まりに来たこともあるのだが、彼女は夜になると家族が恋しくなってしまったのでその日は彼女のお父さんが迎えに来た。二人で別になにをするでもなく、プールに行ったりビデオをみたりただしゃべっていたりした。とにかく、私たちが仲がよかったのでアリアナの弟と私の妹も仲良くなり、家族ぐるみのお付き合いをするようになった。学年が上がってからも私は週末になるとアリアナの家に泊まりに行かせてもらった。夏休みはビーチに行ったりテニスをして毎日遊んで、アリアナのお父さんに「そんなに毎日会って飽きないの?」と笑われたこともある。
七年生になって、世界が百八十度回転した。同学年の子のあいだでは恋とか人生とか誰が誰と付き合っただとか、私にとっては新鮮なことばかりが話題になった。私はその話の輪に入りたかったし、中学からは勉強もいきなり難しくなり、だんだんアリアナとすごす時間が少なくなっていった。それでもアリアナとは親友だった。
八年生もあと残りわずか、卒業まであともう少しというときに、いきなり帰国が決まった。私は、口では「日本に帰りたい」といってはいたものの、いざ帰るとなると心細くなった。帰国してもカルチャーショックとホームシックになってしまった。アリアナに電話をかけると、彼女のお母さんが「めいひとりでも、卒業までうちに来れば?」と言ってくださったので、私はそのことばを真に受けて、本当にサイパンに帰って二か月間マムーディー家に泊めていただいた。改めて、アリアナという親友がいて私はなんて幸せなんだろうと実感した。
卒業後、私は再び帰国して、日本の中学校に入った。WPSを卒業できたおかげで、気持ちにもけじめがついて、もうホームシックになるようなことはなかった。それからはずっと高校入試のことで忙しくなってしまい、やっと会えたのは中学三年生の冬休みだった。今度は、みんなにうちに泊まってもらった。それからまた三回ほど会っている。
ついおととい、eメールの受信トレイに、アリアナからメールが届いていた。「めい、久しぶり!! 調子はどう? 私はやっと夏休みがおわったところ。みんな元気にやってます。三か月半ぶりの数学は、ちょっとキツいけど!……」彼女に負けないように、私もがんばろう思う。
第2作 かちかち山
鈴木 めい
世間では、かちかち山の狢(むじな)は悪い奴だ、と言われてきた。みんな、兎たちの話だけ聞いて、兎を英雄に、狢を悪役に仕立てて、話をどんどん誇張していくからだ。でも、本当は狢は無実の罪で殺されたんだ。兎と狢とどっちが悪いか、あんたに決めてもらおう。
あるところに、塩爺(しおじい)と千代婆(ちよばあ)という老夫婦がいた。二人は地蔵を助けたとかで、若いころは金には不自由しない生活をしていた。しかし、二人が年を重ねるにつれて財産も減ってきた。塩爺は動物好きで、獣を殺すことだけはしたくないと思っていたが、笠を作るだけでは明日の食事にも困るほどになったので、とうとう狩人になることを決心した。
塩爺が森に出かけると折り良く一匹の狢が現れた。塩爺は狢に銃口を向けて一発打った。弾は狢にあたらなかったが、狢は驚いて気絶した。塩爺は狢が死んだと思って、それを持って帰った。そして、千代婆に「今晩は冷えるから、薪をとってくる」と言ってまた山へ出かけて行った。千代婆がえっちらおっちら米をついていると、頭上から鳴き声が聞こえてきた。ふと見上げてみると、天井に吊るしておいた狢が我に返って、怯えて鳴いているのだった。千代婆は憐れに思って、狢に話しかけた。
「お前、私と取引をしないかい。もし米つきを手伝ってくれたら、逃がしてやるよ。塩爺だって、本当は動物を殺したりしたくないんだよ。帰ってきたら、私が見てない隙にお前が逃げたとでも言っておくから」狢は喜んで千代婆を手伝った。しかし少しすると、狢も疲れて重い杵を持ち上げるのがやっとになってきた。あともう少しで終わるというところで、狢は誤って、米粒を拾おうとかがんだ千代婆の頭の上にきね杵を振り下ろしてしまった。狢は驚き慌てて千代婆に駆け寄ったが、老女はすでに息絶えていた。狢は恐ろしくなって、一目散に自分の穴に逃げ帰り、一部始終を家族に話した。狢の妻はこう言った。
「明日にでも行って、謝ってくるべきだと思うよ。そうでないと、おじいさんにあんたがわざとおばあさんを殺したんだと思われてしまうよ」
一方、塩爺は帰宅して、千代婆が死んでいるのを見て驚き、嘆き悲しんだ。すると、木にとまって成り行きを見ていたカラスが自分が今目撃したことを話した。カラスには狢が故意に殺人を犯したのかどうかは分からなかった。塩爺がおいおい泣いているところに、兎がやってきた。この兎は、むかし罠にかかっているところを爺さんに助けてもらい、それ以来よく遊びに来ていたのだ。
「塩爺、塩爺さん、どうしたのですか」
「それがのう、悪い狢がばあさんをだまして殺してしもうた」と、塩爺は泣く泣く兎にカラスから聞いた話を繰り返した。兎は少し考えていたが、
「おじいさんは僕の命の恩人です。狢をこらしめないうちは千代婆さんも浮かばれますまい。ここはひとつ、僕に任せてください」と言った。塩爺は涙ぐんで兎に礼を言った。
兎は自分の穴に戻ると、同居していた狐とカワウソに塩爺のことを話した。二匹とも塩爺には日頃から世話になっていたので、狢退治には反対しなかった。
次の日。狢は、塩爺に謝りに行くために穴を出たものの、爺さんの怒りを考えると決心が揺らいだ。狢の足は、柴刈り場へ向かった。狢が柴を刈っているところに、例の兎が通りかかった。
「狢さん、そんなにいっぱい柴を刈って、全部ひとりで持てるんですか」狢は物思いにふけりながら仕事をしていたので、無意識のうちに山ほど柴を刈ってしまっていたのだ。狢が困っていると、兎は「なんだったら、僕が手伝いましょうか」と申し出た。狢はありがたそうに笑った。
そうしてふたりで半分ずつ柴を背負って歩いていたが、しばらくすると、兎が道にうずくまって、ウンウンと苦しそうにうなりだした。狢は慌てて兎に駆け寄った。「兎どん、どうしたんだい」
「いえ、ちょっとお腹が痛くなっただけです。僕のことは気にせずに、先にいっていてください、すぐ追いつきますから……」
「君はおいらを手伝ってくれたのに、おいらが苦しんでる君を放っておくと思うかい。その柴はもういいから、君、僕が背負ってる柴の上に腰かけなさい」
そうして狢が柴と兎をおぶっていくうちに、兎は隠し持っていた火打石をかちかちと叩き始めた。狢は「はて、兎どんは煙草でも吸うのかな」と思ったが、兎が「ああ、もうかちかち山に来たのか…」とつぶやいたので、納得してそのまま歩き続けた。兎は火を起こすと、薪に火をつけて、さっさと逃げた。狢は背中に大火傷を負った。狢は痛さのあまりに動けなくなり、日は沈んでまた昇った。
翌日、狢がなんとかして川に行こうとしていると、向うから狐の薬屋がやってきた。狐は狢の火傷のひどさに同情するふりをして、火傷の薬だといって唐辛子の粉を狢の背中にすりこんだ。狢は眼に涙をためて、「いたい、いたい。背中が燃え上がるようだ」
といったが、狐は「あたしも火傷のときに使ったことがあるので、痛むのはわかります。でも、この薬よく効くんですよ。痛みは少し続きますけど、火傷はじきに治ります」と言って、立ち去ってしまった。狢が痛みで気絶しているところに、父親が帰ってこないので心配して探しに来た息子が通りかかった。息子は急いで父親を穴に連れて帰ったが、背中の火傷は悪化して、狢は一週間ほど生死の狭間をさまよった。やっと歩けるようになったある日、狢は家族が安静にしていろと反対するのを押し切って、川の冷たい水に火傷をさらそうと出かけていった。狢が水に浸っていると、漁師らしいカワウソが舟で川を下ってきて
「おい、狢の旦那、そんなとこでなにしているんだい」と陽気に呼びかけた。
「おらあ、ちょっと水浴びをしているだけだよ。あんたは漁師さんかい」
「その通り。こうして雑魚をとってるんだが」といってカワウソは目くばせをした「どうだい、ちょっくら俺と一緒に魚釣りをしないかい」狢は喜んで舟に乗り込んだ。
川が深く、流れが急になったところで、カワウソはいきなり立ち上がった。すると、彼が座ってふさいでいた大きな穴から水が勢いよく流れ込んできた。狢は慌てふためいた。「カワウソどん、おいら泳げねえんだ、助けてくれぃ」
カワウソの表情は、冷たく硬くなった。「あんたは、罪のない優しいおばあさんを殺した。あの世に行っても千代婆に許してもらえるものか。せいぜいあっちでゆっくり罪滅ぼしするんだな。あばよ」弁解する狢の声を背にして、カワウソは水の中に飛び込んで見えなくなった。
狢の死体は海まで漂って、今では魚でさえ泳がないような深い海の底に横たわっている。
これが本当のかちかち山の話だ。なんで俺なんかにそんなことがわかるのかって? 兎に殺された狢が俺の親父だからだ。俺はおしゃべりなカササギが知らせを持ってくる前に親父の死を知っていた。親父の霊が訪れて、俺にすべてを話したからだ。仇討ちなんてことばは、親父は一言も口に出さなかった。親父は、大変哀しそうな瞳をしていた。俺が兎たちの穴に放火してやったことを知ったら、あの瞳はさらに寂し気になるだろう。今では奴らも閻魔様の僕となっていることだろう。俺は許せなかったんだ、謝罪して心を入れかえようとしていた親父を卑怯な手口で殺した奴らが!!
俺の犯罪も明るみに出て、俺は処刑されることになった。一人でも多くの人にかちかち山の本当の話を知ってもらうために、俺は今、筆を執っているのだ。



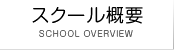



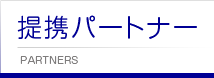
 Copyright© CREATE RAPID READING SCHOOL All Rights Reserved.
Copyright© CREATE RAPID READING SCHOOL All Rights Reserved.