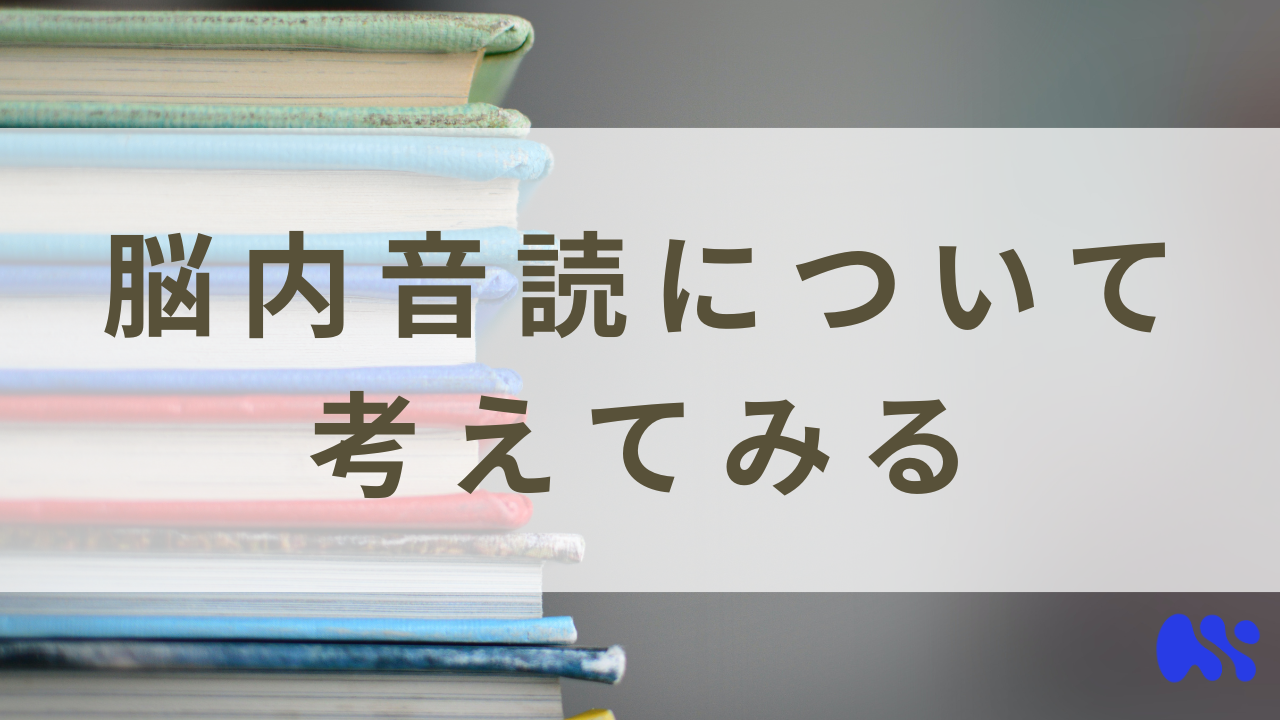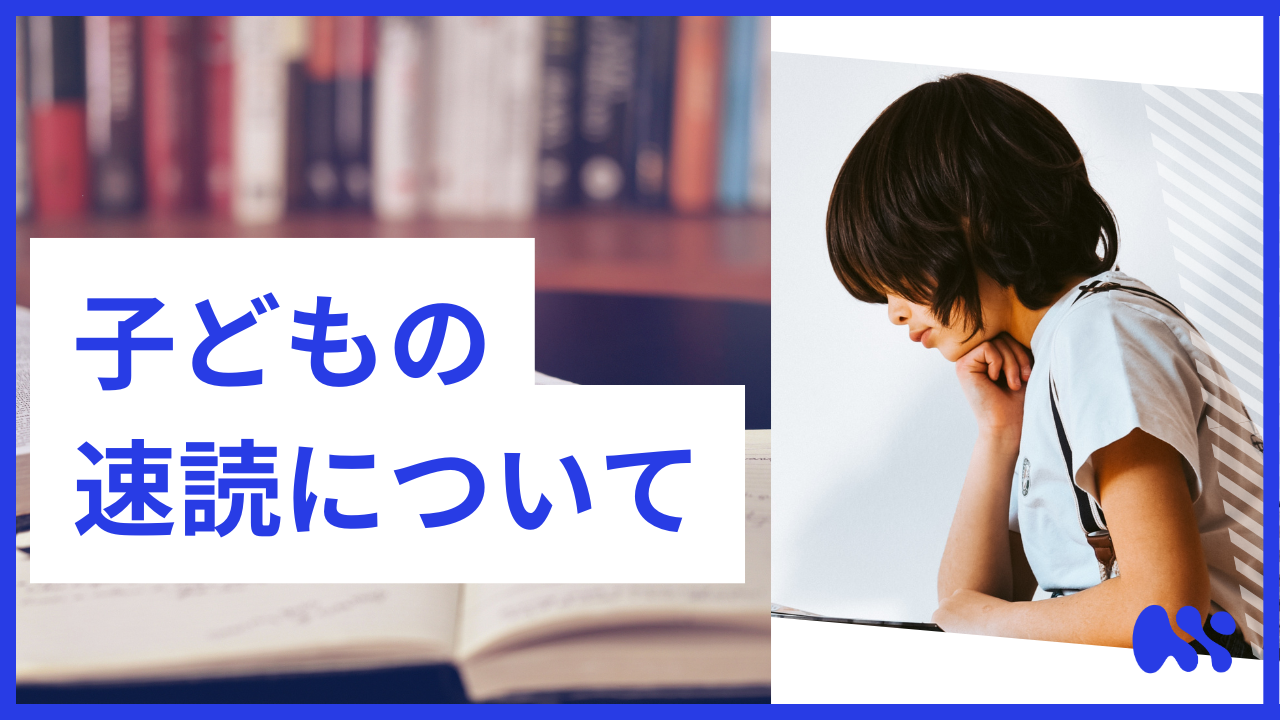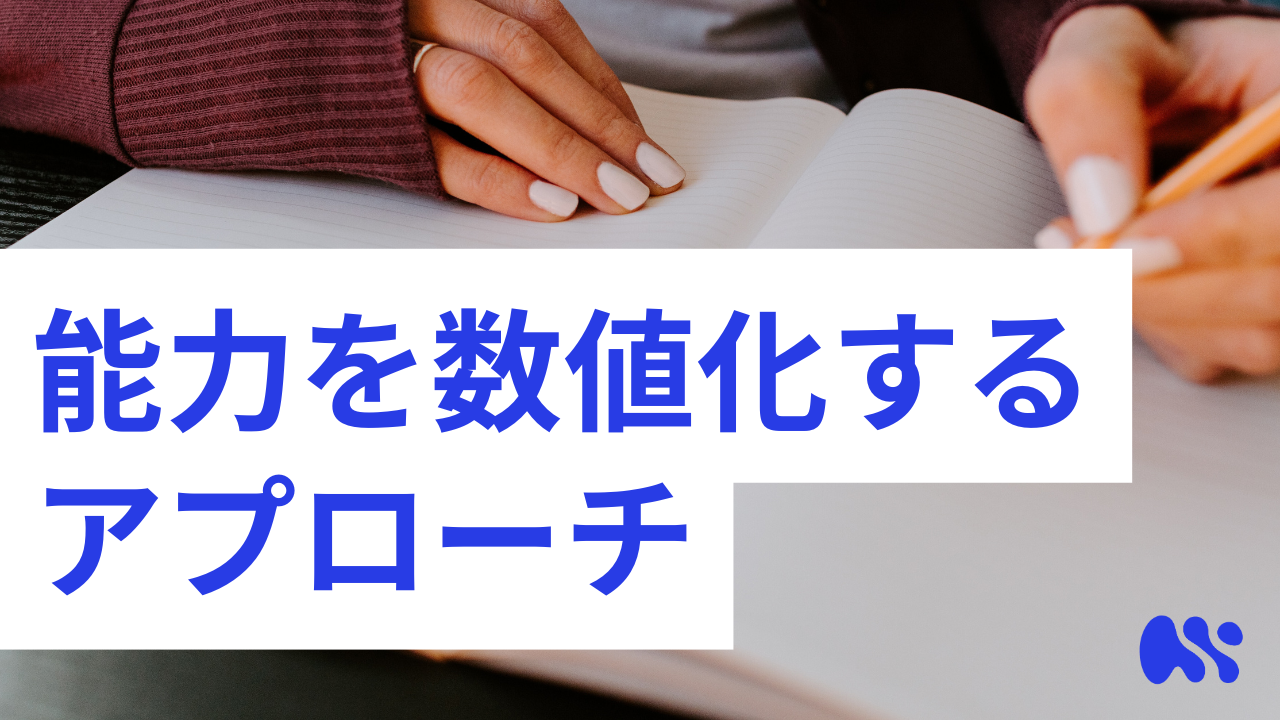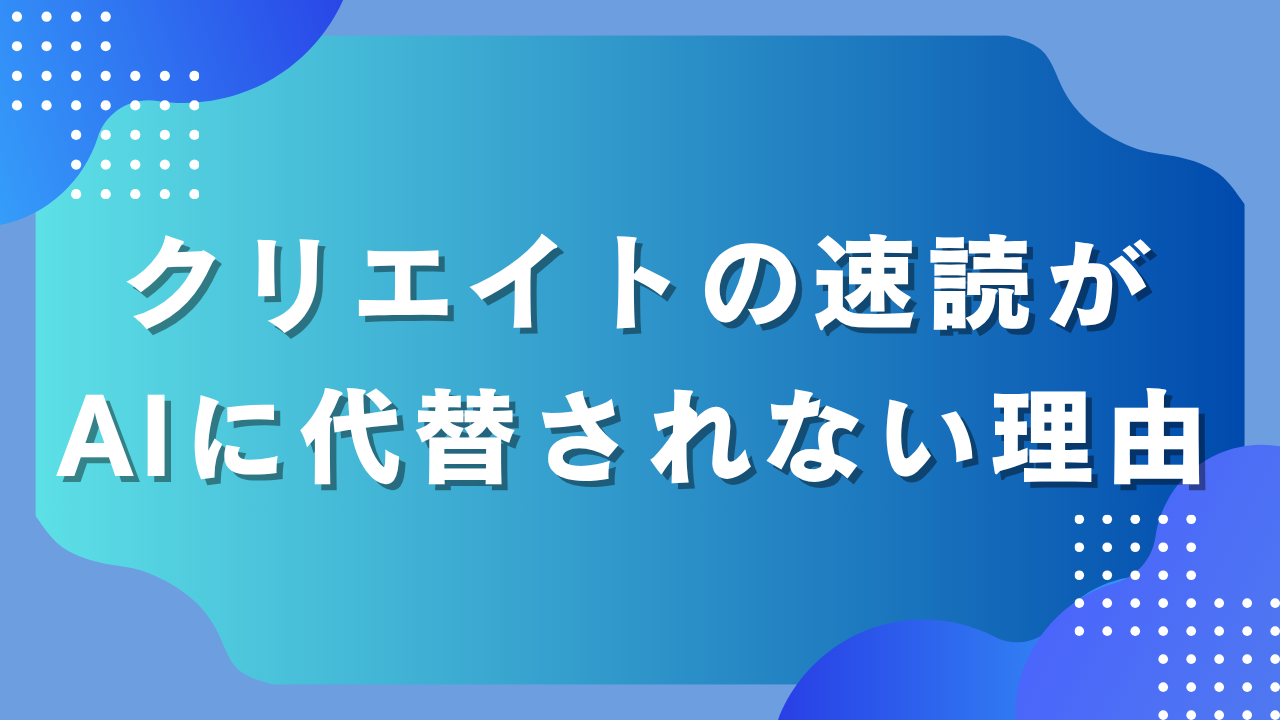
ビジネスの現場における生成AIの使用率
BCGの調査(2025年6月)によると、ビジネスの現場において、生成AIを日常的に使用する人の割合は世界平均で7割を超えています。
日本はやや遅れており、51%という数字ですが、それでも過半数です。
参考:日本は生成AIの業務活用、AIエージェント導入ともに出遅れ BCG調査
速読はAIに代替されるか
では、クリエイトの速読プログラムによって身につくインプット力は、生成AIに代替されうるか。
代替されることはなく、むしろどれだけ生成AIが進化しても、人間側に求められる能力として残り続ける、というのが私の考えです。
理由を3つ挙げてみます。
読む仕事が増える
1つ目の理由は「読む仕事が増える」です。
雑多な作業やアウトプットをつくる仕事が巻き取られた結果、
- 提示された文献を読み比べる
- 出力された文章をチェックする
といった読む仕事の割合が増えています。
具体例として、シンプルなレポート作成業務を見てみましょう。
多少の行き来はありますが、「リサーチ→インプット→アウトプット」という進行になります。
今は欲しい情報をチャットで伝えるだけで文献が集まりますし、まとまった文章を書かせるのも容易です。
生成AIがなかった時代と比較すると、両端のリサーチとアウトプットは、ものすごく楽になっています。
しかし、どれだけ技術が発展しても、自分のアタマに情報を入れる作業だけは、外部化できません。
読む仕事が増える、別の言い方をすると、読む仕事だけは残り続けるのです。
読む仕事は任せきりにできない
2つ目の理由は「読む仕事は任せきりにできない」です。
読む作業も生成AIに要約させればいいじゃないか、という批判もあるでしょう。
たしかに、簡単にもっともらしい回答を得ることはできますが、その質はケースバイケース。
自分の専門領域で使ったことがある方なら、手放しに信用できないとおわかりでしょう。
- 10の情報を自力で整理できる人が、その思考プロセスの一部に生成AIを組み込んで、たどり着いた1
- 10の情報を処理するだけの体力がなく、生成AIが出力した要約を、無批判に受け入れた人の1
両者は、一見同じアウトプットに見えても、その質に大きな差が生まれます。
己の読む力でもって、情報の全体像を把握し、生成AIのアウトプットを評価・監督する役割は失われません。
あらゆる勉強の土台となる
3つ目の理由は「あらゆる勉強の土台となる」です。
デジタルスキルだろうと、その他の先端分野だろうと、その勉強の入口には、テキストを読む作業があります。
分厚いテキストや専門書を読みこなすには、活字と向き合う体力が必要です。
クリエイトの速読トレーニングは、単なる速さ競争ではなく、集中力・理解力・情報処理能力を底上げする「読みの基礎体力づくり」です。
あらゆる勉強の土台となるインプット能力を、トレーニングのなかで体系的に鍛えていきます。
こうして身につける力は、私たちが自分のアタマをつかってものを考える限り、その価値が揺らぐことはありません。
AI時代に求められる唯一のハードスキル
以上、クリエイトの速読がAIに代替されない理由3選でした。
生成AIが“アウトプット”を引き受けてくれる時代だからこそ、よりいっそう「読む・選ぶ・判断する」といった”インプット”の筋力が求められます。
これだけ技術革新が進むなか、生成AIに代替されないハードスキルとして今後も残り続けるのは、もはや速読だけというのは言い過ぎでしょうか。
この記事のタグ
劉 智秀 1999年東京都生まれ/栄東中学・高等学校/東京大学経済学部卒/クリエイト速読スクール二代目代表