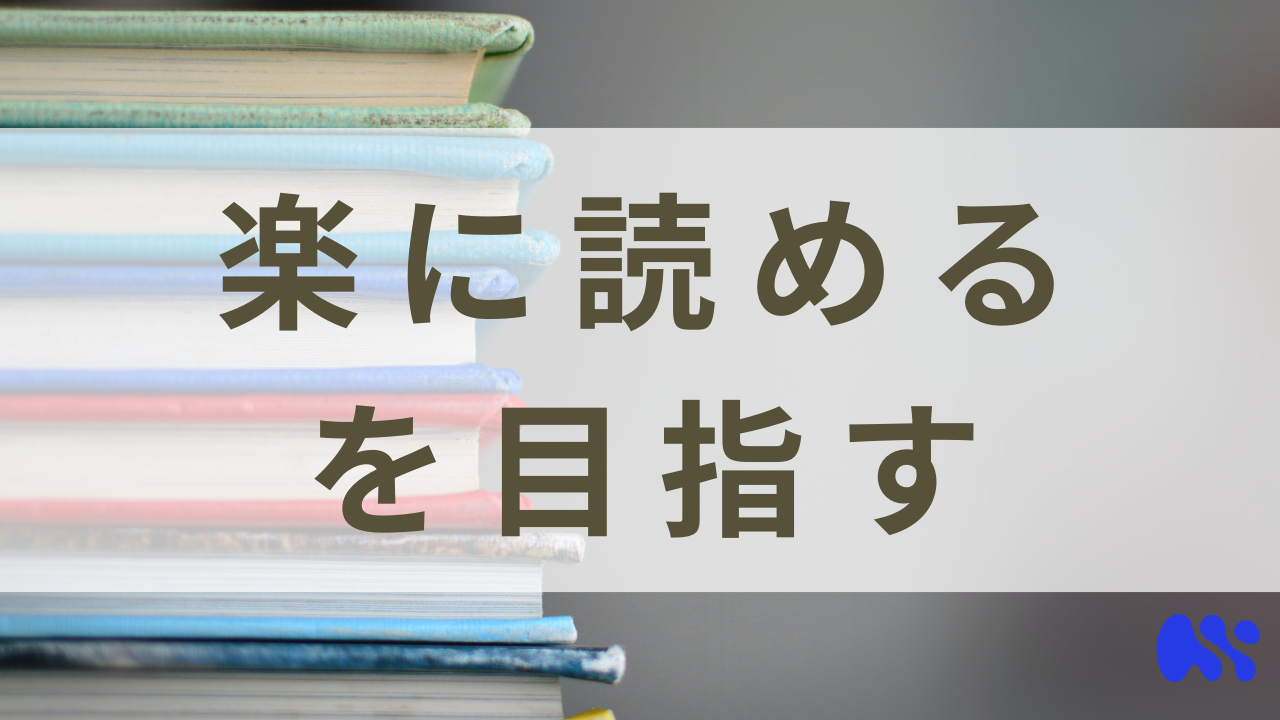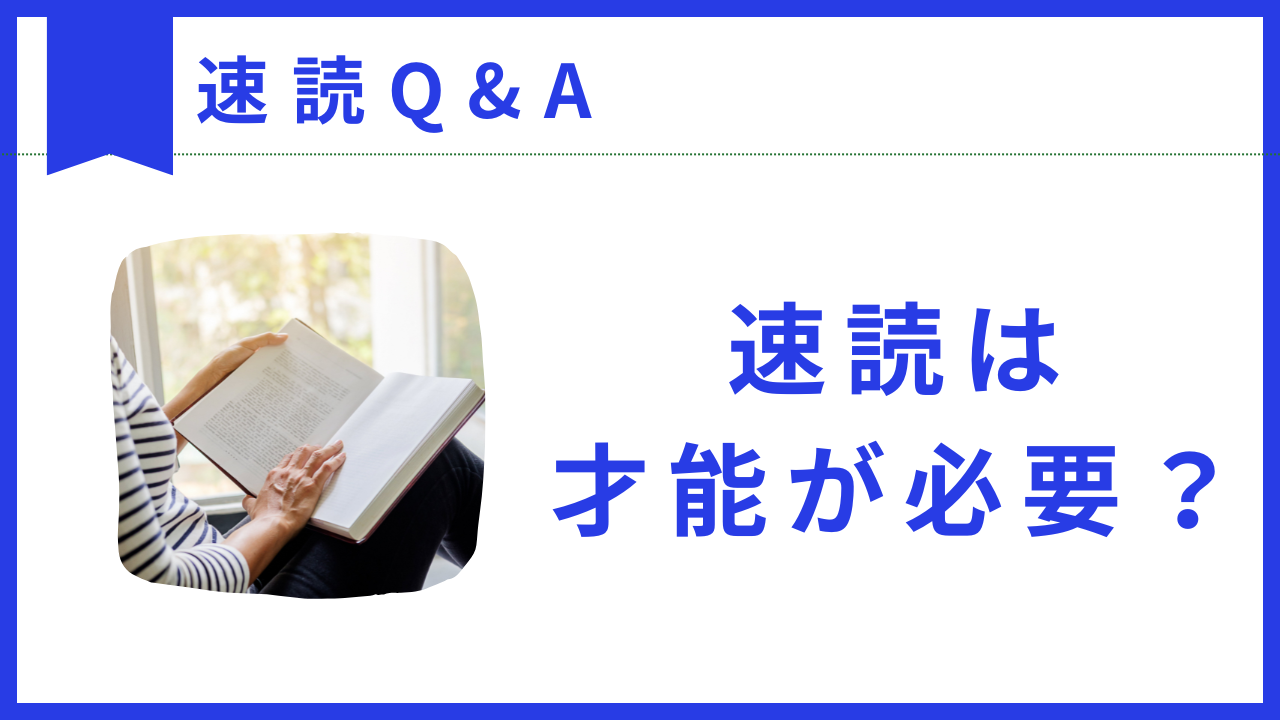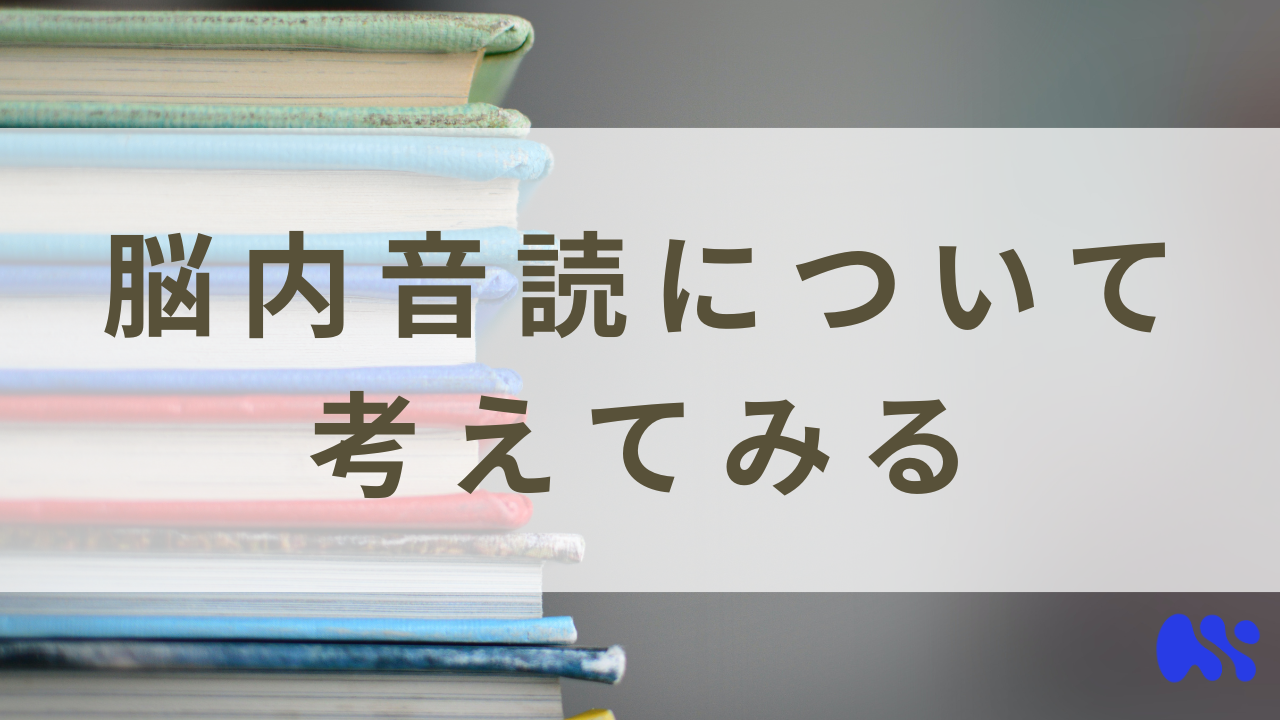
目次
脳内音読とは
脳内音読とは、声には出さないが、頭の中で文字の音を読み上げることで、文章内容を理解する読み方です。
表現の統一がされていない領域であるため、他にも「内読・内声化・音声化」といった表現がされることもありますが、脳内音読と同じ内容を表していると考えて良いでしょう。
訓練を受けていない人が文章を読むときには、通常、この脳内音読になっています。
視読とは
一方、活字慣れした人が素早く文章を読もうとする際は、脳内音読を行いません。
文字を音に変換する処理プロセスが、読書速度を上げるうえでの足枷となるためです。
速読ができる人は、その代わりに「視読」という読み方になっています。
視読とは、文字を音に変換することなく理解する読み方です。
一定のまとまりで文字を捉えることで、音声情報を介在させることなく、言葉の意味をとります。
視読では、このように処理プロセスが簡略化されるため、読書速度が上がるのです。
音読しないと理解できない?
視読は、特殊能力ではありません。
私たちは文章を読むとき、すでに音読しないまま理解しているのです。
(以下『図解でわかる 速読のすごいコツ』p.33.34 より)
たとえば、本の中に、「フォークを使う」 「フォークボールを投げる」 「フォークダンスを習う」という表現があったとします。 「フォーク」は日本語の表記としては同音ですが、それぞれ異なる意味を持ちます。しかし、実際の私たちは、この文を読むたびに立ち止まって意味を考えることはあまりありません。文脈に合わせて、自然とそれにふさわしい意味を思い浮かべて読み進めることができます。
これは、無意識に、「フォーク」に続く「~を使う」「~ボールを投げる」「~ダンスを習う」という部分を同時に読み取っているからです。 文章の前後関係を目で認識して「フォーク」の理解を助けているため、音読する前に単語を認識できています。
音読せずに内容を理解する力は、本来、誰もが持っている力なので、トレーニングすれば誰でも活用できるようになります。 それでも、音を介してでないと文字を認識できないと思ってしまうのは、これまで慣れ親しんできた音読の習慣のせいでしょう。 音読にはたくさんのよい点がありますが、文章を速く認識する観点では、むしろ遅読の原因になります。
脳内音読を止められない理由
読むのが速い人は、脳内音読をしない。では、「脳内音読を止めれば、視読ができるようになるのか」というと、そこまで単純ではありません。
人間の脳は、無駄な情報処理をしません。つまり、脳内で音読をしている人は、文字を音に変換するプロセスが、文章理解に不可欠なものとなっているのです。
そのため、「脳内音読を止めるぞ」という心がけで対処することは難しく、かりに脳内音読を止められたとしても、理解が置き去りになってしまいます。
特別なテクニックを知れば、解決する。そういった類の問題ではありません。
自らの処理プロセスを、再構築することが必要なのです。
脳内音読をやめる方法
「処理プロセスを再構築する」とはどういうことか。具体例をあげましょう。
神経系の左右差は、経験と共に拡大される
あなたが右利きであると仮定します。
左手で文字を書くことをイメージしてみてください。
筆記のスピードは右手の半分以下になり、文字の形は崩れるはずです。
“このような能力差は神経系の左右差から生じる”とされています。
左右差の発生メカニズムは、いまだにわかっていないことが多いものの、”おそらくは生得的に存在するわずかな左右の機能差が経験と共に拡大された物である”と考えられています。
出典:『日本神経回路学会誌』 Vol.22, No.1(2015),「運動系における左右差」, p.17
神経系の再構築には、訓練しかない
いきなり左手で滑らかに書くことは難しいでしょう。
しかし、左手で文字を書く能力は、誰もが身に付けることができる能力です。学生時代を振り返ってみると、利き手を骨折し左手で板書を取ることになった友人が、学年に一人はいたはずです。
その能力は、ある日突然、ハッと開眼するものではありません。地味なトレーニングを継続して行うことで、少しずつ神経系が再構築され、身についていくのです。
視読の習得には、訓練の積み重ねが必要
慣れ親しんだ習慣を再構築するという点で、視読習得の苦労は、「左手で文字を書くこと」に似ています。
脳内音読の習慣は、長年の経験によって強化されています。
その解消には、よく考えられたメソッドにしたがった、地道なトレーニングの積み重ねが必要なのです。
クリエイト速読スクールの授業
クリエイト速読スクールの1コマ90分の授業は、音読を必要としない数字や記号をつかったトレーニングから始まり、やがて文を用いたトレーニングへと移行していきます。
1回1回の授業で、記号処理から文章処理へと丁寧に橋渡しを行うことをねらいとしています。
一つひとつのトレーニングに全力で集中する経験を重ねることで、自然と脳内音読が解消される設計となっています。
「視読の習得」は速読のゴールではない
私たちは、「視読の習得が速読のゴールである」とは考えていません。
たしかに、視読を身につけると、読書速度は高まります。
なぜなら、
というように、処理プロセスが一部省略されるからです。
しかし、それは、「理解」の手前のプロセスが簡略化されたに過ぎません。
勉強や仕事で通用する、読書の楽しみを損なわない、実用的な速読を身につけるためには、読解プロセスの最後に待ち受ける、「理解」の力を鍛える必要があるのです。
当スクールの授業において、文字の認知プロセスに焦点を当てたトレーニングは、全体の1/3に過ぎません。
認知プロセスの改善と並行して、理解力向上のトレーニングにも挑戦していただくカリキュラムとなっています。
どのようなトレーニングを行い、どのような成果をあげているのか。どうぞ、当ブログの「受講生の声」カテゴリをご一読ください。
この記事のタグ
劉 智秀 1999年東京都生まれ/栄東中学・高等学校/東京大学経済学部卒/クリエイト速読スクール二代目代表