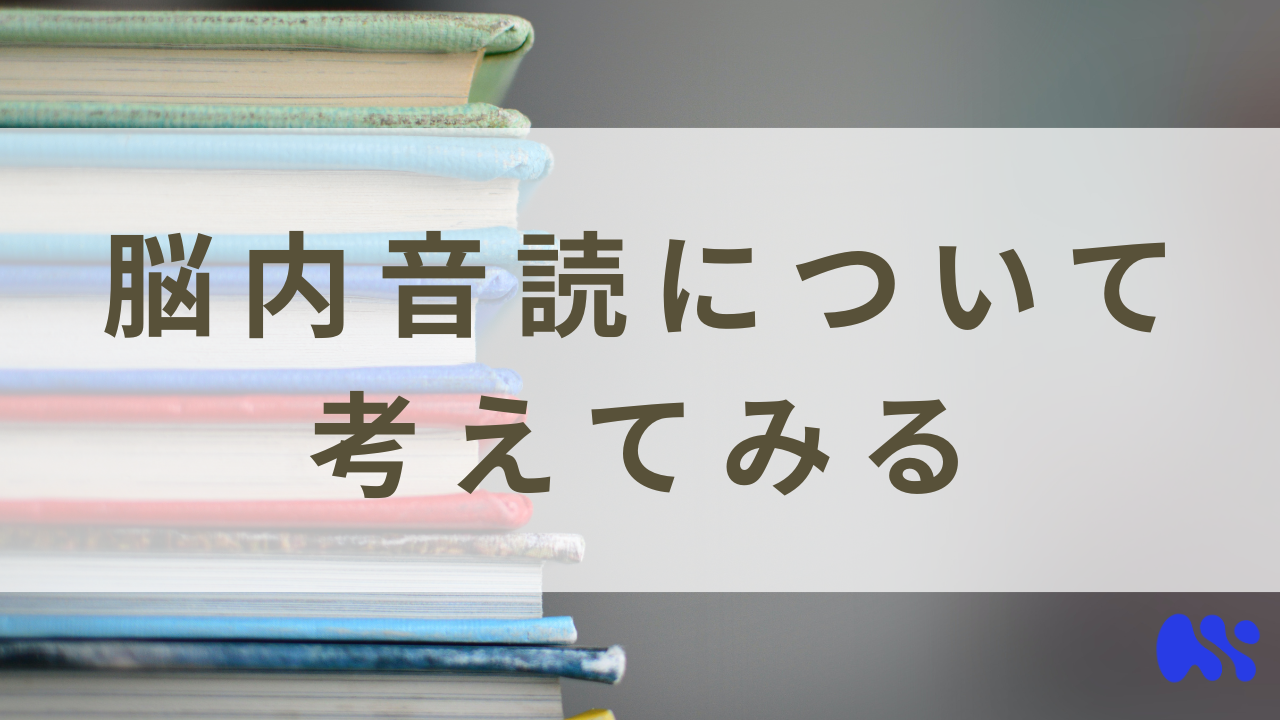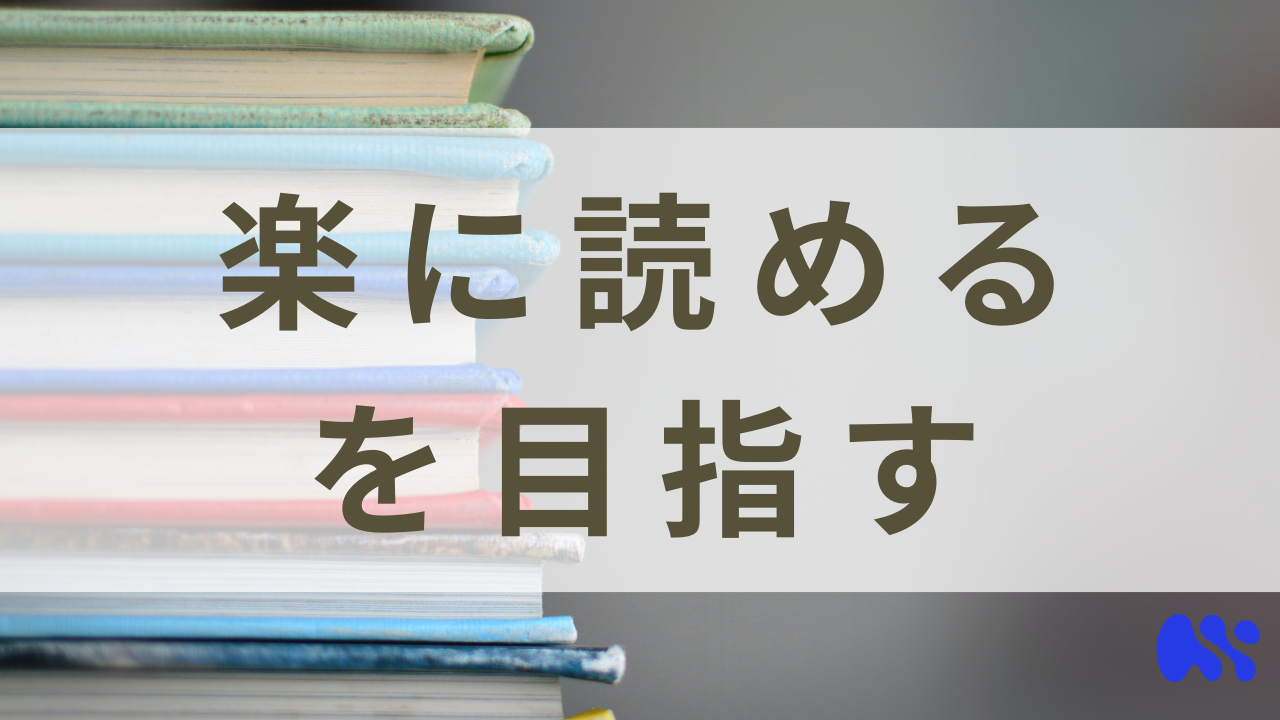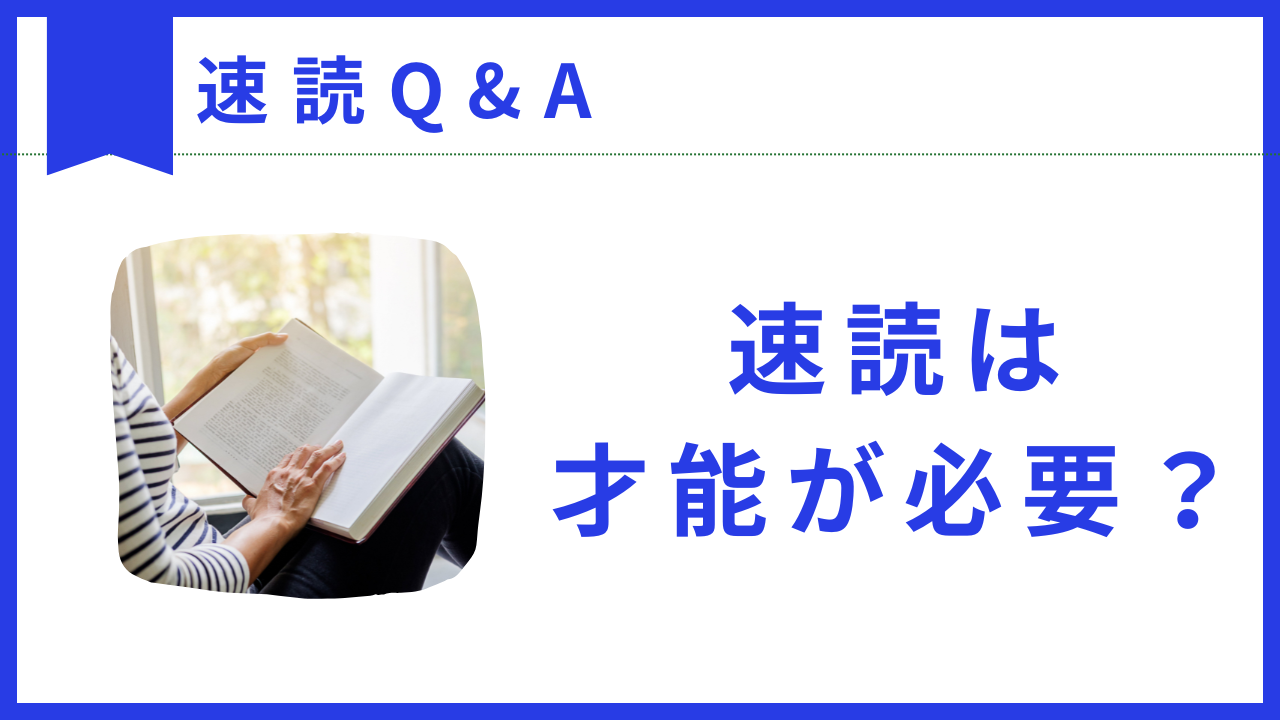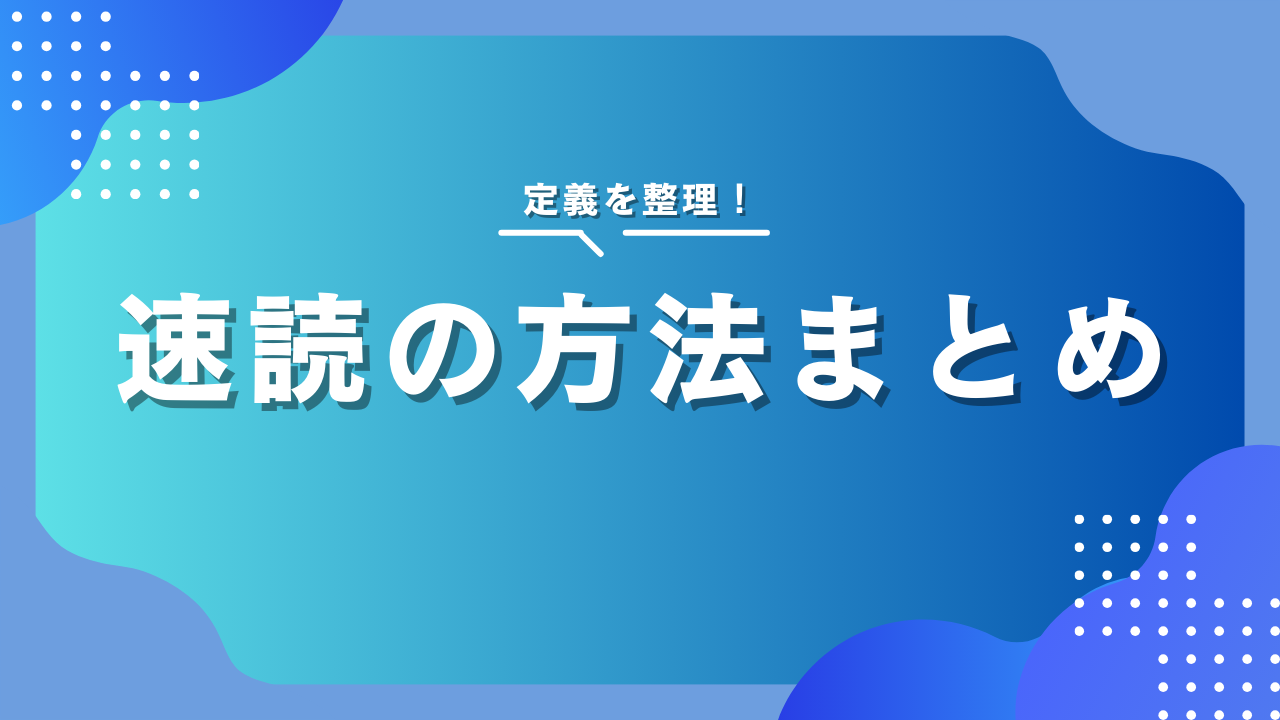
目次
この記事では、速読の方法として紹介されることが多い能力やテクニックの名称を、定義とともにまとめていきます。
速読の方法(能力)
まずはじめに、「そもそも読むという行為には、どのような処理プロセスがあり得るのか」という観点でのご紹介です。
音読
広辞苑での定義は、上記のとおりです。
文字情報を、自分の声で読み上げることで、音声情報として捉え直し、その音声情報をもとに理解を深める読み方です。
「小学校学習指導要領(平成 29 年告示)解説」では、「音読」という単語が、文中に80回も使われており、日本の国語教育において、音読が重要視されていることがわかります。
参考:文部科学省 小学校学習指導要領解説(2023年9月2日閲覧)
音読の際には、文章を目で追い、声に出し、耳で聞く、という複数の作業が同時に行われます。
読むことにくわえて、話す、聞く練習にもなるため、国語だけでなく、英語の勉強法としても取り上げられることが多い読み方です。
速読という観点では、悪者扱いされることが多いですが、音読そのものは、多くのメリットがある読み方だと言えるでしょう。
黙読
黙読は、音読の対義語として位置付けられています。
声を出さずに読んでいれば、頭の中でどのような処理を行なっていても、その読み方は黙読に該当します。
黙読という言葉の定義においては触れられていない、頭の中での処理プロセスに着目すると、
黙読はさらに次の3種類に分類されていきます。
脳内音読(内読・内声化・音声化)
「声には出さないが、頭の中で文字の音を読み上げることで、文章内容を理解する読み方」を、この記事では、脳内音読という言葉で表現しています。
表現の統一がされていない領域であるため、他にも「内読・内声化・音声化」といった表現がされることもありますが、脳内音読と同じ内容を表していると考えて良いでしょう。
訓練を受けていない人が本を読むときには、通常、この脳内音読が用いられます。
視読
視読とは、文字情報を、音に変換することなく理解する読み方です。一定のまとまりで文字を捉えることで、音声情報を介在させることなく、言葉の意味をとります。
視読は、特殊能力ではありません。私たちは文章を読むとき、すでに音読しないまま理解しているのです。
(以下『図解でわかる 速読のすごいコツ』p.33.34 より)
たとえば、本の中に、「フォークを使う」 「フォークボールを投げる」 「フォークダンスを習う」という表現があったとします。 「フォーク」は日本語の表記としては同音ですが、それぞれ異なる意味を持ちます。しかし、実際の私たちは、この文を読むたびに立ち止まって意味を考えることはあまりありません。文脈に合わせて、自然とそれにふさわしい意味を思い浮かべて読み進めることができます。
これは、無意識に、「フォーク」に続く「~を使う」「~ボールを投げる」「~ダンスを習う」という部分を同時に読み取っているからです。 文章の前後関係を目で認識して「フォーク」の理解を助けているため、音読する前に単語を認識できています。
音読せずに内容を理解する力は、本来、誰もが持っている力なので、トレーニングすれば誰でも活用できるようになります。 それでも、音を介してでないと文字を認識できないと思ってしまうのは、これまで慣れ親しんできた音読の習慣のせいでしょう。 音読にはたくさんのよい点がありますが、文章を速く認識する観点では、むしろ遅読の原因になります。
フォトリーディング
フォトリーディングとは、以下の英単語を組み合わせた和製英語です。
カメラで写真を撮るように、大量の文章を一瞬で理解する読み方とされています。
言葉の成り立ちから「写真記憶・映像記憶」と呼ばれる能力と、関係があることがわかります。
画像処理のプロセスが含まれている点で、これまでに紹介した読み方とは、根本的に異なります。
速読の方法(テクニック)
ここからは、速読のコツとして取り上げられることの多い、7つのテクニックをご紹介していきます(便宜上、読書を前提として執筆しております)。
スキミング
スキミングとは、英単語の動詞「skim」に由来する言葉です。
言葉の定義からもわかるように、精度を落としながらも、スピードを優先して読む技術を指します。
文章のおおまかな内容を把握したいときに、役立つテクニックとされます。
スキャンニング
スキャンニングとは、英単語の動詞「scan」に由来する言葉です。
二つ目の「〜をざっと見る」という意味は、スキミングとかなり似ています。
しかし、一つ目の意味に注目すると、特定の情報だけを集中して探すという独自のニュアンスが含まれていることがわかります。
ここにスキミングとの違いがあると言えるでしょう。
見出し読み
見出し読みとは、「見出し」と「読む」という二つの言葉をつなげた造語です。
広辞苑より
見出しを丁寧に読むことで、そのあとに続く文章内容を受け入れるための、頭の準備をすることができます。
読むスピードを上げるためだけでなく、文章内容を整理しながら読む上でも役に立つテクニックとして紹介されることが多いです。
もくじ読み
もくじ読みとは、「もくじ」と「読む」という二つの言葉をつなげた造語です。
定義の中に「見出し」という表現が使われていることからも、もくじ読みと見出し読みとの関連性の高さがわかります。
もくじは、書物全体の設計図のような役割を果たします。
見出しと同様、速読だけでなくスムーズな情報整理にも役立つテクニックとされます。
漢字に注目
文字には、文字単体では音しか表すことができない「表音文字」と、文字単体で意味を表す「表意文字」の2種類があります。
アルファベットや平仮名は表音文字、漢字は表意文字に該当します。
1文字あたりの情報量は、表意文字の方が多くなります。
「漢字に注目」とは、文章中に使われている漢字に意識を向けながら読む手法です。
表意文字の特徴を活かした読み方と言えるでしょう。
接続詞に注目
接続詞とは、品詞(文法上の性質や振舞いに基づく語の分類)の一種であり、文と文を接続する役割を果たします。
具体的には「また」「そして」「なぜなら」「しかし」などが該当します。
種類によって働きが異なりますが、接続詞に注目することで、文章の展開を予測することができます。
先を予測できることは、そのまま読書速度の向上に寄与するでしょう。
繰り返し読む
同じ本を繰り返し読むことでも、読書速度は上がっていきます。
「なかなか読み進めることができなかった参考書が、使い続けているうちに、スラスラと読めるようになった」
こうした経験をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
教科書や参考書などを何度も回転させることは、科目によっては、有効な勉強法の一つになります。
クリエイト速読スクールの考え方
当スクールの速読プログラムは、テクニックの習得ではなく、能力の底上げを目指すカリキュラムとなっています。
読書速度だけでなく、総合的能力の向上を意図したプログラムです。努力を重ねた分だけ、しっかりと成果が収穫できる設計となっています。
どのようなトレーニングを行い、どのような成果をあげているのか。どうぞ、当ブログの「受講生の声」カテゴリをご一読ください。
この記事のタグ
劉 智秀 1999年東京都生まれ/栄東中学・高等学校/東京大学経済学部卒/クリエイト速読スクール二代目代表