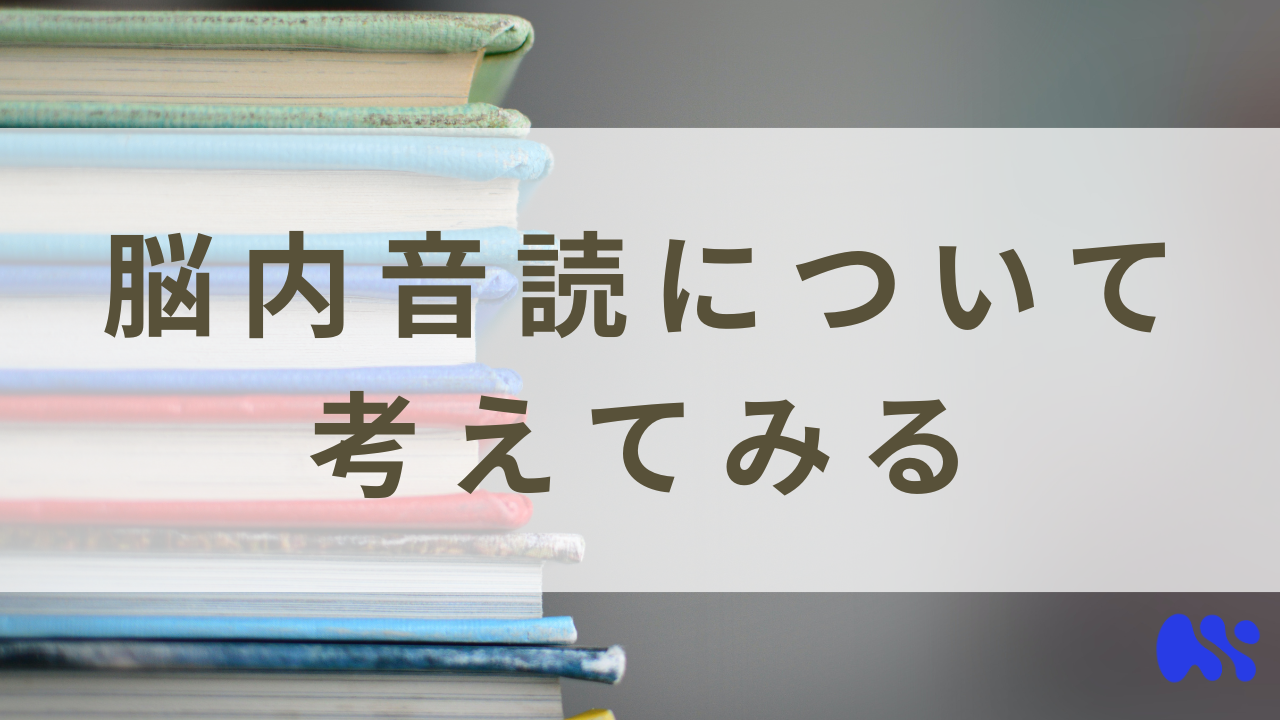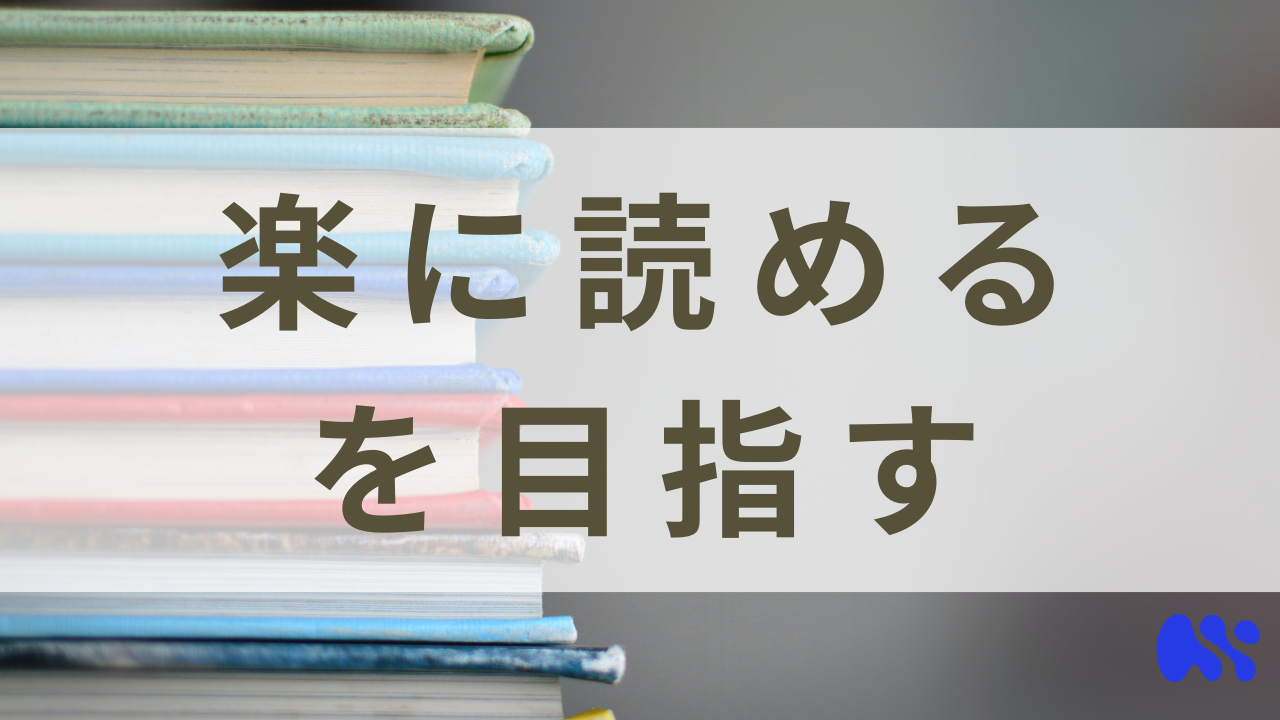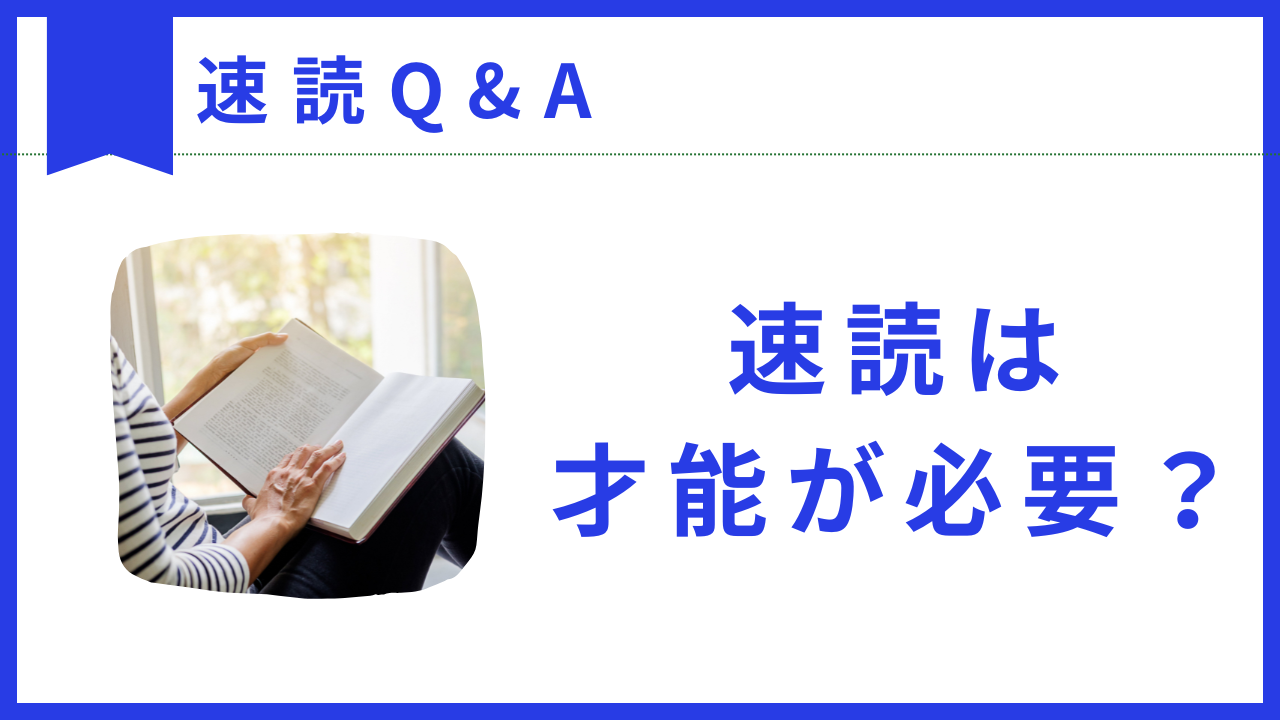目次
この記事では、『キャリアが高まる1日15分速読勉強法』に掲載された、瀧本哲史さんによる寄稿文「BTRメソッドで7つの能力をフル装備」を、一部編集の上ご紹介しています。出版物の詳細についてはこちらをご確認ください。
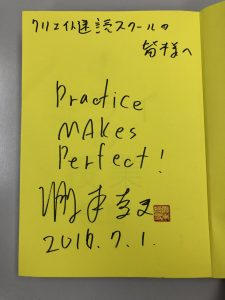
瀧本 哲史
クリエイトの速読の出発点
みなさんは普段、本を読むという行為がどのように行われているか、意識したことがあるでしょうか?
気がつけば日本語が話せていたように、読むことに対しても、とくに意識をしたことはないという人がほとんどだと思います。
しかし、読書が得意な人とそうでない人がいること、読書が好きな人とそうでない人がいることを考えれば、何らかの要素が読む能力に差を与えていることがわかります。
その要素を分析し、トレーニングしようというのが、クリエイト速読スクールの出発点なのです。
読むのが遅い原因は人それぞれ
読む能力とは何でしょうか。これは読書が苦手な人について考えるとわかりやすいと思います。
たとえば、文章を読むときに一言一句にこだわり、読むのにやたら時間がかかる人。これは、生真面目な性格というだけでなく認知視野が狭いことも影響しています。
認知視野が狭いと、脳のなかに一度に入る情報量が少なくなるため、どうしても本を読むのが遅くなります。そうなると、書かれていることの全体像がつかみにくくなります。
本は、いくつかの「文章」が固まり「段落」となり、「段落」がまとまり「節」をなし、「節」を束ねた「章」で1冊が構成されています。この構成をいかに効率的に把握するかが、スムーズな読書を行うカギとなります。
また、読んでいる最中に集中力が途切れ、気づけば字面を追っているだけの人もいるかもしれません。これは、書かれていることがイメージとして浮かばない、あるいは書かれていることを論理的に構成できない、といったことが原因になっています。
このような要素が、スムーズな読書を阻むのです。
やっかいなのは、読むことに必要な要素が何か1つ欠けるだけで、苦手意識を抱き、読書から遠ざかってしまう危険性があること。そうなると、日常的に読書トレーニングが行われないから、さらに読む能力が弱くなるという「遅読のスパイラル」に陥ってしまいます。
この悪循環を断ち切る処方箋が、BTRメソッドなのです。
「本を読む」力のトレーニング
BTRメソッドとは、Basic Training for Readers methodの略で「読書をする人のための基礎的訓練法」という意味です。
「本を読む」という行為に対して、さまざまな角度からアプローチをすることで、より速く、より正確に書かれている内容を理解することを目的としています。
読書をすることは、仕事をするときに求められる能力を鍛えることにも密接につながっています。
具体的には集中力、記憶力、想像力、発想力、論理力、時間管理能力、情報処理能力の7つの能力です。
読書する能力を鍛えるBTRメソッドは、これらの能力をアップグレードするトレーニング方法でもあります。
大人の習い事になぜ速読が良いのか?
理由その1.「速さ」と「理解」を両立するトレーニングだから
速く読めればそれでよいのか?
ひと口に「速読」といっても、世の中にはさまざまなメソッドがあります。そのなかには、やみくもに速さを求めるものも少なくありません。
もちろん、速く読めるようになるに越したことはないでしょうが、理解が追いつかなくては意味がありません。
ビジネスパーソンは、本に書いてある内容を知りたくて読むのです。速く読めても内容が素通りしていく状態では、本末転倒といえるでしょう。
BTRメソッドにおいては、速さとともに、理解度も重視したトレーニングを行っています。そこが、キャリアアップに効く第一の理由なのです。
読書をするときの3つのプロセス
速度と理解を両立するには、読書の3つのプロセスをバランスよく改善しなければいけません。すなわち「認知→情報処理→記憶」です。コンピュータでいえば、「入力装置(キーボード、スキャナ)→CPU→ハードディスク」です。この「情報処理(CPU)→記憶(ハードディスク)」にあたる部分が、理解度に関係しています。
速さばかりを追求する速読メソッドのトレーニング内容を見ると、認知視野を鍛えることだけに注力しているものが多いのです。その結果、たしかに認知の範囲は広く取れるようになります。しかし、情報処理と記憶が追いつかないために、逆に理解度が下がってしまいます。まさに、パソコンにたくさんの情報をインプットしたら、処理がおいつかずフリーズしてしまう状態です。同じことが脳内で起こっているのです。
自分の弱点を知りバランスよく鍛える
BTRメソッドでは、3つのプロセスをすべて鍛えるトレーニングメニューがそろっています。具体的には、認知(キーボード、スキャナ)視野拡大のトレーニングに関しては、「サッケイドシート」「ヘルマンシート」「ミディアムシート」「ランダムシート」「パターンシート」「ユニットブック」。情報処理能力(CPU)をアップするためにイメージ処理や論理関係をスピーディに判断する力を鍛える「スピードボード」「ロジカルテスト」。記憶力(ハードディスク)をアップする「イメージ記憶」「イメージ読み」などが、それにあたります。
さらにBTRメソッドでは、これらのトレーニング後、すべてをスムーズにつなぐ「倍速読書トレーニング」がプログラムされています。コンピュータにたとえれば、OSにあたります。コンピュータでも、CPUだけをバージョンアップしても全体のパフォーマンスはよくなりません。それと同様に、「認知→情報処理→記憶」のすべてを鍛え、さらに、つないで使えないと意味がないのです。
トレーニングでは、成績を計測しながら進めていくので、自分の強み、弱みが確認できるようになります。
読書の効率は、認知、情報処理、記憶の掛け算で決まりますので、弱みを補強したり、強みをさらに伸ばすことで、読書の効率を上げることができます。弱みを補強することで、強みをいっそう活用できるようになりますし、強みをさらに伸ばすことで、弱みをカバーするという戦略もあります。
とくに、最初のうちはなかなか弱みが改善できずに焦りを感じるかもしれません。しかし、強みを伸ばしていくうちに、トレーニング効果を実感し、余裕をもって本を読めるようになることで、あとからだんだんと弱みが改善されていくというプロセスを経るのがほとんどのケースです。
理由その2.速く読めることと、生産性の向上には相関があるから
どんな仕事にも読む作業がある
資料を読み込んでのリサーチ・企画立案、レポート作成、膨大な報告書のチェック、等々。
ナレッジワーカーと称される人々の業務は、業種を問わず、文字情報との格闘が大半を占めているといっても過言ではありません。
近年ではITが発達し、以前なら電話でやりとりしていたこともメールで済ませることが増えてきました。そうなると、サービス業に従事する人やスキルワーカーなど、比較的文字情報を扱うことが少ない業種でも、その処理と無縁ではいられません。取引先とのメール連絡などを考慮すると、少なくとも業務の30%くらいは文字情報の処理を行っていると思います。
仮にあなたが、BTRメソッドのトレーニングを通じて3倍の速さで文字情報を処理できるようになったとして計算してみます。
業務の30%にあたる文字情報の処理が3分の1の時間でできるようになるわけです。すると、それだけでも25%も生産性が改善したことになります。
当然のことながら、文字情報を取り扱う割合が高い業務の人は、25%といわず、それ以上もの効果が期待できるわけです。このことが、最も短期で実感できるBTRメソッドのキャリアに対する効果です。
資格試験などスキルアップに役立つ
次に中期的に見ると、資格取得に役立つという効果があります。BTRメソッドを開発したクリエイト速読スクールでは、多くの難関資格試験の合格者を輩出していますが、もちろんそれも偶然ではありません。
「速さ」と「理解」を両立するBTRメソッドだからこそ、資格試験のためのテキストを効率的に深く勉強することができます。イメージ記憶は、直接、暗記力を鍛えるトレーニングになっています。
試験本番でも、BTRメソッドは効果を発揮します。試験はほとんどが文字情報の処理であることを考えれば、それも当然のことです。
ビジネス競争が激化し、企業が終身雇用や安定を約束できなくなった現代。これからは業務を効率的に処理して時間をつくり、スキルアップのために勉強し、ビジネスパーソンとしての市場価値を高めていく必要があるでしょう。
マネジメントに必要な知識やノウハウを蓄積できる
業務を効率的にこなし、スキルアップにも余念がない。そんなビジネスパーソンなら、順調にキャリアの階段を上っていくでしょう。そうして、マネジメントクラスに立っととき、強く実感できるBTRメソッドの効果があります。
それは、速読によって読書が習慣化したことによって得られる、知識やノウハウの蓄積です。マネジメントは、業務に精通しているだけでは通用しなくなっています。部下を束ね、組織を運営していくには、総合的な力が求められるケースも多くなります。
総合的な力とは、幅広い知識と経験を地道に積み重ねることで養われていくものです。しかし、どんなに懸命に生きてきたとしても、個人が経験から学べることはたかが知れています。それを効率的に補う手段の1つが読書です。読書を通じてなら、いつでも、どこでも、ありとあらゆる分野から学ぶことができます。
豊富なインプットがなければ、優れたアウトプットなど出しようがありません。
読書による知識やノウハウ、経験の蓄積は、長い目で見れば大きな差となって帰ってきます。
プロイセン王国の宰相ビスマルクの言葉に「賢者は歴史から学び、愚者は経験から学ぶ」というものがあります。
短時間に本を読み重ね、他者の思考や経験を疑似体験し、自分の経験にフィードバックしていくことは、最も学習効率が高いものになるといえます。
理由その3.ビジネスパーソンが続けられるよう設計されているから
トレーニングが続かないと意味がない
どんなに優れた効果をもつトレーニングだとしても、続けられなくては意味がありません。BTRメソッドとは、いわばアスリートが競技で優れたパフォーマンスを発揮するための、体力トレーニングです。ビジネスパーソンが、それぞれの分野でよいパフォーマンスをあげるために行う、頭脳トレーニングなのです。
体力トレーニングを1日、2日やったところで、効果は出ません。1か月、2か月と継続することによって、初めて効果が実感できるようになります。BTRメソッドも同じです。このようなトレーニングでは、忙しいビジネスパーソンが無理なく続けられるしくみが不可欠です。
スキマ時間を使ってできるトレーニングメニュー
今回、本誌でご紹介するBTRメソッドは、1セットが15分〜40分程度でできるように構成されています。どんなに忙しい人でも、この本をバッグに忍ばせておけば、ちょっとしたスキマ時間にトレーニングをすることができます。
文字を読む速さを鍛えるためのトレーニングなので、時間を意識して進めるのがポイントです。1分、2分と意識をしているうちに、濃い時間の使い方ができるようになり、時間感覚も研ぎ澄まされていきます。
このように短時間集中するトレーニングを繰り返すと、そのほかの勉強をするときでも、スキマ時間を有効に活用できるようになります。そして、スキマ時間を有効に活用できるようになるということは、”継続する仕組み”を自分のなかにつくれたということです。
成果が数値化され、一目瞭然。モチベーションがアップ
BTRメソッドでは、各トレーニングの進捗が数値化されているので、定量的に管理することが可能です。また、読書を効率化するためのKPI(Key Performance Indicators:目標の達成度を計るための評価指標)と、それを改善するためのトレーニングがうまくリンクしています。これにより、自分の弱点を発見し、弱点のトレーニングを的確に行い、改善結果を実感するという「PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクル」を確実に回すことができます。
これは、トレーニングを続けるモチベーションを維持するためにも有効です。毎日、1項目だけでも自分の新記録が更新できれば、達成感を味わうことができます。スポーツジムも「タイムが短縮できた」「体脂肪率が減った」「いままで上げられなかったウェイトが楽に上げられた」……、と実感できるからこそ続くものです。
ゲーム感覚で楽しめる飽きがこないトレーニング
BTRメソッドのトレーニングの長所は、ゲーム感覚で楽しめることです。実際やってみると、1つひとつのトレーニングが楽しくて、飽きがきません。無理せず継続できるばかりでなく、「もっといい成績を出したい」「やらないと、なんとなく気持ち悪い」というようになっていき、ある種の常習性があります。
そうなると、「楽しいけど、これで本当に成果がでるのあろうか?」と疑問も湧いてきますが、大丈夫です。すべてが認知能力、情報処理能力、記憶力の改善につながるトレーニングですから、楽しみながらキャリアアップに必要な7つの能力を鍛えていくことができているのです。
トレーニング後には、脳が心地よく疲労しているのがわかります。それは、スポーツジムで運動をしたあと爽快な気分になるのと似ています。脳のいつも使っていない部分が活性化される感覚を、ぜひ、読者の皆さんにも体験していただきたいと思います。
『キャリアが高まる1日15分速読勉強法』(日本実業出版社)所収
瀧本 哲史(たきもと てつふみ)さん
この記事のタグ
劉 智秀 1999年東京都生まれ/栄東中学・高等学校/東京大学経済学部卒/クリエイト速読スクール二代目代表