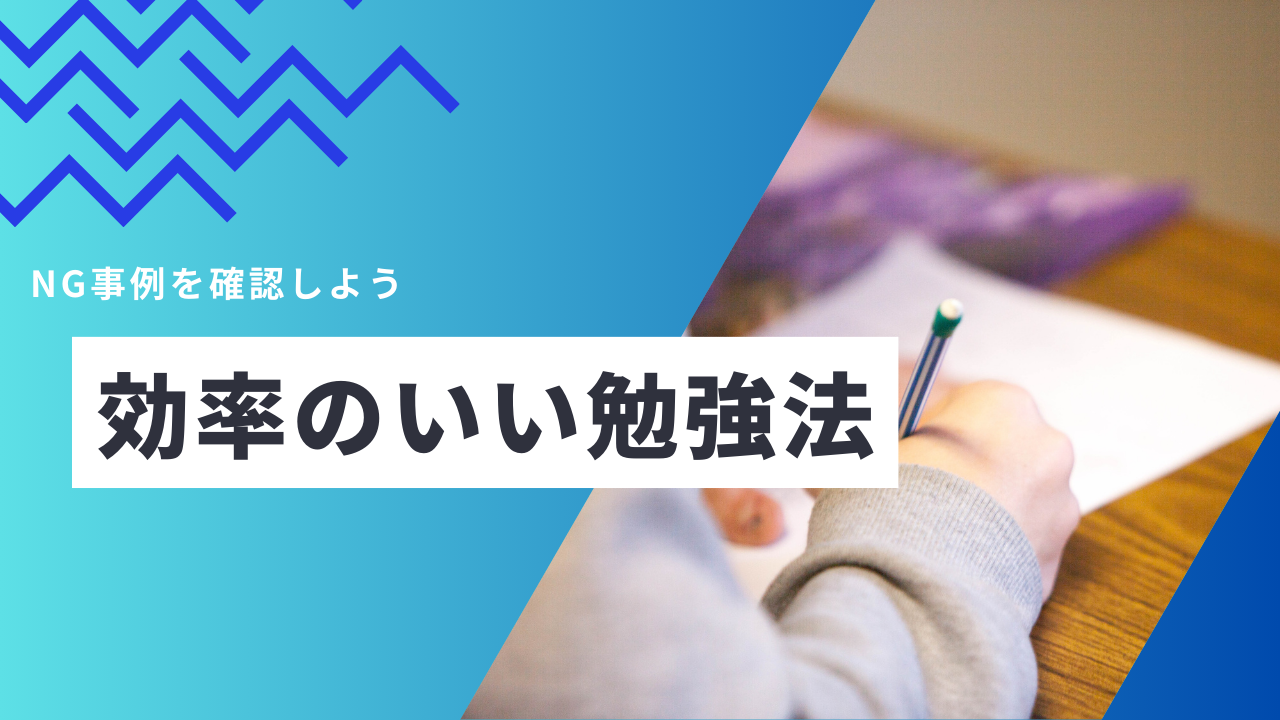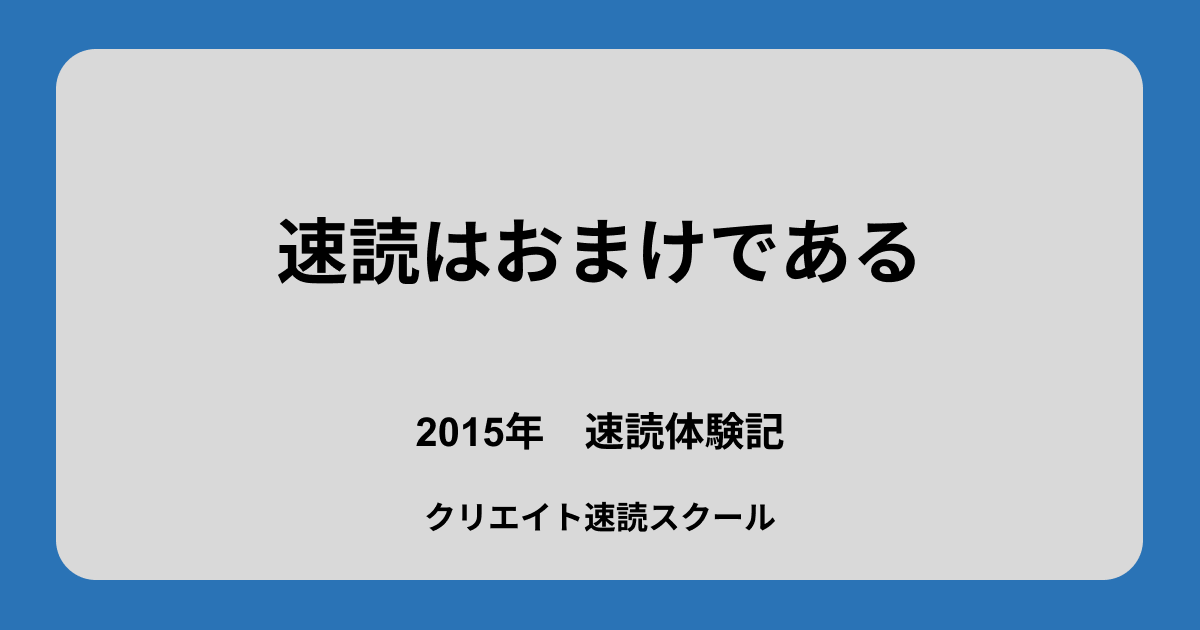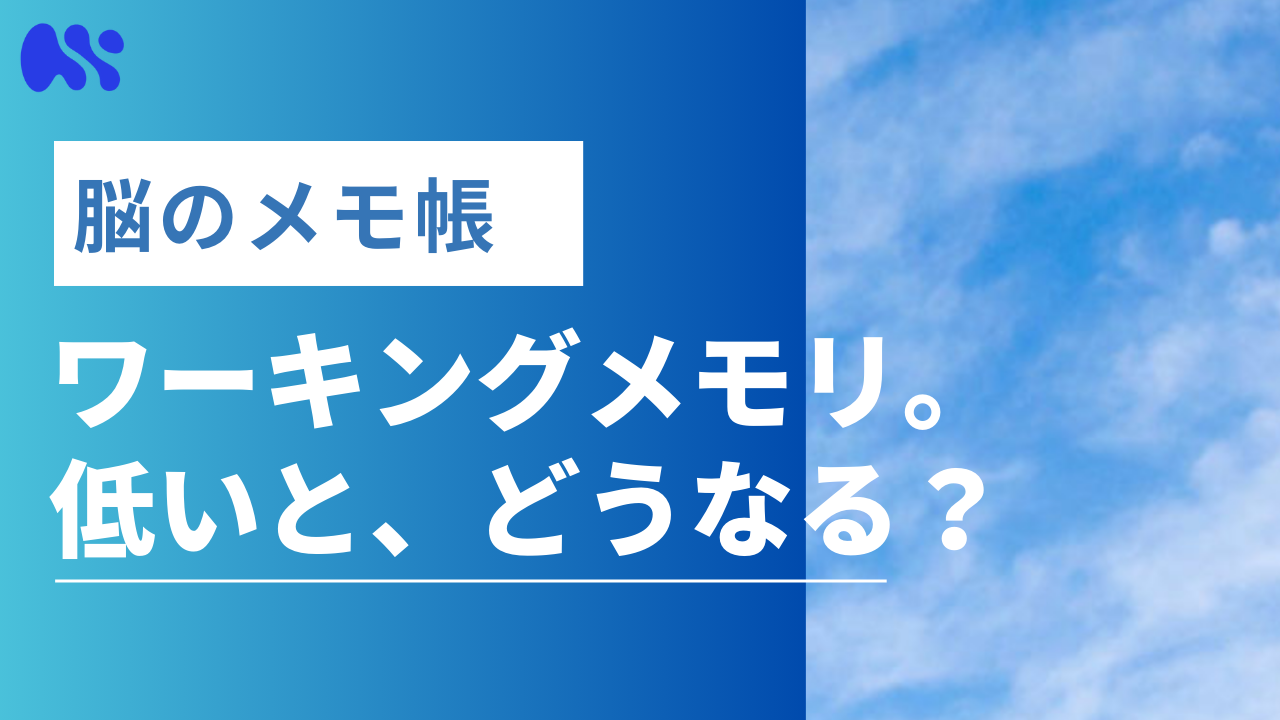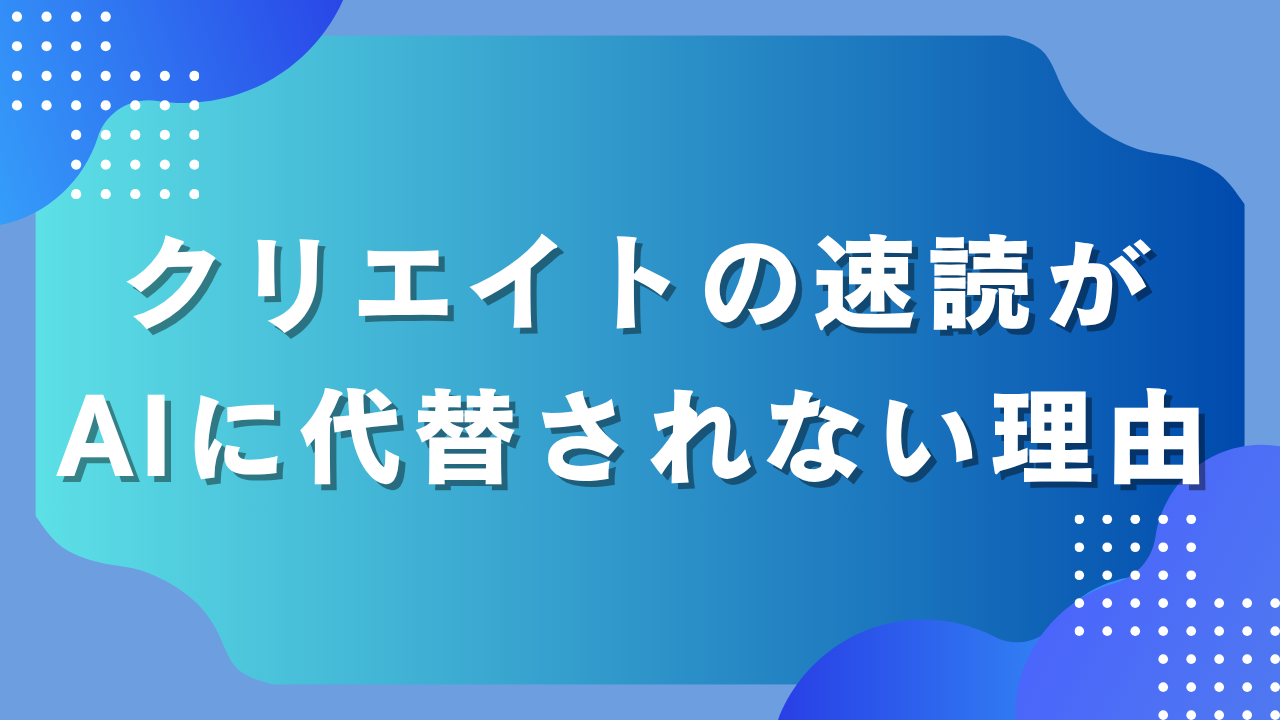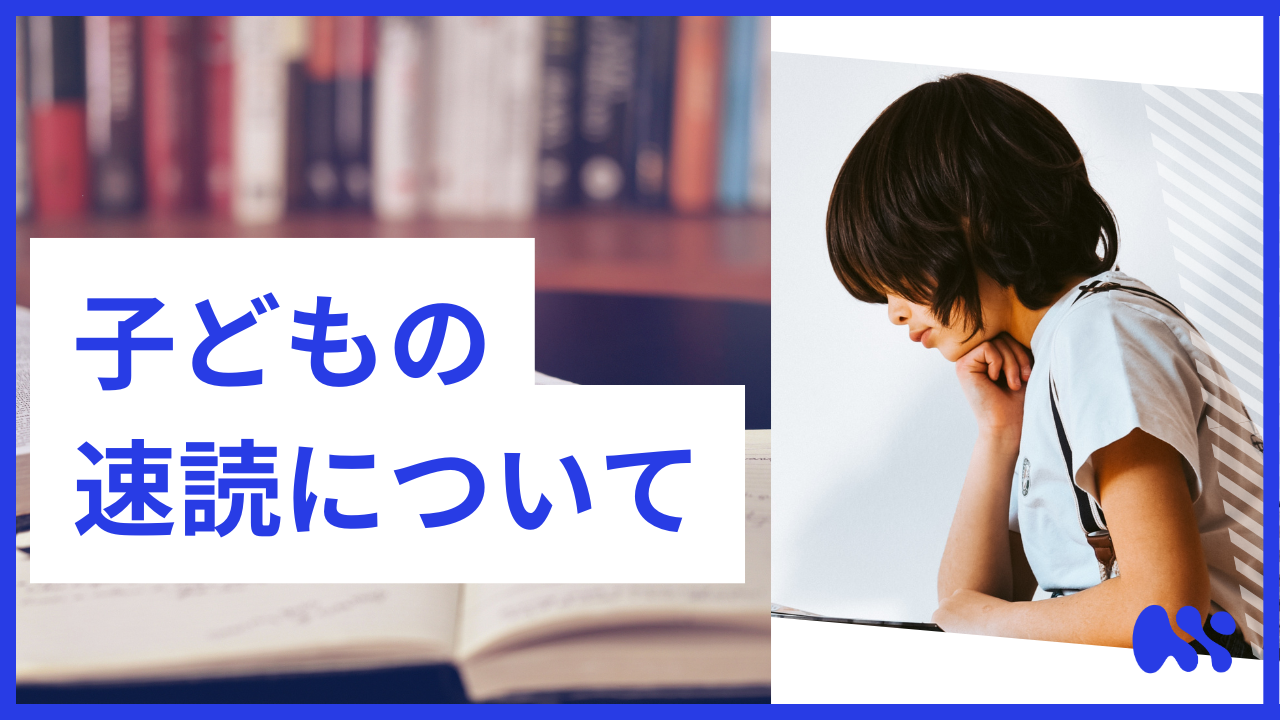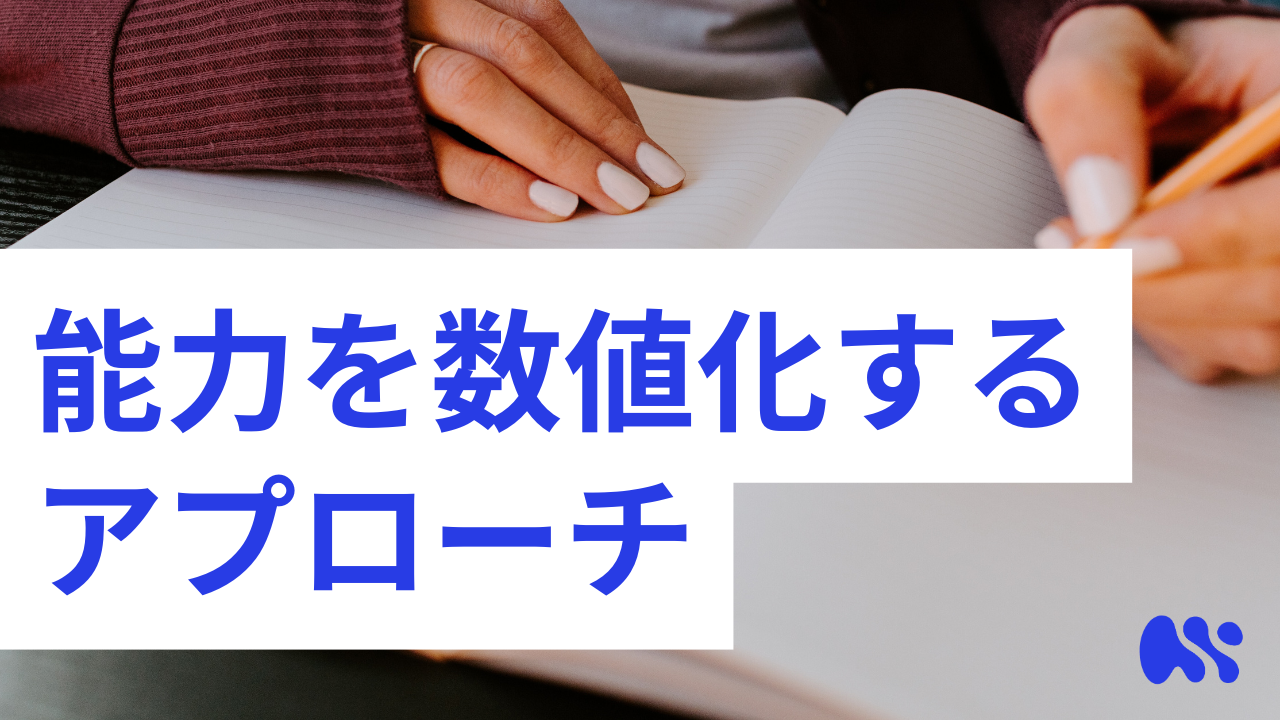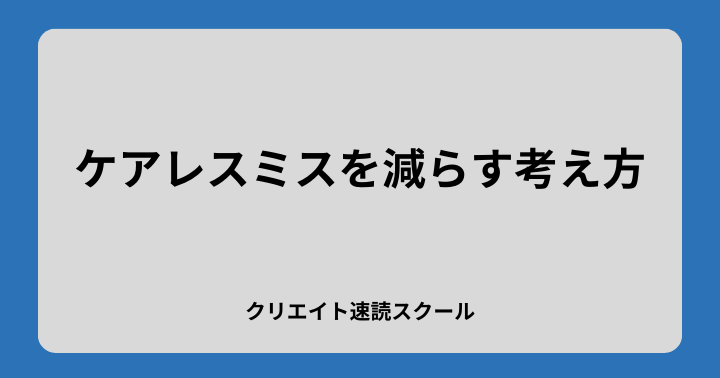
目次
この記事では、ケアレスミスが多い人の特徴と対策についてご紹介しています。
ケアレスミスとは
大辞泉より
ケアレスミスは、本来であれば防げたはずの間違いや失敗を指します。
ケアレスミスが多い人の特徴
思い込みが激しい
思い込みは、問題文や指示を的確に捉えることを妨げ、ケアレスミスの原因となります。
「自分は間違っているはずがない」という思い込みがあると、たとえ見直しを行ったとしてもケアレスミスは防げません。
見直しを行う際は、どこかにミスがある前提で、確認をすることが大切です。
焦っている
焦っている状況では、細部にまで注意を払う余裕が失われ、ケアレスミスをしてしまいます。
本番を迎える前に、十分な準備を行うことで、焦りは軽減することができます。
体調がすぐれない
ケアレスミスは、睡眠不足や発熱など、体調不良が原因となることも多いです。
体調不良は、集中力や判断力の低下を引き起こし、問題文の誤読や計算ミスなどに繋がります。
試験直前期は、勉強と同時に、体調管理にも気を配りましょう。
よくあるケアレスミスの原因
問題を読み違えてしまう
問題の指示を読み違えることで起きるケアレスミスです。
たとえば、問題文では「誤っているものを選択せよ」と指示があるにもかかわらず、正しいものを選択してしまうといった場合です。
解答欄を間違えてしまう
解答欄を間違えるケアレスミスは、特にマークシート形式のテストでよく見られます。
一つずれた場所に解答を記入してしまう、または複数の問題に対して同じ解答欄を使用してしまう、などがあります。
文字を書き違えてしまう
誤った文字を書いてしまう場合です。
この種のミスには漢字や英単語のスペルに多いです。形が似ている漢字、綴りが似ている英単語には注意が必要です。
簡単な処理のミス
計算ミスや、十分性の確認不足など、簡単な処理のミスも、ケアレスミスの代表格として挙げられるでしょう。
ケアレスミスを減らす「しくみ」を作ろう
ケアレスミスとは、ケア(care)が足りていない(less)がゆえに発生するものですから、的確なケアを行うことさえできれば、確実に数を減らすことができます。
ここからは、具体的なケアの方法を紹介していきます。
ミスのパターンを把握→自分ルールを作る
ケアレスミスを防ぐ効果的な方法は、自分がどのようなミスを繰り返しているのかを把握することです。
ケアレスミスは特定の状況や条件下で頻繁に発生することが多く、これらのミスは個々の癖や思考パターンに原因があります。
そのため、犯してしまうミスのパターンを把握し、注意を向けることでケアレスミスをぐっと減らすことができます。
筆者は「2+3=6」といったように、簡単な足し算を、反射的に九九に変換してしまう計算ミスが多かったのですが、一度ミスのパターンを認識したうえで、「一桁同士の計算が出たときは、足し算と掛け算の混同に注意する」というルールを設けたところ、急激に数を減らすことができました。
自分のミスのパターンにあわせた、見直しのしくみを作ることに挑戦してみましょう。
見直しをする時間を設ける
ケアレスミスを減らすためのしくみとして、見直しの時間を設けてみましょう。
試験最後の1.2分を見直しに充てるだけでも、十分な効果が見込めます。
問題文は特に丁寧に読む
試験は時間との戦いでもあるため、一言一句を丁寧に読むことは、現実的ではありません。
そこでおすすめなのが、問題文だけを、特に丁寧に読む手法です。
問題の指示を的確に把握することは、ミスを減らすだけでなく、解答に不要な思考プロセスを排除するうえでも大切です。
睡眠をしっかりとる
試験前日は徹夜をしたくなりがちですが、ケアレスミスを防ぐという観点からは、おすすめできません。
睡眠不足は情報処理能力の低下に直結することは、経験的にも納得される方が多いと思います。
当スクールでは、情報処理能力を鍛える脳トレを提供していますが、「睡眠が足りない日はスコアが下がった」という感想が散見されます。
大事な試験の前は、しっかりと睡眠をとることを心がけましょう。
参考:西野 精治, 2017年3月, サンマーク出版, 『スタンフォード式 最高の睡眠』
勉強に集中するために
「そもそも勉強に集中することができない」という方には、以下の記事がおすすめです。
ぜひご一読ください。
この記事のタグ
劉 智秀 1999年東京都生まれ/栄東中学・高等学校/東京大学経済学部卒/クリエイト速読スクール二代目代表