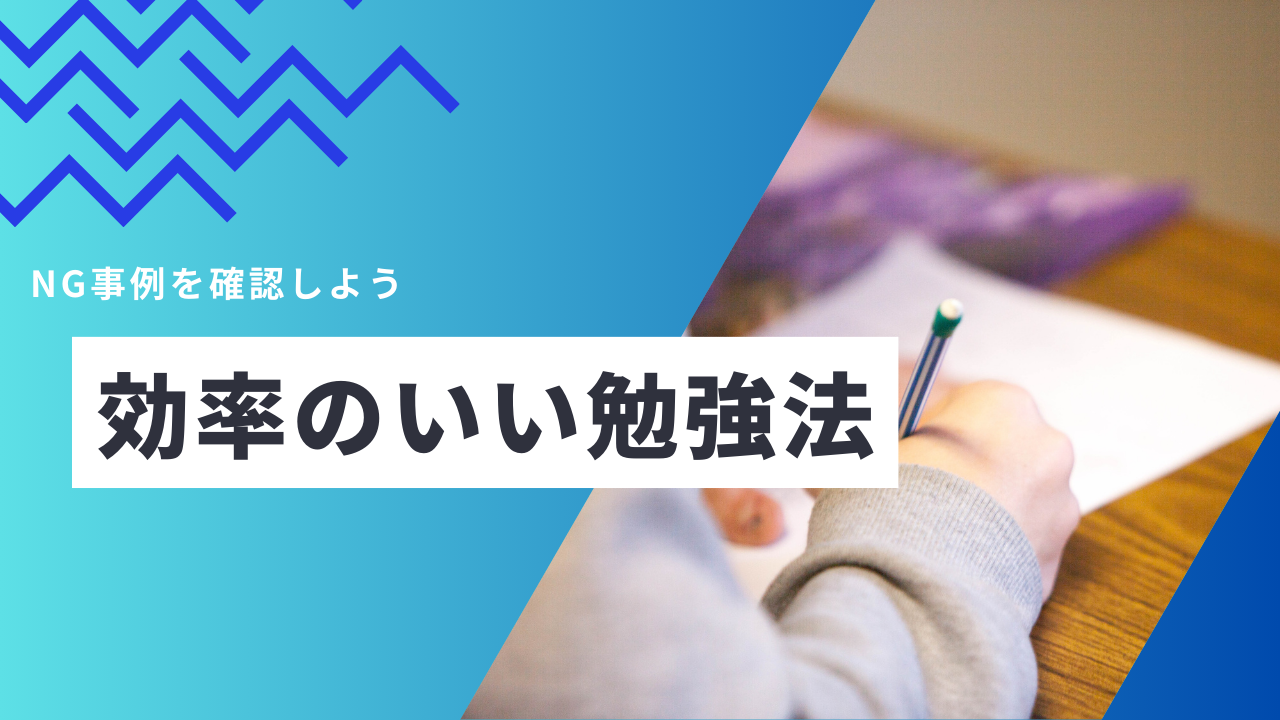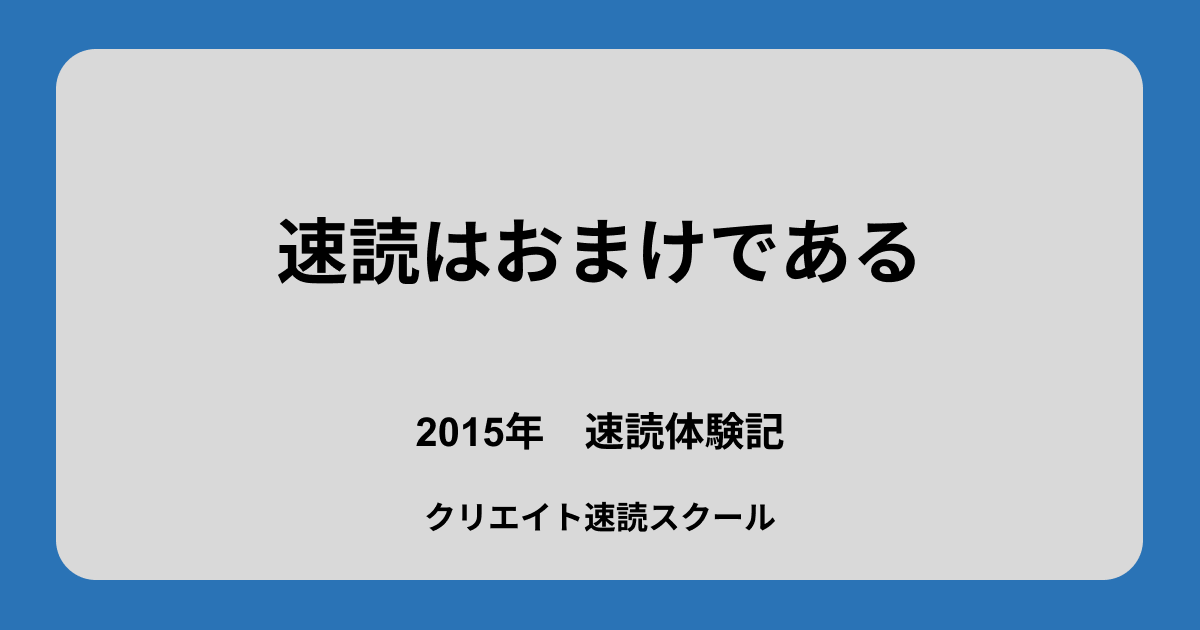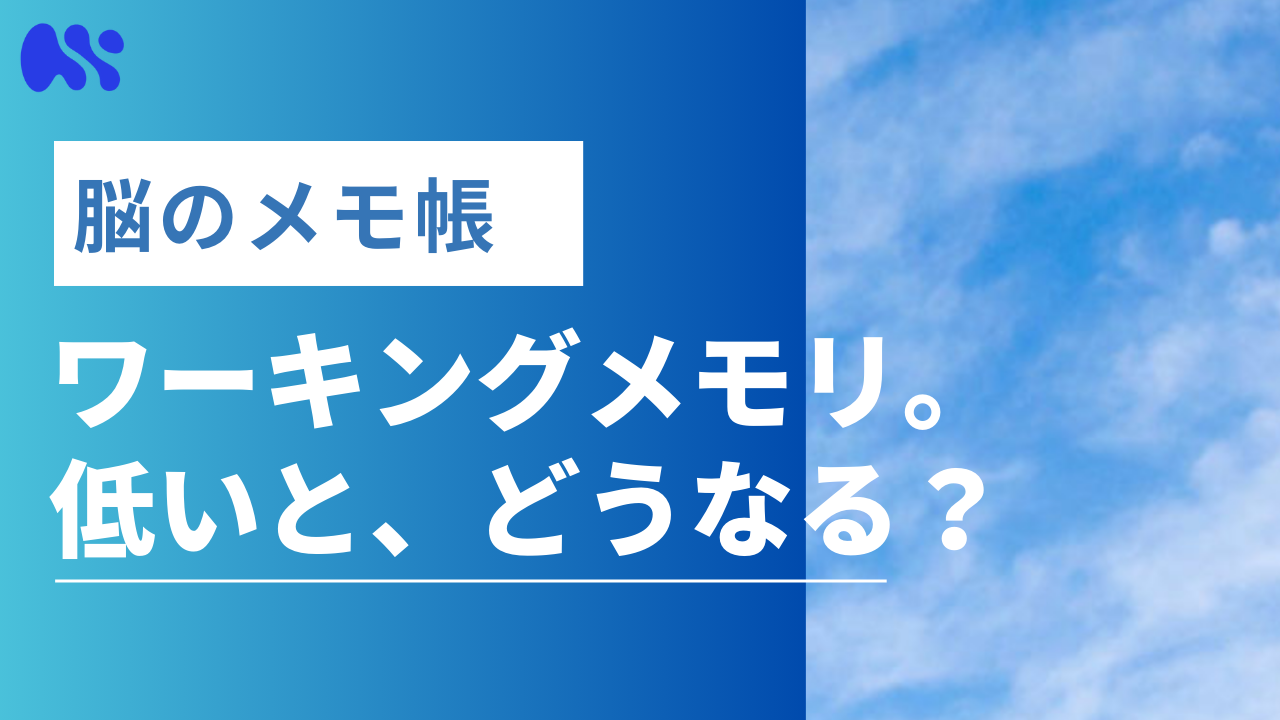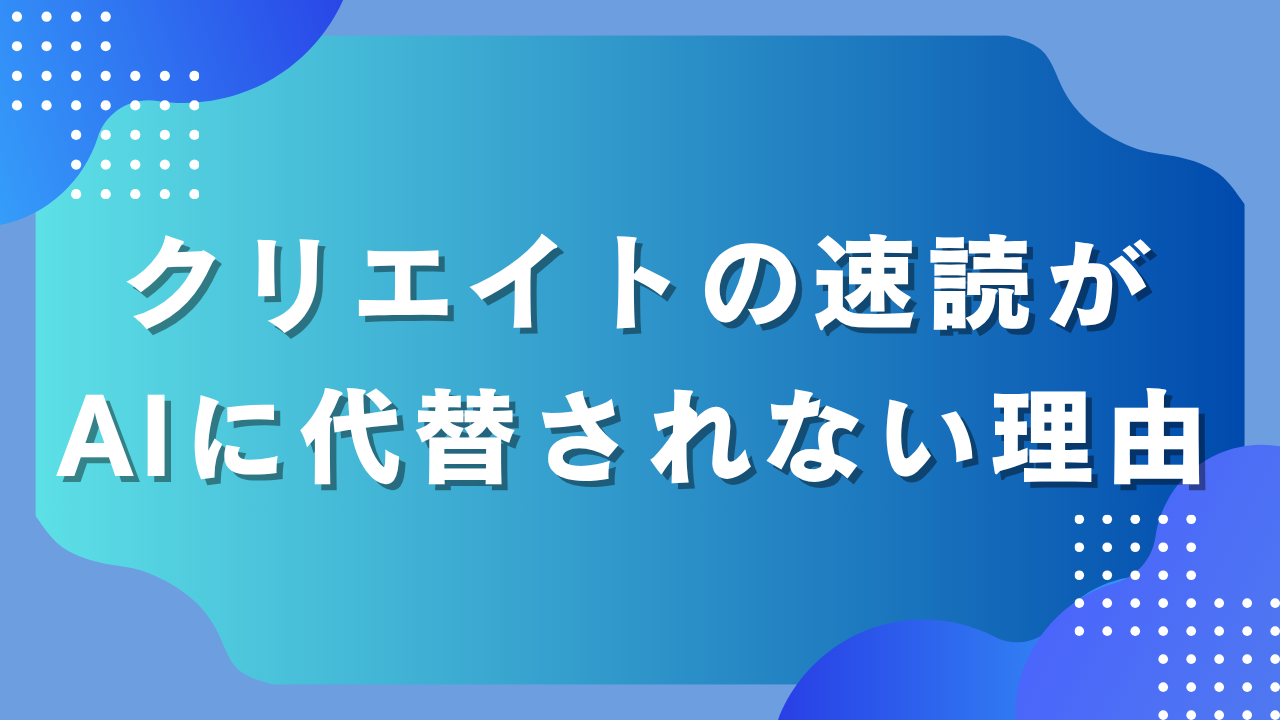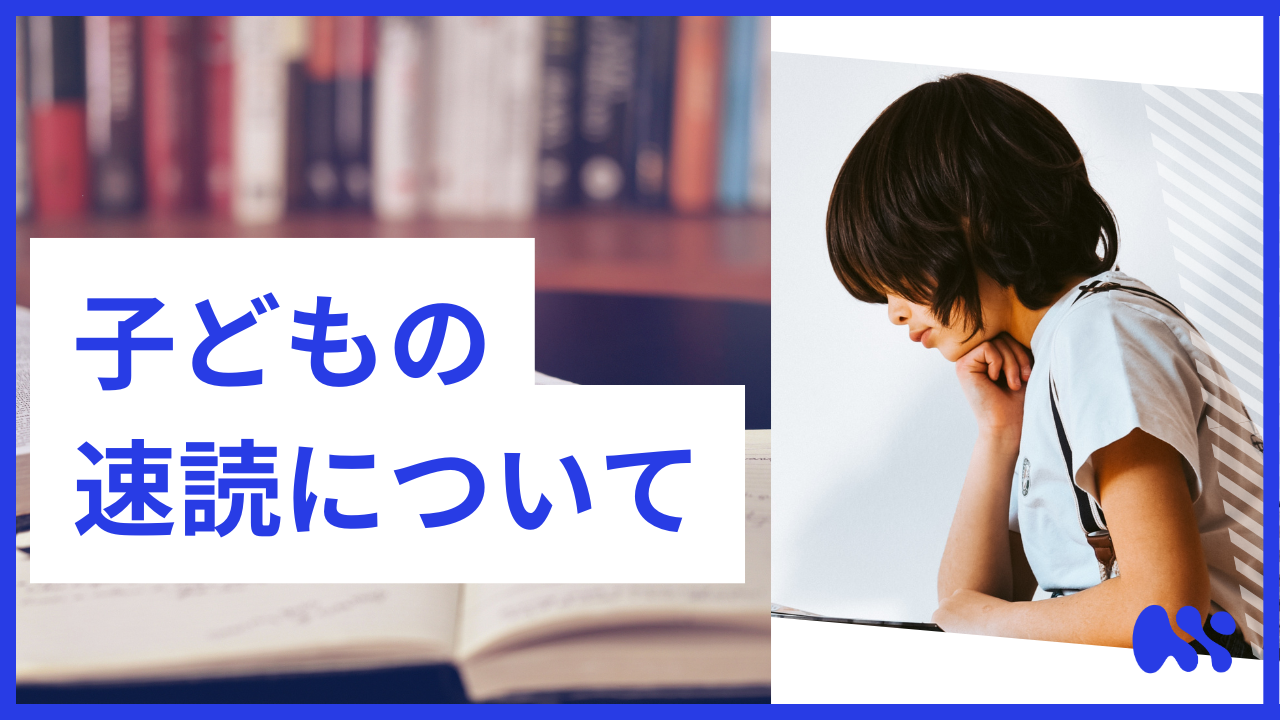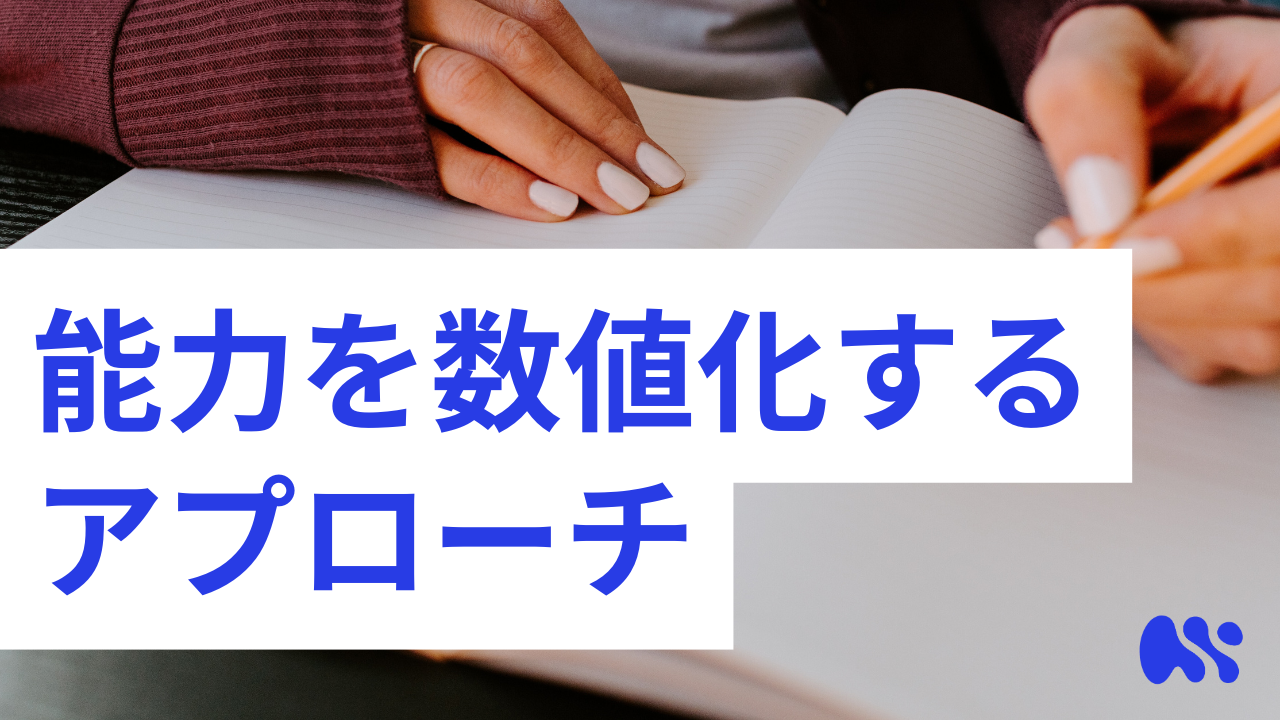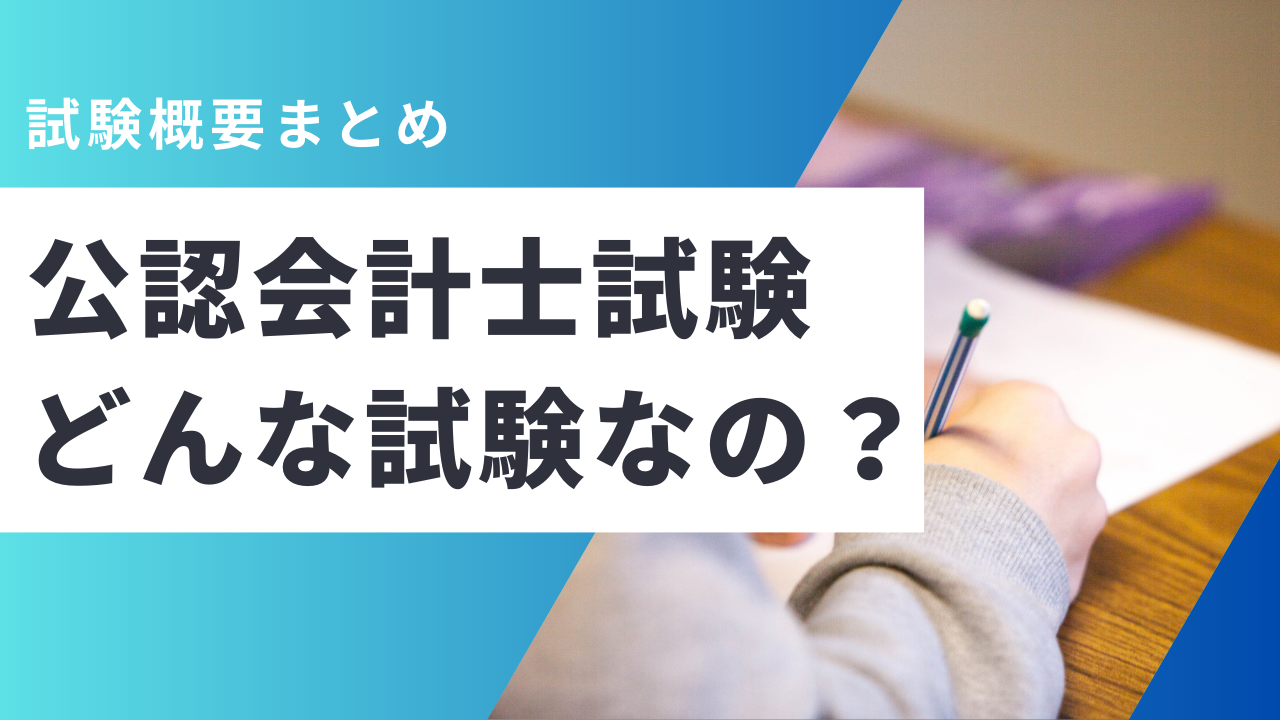
目次
この記事では、公認会計士試験の概要をご紹介しています。
公認会計士試験の全体像
はじめに、合格までの流れについて解説します。
合格までに2回の試験がある
公認会計士試験に合格するためには、「短答式試験」と「論文式試験」の2つを通過する必要があります。
短答式試験と論文式試験の違い
短答式試験はマーク式、論文式試験は記述式、というのが大きな違いです。
また、試験の目的にも、次のような違いがあります。
| 短答式試験 | 論文式試験 | |
|---|---|---|
| 試験の目的 | 会計にまつわる幅広い知識を有しているかを確認すること。 | 会計にまつわる深い思考力およびそれらを表現する論述力を有しているかを確認すること。 |
公認会計士試験の受験資格
受験資格とは、「試験を受けるにあたり求められる要件」のことです。
具体的には、学歴や実務経験などが挙げられます。
公認会計士試験は誰でも受験できる
公認会計士試験には、受験資格は設けられていません。
三大国家資格(医師・弁護士・公認会計士)のなかでは唯一、誰でも受けることができる試験となっています。
公認会計士試験の合格率
各試験毎の合格率は、以下の通りです。
短答式試験(第Ⅰ回・第Ⅱ回)の合格率
| 短答式試験 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合格ボーダー | 63%・63% | 57%・64% | 62%・中止 | 68%・73% | 71%・69% | 75%・未実施 |
| 平均点 | 44.2%・42.6% | 38.9%・46.1% | 47.3%・中止 | 47.5%・47.5% | 46.4%・45.6% | 50.5%・未実施 |
| 合格率 | 16.6%・12.7% | 15.7%・12.9% | 21.6%・中止 | 12.1%・7.9% | 10.4%・8.8% | 10.8%・未実施 |
短答式試験は、受験者数の変動にあわせて、合格率が大きく上下します。
また、第Ⅰ回試験よりも、第Ⅱ回試験の方が、合格率が低い傾向にあります。
論文式試験の合格率
| 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 | 3,792人 | 3,719人 | 3,992人 | 4,067人 | 4,192人 |
| 合格者数 | 1,337人 | 1,335人 | 1,360人 | 1,456人 | 1,544人 |
| 合格率 | 35.3% | 35.9% | 34.1% | 35.8% | 36.8% |
論文式試験の合格率は、毎年安定しています。
これは、受験者の増減に応じて、短答式試験の段階で人数の調整を行なっているためです。
会計士試験全体の合格率
| 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | 令和5年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 願書提出数 | 12,532人 | 13,231人 | 14,192人 | 18,789人 | 20,317人 |
| 合格者数 | 1,337人 | 1,335人 | 1,360人 | 1,456人 | 1,544人 |
| 合格率 | 10.7% | 10.1% | 9.6% | 7.7% | 7.6% |
受験者数の増加に伴い、年々合格率が低下しており、より難しい試験になっています。
公認会計士試験に必要な勉強時間
2つの異なる切り口から、勉強時間について考察してみます。
標準的な学習期間は2年間
公認会計士の予備校では、一般的な学習コースとして、2年間のコースが用意されていることが多いです。
1日平均5時間の学習を2年続けると約3500時間となり、一般的な目安といわれる値になります。
講義を受けるだけでも1000時間はかかる
1科目あたり「3時間×30コマ」というのが、初学者向けに開講される講義の平均ボリュームです。
論文式試験合格までには「財務・管理・監査・企業・租税・経営(選択科目)」の6科目を学ぶ必要があります。
「3時間×30コマ×6科目=540時間」です。
授業を受けて、同じ時間復習をするだけでも、1000時間は必要となる計算です。
実際には、本番レベルを想定した演習、継続的な知識のメンテナンスも必要となります。
最速合格であっても、1500時間を下回るケースはまずありません。
公認会計士試験の主要4科目
財務会計
企業間で比較可能な形で記録をとるべく、会計にはさまざまなルールが定められています。
財務会計では、会計記録を作成する際のルールを学びます。
簿記で学習する内容と地続きになっていますが、現代の複雑な取引に対応するために、簿記よりも高度な内容を学びます。
各企業が異なる基準で記録を作成してしまうと、情報の比較ができません。
会計記録の比較可能性と信頼性を担保するべく、財務会計が必要となるのです。
管理会計
管理会計では、会計データから、意思決定に役立つ情報を抽出する手法を学びます。
商品の価格、生産量、年度予算、投資可否など。経営するなかで直面する、さまざまな意思決定に、数字の観点から切り込んでいきます。
経営に直結する科目であるため、経営コンサルティングとも深い関わりがあります。
参考:篠田 朝也, 藤本 康男, 2019年6月, 東京図書出版, 『中小企業のための管理会計 理論と実践』
企業法
会社法を中心に、商法や、金融商品取引法など。
企業法では、企業にまつわる法律を体系的に学びます。
最低限の法律リテラシーを身につけることで、法律関連の問題に直面した際に、自ら対応策を練ることができるようになります。
監査論
監査論では、監査のルールやプロセス、証拠の集め方や評価の仕方などを学びます。
監査には、不正を発見するだけでなく、不正が発生しにくい組織づくりの視点も含まれています。
こうした視点を学ぶことは、たとえ監査業務以外のキャリアを選択したとしても、十分に役立ちます。
公認会計士試験に向いている人
公認会計士の勉強が自分に向いているかを判断するうえでは、「簿記3級」の資格に挑戦してみるのがオススメです。
多くの予備校では、無料で簿記3級の講座を公開しています。
まずは簿記3級の勉強をしてみて、手応えを感じることができれば、公認会計士の勉強に向いているといえます。
以下、CPA会計学院が提供する、無料体験講義の詳細ページです。ご参考までに。
(当サイトは、アフィリエイト契約を行っていません)
『会計の世界史』
会計にまつわる制度や知識は、日常生活で触れる機会が少ないため、縁のない話と感じられる方も多いでしょう。
しかし、その成り立ちは、私たちの生活と深く結びついた、動的な歴史の集積です。
『会計の世界史』は、ビジネススクールで会計学を開講する著者による、会計の歴史物語です。
会計の誕生から現代に至るまでの変遷を、誰でも楽しめるように、豊富なエピソードを交えて解説しています。
- 会社の誕生と大航海時代には、深いつながりがある
- 子どものお小遣い帳と会計帳簿。何が違うの?
- 財務諸表がないと、誰がどう困るの?
会計の魅力を、歴史とともに語る本書は、すべての方にお薦めできる一冊となっています。
どうぞご一読ください。
参考:田中 靖浩, 2018年9月, 日本経済新聞社, 『会計の世界史 イタリア、イギリス、アメリカ――500年の物語 』