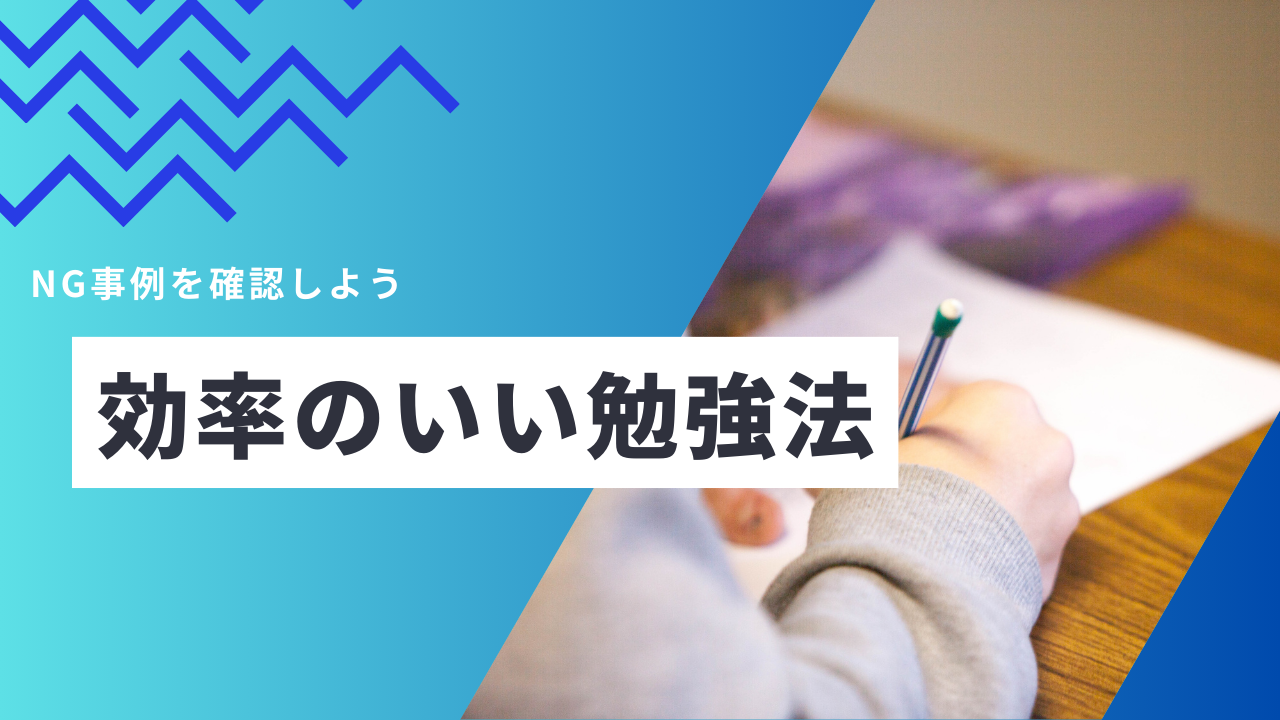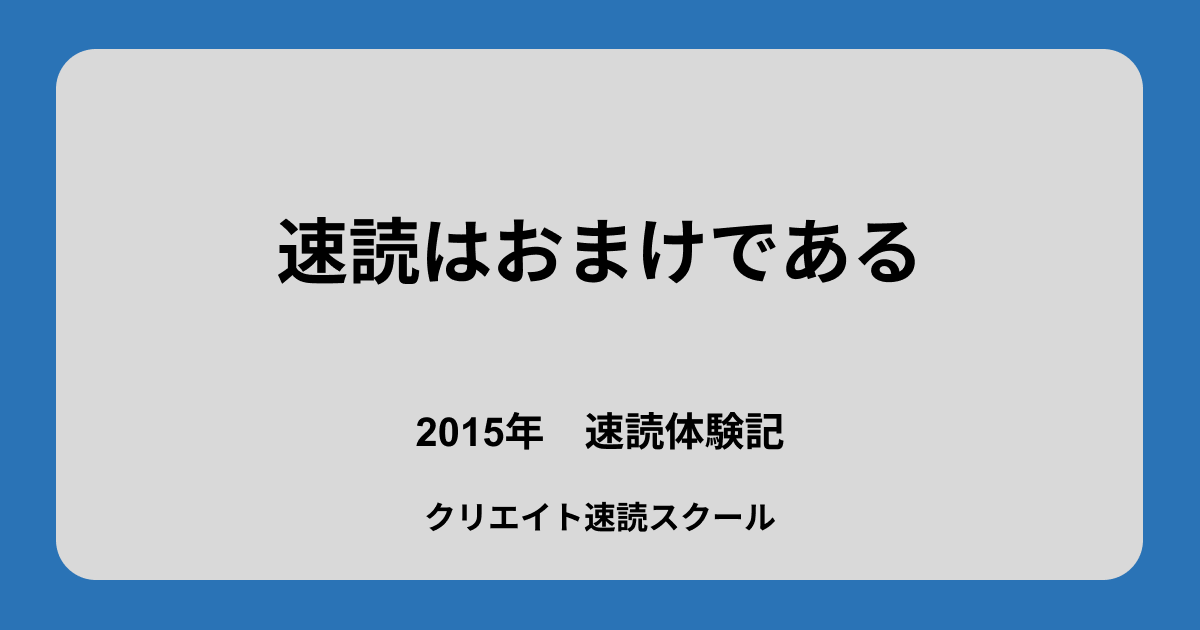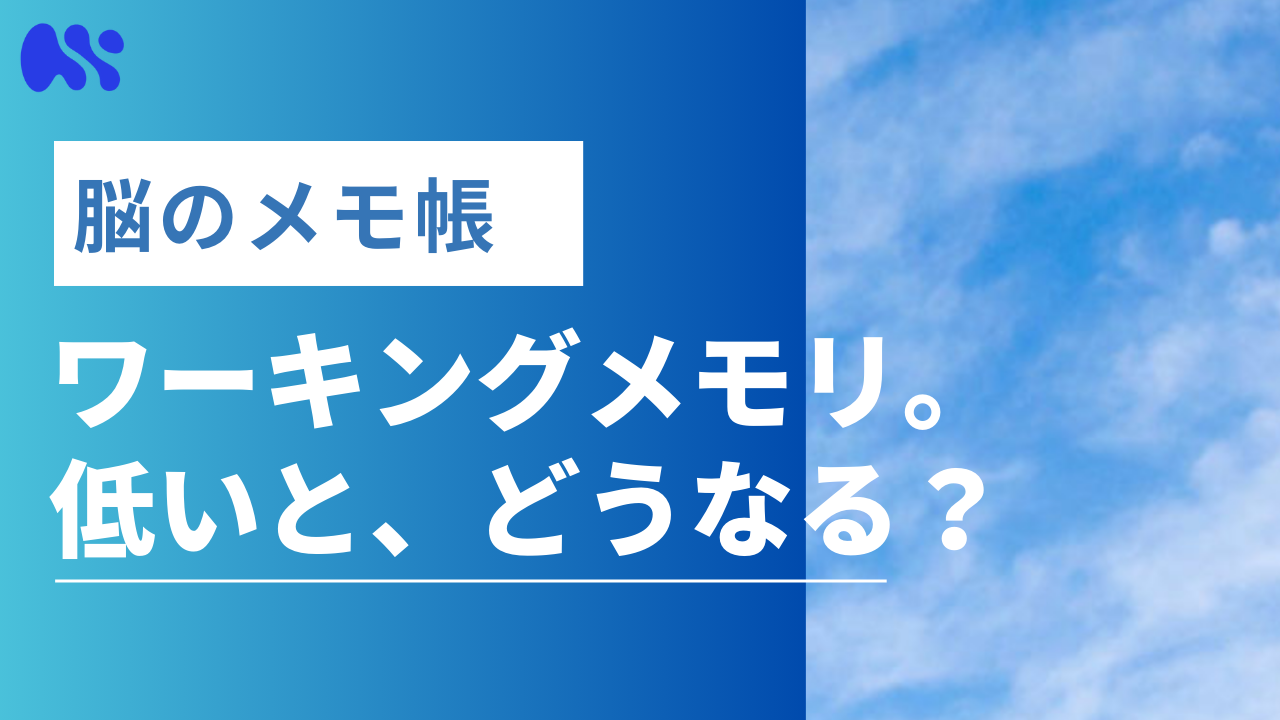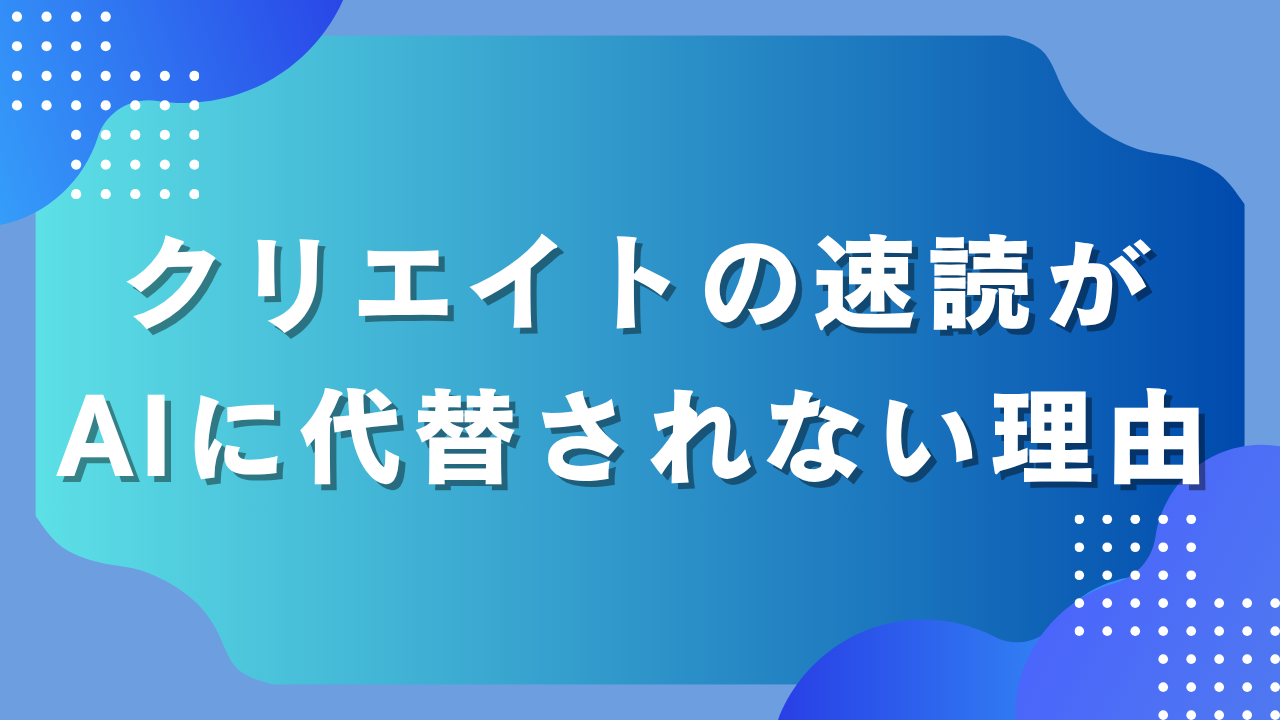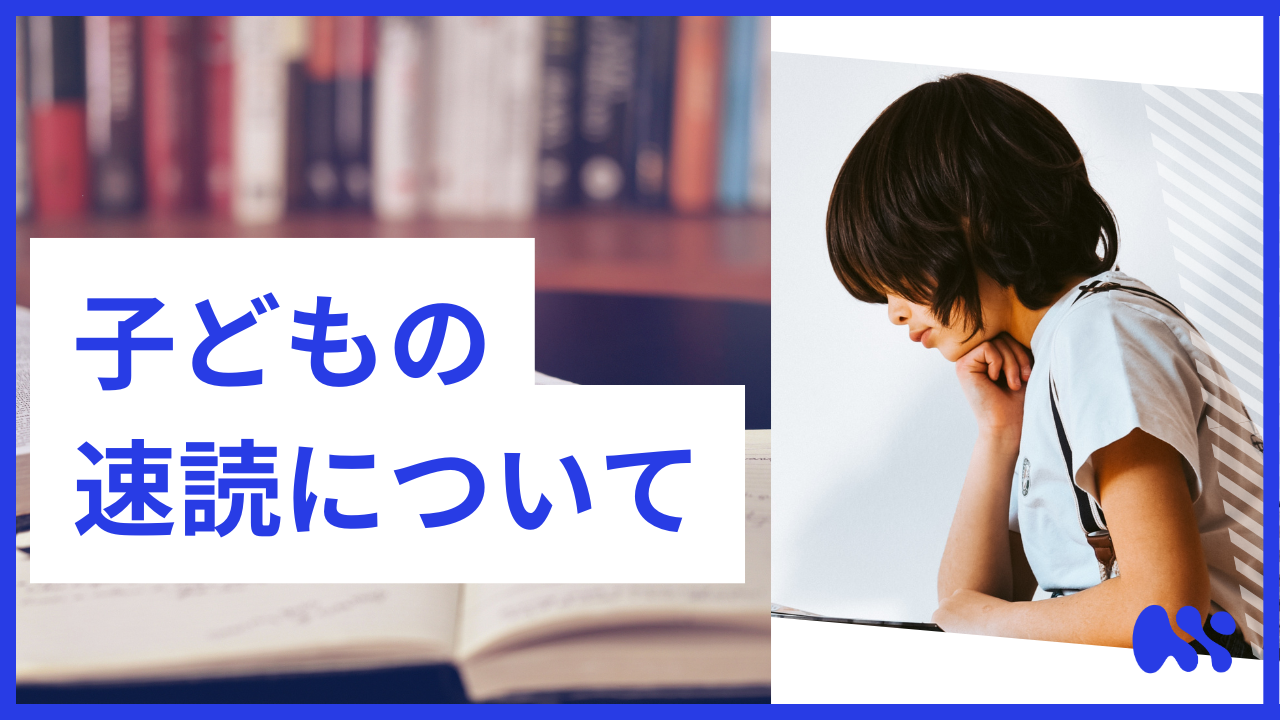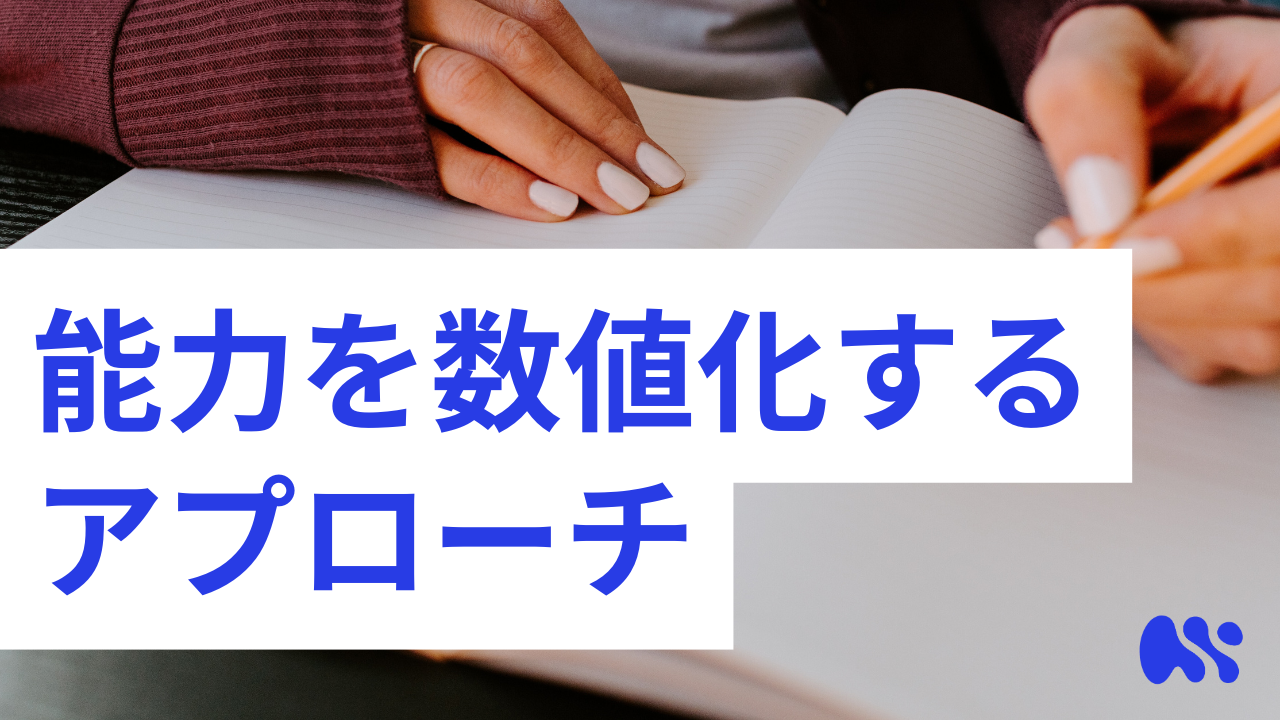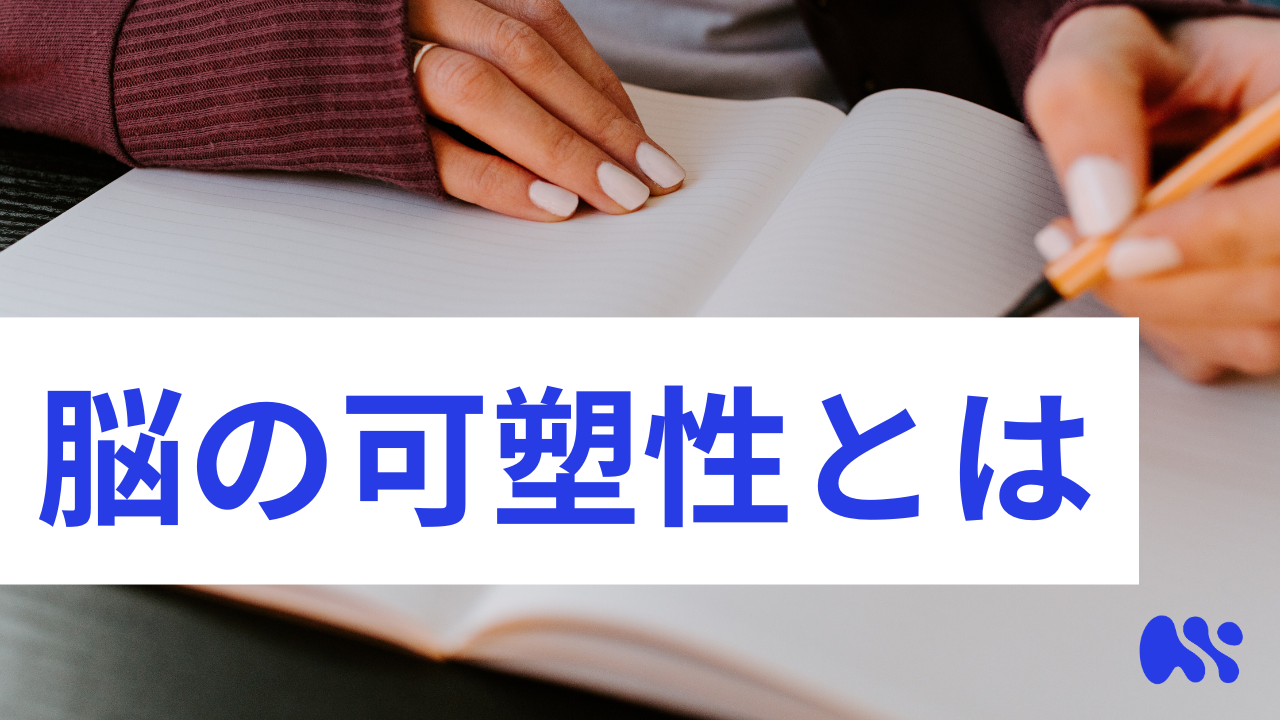
この記事では、以下の文献を参考に、可塑性についての解説を行なっています。
参考:塚原 仲晃『脳の可塑性と記憶』岩波現代文庫, 2010年5月
可塑性とは
私たちの身の回りには、変形しやすい物質と、そうでない物質があります。
「可塑性」とは、物質が外部からの力を受けて変形した後、その変化を維持する性質のことを指します。
例えば、粘土や金属は可塑性が高く、一度変形すると、ひとりでに元に戻ることはありません。
一方、ゴムのように弾性を持つ物質は、変形しても元の形に戻る性質があります。
脳の可塑性とは
脳には、外部からの刺激によって、神経細胞のネットワークが変化し、なおかつその変化がのこる性質があります。
この性質は「脳の可塑性」と呼ばれています。
幼少期は新しい言語や技能を習得しやすいことが知られていますが、これは、幼少期は特に、脳の可塑性が高いためです。
たとえば、事故によって脳の一部が損傷し、手や足をうまく動かせなくなった人が、リハビリを通じて再び動作を取り戻すケースがあります。
これは、繰り返し訓練を行うことで、損傷を受けた部分の運動機能を、脳の別の領域が担うようになるためです。
私たちが、何か新しい技能を身につける際にも、その学習は、脳の可塑性に依存して成立します。
脳は機能的な形に進化する
学習過程では、同じ神経細胞のネットワークが同じパターンの活動を繰り返すなかで、より効率的なシステムへと自らを変化させます。
これは、筋力トレーニングを続けることで、筋肉が発達するのと似ています。
新しいことを学ぶたびに、脳はそれに適応し、より機能的な形に進化するのです。
脳とコンピュータの違い
コンピュータは膨大な情報を記憶できますが、処理機能そのものが変化することはありません。
一方、脳は経験によって自ら変化し、新しい状況に適応する能力を持っています。
コンピュータはプログラムされた通りにしか動作しませんが、人間の脳は学習を通じて変化します。
この柔軟性が、脳とコンピュータの大きな違いです。
速読トレー二ングで脳を鍛える
神経回路の強化には時間がかかりますから、学習には、反復が不可欠です。
だからこそ、脳の処理機能そのものを変えることを目指す、クリエイトの速読トレーニングは、一定の訓練量が必須となるのです。
スコアに現れるのは、今日この日ではないかもしれません。
しかし、トレーニングのたびに、一歩一歩確実に、アタマは変化していきます。
「脳には可塑性がある」という切り口で、一度自分のトレーニングを振り返ってみると、何か新しい発見があるかもしれません。
この記事のタグ
劉 智秀 1999年東京都生まれ/栄東中学・高等学校/東京大学経済学部卒/クリエイト速読スクール二代目代表