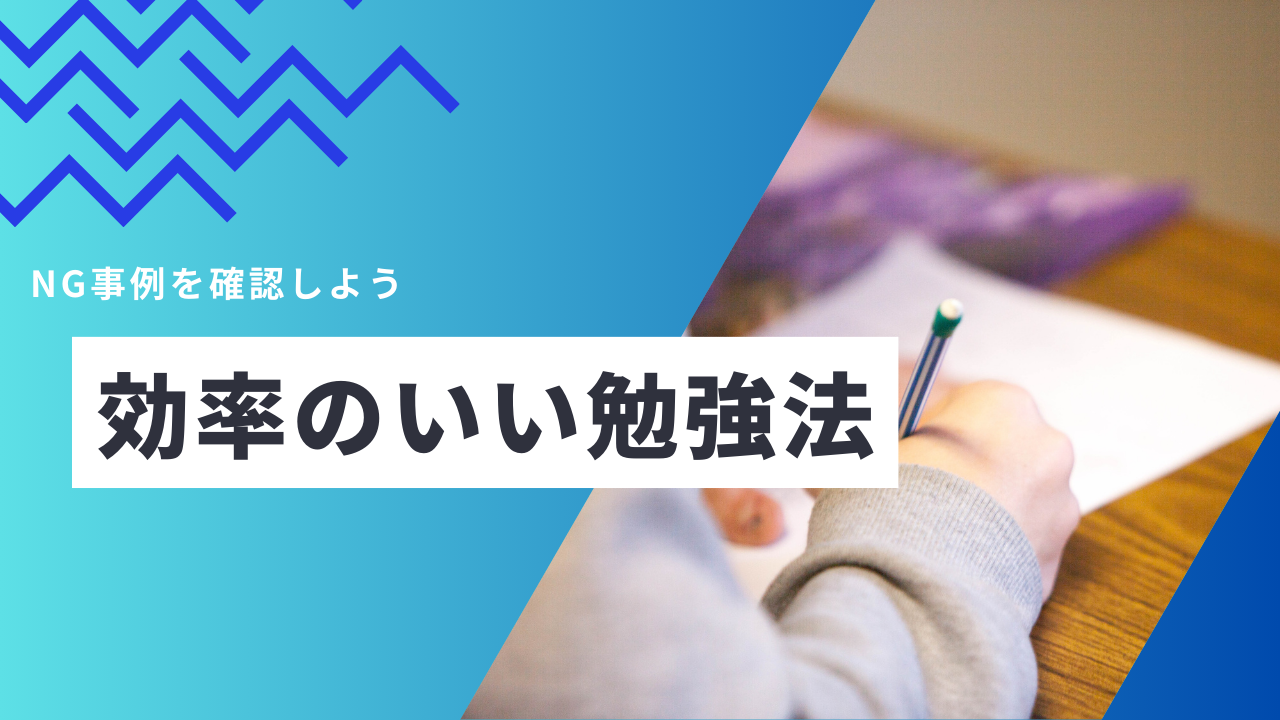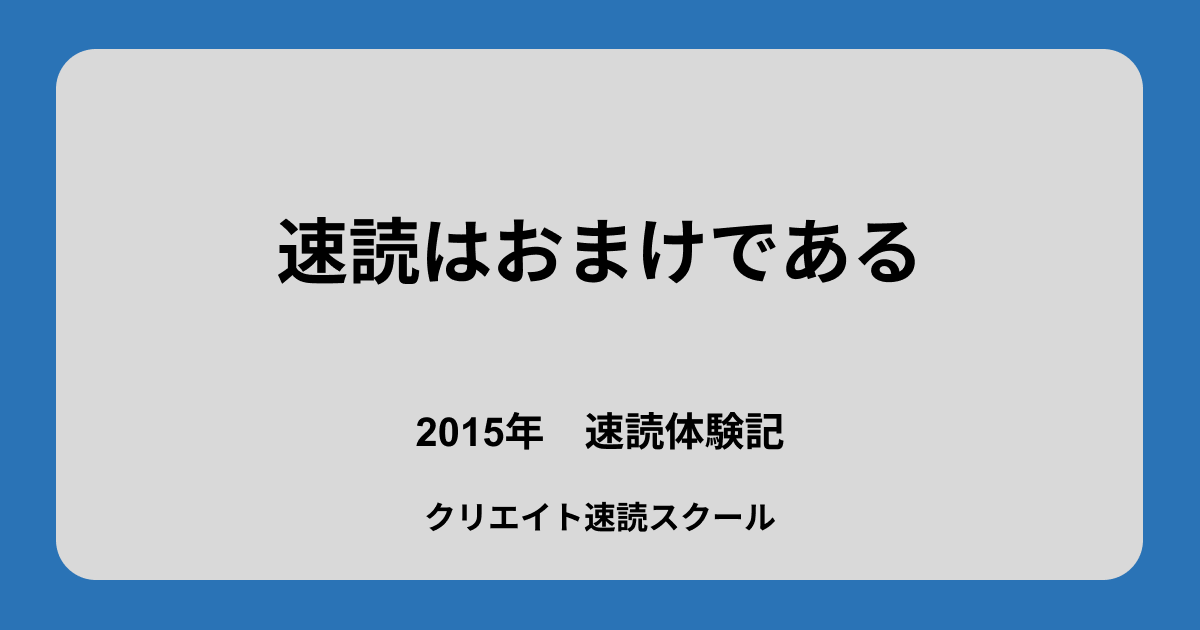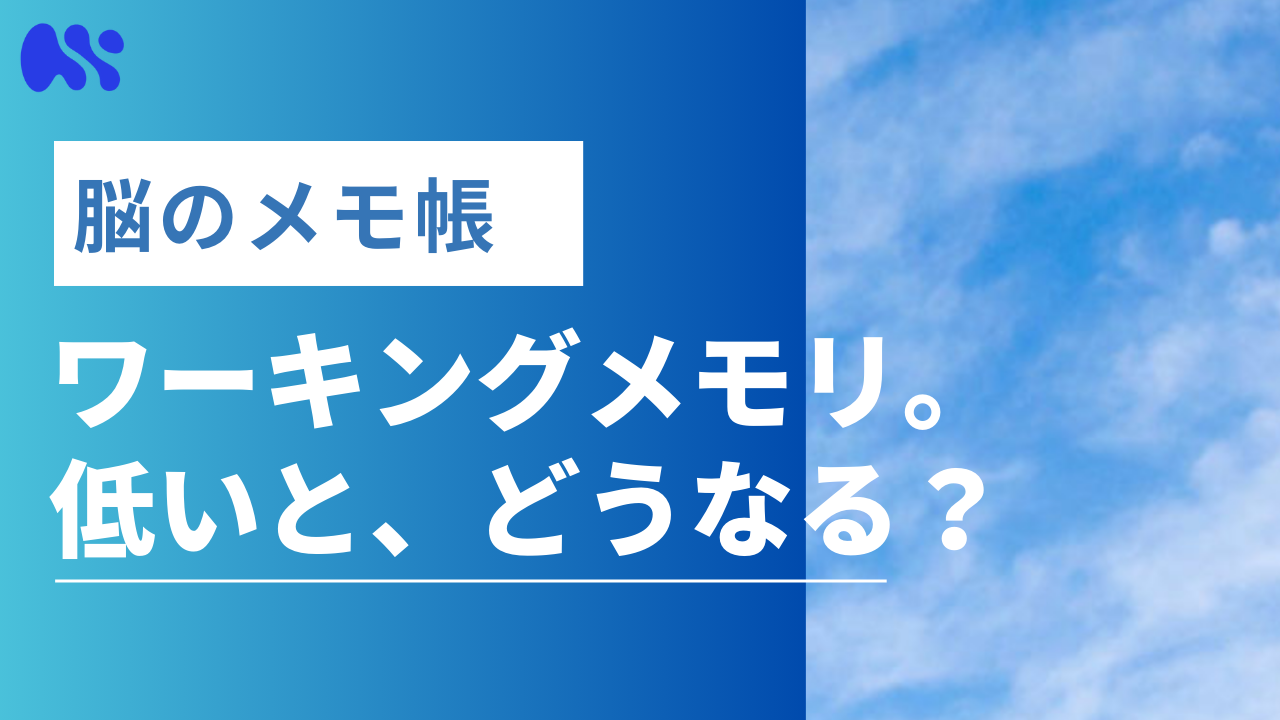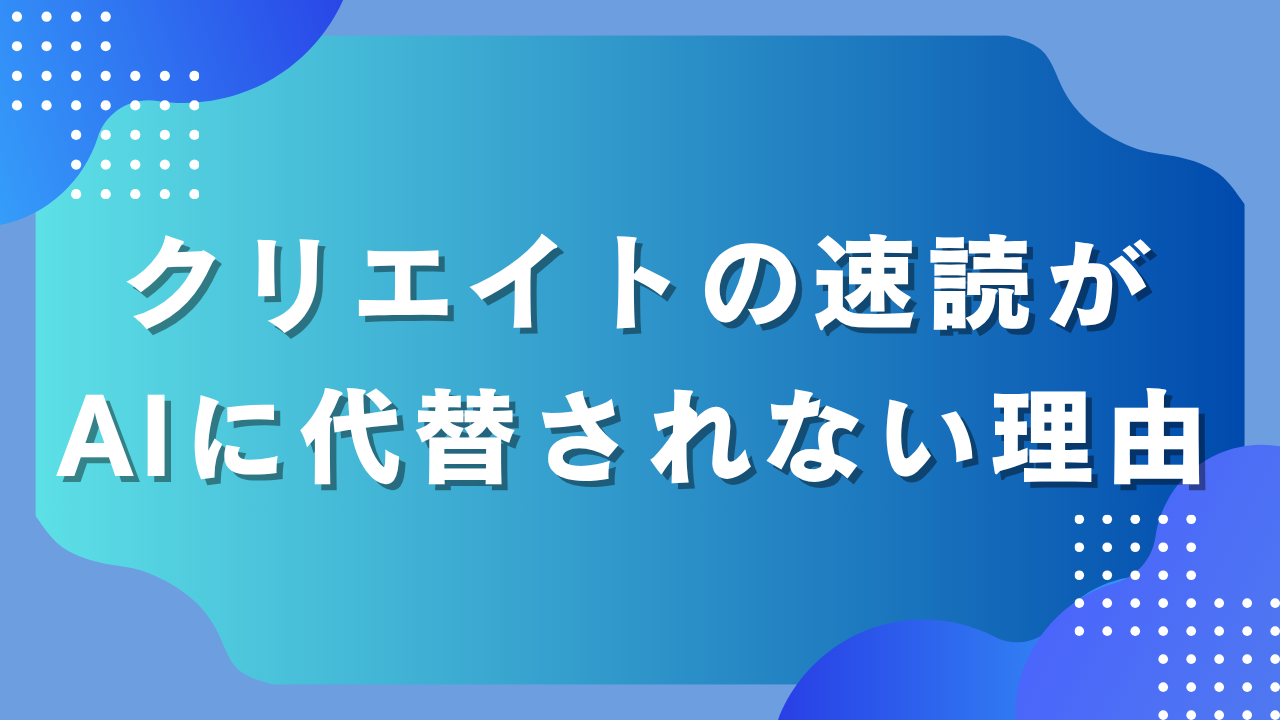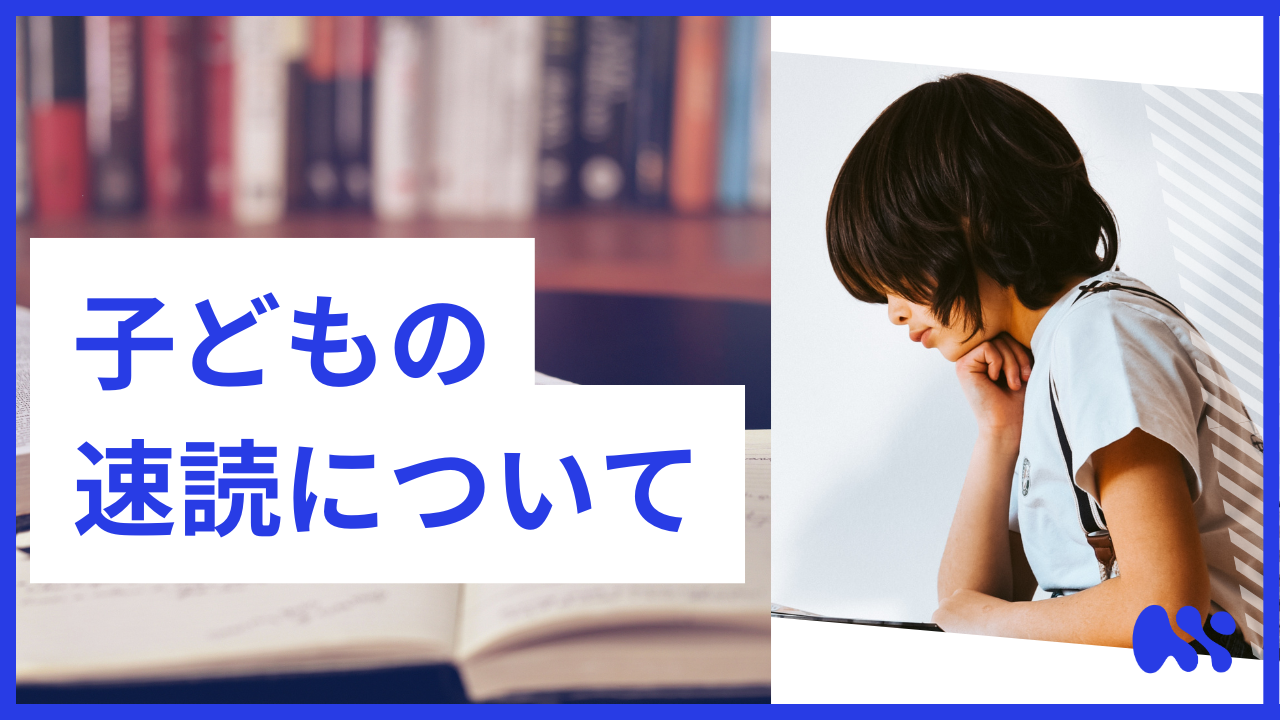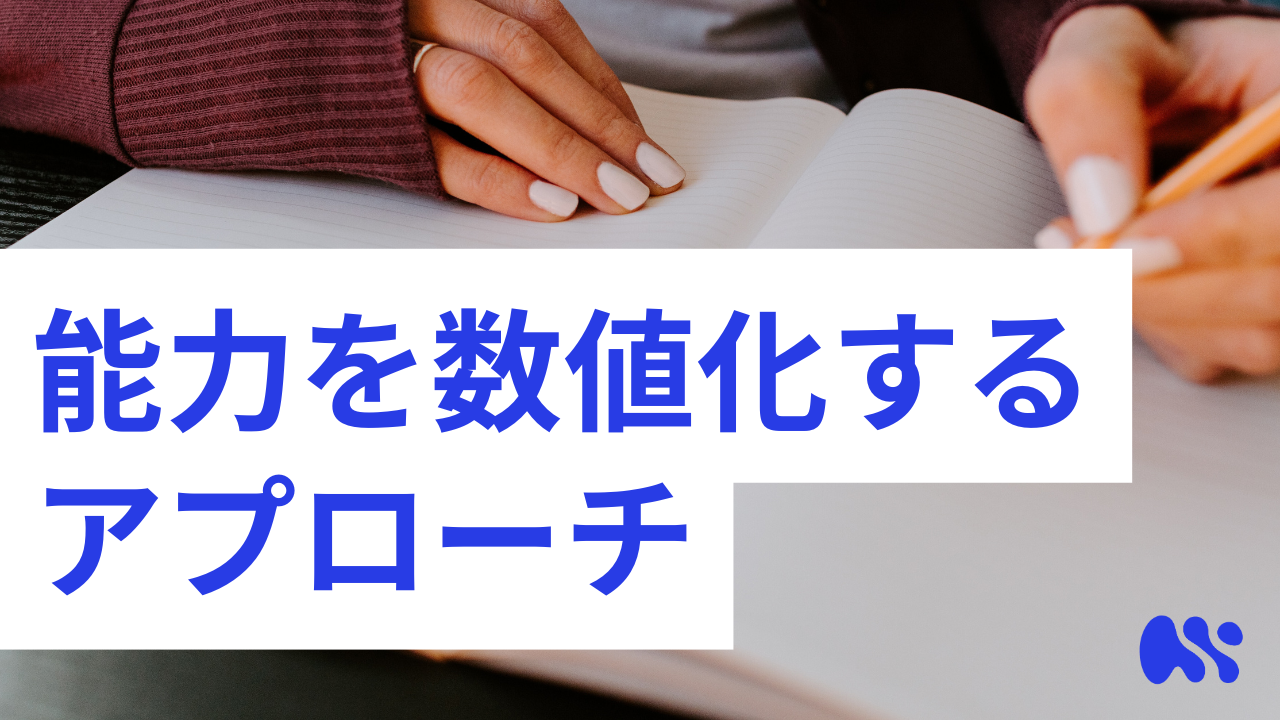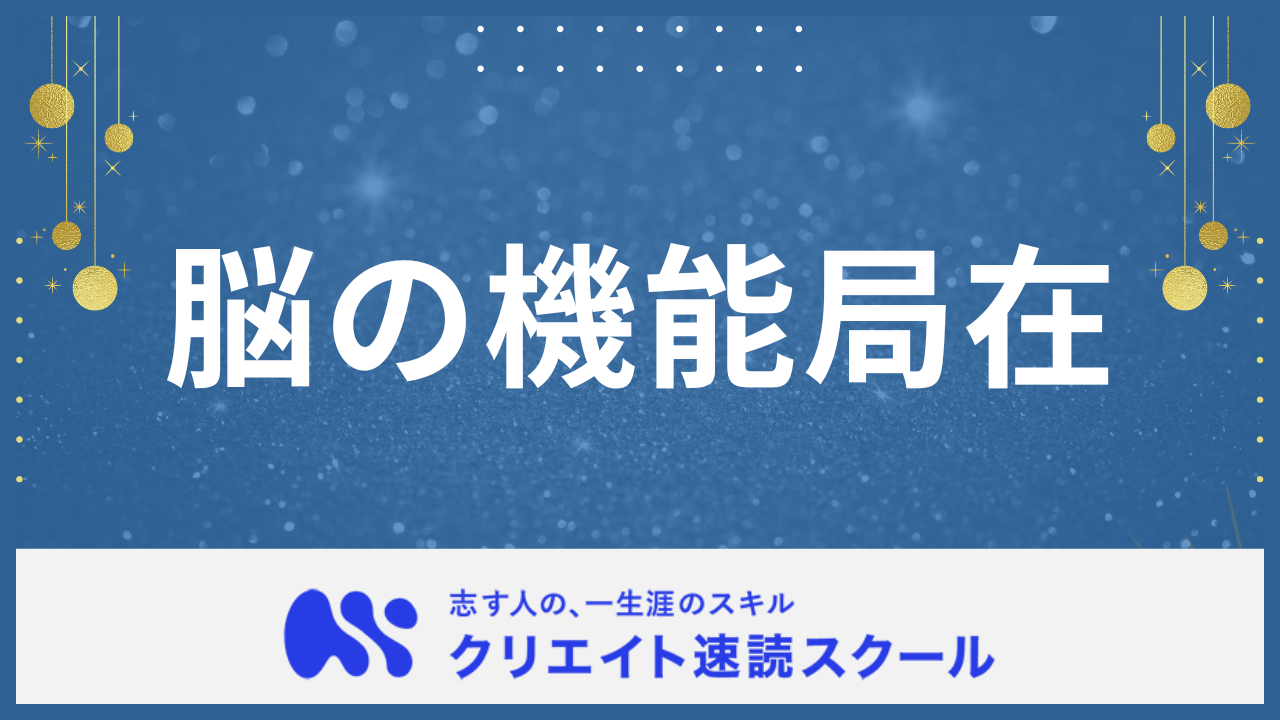
脳の機能局在とは
脳は場所によってはたらきが違うことがわかっており、こうした特徴は「脳の機能局在」と呼ばれています。
この事実は、外傷や病気によって脳の一部が障害を受けた後、現れる症状を観察することで、明らかにされました。
現在ではfMRIなどの先端技術によって、脳の活動をリアルタイムで観察することが可能になり、機能局在の理解が進んでいます。
脳の機能局在の例外
身体の感覚や操作など、比較的単純な機能については、脳領域との対応関係が明確です。
しかし、高次の機能については、どの程度機能局在が成り立つのか、かならずしもはっきりしていません。
認知・判断・意識といった機能は、複数の脳領域の連携によって実現している場合があるのです。
脳は統合的なシステム
たとえば、読書ともなると、感覚系から運動系まで、広い領域の細胞がはたらいています。
シンプルに思える課題であっても、遂行中の脳を観察すると、多くの領域がほぼ同時に活性化していることがわかります。
脳の機能局在は、各領域が他から切り離され、単独ではたらいていることを意味しません。
脳はバラバラの部品の集合ではなく、互いに情報を交換し合いながらはたらく、統合的なシステムなのです。
「右脳を使えば速読ができる」という誤解
こうした脳の特徴をふまえて考えると、「右脳を使い、潜在能力を解放すれば、速読ができる」という主張の問題点に気がつきます。
第一に、文字を読むという高度な情報処理においては、誰しもが、脳全体を活用しています。
脳の一部が使われていないとしたうえで、それが潜在能力であるとするのは明らかなミスリードです。
第二に、読書は、脳の単一の領域だけでなく、複数の領域が連携することで成り立つものです。
脳の一部を鍛えさえすれば、速読が可能になるというのは、脳の実態を無視しているといえます。
実践重視の速読トレーニング
クリエイトの速読トレーニングは、学術的知見を裏付けとしつつも、その大部分が、実践の中で形作られています。
実践と結びつかない理論には、意味がないからです。
生徒さんが仕事や勉強に活かせることを第一に考えてきた結果、他に類を見ない実績をあげています。
私たちは、教室運営の経験が、速読に関する学問的な研究に貢献することを強く望んでいます。
何かご協力できることがあれば、ぜひご連絡ください。
この記事のタグ
劉 智秀 1999年東京都生まれ/栄東中学・高等学校/東京大学経済学部卒/クリエイト速読スクール二代目代表