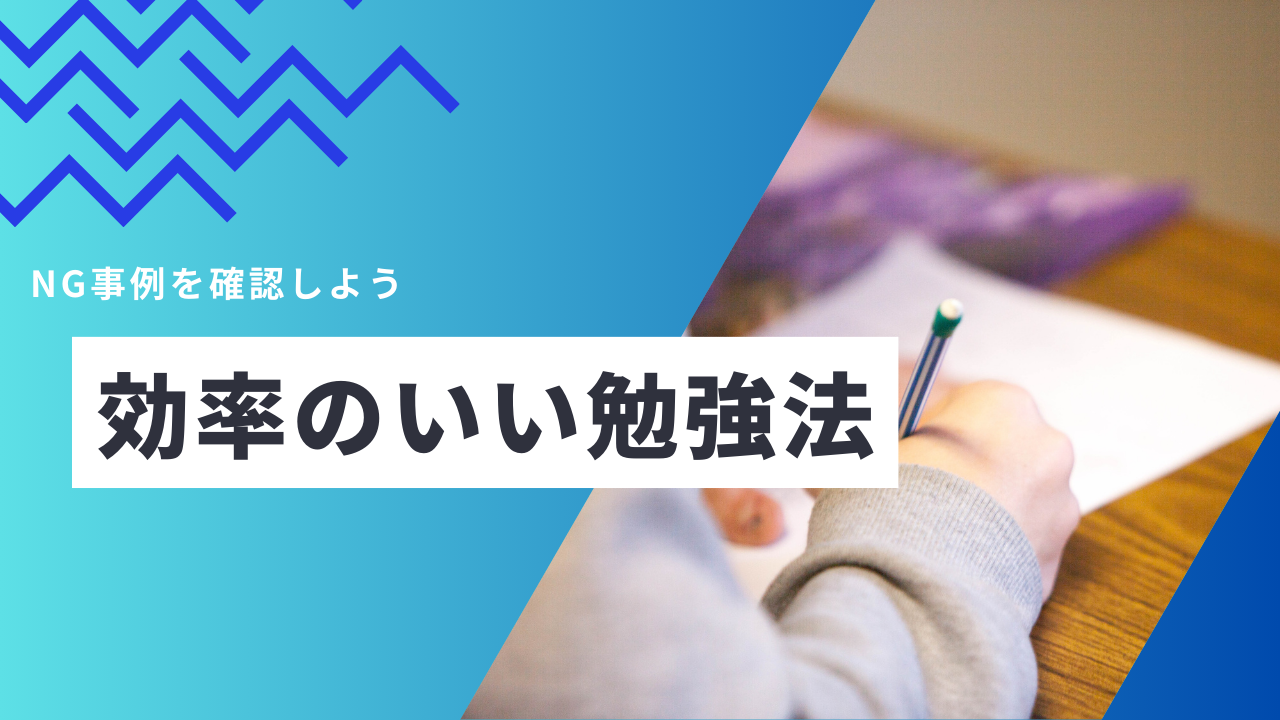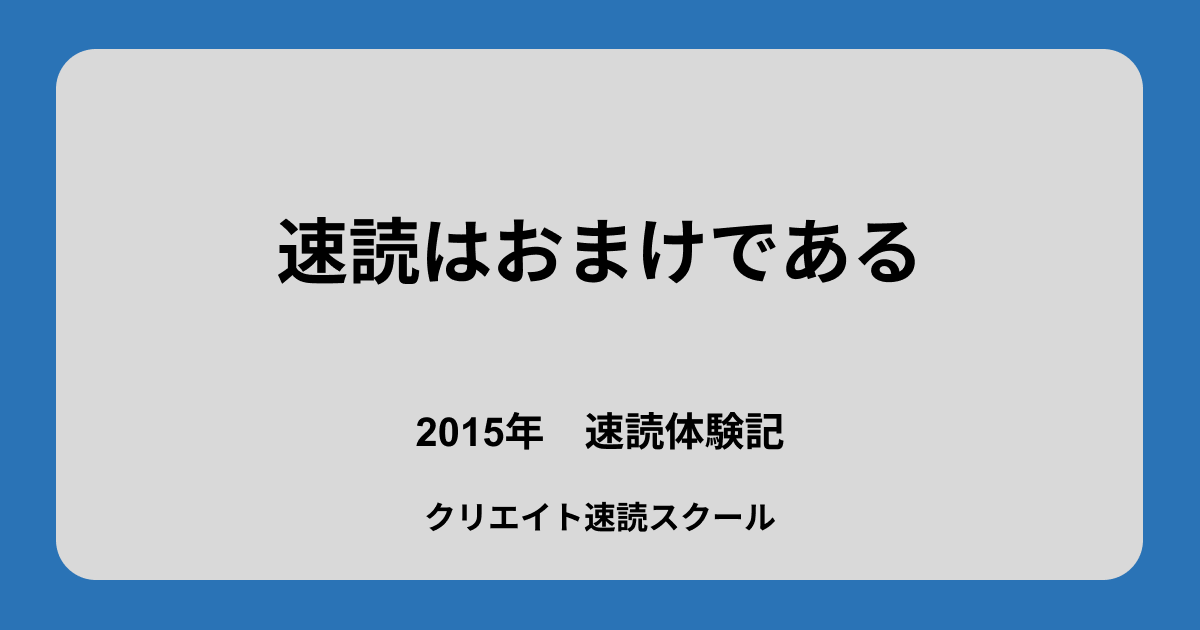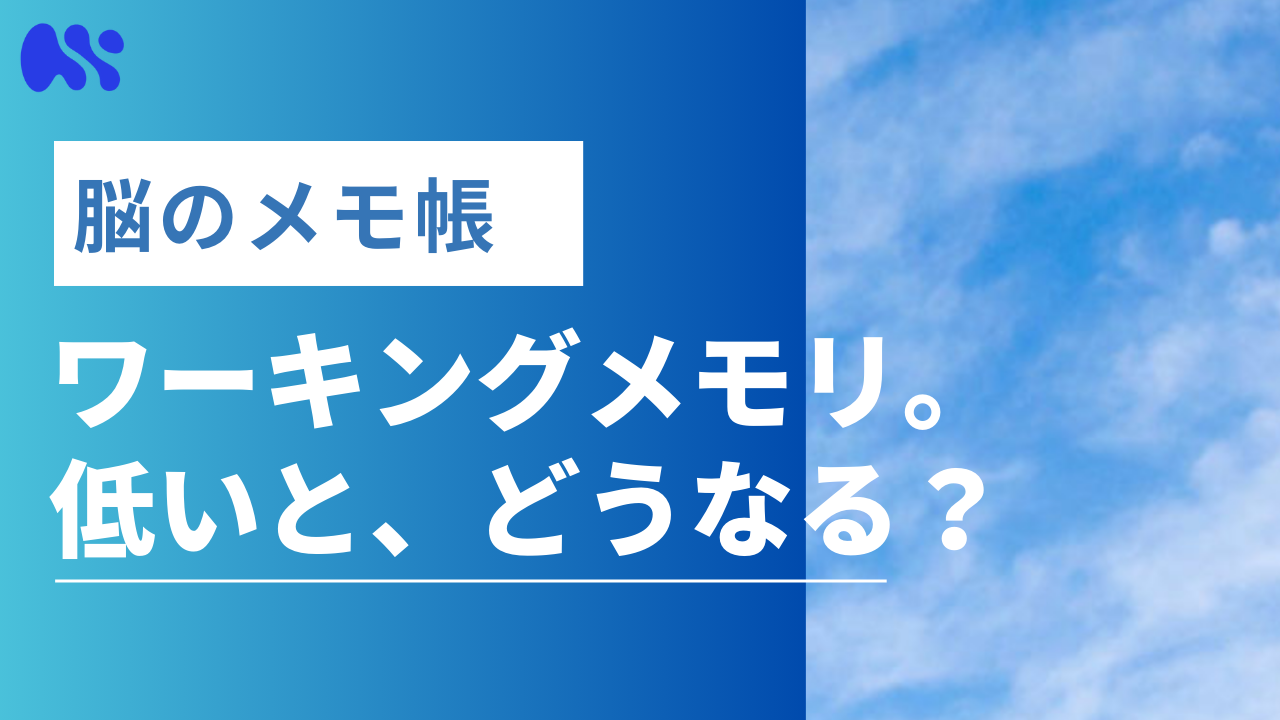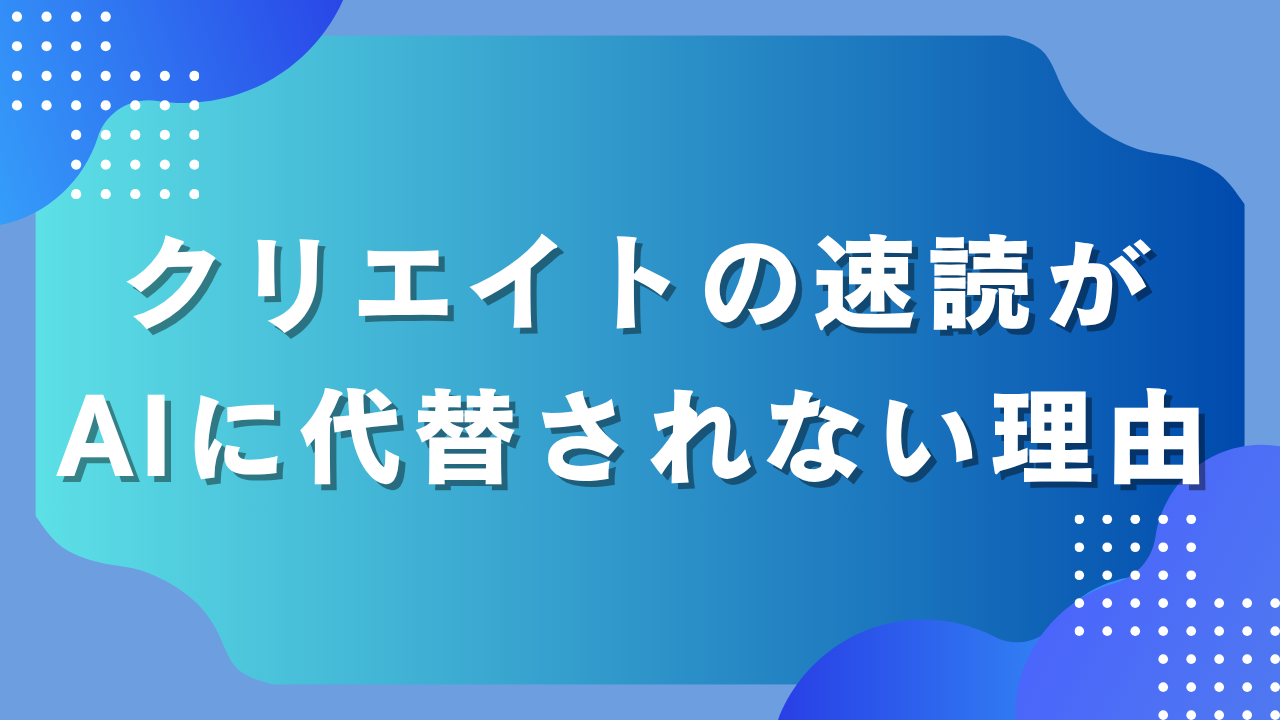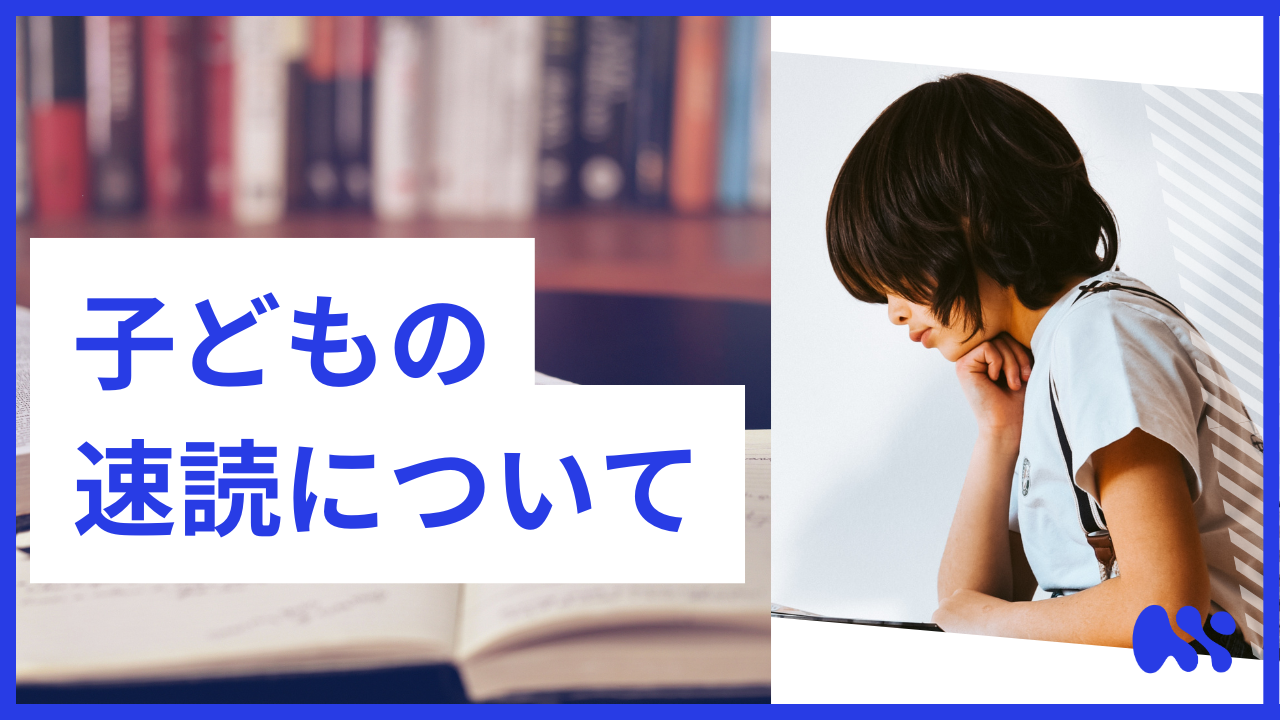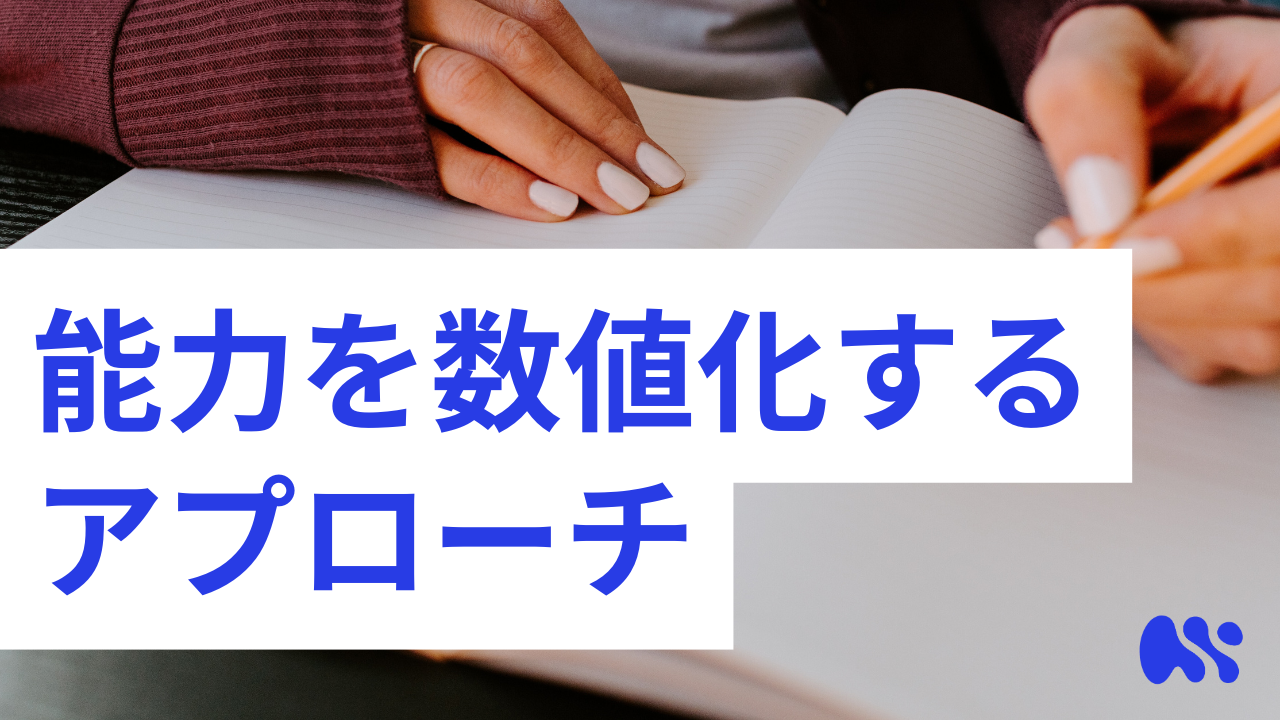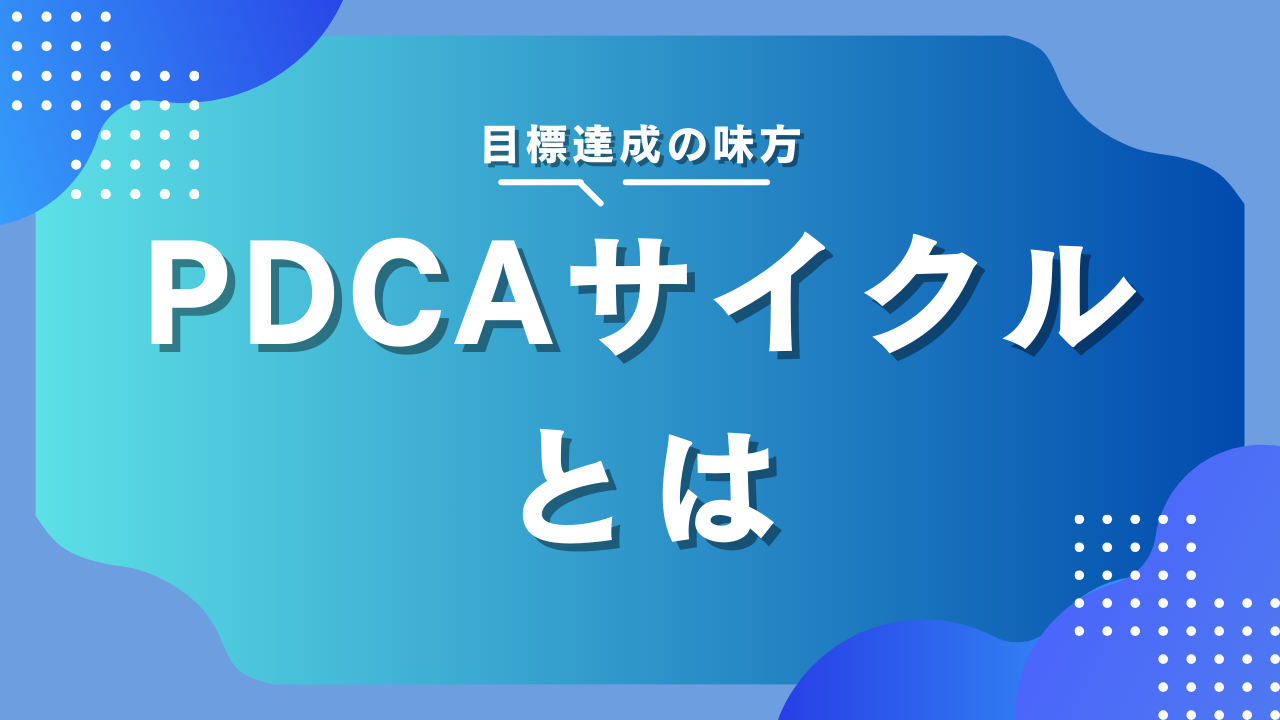
目次
PDCAサイクルとは
PDCAサイクルとは、継続的な改善と学習の促進を目的とした、問題解決のためのフレームワークです。
Plan(計画)、Do(実行)、Check(検証)、Action(改善)の一連のプロセスを繰り返すことで、問題の解決を目指します。
PDCAサイクルのメリット
着実に進捗が生まれる
進捗の可視化と、連続的な改善サイクルが、PDCAの強みです。
かりに目標を達成することができなくとも、失敗体験を通じてプロセスが最適化されるため、着実に進捗を生み出すことができます。
作業に集中できる
PDCAサイクルでは、Plan(計画)の段階で、目標と具体的な方法やスケジュールを設定します。
実行の前に、明確な計画を立てることで、作業に集中することができます。
PDCAサイクルのステップ
Plan(計画)
PDCAサイクルの最初のステップです。
目標達成に向けた、具体的な行動計画を考えます。
行動計画に沿ってサイクルが進行するため、最も重要なステップとなります。
以下の4点を明確にするのがポイントです。
- 目標の設定
- 課題の洗い出し
- 課題のタスク化
- タスクを優先づけ
参考:スケジュール管理の第一歩は、タスク管理から。タスク管理が上手い人の特徴。
Do(実行)
行動計画にしたがって、タスクを実行していくステップです。
後のCheckの段階で分析ができるよう、トラブル等があれば、メモをしておきましょう。
Check(検証)
実行した結果を評価し、計画との比較を行います。
目標に対してどれだけ進捗があったか、新たな問題や課題が発生していないか、を確認します。
このステップによって、実行プロセスの成果や問題点が明らかになります。
Action(改善)
検証結果をもとに、次の行動計画を立てる段階です。
今後に向けた対策と改善策を考えたうえで、再びPlanのプロセスに戻り、新たな「PDCAサイクル」を回していきます。
PDCAサイクルの成り立ちと日本への導入
PDCAサイクルは、日本独自の管理手法と考えられています。
ここからは、PDCAサイクルが日本で広まるに至った経緯をご紹介します。
1930年代のアメリカ
PDCAサイクルによる管理手法は、1930年代アメリカの製造業に由来します。
当時の製造業は米国経済を支える一大産業でした。
花形産業として大量生産・大量消費を支えた、当時の製造業の課題は、
- いかにして、製造工程で出てくる不良品の割合を減らすか
- どのようにして、工場労働者の生産性を維持・向上させるか
といったものでした。
これらの課題に対処したのが、現在の経営コンサルタントの前身にあたる「コンサルティング・エンジニア」と呼ばれる人たちです。
主に理工系の修士号や博士号を持つコンサルティング・エンジニアは、製造工程における品質管理・生産性向上に取り組んでいました。
PDCAサイクルの起源
アメリカの統計学者であったウォルター・シューハート博士は、時代の要請に応える形で、製造業における諸課題を解決するための管理手法を提唱しました。
これがPDCAサイクルの起源とされています。
PDCAサイクルはアメリカで広まらず
時代が進み、1950年代のアメリカの製造業では、生産量の向上が重視されていました。
このとき、量産のカギとなったのは、製造工程において、専門知識を必要としない標準化された作業を導入し、熟練度の低い労働者を大量に投入することでした。
その結果、自ら試行錯誤する必要性が乏しくなった製造業の現場で、PDCAサイクルが必要とされることはありませんでした。
PDCAサイクルは日本で広まった
時は同じく1950年代の日本では、戦後の産業再建のために、日本科学技術連盟(通称:日科技連)が設立されました。
日科技連はシューハート氏の著作に注目し、弟子のデミング氏を日本に招集することを決めます。
来日したデミング氏は、シューハート氏の教えを元に、戦後産業復興のため政策づくりを進めました。
デミング氏が紹介したサイクルが、日本企業において、すべての業務に適用可能なように徐々に修正されていき、現在のPDCAサイクルに至ります。
参考:稲田 将人, 2020年6月, 日本経済新聞社, 『PDCAマネジメント』
PDCAサイクルが古い/時代遅れとされる理由
PDCAサイクルは古い? 時代遅れ?
- PDCAサイクルを回すのに時間がかかる
- 突発的な問題に対応できず、柔軟性に欠ける
不確実性への対応に注目が集まる現代において、これらの欠点を指して「PDCAサイクルは時代遅れ」とする動きがあります。
しかし、これらの指摘はいずれも、フレームワークの使い方次第で、解決ができる事柄です。
「計画を立て、実行し、振り返りをする」という思考の枠組みが、陳腐化することはないでしょう。
OODAループ
PDCAサイクルの欠点を克服する、新たなフレームワークとして注目を集めているのが、OODA(ウーダ)ループです。
OODAループは、Observe(観察)、Orient(状況判断)、Decide(意思決定)、Act(実行)の4つのフェーズから成ります。
ループの名前がつくように、必要に応じて途中で、前の段階に戻ることができるのが大きな特徴です。
OODAループについては、下記の記事にて解説しています。ぜひご一読ください。
PDCAサイクルに関するお薦め書籍
『PDCAマネジメント』
PDCAサイクルは、着実に成果に近づくことができる、強力なフレームワークです。
PDCAサイクルという概念は広く認知されていますが、PDCAサイクルの具体的な方法や運用の仕方については、その知名度ほどには浸透していません。
トヨタの自動車工場、マッキンゼーを経て、様々な業界の事業再生に関わってきた著者による本書では、組織におけるPDCAサイクルの回し方が解説されています。
PDCAサイクルを用いたマネジメントや、その歴史について興味がある方にお薦めの一冊です。
参考:稲田 将人, 2020年6月, 日本経済新聞社, 『PDCAマネジメント』
『鬼速PDCA』
PDCAサイクルは、組織のマネジメントだけでなく、個人の目標達成の手法としても用いられます。
『鬼速PDCA』は、野村證券にて異例の速さでキャリアを築き上げた著者による、個人レベルでのPDCAサイクルについてまとめた実践書です。
「3か月でTOEIC800点をとる」といった個人の目標に、PDCAサイクルを活用することを目指す内容です。
- 成功させるための具体的な目標の立て方
- 目標を達成するための課題の洗い出し方
- 複雑な課題をタスクに分解する方法
大学受験生や資格試験受験生など、PDCAサイクルを回し、確実に目標を達成したい方にお薦めの一冊です。
参考:冨田 和成, 2016年10月, インプレス, 『鬼速PDCA』