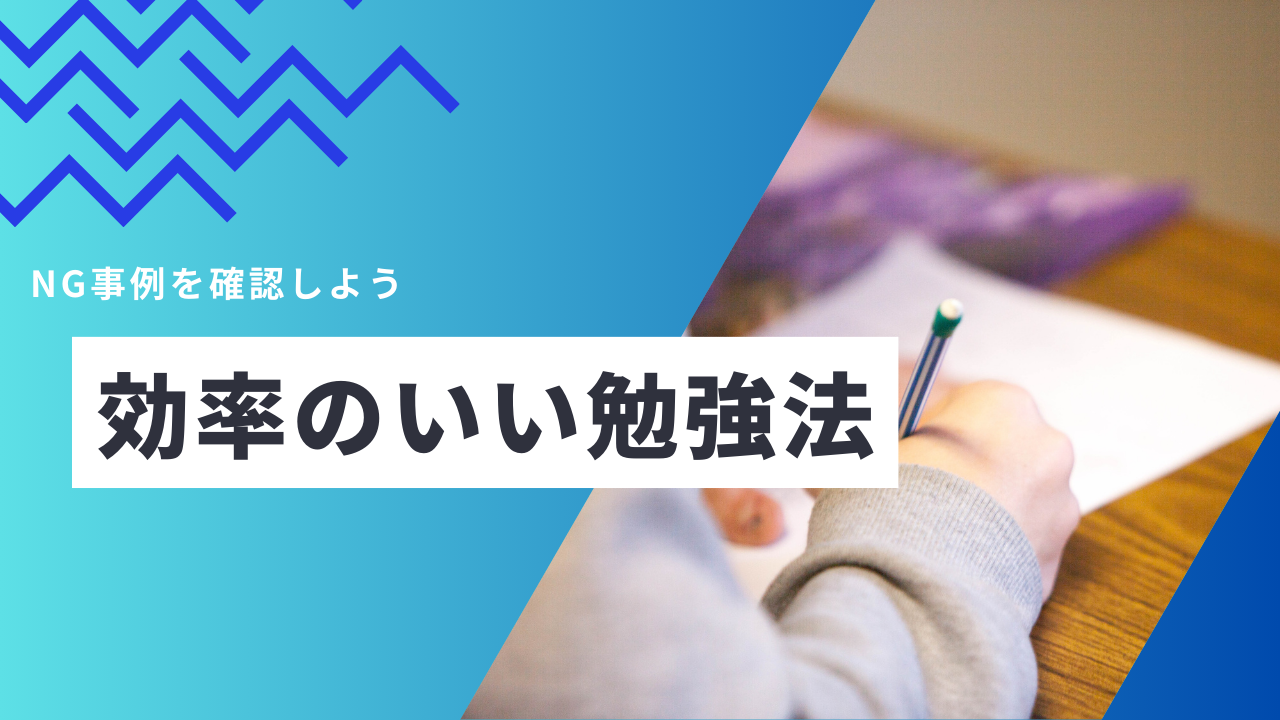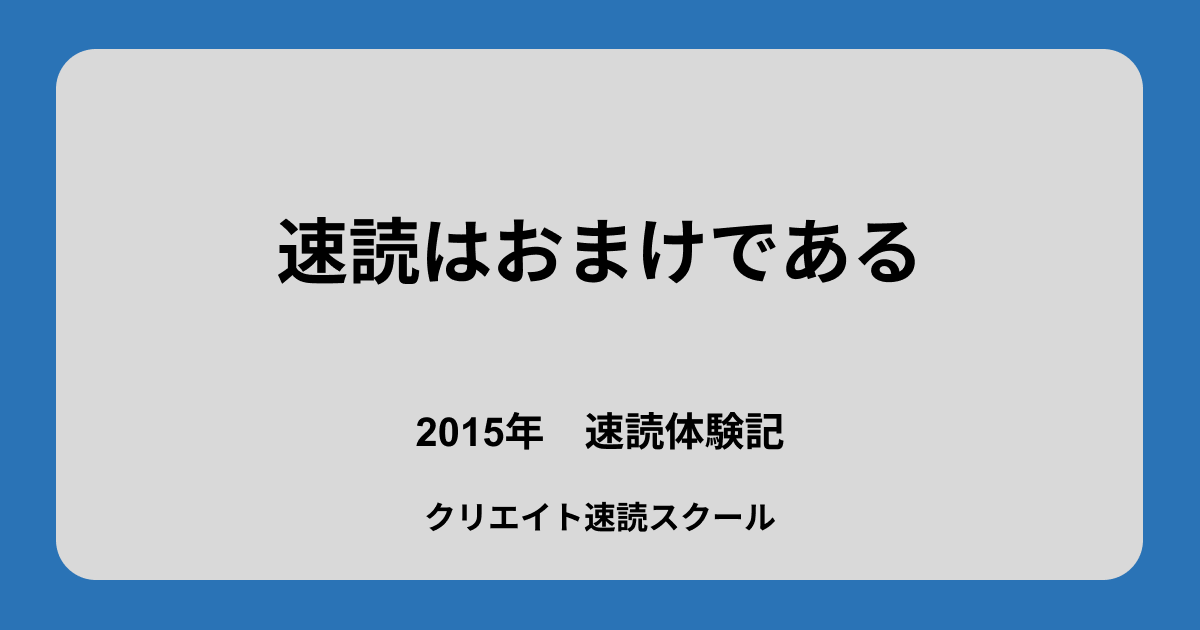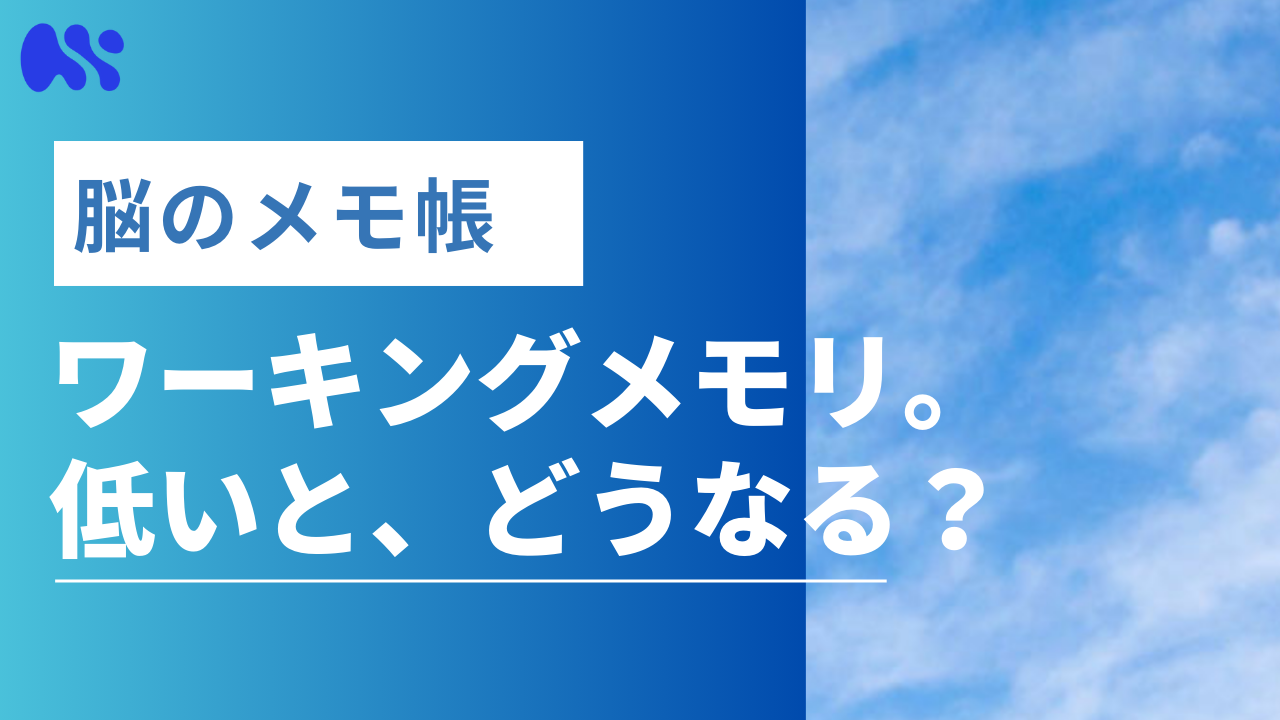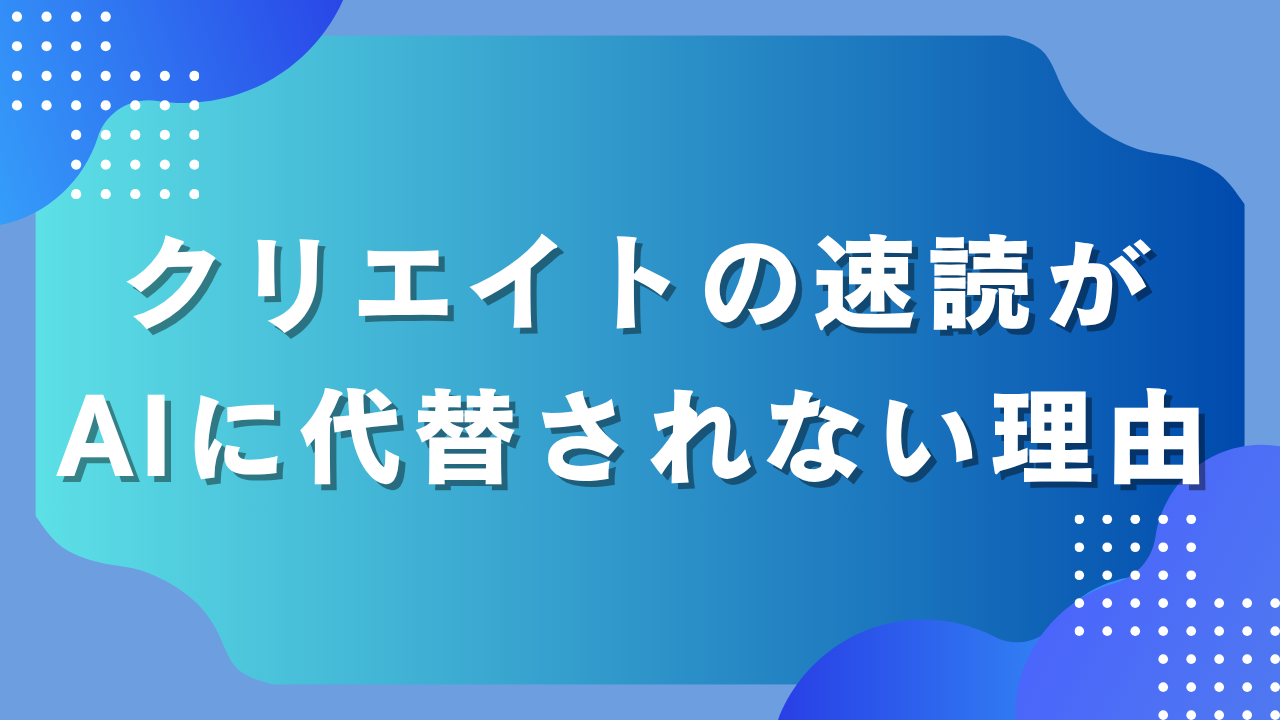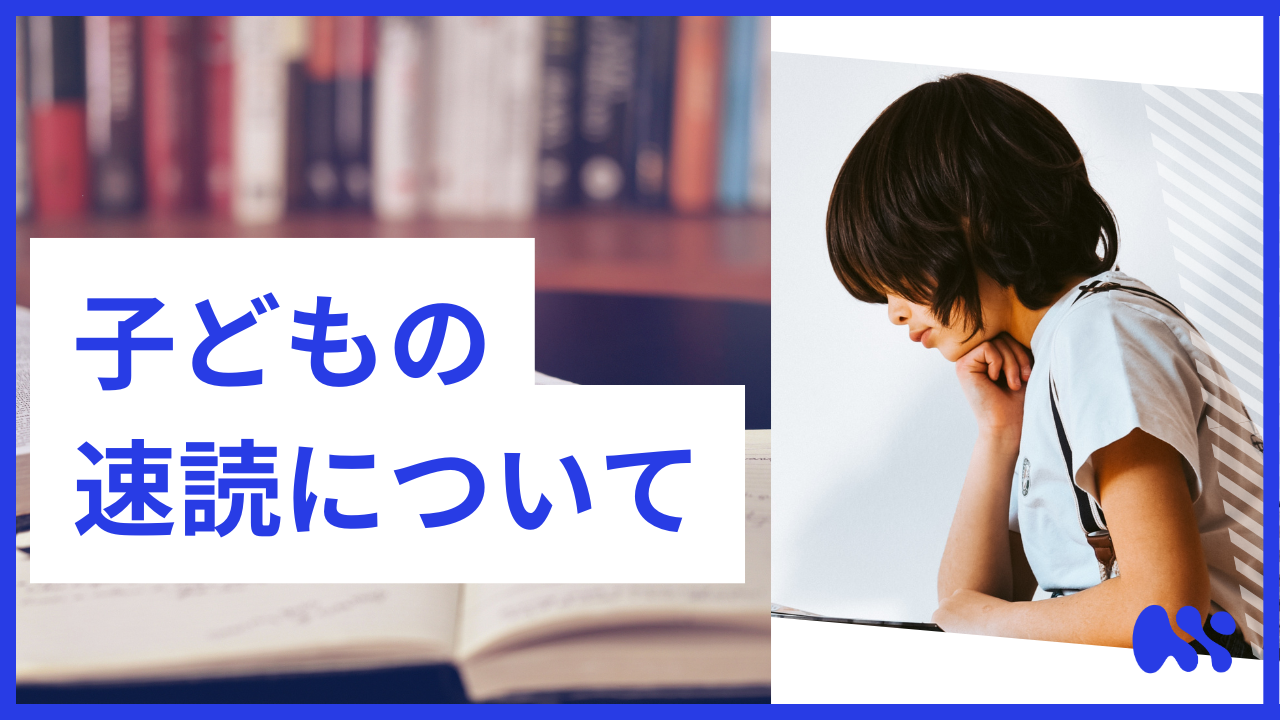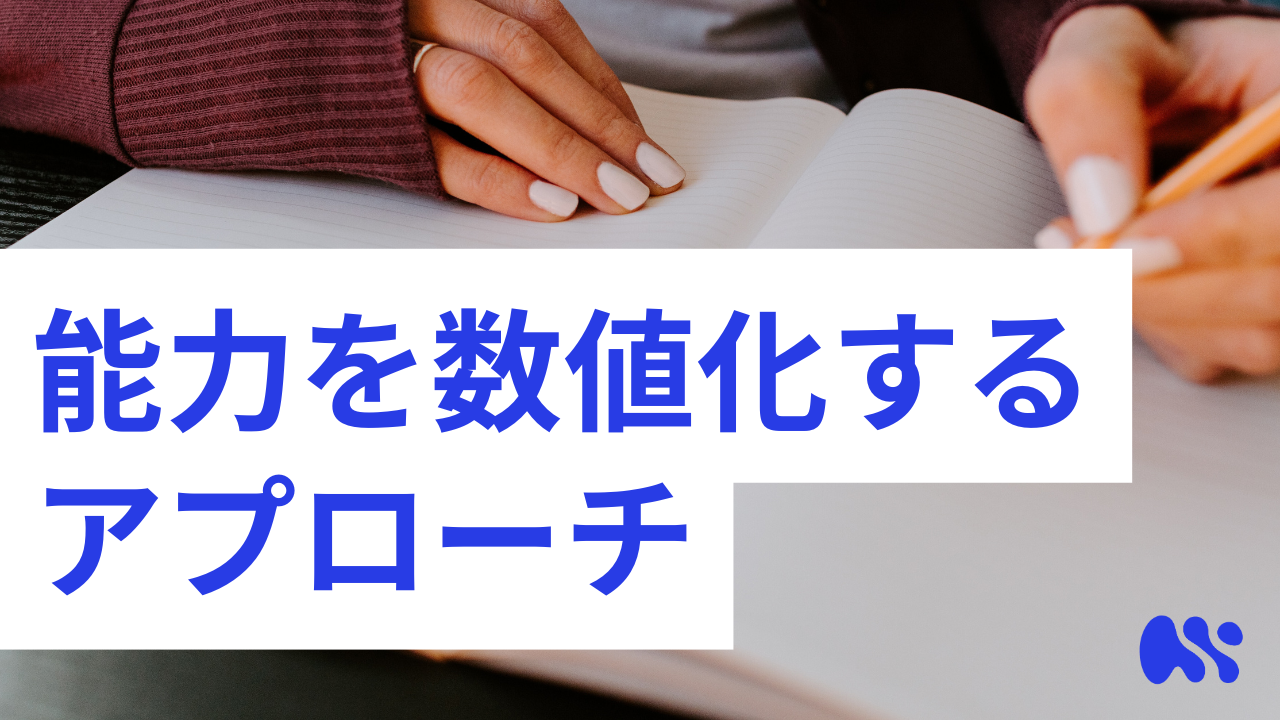目次
この記事では先延ばし癖の原因や、デメリット、治し方ついてご紹介します。
先延ばし癖の3つの原因
心理学者のピアーズ・スティール氏は、先延ばし癖の原因を、エディー型、バレリー型、トム型の3つに分類しています。
エディー型:課題を達成する自信がない
課題を達成する自信がないと、「どうせ良い結果は得られない」と考えてしまい、先延ばしをしてしまいます。
エディー型は、上記のような悪循環に陥りやすい傾向にあります。
バレリー型:課題に楽しみを感じられない
課題に対して興味関心がなく、内容が嫌いであればあるほど、先延ばしをしてしまう傾向にあります。
苦手な科目の宿題が溜まってしまうケースは、バレリー型の先延ばしといえるでしょう。
トム型:衝動に駆られやすい
衝動に駆られやすいと、課題をこなすことで得られる結果よりも、目先の欲求を満たすことを優先してしまい、先延ばしをしてしまいます。
参考:ピアーズ・スティール(著)池村 千秋(訳), 2012年6月, CCCメディアハウス,『ヒトはなぜ先延ばしをしてしまうのか』
先延ばし癖と完璧主義
先延ばし癖のある人の特徴として、完璧主義が挙げられることが多いです。
しかし、これまでの研究から、先延ばしと完璧主義のあいだには、ほとんど相関関係がないことがわかっています。
参考:ピアーズ・スティール(著)池村 千秋(訳), 2012年6月, CCCメディアハウス,『ヒトはなぜ先延ばしをしてしまうのか』
先延ばしのデメリット
作業の質の低下
先延ばしをすると、作業に充てる時間が削られてしまいます。
その結果、作業の質が低下してしまいます。
信頼を失う
先延ばし癖がある人は、締め切りを守れないことがあります。
締め切りを守れないと、周囲から責任感に欠けるとみなされ、信頼を得るのが難しくなります。
時間に追われストレスがかかる
先延ばしをすると、作業時間が限られ、締め切りに追われることになります。
焦燥感を抱えながらの作業は、精神的ストレスの原因となります。
参考:スケジュール管理の第一歩は、タスク管理から。タスク管理が上手い人の特徴。
先延ばし癖を治す方法
一口に「先延ばし癖」と言えど、その原因はさまざまです。
先延ばし癖を治すには、原因に合った方法を実践していくことが必要です。
エディー型:課題を達成する自信がない場合
課題に対して自信がない場合、失敗を恐れ課題を避けてしまいます。
そのため、失敗への恐れを解消することが主な方法となります。
小さな成功体験を積む
自信がなく、課題を先延ばししてしまう方には、小さな成功体験を積むことが効果的です。
小さなことでも成功を積み重ね、自信をつけることで、失敗に対する恐怖を解消することができます。
まずは課題をいくつかに分け、進捗の度合いを記録につけることで、成功を可視化してみましょう。
失敗を想定する
あらかじめ、失敗を想定しておくことで、失敗した際の自信の喪失を軽減することができます。
バレリー型:課題に対して楽しみを感じられない場合
課題に対して楽しみを感じられない場合は、課題に対する興味関心がなく、やる気を失っている状態です。
課題に刺激を与えることが対応策となります。
課題にゲーム性を与える
課題に関連した目標を定め、ゲーム性を与えることで、課題による刺激をつくり出します。
- 今までの半分の時間で課題を終わらせることができるか挑戦してみる
- あえて周りにタイムリミットを公言し、達成できなければ罰則を設ける
目的意識を持つ
目の前の課題が、大きな目標達成に向けて欠かせない課題であると認識することで、先延ばしを防ぐことができます。
- 将来の夢の実現のためには、志望校に合格する必要がある
- 志望校に合格するには、苦手科目を克服する必要がある
- だから、数学の課題を終わらせないといけない
このように、課題の延長上に、自分の目標があることを再確認してみましょう。
トム型:衝動に駆られやすい場合
誘惑を断ち切ることが対処法になります。
誘惑を遠ざける
課題をこなすうえで、障害となる誘惑を遠ざけることで、課題に集中することができます。
スマートフォンなどの電子機器は、手の届く範囲に置いてあるだけでも、人間の注意力を低下させることがわかっています。
意思で解決できるものではありませんから、物理的に遠ざけるのがオススメです。
参考:アンデシュ・ハンセン(著),久山葉子(訳), 2020年11月, 新潮文庫, 『スマホ脳』
参考:勉強に集中できる場所の条件とは。勉強場所選びのポイント4選。
先延ばしをするとどうなるか考える
たとえば、締め切りを守れなかったときの周囲の反応を思い浮かべてみましょう。
不都合な未来をイメージすることが、先延ばしを避ける動機づけになります。
『ヒトはなぜ先延ばしをしてしまうのか』
著者のピアーズ・スティール氏は先延ばしの研究の第一人者です。
先延ばしの原因、悪影響、治し方について、膨大な先行研究をまとめた本書の解説は、説得力のあるものになっています。
異なるタイプの先延ばし癖を持つ、3人の登場人物の日常談をもとに、先延ばしの実態に迫る一冊です。
参考:ピアーズ・スティール(著)池村 千秋(訳), 2012年6月, CCCメディアハウス,『ヒトはなぜ先延ばしをしてしまうのか』