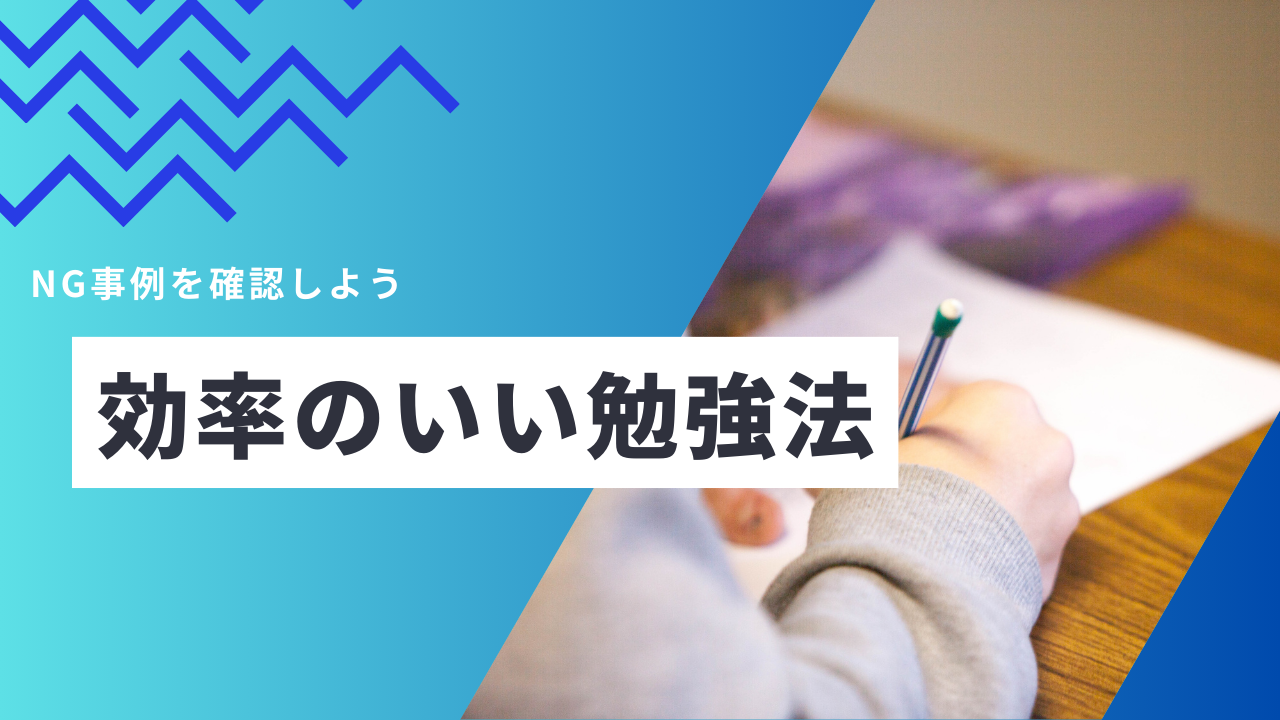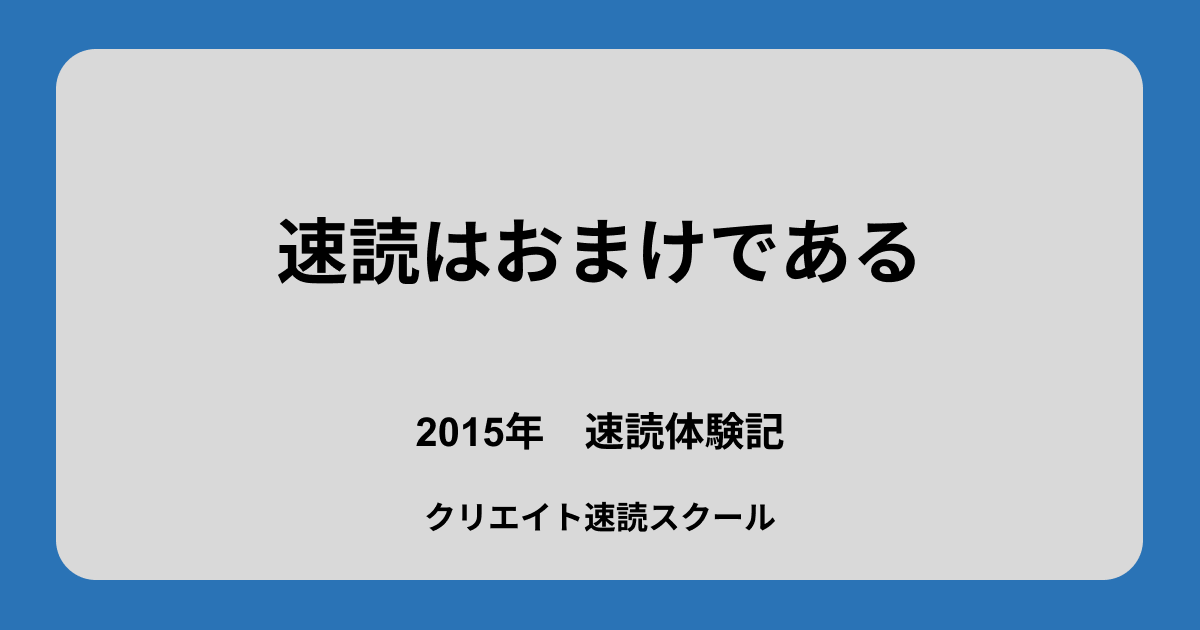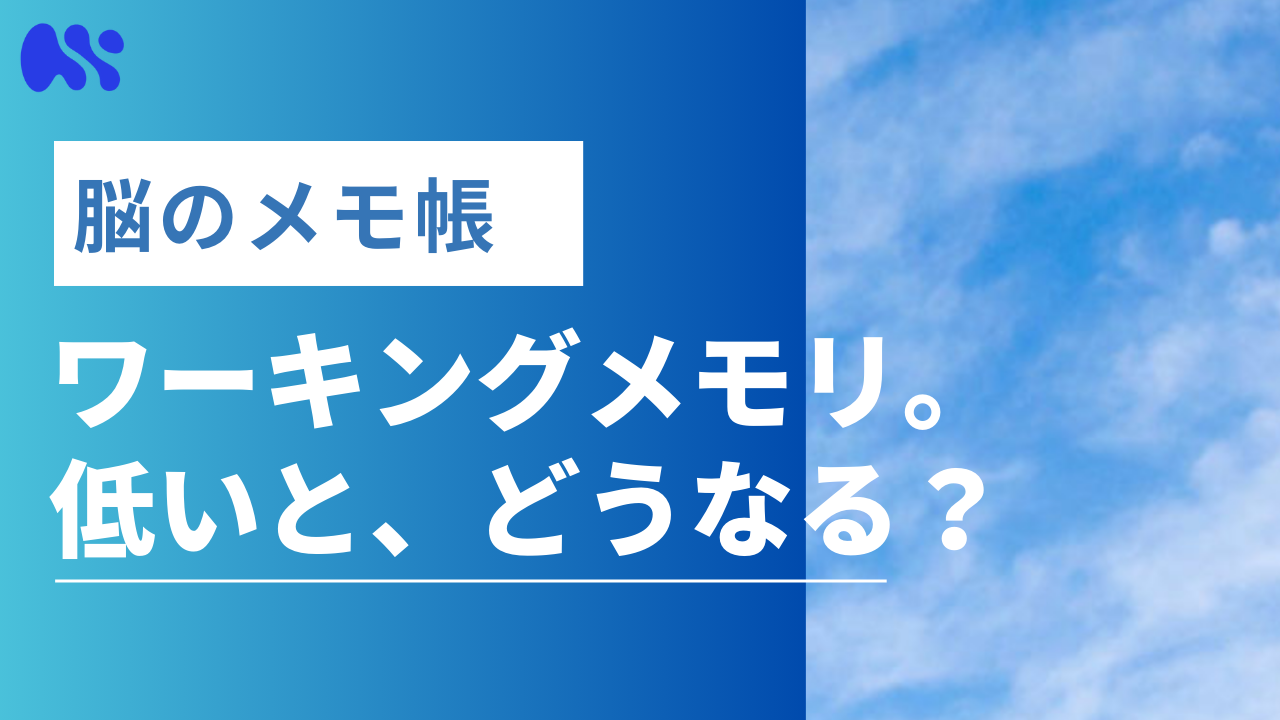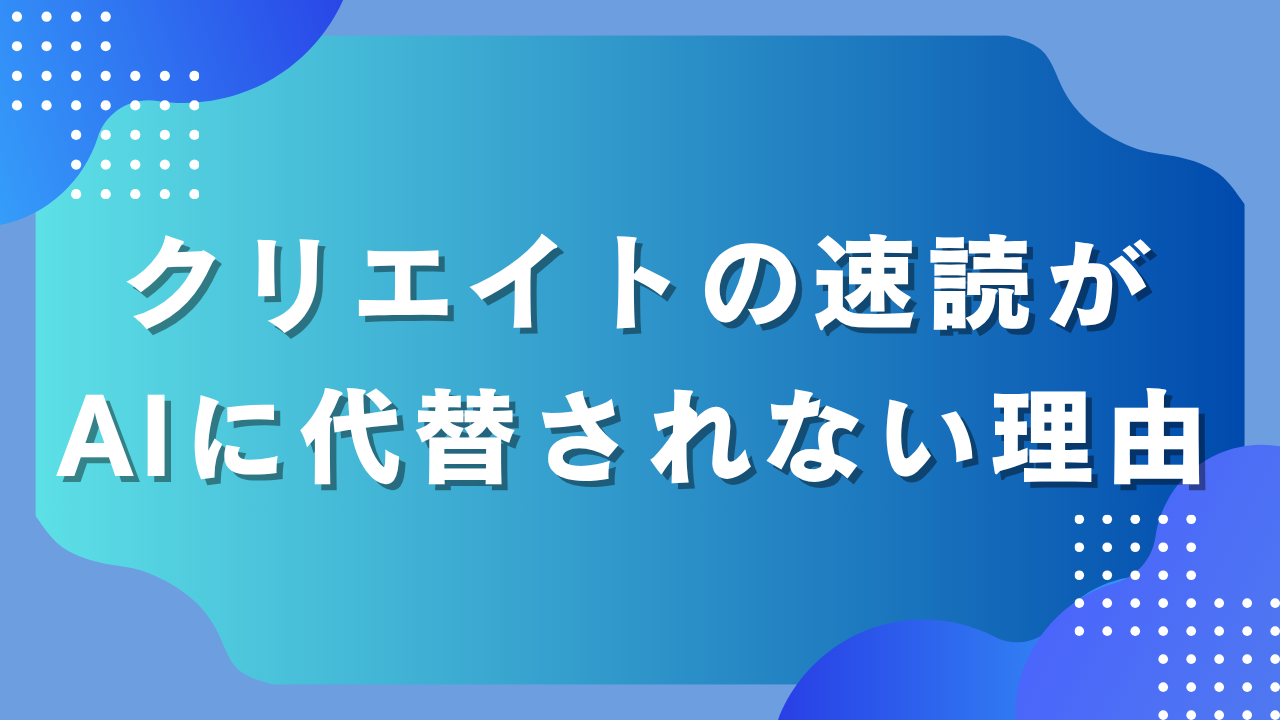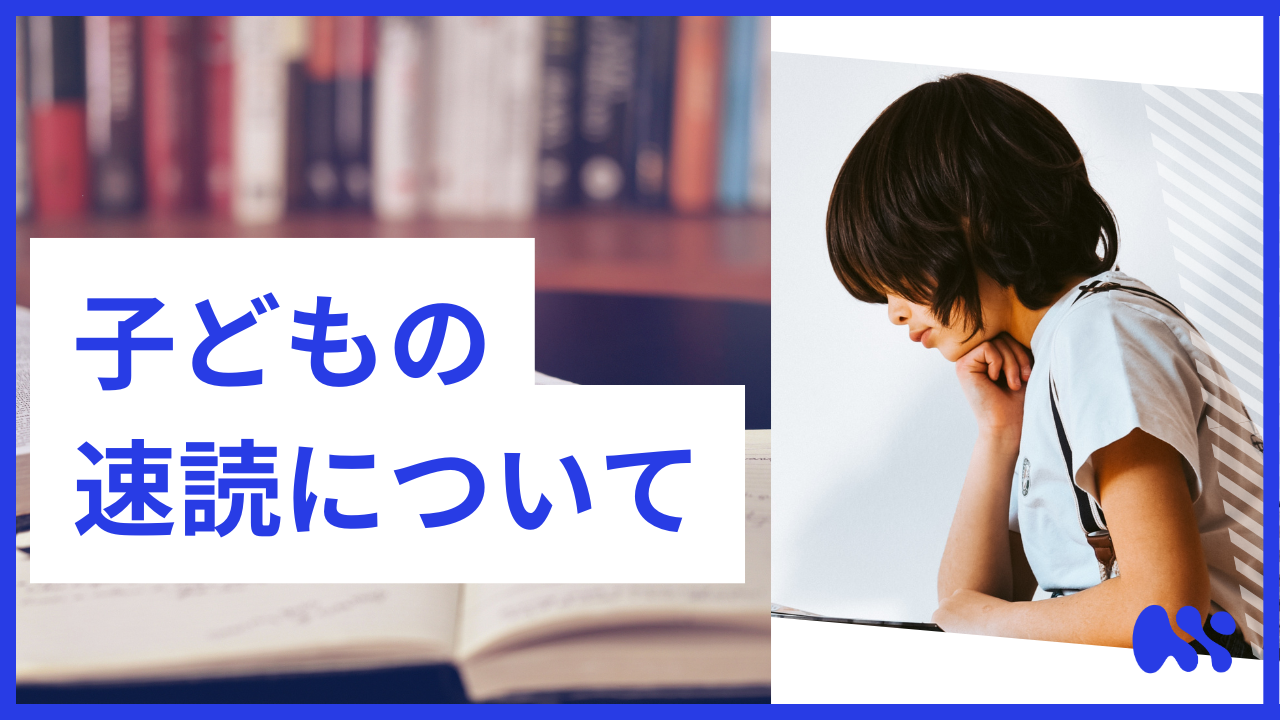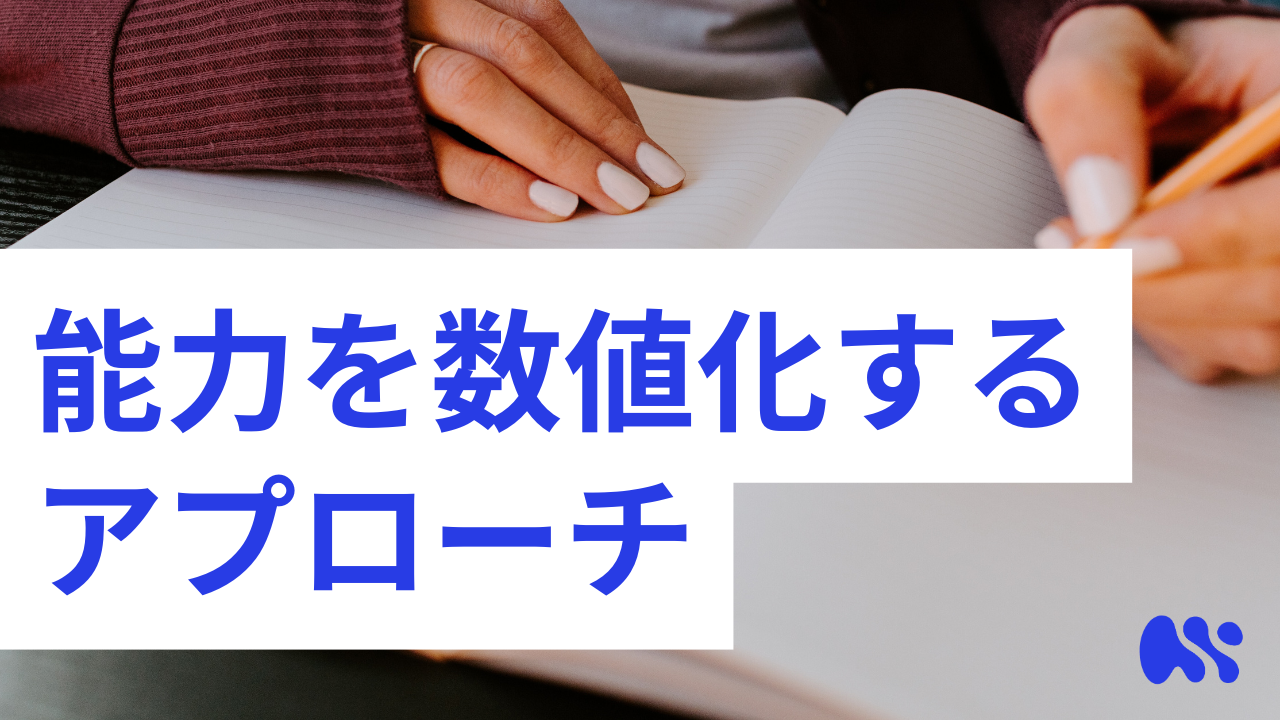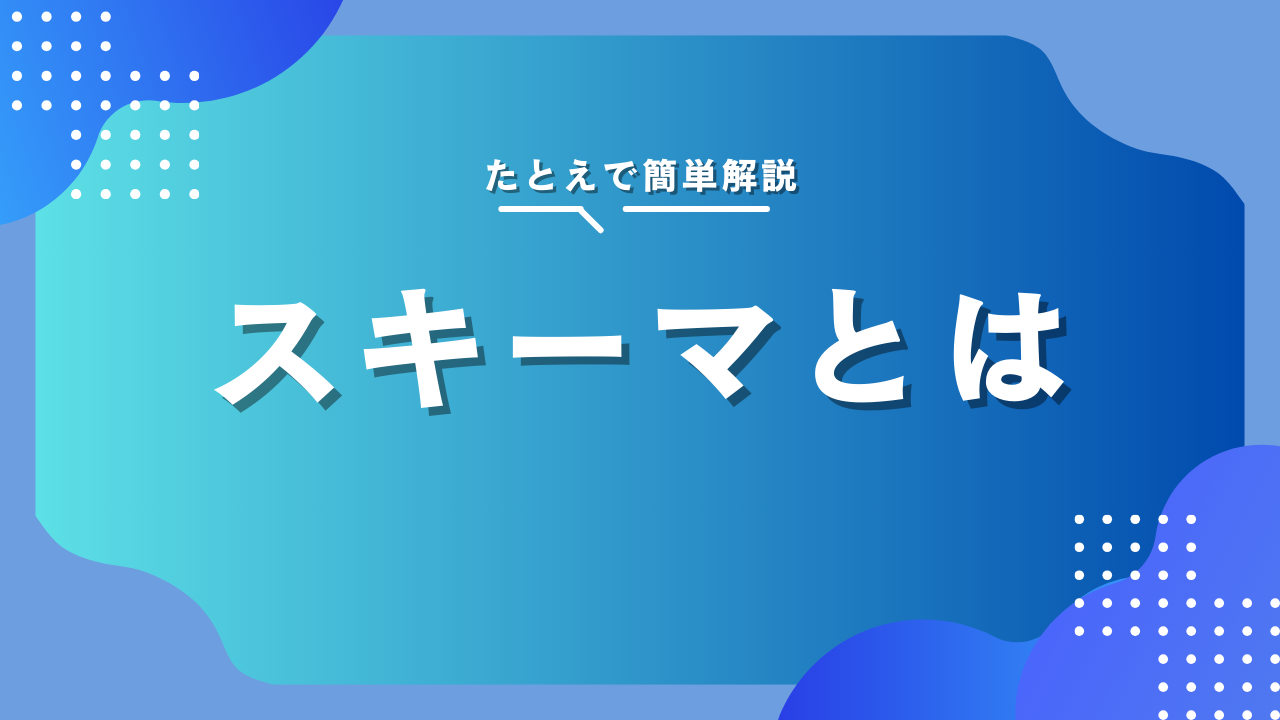
目次
スキーマとは
スキーマとは、「さまざまな事物・事象を認知するとき、既存の知識の枠組みに照らして解釈する、定型的な認知の仕方のこと」と定義されます。認知心理学の用語です。
出典:鹿取 廣人, 杉本 敏夫, 鳥居 修晃, 河内十郎 (編), 2020年7月, 東京大学出版会,『心理学〔第5版補訂版〕』
知識・経験の集合を参照することで、できるだけ省エネをしようとする、私たちの脳の特性を意味します。
スキーマの働きを体験してみよう
これから、スキーマがどのようなものか、体験していただきます。次の文章内容が何を表しているか、考えてみてください。
「手続きはまったく簡単だ。まず、ものをいくつかの山に分ける。もちろん量にもよるが、一山でもよい。設備がないためよそに行くなら、それが次の段階だし、さもなければ準備ができたと言える。大切なのは、やりすぎないことだ。多すぎるよりは、少なすぎるほうがましだ。この注意はいまはわからなくても、守らないとすぐ面倒なことになるし、高いものにつく。最初この作業は複雑に見えるかもしれないが、すぐ生活の一部になってしまう。近々作業は必要がなくなるかもしれないが、誰も予想などできない。手続きがすべて終わると、また山分けして整理する。それを決まった場所にしまう。それは再び使用され、再び同じことが繰り返される。とにかくそれは生活の一部なのだ」
いかがでしたか。一読では意味がとれなかったはずです。
正解は、洗濯です。
これは、正しく「洗濯」のスキーマを参照すれば簡単に理解できるにもかかわらず、適切なスキーマを参照できないと、途端に理解が難しくなる例です。
出典:Bransford, J. D., & Johnson, M. K. June 1973, New York: Academic Press. 『Consideration of Some Problems of Comprehension』 In W. G. Chase (Ed.), Visual Information Processing (pp. 383-438). http://dx.doi.org/10.1016/b978-0-12-170150-5.50014-7
スキーマの特徴
スキーマは、私たちが生活するうえで、どのような役割を担っているのでしょうか。
物事の理解を促進する
まず、スキーマによって、物事の理解が促進されます。これは、先程の「洗濯」の例がわかりやすいです。
適切なスキーマが活性化されることで、不完全な情報であっても、効率よく状況を把握することができます。
たとえば、
「お母さんどこにいった?」
「さっき、スーパーにいったよ」
という文を読むときには、これは会話文である、スーパーとはスーパーマーケットのことである、スーパーに行くのは買い物のためである、といった前提があります。
「お母さん」「買い物」といったスキーマが活性化されることで、文の意味が瞬時にわかるのです。
出典:道又 爾, 北﨑 充晃, 大久保 街亜, 今井 久登, 山川 恵子, 黒沢 学 (著), 2011年12月, 有斐閣アルマ,『認知心理学――知のアーキテクチャを探る〔新版〕』
記憶や認知の負荷が減る
新しい事柄であっても、スキーマを活用し、すでにある知識に関連づけていくことで、記憶や理解にかかる負荷を減らすことができます。
たとえば、同じ作家の本を何冊も読んでいると、他の本よりも楽に読めるようになってきます。これは、その作家の文体に対するスキーマが構築され、認知の負荷が減るためです。
スキーマの特性を勉強に活用しよう
ここからは、スキーマの特性を、勉強に活かすための視点を2つ紹介します。
まずは質より量
新しいことを学ぶ際には、スキーマを持たない状態からのスタートとなるため、大きなストレスがかかります。
ここで重要なのは、いきなり細部に拘ろうとしないことです。わからないところは飛ばしてかまいません。まずは知識のつながりを意識しながら全体像を捉え、大まかなスキーマを形成していきましょう。
たとえば、世界史では、やみくもに暗記をするよりも、まずは歴史の流れ(通史)をイメージするほうがよいとされます。個々の要素を関連づけるための土台をつくり、丸暗記からの脱却を図ろうというわけです。
最初に全体像の理解に時間を割くことは、一見すると効率が悪いように思えますが、長い目で見るとスキーマが形成されることで、むしろ記憶・理解がしやすくなります。
これは、情報量が増えることでかえって覚えやすくなることもある、という記憶のしくみとも関係しています。
試験前にリハーサルをする
スキーマが形成されていない状態では、ちょっとしたトラブルがパニックを誘発し、実力を発揮することができません。
大学入試や資格試験では、本番を迎える前に、試験日と同じスケジュールで家から会場まで移動したり、過去問を解いてみたりすることが有効です。
試験に関するスキーマを作っておくことで、些事に気を取られることなく、試験に集中することができます。
読むのが速い人の特徴
読む速さは、読書についての知識・経験の集合(=読書スキーマ)に大きく影響されます。
過去の読書経験から、読書スキーマが形成されている人は、認知の負荷が少なくて済むため、速く読むことができるのです。
様々な切り口から読書スキーマを形成していく
読書スキーマ形成のためには、一定の読書量が必要です。しかし、スキーマが不十分であるうちは、一冊の本を読むことも重労働です。
昨日、文化庁が公表した「国語に関する世論調査」では、読書離れを示すデータが話題になりました。
参考:「月に1冊も読書しない」が6割超 進む読書離れ(毎日新聞)
たしかに、活字よりも手軽な媒体を好むようになった、という側面もあるのかもしれません。
しかし、当スクールを訪ねてくる生徒さんの声を聞くと、読むことの苦しさが背後にあるのではないかと感じます。
「本当は読みたいけど、読むのが苦しいから、本に手が伸びない」という人の方が多いのではないでしょうか。
クリエイトでは、読書に必要な認知のパターンを細分化し、多種多様なトレーニングをご用意しています。
様々な切り口から読書スキーマを形成していくことで、まずは本に集中する力をつけます。
読むのが苦しい方、活字に抵抗がある方、ぜひ一度体験レッスンにおいでください。頑張ろうとする人を、具体的なトレーニングで応援する教室です。
この記事のタグ
劉 智秀 1999年東京都生まれ/栄東中学・高等学校/東京大学経済学部卒/クリエイト速読スクール二代目代表