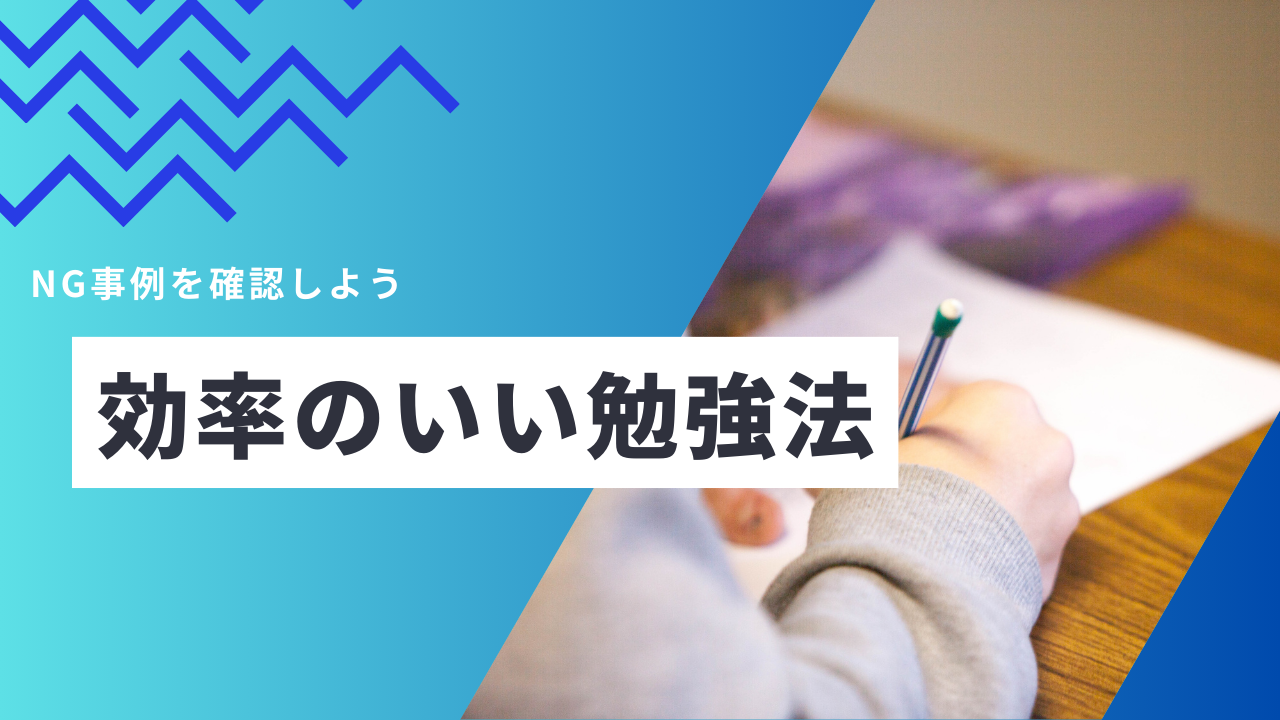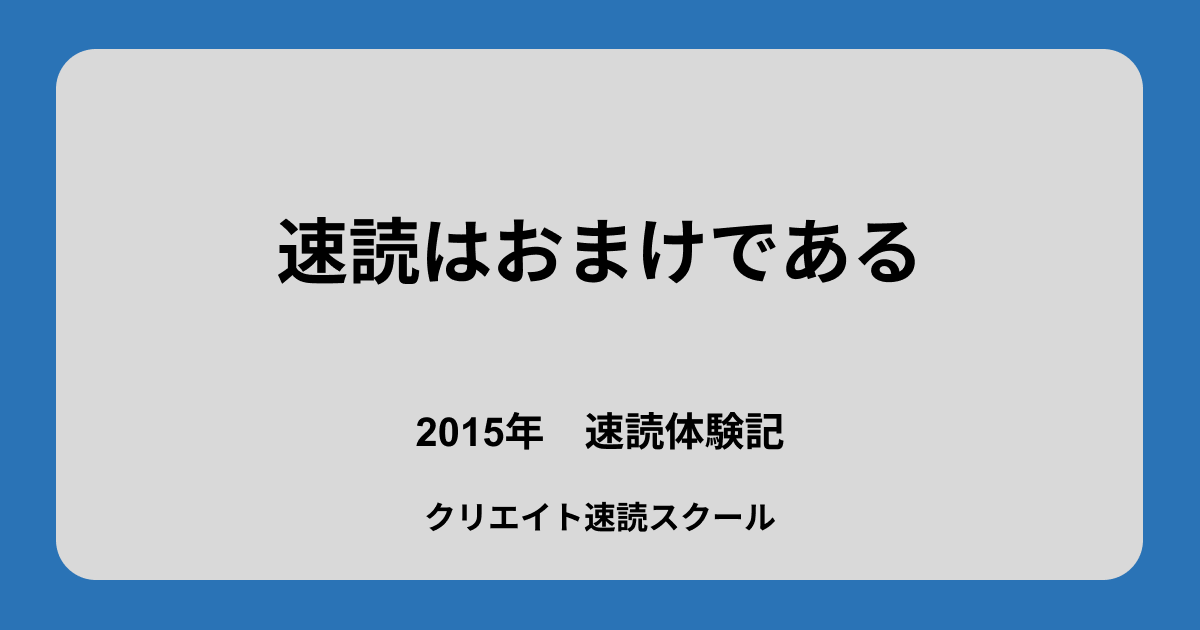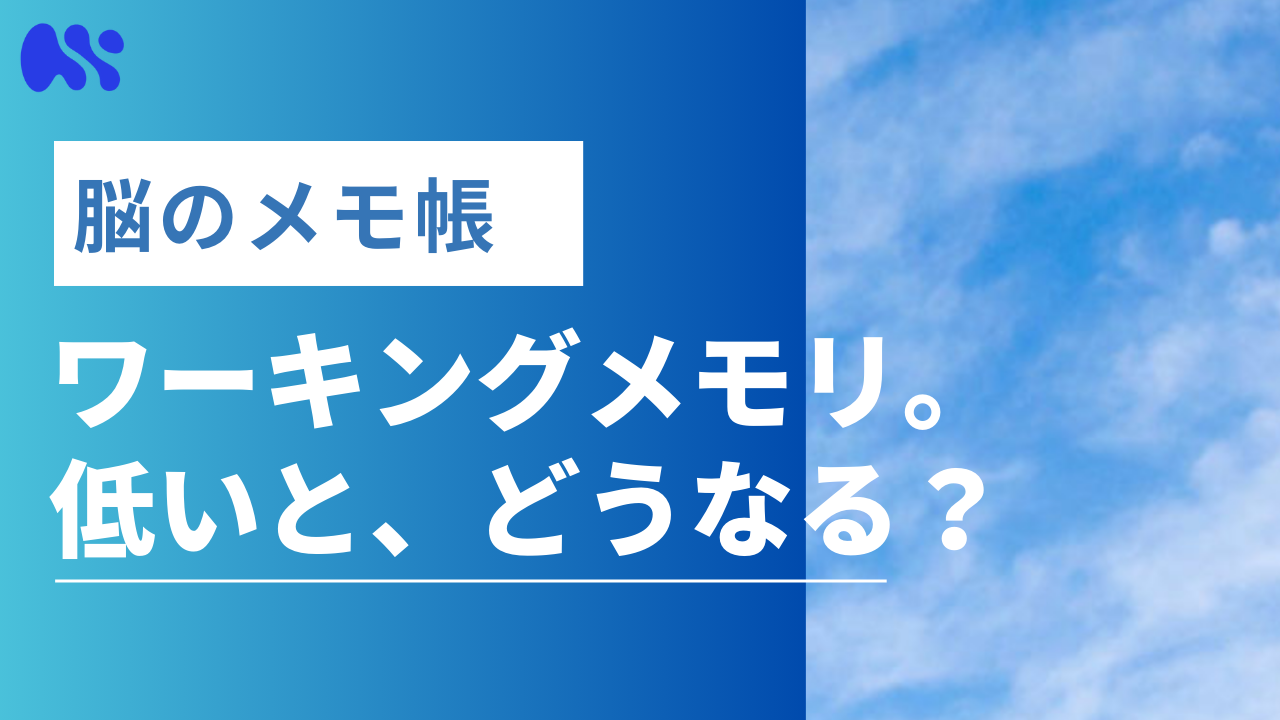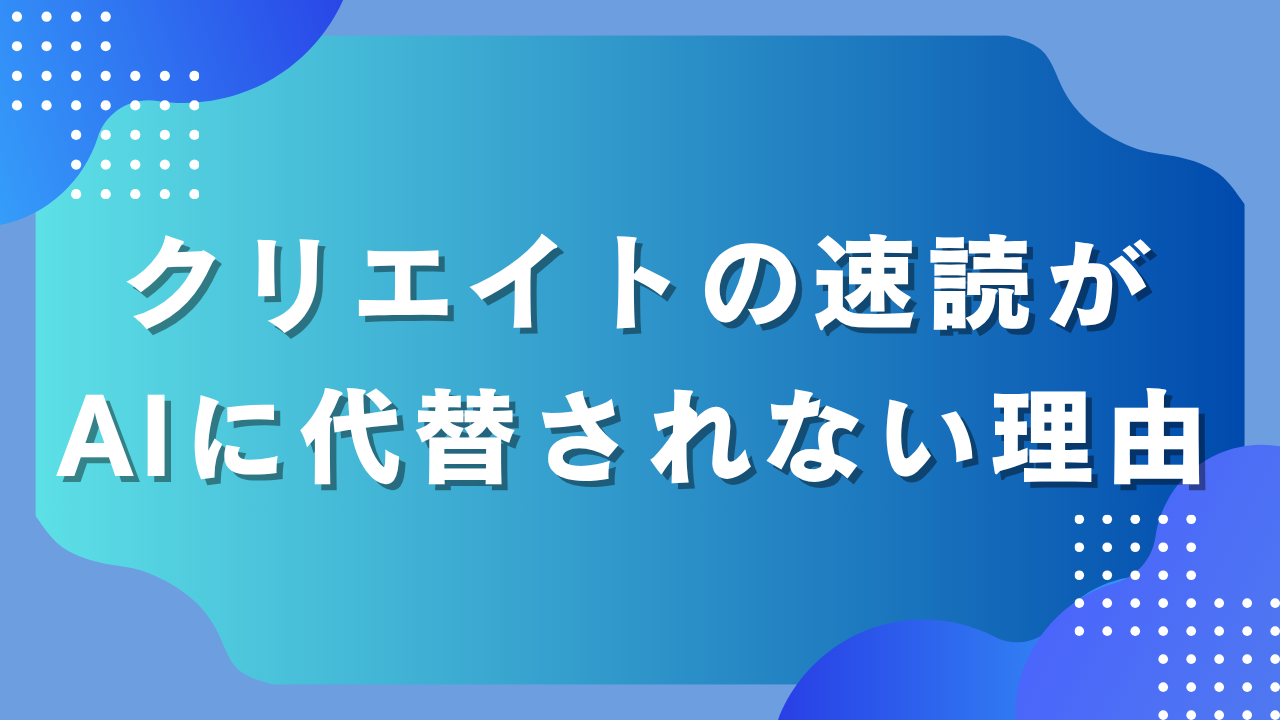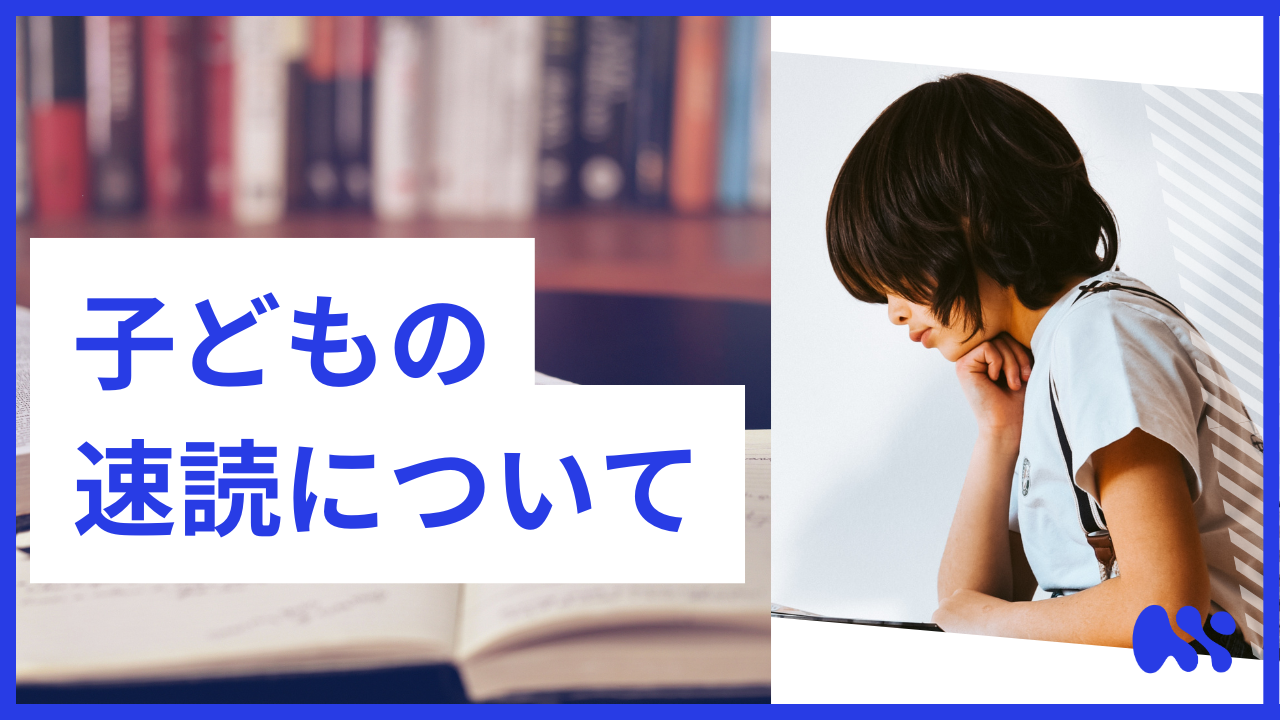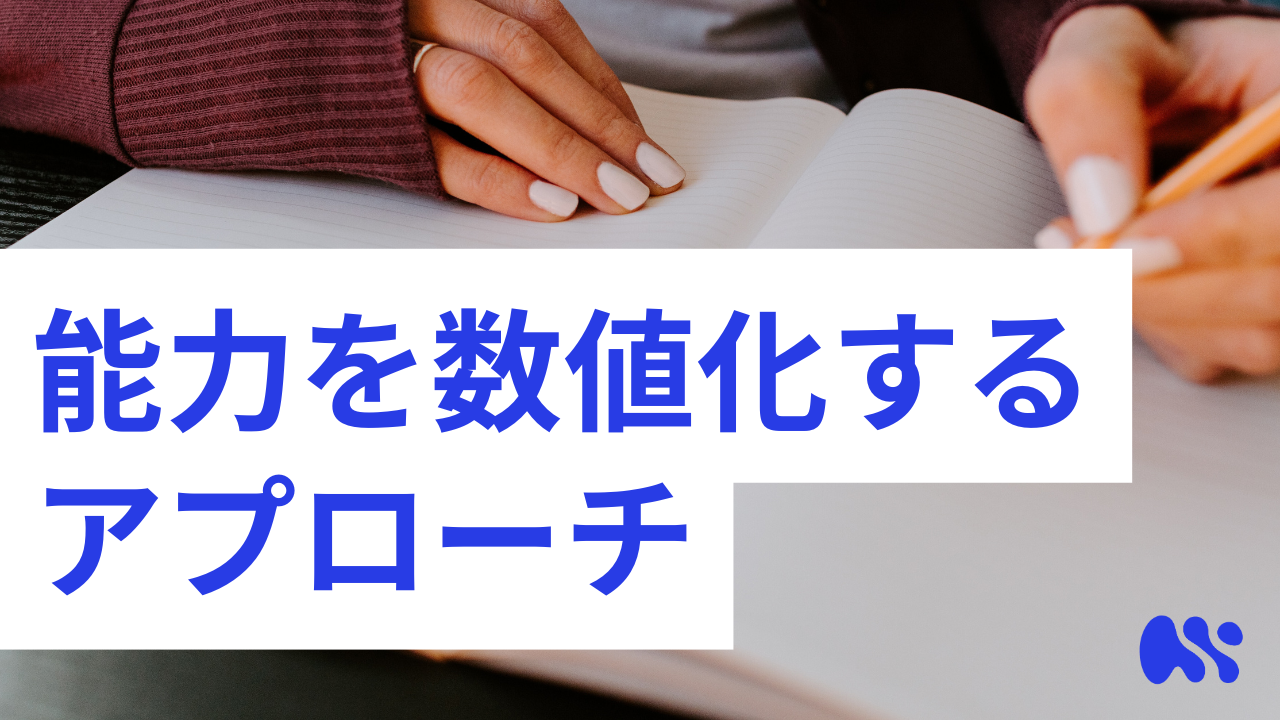目次
この記事では、「社会人の勉強」をテーマに、関連する統計・メリット・勉強法・習い事などをご紹介しています。
社会人で勉強する人の割合
総務省が行なっている「令和3年度社会生活基本調査」によると、有業者*のうち「学習・自己啓発・訓練」*をしている人の割合は25歳~29歳では49.6%、30~34歳では47.3%、34歳~39歳では45.4%となっています。
上記の結果から、若い社会人、特に25歳から39歳の年齢層では、半数近くが積極的に学習や自己啓発に取り組んでいることが分かります。
*有業者とは、ふだん収入を得ることを目的として仕事をしており、調査日以降も仕事を続ける者、および仕事は持っているが、現在は休んでいる者を指します。
*「社会生活基本調査」における「学習・自己啓発・訓練」とは、個人の自由時間の中で行う学習、自己啓発や訓練をいいます。社会人の職場研修や、児童・生徒・学生が学業(授業、予習、復習)として行うものは除き、クラブ活動や部活動は含むものとされています。
社会人に人気の勉強内容
仕事に活かすための勉強
同じく「令和3年度社会生活基本調査」によると、25~39歳の有業者が取り組んでいる学習や自己啓発の内容としては、「パソコンなどの情報処理」が20.3%と最も多く、以下、「英語」が 13.7%、「商業実務・ビジネス関係」が 13.5%*と続いています。
つまり、仕事でのスキルアップを目的にしている人が多いことが分かります。
*総務省が公表している「令和3年度社会生活基本調査」に基づいて、各年齢層(25~29歳、30~34歳、35~39歳)のデータを用いて算出。算出方法は、各カテゴリにおける行動者率を、それぞれの年齢層の推定人口で加重平均を用いました。
最新の人気資格ランキング
リスキリングや学び直しが注目される中、特に資格試験を目指す方が増えているようです。
人気の資格については、「生涯学習のユーキャン」が発表している2024年版のランキングをご確認ください。
社会人の勉強方法と予算データ
勉強の手段
株式会社アスマークの「ビジネスの自己投資に関する調査」によると、自己投資として、20代から50代の有職者のうち56.4%が「読書」、48.8%が「資格取得」、36.0%が外部セミナー・講習への参加」を活用しているようです。
出典:株式会社アスマーク調べ「ビジネスの自己投資に関する調査」(2021年)
勉強の予算
月に費やす自己投資の費用では、全体の46.6%が1万円未満、27.4%が1~3万円、15.4%が3~5万円と続いています。
一般社員クラスでは、月1万円以下が51.2%、5~10万円が15%であるのに対し、部長クラスでは、月1万円以下が29.5%、5~10万円が26.2%であることから、役職が高いほど勉強に費用をかけていることがわかります。
| 回答者 | 1万円未満 | 1~3万円未満 | 3~5万円未満 | 5~10万円未満 | 10~30万円未満 | 30万円以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般社員クラス | 51.2% | 26.0% | 15.0% | 12.5% | 2%未満 | 2%未満 |
| 係長クラス | 46.5% | 31.9% | 12.5% | 8.3% | 2%未満 | 2%未満 |
| 課長クラス | 43.0% | 32.0% | 16.0% | 6.0% | 3.0% | 0% |
| 部長クラス | 29.5% | 23.0% | 26.2% | 6.6% | 8.2% | 6.6% |
| 役員クラス | 27.5% | 27.5% | 15.0% | 15.0% | 7.5% | 7.5% |
出典:株式会社アスマーク調べ「ビジネスの自己投資に関する調査」(2021年)
社会人が勉強をするメリット
リスキリングになる
リスキリング(re-skilling)とは「学び直し」を意味する言葉です。
技術の進歩や産業構造の変化により、求められるスキルが変わっていくことがあります。
そうした中でも第一線で活躍される方々は、勉強の時間を確保している傾向にあります。
業務や仕事に対する理解が深まる
業務や仕事に対する理解が深まることも、社会人が勉強をするメリットのひとつです。
たとえば営業職がマーケティングの知識を学ぶことで、自社製品の強みを明確に認識できるようになります。
その結果、自社製品の優位性を顧客に効果的に訴求することが可能になります。
選択肢が増える
社会人が勉強をすることで、キャリアの選択肢を広げることができます。
たとえば、営業職であっても、簿記や財務の知識があると、異動や社内公募で、財務部門の仕事に就くチャンスが得られます。
現職の仕事を豊かにするだけでなく、キャリアの選択肢を広げるうえでも、勉強は重要な意味をもちます。
社会人の勉強方法
オンライン学習
社会人の勉強方法の一つとして、メジャーになりつつあるのがオンライン学習です。
スマートフォンやPCで、場所・時間を問わず学習できる点が、少ない時間を活用する社会人にマッチしています。
主な学習プラットフォームとしてUdemyやCourseraなどがあります。
書籍や教材による自習
書籍は、体系的に知識を整理し、自分のペースで繰り返し学習できるため、特定分野を集中的に学びたい場合には、効果的な手段となります。
スクールに通う
法律・医療・会計などの専門性の高い分野については、独学よりもスクールを利用される方が多いようです。
一定の時間を確保できる場合は、スクーリングを検討してみるのも、選択肢の一つです。
勉強を続けるコツ
目的を明確にする
仕事の合間を縫って勉強を続けることは、容易ではありません。
モチベーションを維持するためにも、勉強を始める前に、目的を明確にしましょう。
具体的に「資格をとって転職する」といった目的意識があると、気持ちが折れにくいです。
勉強場所を決める
家庭や仕事との切り替えがスムーズにできるよう、勉強場所を決めてしまうことをおすすめします。
最寄りのレンタルスペース・自習室などを契約するのも選択肢の一つです(月額8,000〜15,000円)。
参考:勉強に集中できる場所の条件とは。勉強場所選びのポイント4選
学習計画を立てる
漠然と「勉強しよう」と意気込んでも、仕事終わりの疲れた体では、机に向かえないことがほとんどです。
そのため、事前に、目標と連動した学習計画を立てることをおすすめします。
計画はできる限り具体的な内容とし、「いつ」「どこで」「何を勉強をするか」を設定します。
以下の記事では、タスク管理に焦点を当て、計画作りのポイントをご紹介しています。
隙間時間を利用する
通勤時間や電車の待ち時間などを少しずつ勉強にあてることで、勉強時間を確保できます。
すぐに手が伸びるよう、学習内容や参考書は、コンパクトなものを選びましょう。
勉強する社会人には「速読」がおすすめ
少ない勉強時間で勉強を進めるうえでは、学習時間をいかに有効活用するか、という視点が大切になってきます。
以下の記事では、投資家瀧本哲史氏に「大人の習い事としての速読」をご紹介いただいています。
大人の習い事になぜ速読がいいのか? という疑問に答える内容となっています。
どうぞご一読ください。
受講生の声
「入会を決めた理由」企業を分析するアナリストの仕事をしており、有報などの開示資料をはじめ、様々な書籍や、論文を読む機会が多く、そのスピードが生産性に直結するから。速読というと、単に文章が速く読めるだけという印象がありますが、認知能力の基礎を鍛えているのだと認識するようになりました。サッカーでいうところの体力や筋力を鍛えているイメージです。
「入会を決めた理由」仕事柄、大量のインプットを必要とするため、インプットを効率的にやっていく、及びアウトプットの精度も高めていきたいため。あわせて小説etc本を読むのが好きなので、空いている時間を上手く使って本を読んでいきたい。
「入会を決めた理由」大量の仕事関連の資料を理解しながら読む必要があるため。加えて、今後さまざまな試験を受ける予定であり、限られた時間の中で、多くのことに取り組むために相当の能力アップが必要だと考えたからです。読む本のジャンルが広がりました。これまで専門書や論文を読むことにかける時間が膨大だったため、スクールで多様なジャンルの本に出会えることを楽しみながら通えています。
(医大勤務 Tさん)
読書スピードが伸びてインプットに使う時間が減ったおかげで、アウトプットに使う時間が増えています。1年ほど前は参考書を読むので疲れてしまい、大事と分かっていてもアウトプットに時間を使うことができていませんでした。
(商社マン Mさん)
コロナ対策も兼ねて、クリエイトには車で通ってます。運転中、視野角が拡がって様々な情報を見落とさずに収集することが出来、また判断力も上昇したと実感します。
(営業マン Hさん)
仕事における情報処理能力は上がってきたと思います。打合せで議論についていくのが楽になり、発言時も、以前は発言内容が論理が飛躍したり脱線したりしていたのですが、整理しながら発言できるように少しずつなってきて、変わってきた感じがしています。
処理可能な量が増えたので、最近は結論だけではなく、なぜそのようなアプローチに至ったのか等の過程の部分も丁寧にみることができるようになりました。そうなると知識の幅も広がりますし、相互理解も深まります。それは思考体力がついて余裕が生まれたからこそだと思っています。
今まで実用書(250ページ前後)を読むのに3時間以上かかっていたが、今は1時間ちょいで読めるようになった。本を読むにあたっての情報処理スピードや要点をつかむ能力が10回の受講だけでも大幅に向上した実感あり。
(銀行員 Hさん)
1か月間の読了冊数が入会直後と比べ4.5倍になりました! 3月→4冊、4月→12冊、5月→18冊。倍速読書訓練により、読書時の理解度、スピードをコントロールできるようになったことが、この結果に繋がってると思います。
一番変わったと感じるのは読書に対する集中力。専門書等は、あと何ページでその章が終わるのかを気にしながら読んでいたが、気づいたら読み終わっていることが増えた。また、集中し始める速度も上がったため、隙間時間での読書を楽しめるようになった。
(弁護士 Kさん)
この記事のタグ
劉 智秀 1999年東京都生まれ/栄東中学・高等学校/東京大学経済学部卒/クリエイト速読スクール二代目代表