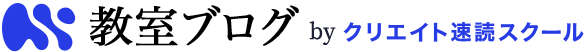2007-10-23
納得のできる予備校選びをするために
クリエイト速読スクールの講師、大西隆さんより「公務員試験に関して」の原稿が届きました。
今回から数回にわたって、公務員試験の予備校選びの基準について考えを紹介していきます。公務員試験対策のために予備校に通う場合は、最低でも年間30万円近くの出費になるので、失敗は許されません。そのため、殆どの受験生が入校前に複数の塾のパンフレットを読み、情報収集をして最善と思える塾に通います。しかし、高いお金を払っても、入校前に自分が想定していたサービスを受けられないことや、自分の選択に後悔するケースは後を断たないのが現実です。このように失敗する理由は、着眼すべきポイントをはずしているからです。こういう不幸なケースを一つでも減らし、一人でも実のある予備校選びをするために、いくつか私の経験から着目すべきポイントを詳細していくことにします。また、予備校のパンフレットのウラを見抜く方法も同時に伝授します。
では、予備校選びをする際に見るべきポイントを列挙してみましょう。それは、①公務員試験について知る、②民法の授業数をチェックする、③面接対策をチェック、④論文対策をチェック、⑤講師が常勤かチェック、⑥自習室やカウンセリングなどのチェック、⑦合格実績もチェック。どうです、見るべきポイントが異なっているので、少々違和感を覚える方もいらっしゃると思います。
しかし、一般的な予備校選びだと、専ら⑦の合格実績ばかり着目する傾向にありますが、公務員試験に関しては、その方法は極めて危険です。何故なら、合格者数の算定方法が予備校間で違いが生じているからです。本当は内定者数または最終合格者数のみ掲載するべきにもかかわらず、一次試験突破者の数も平気で加算している予備校が多いのが現状です。中には、模試を一回受けただけの受験生の実績を予備校の実績に加算するなど、露骨に実績を水増しするケースもあります。事実、大手予備校Aは昨年にパンフレット訂正という行政指導を受け、大手予備校Bは文部科学省のホームページで悪質行為を行ったとされ文部科学省から公表(ホームページなどで、企業名と悪質と見なされた行為を公表すること)という行政罰を受けています。
一般的な予備校選びに潜む危険なポイントは、以後に渡って詳細に述べますので今回はこの辺に留めておきます。大学受験予備校と同じような基準で選ぶと、失敗する危険があるということは、もう一度ここで明記しておきます。
それでは、次回は①の公務員試験制度について細かく検討していきます。 大西 隆