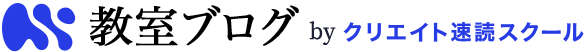2017-05-08
自分の読み方とは全く異なる深い内容理解をしている光景を何度も目の当たりにして、
第67期文演(17/1/28~4/22)アンケートです。
第1回は、仕事をしながら税理士試験の勉強をしているAさんです。
これから、中小企業診断士試験にもチャレンジしようしています。
Aさんの文演アンケート
Q.1 当講座をどんな目的で受講しましたか?
A.1 一番の目的は中小企業診断士試験の勉強に役立てることです。特に2次試験に合格するには、与件文と問題文から出題者の意図を読み取った上で、出題者が要求していると思われる答えを答案用紙上に論理的に表現しなければなりません。カリキュラムが進むにつれ、私は自分の読解力や文章力に不安を覚えるようになっていました。そんな折、以前松田さんに薦められた「文演」を思い出しました。過去の受講生の体験記にも「読む力と書く力の両方を鍛えられる」とあり、きっと試験勉強に役立つだろうと思い受講を決めました。
Q.2 「文演」を受講して文章への印象で変わったことがありますか?
A.2 文演を受講が進むにつれ、普段読んでいる書籍がいかに高度な品質管理基準をクリアして世に出てきているのかを思い知りました。また、普段のメールやSNS等で目にする自他の文章の至らないところが目に飛び込んでくるようになりました。授業で扱われる文章の「悪い見本」へのダメ出しを通じ、今までは漠然と気持ち悪いと思うことしかできなかった文章についても、「これは授業で読んだあの文章のパターンだ」という具合に、どこに問題があるかを意識するようになりました。
Q.3 宿題の「要約」はどうでしたか?
A.3-1 「授業前」 まず受験勉強と並行して受講していたため時間を捻出するのが大変でした。とはいえ細切れの時間で課題文をチラ見する程度では太刀打ちできないだろうと思い、要約する際にはまとまった時間を取りました。実際に行った手順は以下のようなものでした。
1) 骨子と思われるところに線を引く。
2) 1)で線を引いた部分を一度全部抜き出す(この時点では規定の倍の1500字以上ありました)。
3) 冗長な箇所や繰り返し部分の削除、複文から単文への修正、という地道な作業を繰り返して規定の文字数(750字)に収める。
3)が一番怖い作業でした。誤って重要なところまで削ってしまうのではないかとびくびくしながら行いました。この段階では作図用のソフト上で一文ずつ分解し、それらをツリー状に配置して、構成も同時に考えました。上記の工程を経て、提出期限の一週間前には何とか規定の750字に収まりました。しかしなぜか前半に比重がかかりすぎていました。その状態で一度仮提出したのですが、案の定バランスが悪いとの指摘が松田さんからありました。やはり期日ギリギリまで考えようと思い、構成を練り直して何とか期限前日に提出しました。
A.3-2 「授業後」 構成は一度練り直したこともあり、多少は自信を持っていました。しかし蓋を開けてみると入れるべきキーワードを入れられなかった反面、あまり重要でないところに一段落割いてしまっていました。前者のキーワードは最初の手順で線を引いた際にスルリと抜け落ちていました。後者は「小見出しで使われている言葉だから重要だろう」という安易な考えで一段落割いてしまいました。しかし、松田さんの説明を後から反芻すると、確かに筆者はその部分に重きを置いていない、ということを納得しました。どちらも自分の読解不足を思い知らされる内容でした。
Q.4 全体的な感想をお聞かせください。
A.4 前述したとおり、講座は全体を通じて配布される文章の「悪い見本」に対してダメ出しをしていく、というものでした。序盤は比較的わかりやすい形式的な不備が多く、何とか発言できたのですが、講座が進んでいくにつれ、文章の内容、ひいては文章に書いていないことにまで考えを巡らせなければ指摘することができなくなっていきました。そのようなときは一緒に受講していたメンバーや松田さんの意見に助けられました。自分一人では表層的な読み方しかできませんでしたが、周りの人たちが同じ文章について自分の読み方とは全く異なる深い内容理解をしている光景を何度も目の当たりにして、文章を読み書きする際の様々な視点を知ることができました。
今回私が得た一番の教訓は、「正しい文章を書けることも大事だが、自分が書いている文章は本当に今ここで書くべきものなのかどうかを考えることも同じくらい大事だ」ということです。伝えたいことがあればあるほど、文章は冗長になりがちです。しかし、悲しいことに人は他人の文章には無関心です。人に読んでもらうためには「敢えてここでは書かない」という判断も時には必要なのだ、ということがよくわかりました。文演で学んだことは当初の目的だった筆記試験対策はもちろん、文章に関するあらゆる場面で役立つことでしょう。メンバーの中には高校生もいましたが、若いうちにこのような貴重な学びの機会に巡り会えることは羨ましい限りです。私も学んだことを風化させぬように、日々実践を通じて文章の勉強を続けていこうと思います。どうもありがとうございました。
2016-08-01「先日古本屋で本を一冊立ち読みで読み切りました(漫画ではありません)」のAさんです。
Aさんは中小企業診断士試験に受かったら、経営者のよき伴走者になります
断言できます。
2つの試験のためにも、速読、再開してくださいね。
ところで、仮幹事をお願いした2017-04-30のTさんの話によると、「勉強会」に高校生の2人も登録してきたとのことです。
明敏な大人たちにゴシゴシ揉まれればいいのです。  真
真