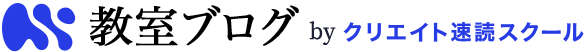2015-02-25
自分と他人、2つの目線から文章を読んだことで、記憶が鮮明になった
第62期文演(14/9/27~12/6)アンケートからです。
きょうは、2014-06-17「本をよむときの集中力をつけようと思った」の慶大生Tさんです。
Tさんの文演アンケート
Q.1 当講座をどんな目的で受講しましたか?
A.1 大学で文章を書く機会が何度かあり、その度に書く力がないことを痛感していたため。文章の内容について吟味する機会はあったが、文章の型や作法について考えた経験はなかった。過去に参加した人たちのアンケートを読んでいると、要約の課題を通じて文章について実践的に考える作業があることがわかり、興味がわいた。それと、単純に言葉について深く考えたかった。「文は人なり」という言葉もあるし、言葉のニュアンス、紡ぎ方一つで表現はさまざまに形を変える。言葉や表現、文章に向き合い、感受性を磨ける機会になったら、という願いもあった。
Q.2 「文演」を受講して文章への印象で変わったことがありますか?
A.2 文章を立体的に見ようとするようになった。文演を受ける以前は内容をとることに必死で文章の構成、量、使われる表現の気配り、配慮などを見ようとしなかった。こうした文章の型と内容は関連しており、文章の型を見ることができれば、内容理解に大きく役に立つことを実感できた。
Q.3 宿題の「要約」はどうでしたか?
A.3-1 「授業前」 文章を大雑把に読んだ後、2週間前から空き時間を使って少しずつ書き始めた。決められた字数にはすぐに達したが、文章の構成や比重、表現の厳選にかなりの時間を要した。段落構成はどうすればよいのか? 何を多めに書いてなにを削るか?自分の言葉に直すかそのまま文章の言葉をつかうか? を考えた。何度見なおしても直すことがどんどん出てきて、永久に書き終わらないのではないかと思うほどだった。期限通りに自分で完全に満足のいく要約を仕上げることはできなかった。提出後に他の方の要約を読んでみると、同じ文章を要約したにもかかわらず個々人で解釈や表現に違いがあることに驚いた。他の人の要約を見直しながら自分の要約を改めて見直してみると、自分の至らない点をいくつか発見できた。
A.3-2 「授業後」 文章を要約するためには内容と構成の2つを文章から忠実に読みとり、さらに要約内で表現しなければならない。僕の場合は読み取りも表現もまだまだ抜けがあった。他の人の要約と比較しても気づかなかった様々な点を松田さんにご指摘いただいた。まとめて書いたつもりが、まったく整理されていなかったこと、何気なく書いてしまい作者の意図とずれてしまったこと、自分では気づけないことが多かった。
自分の講評だけでなく、他人の講評を聞けたのも大きい。他人の要約は自分が書いたものではないので、松田さんの講評を客観的に聞くことができた。書き手—読み手の立場から指摘をいただくのも勉強になるが、同じ指摘する立場でこのように指摘するのか、と考えられたのはよかった。また、要約した文章の内容は頭の中に鮮明に刻み込まれた。要約対象の文章が非常に良い内容であること、18個の形の違う要約にふれたこと、自分と他人、2つの目線から文章を読んだことで、記憶が鮮明になった。204ページある本のうちのたった12,3ページの内容がこれほど濃く、様々な場面で意識、活用できるものだ、ということは要約するまで気づけなかった。これだけ深い(と自分の中で思える)読みを経験すると、いままで読んできた文章の中で見過ごしてきたものがたくさんあるのでは? と後悔の念に若干かられた。おなじ文章を何度も何度も読み、要約して味わう楽しさ、奥深さ、効率の良さを知った。速読をやっていると、本をたくさん読めることがよいこと、という感覚に陥りがちである。もちろん量も大事である。しかし、乱暴な言い方をすれば、量は時間があれば何とかなってしまう。しかし質を意識することは時間があっても難しいし、しかも人によって質の高め方は違う。この違いを認識しあえればもっと人と話していて楽しくなるのではないか。多く読むだけでも大変なのに、質ももっと意識しなければならなくなった。視野が広がって楽しいが、大変である。
要約のプロセスは勉学における様々な場面で意識できた。新しい概念を取り込むことも一種の要約である、という自論がおぼろげながら出来上がった。キーワード同士を有機的に組み立てて、その分野の言語でつないでいく、という流れだ。要約の課題文と要約するプロセス、自分の作った要約の3つからめいいっぱい、多くのことを学べた。密度が濃い勉強とはこういうものだ、と実感した。
Q.4 全体的な感想をお聞かせください。
A.4 文章の講座ということで多少身構えたが、最初の数回の授業で、すんなりなじむことができた。速読の授業と根っこが全く同じだからなのだと今自分では思っている。
速読は基本的に自分で何かを探す授業だ。あーだこーだ時間と頭を使いながらスコアを上げる目標を持ち、講師のアドバイスとブログの声を足掛かりにして自分と向き合い、技術の向上をはかるものだ。「文章を書く」ことに主眼を置いたとされる文演でもコンセプトは基本的に同じだった。考える材料(文章)が配られ、自分の頭で文章について考え、発言したい人は発言し、松田さんの話と合わせてもう一回考える。この繰り返しだ。文章の題材、ポイント、テーマ、格調、要約とさまざまに形は変わるが基本は同じだ。ただ、文章を読む速読に、書くことが加わる。しかも比重は書くことにあるので、松田さんのコメントが多くなる。逆に言えばそれだけの違いだ。2つとも主体的に参加すればするほど、面白くなるのは間違いない。
速読に終わりがないように、文演も8回の講座をもとにもっと応用できる。そもそも8回の講座の内容をまだ完全に咀嚼できていない。それほどに内容の濃い8回であった。
8回の講座を通じての目標は自分なりの型を作ることだった。しかし、この講座を受けていると、逆に自分が文章を書くときに特定の型にあてはめすぎているのでは、と気づいた。限られた表現を使い、限られた構成を用いて、相手のことを考えずに自分のことを考えて文章を書いていた。他人のことを考えて、構成や内容、表現にさりげなく気を使って書かれた文章、要約はやはりよい、と素直に思えた。よい文章は整理整頓されていて、表現したい場面を表現するのに最適な言葉で語られていた。ある高校生の要約を読んで思えたので、書き手の状況など関係ないのだ。いつかこんなに人のことを考えて文章をわかりやすく、さらに自分の味を少しだけ出しながら書けるようになりたいと強く思った。
文章を書けるようになりたいと思って受講した講座で、文章を書くことの難しさ、奥深さを学んだ。今後は自分で内容を咀嚼、応用して「文章を書くことについては、文演が転機になった」と言えるように修練を重ねたい。
最後に松田さんをはじめとする、クリエイト速読スクールのスタッフの皆さま、第62期文演受講生の皆さまにお礼申し上げます。非常に楽しく、有益な時間でした。今後とも、速読、勉強会などの機会がございましたら、よろしくお願いします。
Tさんは、海城→慶應です。
海城高出身者で、Tさんの「文章を書くことについては、文演が転機になった」と似た表現をした若者がいます。
加藤秀行さんです。
「いつかいっぱしの物書きになれたとき、執筆のきっかけは? と聞かれたら「クリエイト速読スクールの文章演習講座を受けた時からですかね」と大きな声で宣伝したいと思う」と体験記に書いてくれました。
彼は、その後、文學界新人賞最終選考5作品に残る書き手にまで成長しています。
文演を受けたことが「転機になった」と、ひとりでも多くの生徒さんに言ってもらえるよう、もう少し老骨に鞭打ちます

Tさんは、速読も72回受けています。
こちらはまたいつか紹介します。  真
真
※クリエイト速読スクールHP
※松浦理英子
どんなタイプの才能も見逃がさない意気込みで選考に臨んでいるが、欲を言うなら、まっとうな文学の才能に加えて、文学を、物事を、自分自身を疑い、道なき道を切り拓く、不幸で勇敢でなまめかしい異能を待つ。 ―文學界新人賞原稿募集より―