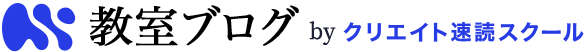2007-05-09
なおしのお薦め本(19)老人介護 常識の誤りb
呆けに関して、その原因についても著者はこう考えます。
「しかしどうして医療は呆けに対してかくも無力なのだろうか。それは、呆けもまた病気ではないからである。老人の物忘れもおもらしも、生理的退行=老化のせいであった。問題は老人自身と周りの私たちが老いとうまく付きあえないことにあった。
しかし、専門家の書いた本にはいずれも、呆けの原因は脳の萎縮(小さくなること)であると書いてあるではないか、と思われる人もいるだろう。痴呆性老人が亡くなった後、解剖して脳を調べてみるとほぼ全例に脳萎縮が見られた、なんて新聞記事を読むと、呆けは脳が萎縮する病気だと思い込んでしまうかもしれない。
しかし、……寝たきり老人を調べてみれば全例に筋肉の萎縮が見られるはずである」
「筋肉の萎縮は寝たきりの結果であって、決してそれが原因ではない」
「呆けもまた同じである。物忘れやおもらしをきっかけにしてプライドを失い、閉じこもったり、閉じこめられたりしたことでコミュニケーションの喪失状態が長く続いた結果、脳が萎縮したのである」
著者は、病院に任せておけばなんとかなるだろう、という思い込みもバッサリ切り捨てます。
「残念ながら、医療関係者はいまだに人間というものを『身体』としてしか見ないことが多い。『身体』が変わらないなら、その人はもうそれ以上良くなるはずはないと思っているから、『一生寝たきりのままです』なんて言うのだが、これを信じてはいけない」
「身体はこれ以上治らなくても、生活が変われば人間を変えることはできるのだ。病院、それも急性期治療の病院は、もっとも生活的要素に乏しい場なのである。だとしたら、寝たきり脱出のためには、一日も早く病院を脱出すべきなのである」
家に帰ってからすることは、「老人の生活習慣を大事にする」居場所づくりです。布団かベッドかの選択についても、人によって違うそうです。
「床から立てる間は布団、立ちにくくなったらベッド、さらに、立てなくなったけどいざれるならもういちど布団で、それも難しくなり車椅子に介助して乗ってもらうためにベッド、というふうに、老人の機能の変化によっても変えていかねばならないということになる」
これこそ、現場を知っている人だけが書ける知恵の言葉だと思います。
ベッドの場合は、高さ(足が床に届くかどうか、立つのが楽かどうか)、幅(マット幅100センチ以上)に気をつける必要があるとのこと。ベッドの柵は、自立的な動きのじゃまになるので不要だそうです。
このほかにも、トイレ、入浴、手すりについても、写真や絵を用いて、無理のない使い方が紹介されています。それらは割愛しますが、最後に「人間の生理的パターン」に即した動き方を二つ紹介します。これは、知っておくと役に立ちます。まず、床ずれ予防のための、寝返りの仕方について。
「まず上を向いて寝て、両膝をいっぱいに立てる。踵がお尻につくくらいだ。次に両手を天井に向かっていっぱいに挙上する。さらに頭と肩を起こしてみる。
この状態で横を向いてみてほしい。力を入れる必要もないくらい自然に向けることが判るだろう」
次に、寝たきり予防のための、起きあがり(寝ている姿勢から座位になること)の仕方について。
「まず十分横を向き、肘で床を押して片肘立位になる。次に肘を伸ばして坐る。ポイントは頭を前へ前へ出してバランスをとること」
これは、下になった腕を大きく開く(体に対して九〇度近く)と楽にできるそうです。やってみましたが、これなら片手でも起きあがれます。ただこの動作は、狭いベッドで柵まであったら絶対にできませんね。あらためて、著者が病院脱出を勧めるのは当然と思った次第です。  なおし
なおし