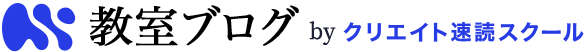2024-03-15
読めるようになるための演習
第84期文演(23/10/14~24/1/13)アンケートです。
きょうは、資格試験受験生のNさんです。
Nさんの文演アンケート
Q.1 当講座をどんな目的で受講しましたか?
A.1 ・司法試験合格。合格への一助にと松田さんから勧められ、改めて司法試験合格者たちの文演アンケートを読み、合格者がやったことを同じようにやって「勝ち馬に乗りたい」と思った。
Q.2 「文演」を受講して文章への印象で変わったことがありますか?
A.2 ・良い文章を書けるようになるためには、良い文章を読むのがよい、とされる。しかし、前提となる良い文章を「正しく」読むのがなかなか難しいと思うようになった。
Q.3 宿題の「要約」はどうでしたか?
A.3-1 「授業前」全容を捉えて自分の言葉でまとめる要約ではなく、筆者の言葉をできる限り登場順に選び取る要約に思いのほか苦戦した。
1回目、まだ新鮮な頭で重要だと思われる言葉を選び取り、字数制限内に収まるように削って仕上げて提出した。課題文のバランスが悪く、「4:6か5:5か6:4に」というルールを破っていた。それでも内容的にはそのバランスが正解だと信じた。
2回目、バランスが悪いので書き直しをせよと案の定言われ、とにかく形式的な5:5を目指して書き換え、提出した。
3回目、最終締切日直前に読み返すとあまりにも不自然な文章で、読むに堪えず書き換え、提出した。文章の構造的には悪くないと思った。
A.3-2 「授業後」悔しい。とにかく悔しい。過去の文演参加者たちが、いろいろな指摘を受けたが後味は悪くなかった、という趣旨のことを感想として書かれていたが、私はすぐにはそのような気分になれそうにない。自分に負けた気がする。
今回の参加者の中で、私は想定解とされるキーワードを最も多く落としていた。文章に対する新鮮味がなくなり、原文を読み返すたびに本当の意味で原文と向き合えなくなり、離れていったのだと思う。原文の言葉が持つ深い意味を考えずに拾い集めることが目的化し、文章全体を俯瞰できなくなったか、あるいは、無意識に、目の前の原文ではなく自分の脳内で再構築した文章を要約していたのかもしれない。
課題が出された後、他の参加者の1人が、毎日一度は原文を読んで要約作業に向き合っているとおっしゃっていた。見倣えたらよかったのだが、私には退屈すぎて無理だと思った。何度も何度も原文を熟読して、曲がりなりにも一度完成させたつもりの要約を修正するのは、試験中の見直しでケアレスミスを見つけるのと同じくらい難しい。一度壊して一から書き換える気力も湧かない。謙虚で真摯なその方の姿勢に感服した。
Q.4 全体的な感想をお聞かせください。
A.4 ・私は文章を書くことを嫌いだとも苦手だとも思ったことはなかった。文法に対するこだわりも強く、広報誌を作成するときは必ず校閲を引き受けていた。そのため、「文章を書く演習」をする「文章演習講座」を受講する必要はないと傲慢ながら思っていた。しかし、「書けるようになるための演習」だけをする場ではなかったのだと今頃感じている。
私の速読スピードは受講回数に対してかなり遅いほうである。子どもの頃から読むのも書くのも遅く、試験では時間切れ、途中答案を頻発しており、とにかく処理速度を速めなければと切羽詰まった状況でクリエイトに通い始めた。遅いことが問題であり、文章や問題文を読むこと自体はできていると自認していた。しかし、私自身の問題点の所在は書くことではなく読むこと、特に読み方にあると考えるようになった。正しく読めなければ、求められる要約はできないのである。つまり、この文演は、「読めるようになるための演習」をする場でもあったと思っている。
司法試験の勉強過程では、過去問や答案練習会の問題を繰り返し解いて、本試験でのパフォーマンスを高めるための訓練をする必要がある。論文問題は長いうえに、何度か繰り返しているうちに事案を記憶している(と思い込んでいる)ため、軽く読み飛ばして論文を書き始めることがある。しかし、このような態度では出題趣旨を見誤るおそれがあるため、今後はできる限り新鮮な気持ちで、二度目以降の問題読み込みに取り組みたい。
要約は誰が書いてもいわゆる金太郎飴(似たような内容の要約)になると思っていたが、実際は、同じ講座を受講し同じ指示を受けて同じ原文を要約したものとは思えないほど個性豊かで、とても驚いた。全てのキーワードを漏れなく拾った要約はなかったが、それぞれに評価されるべき点があった。第84期参加者たちと共に学べたことに感謝している。
文演受講をきっかけに、Nさんには、相手が課題で何を求めているかについて熟考する時間をつくってほしいです。
「論文問題は長いうえに、何度か繰り返しているうちに事案を記憶している(と思い込んでいる)ため、軽く読み飛ばして論文を書き始めることがある」は傍目八目ですが、もっとも注意しなければならないところかと思います。他人の生命や財産に直接関わる職業を目指しているわけですから、「軽く読み飛ばして論文を書き始める」は、模試等でさえ一寸も許されないはずです。
まずはその前に、基礎訓練である速読トレで、プログラムが求めているメニューに積極果断に応えていってほしいです。
これまでが助走で、これからの90分にメリハリをつけて取り組んでみたらどうでしょうか。
ふだん話しあっていると人格者で、誰よりも相手の気持ちを思い遣るのがNさんです
しかし、文章を書き出すと反射的思いの丈派に変身するのは、もったいないです。
とくに勉強中の身には。
なお、資格試験受験生等の場合の呼称は、判別不能のネームにする場合がありますのでご理解ください。  真
真