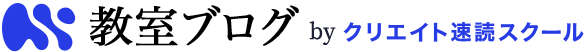2018-01-17
今では拙いながらも積極的に文章を書くようになった
第68期文演(17/9/30~12/9)アンケートです。
きょうは、司法試験受験生のTさんです。
2017-08-18「順位でみると、1483位→536位と、ほぼ1000人を抜いちゃってます」のTさんです。
Tさんの文演アンケート
Q.1 当講座をどんな目的で受講しましたか?
A.1 文演を受講した理由は資格試験受験のためだ。特に論述式の試験が苦手で、それを克服したかった。解答のイメージはあるが、それをうまく文章にできない。あれこれと考えているうちに時間は過ぎていき、結局、考えたことのいくらも表現できないまま試験は終了する。こうした経験を何度もし、そのたびに悔しい思いをした。予備校などが作る答案例を手に入れて読んだりしたが、うまく参考にできなかった。答案例に書かれていることはわかるが、それをどう書くかまでは解説されていない。なにか根本的なところがズレているということだけは分かったが、それが何かまでは分からなかった。「文章の書き方」と銘打った書籍を読み漁ったりもした。説得的な内容が書かれた本も多かったが、文章力が上がるということはなかった。むしろさまざまな主張をいっぺんに頭に詰め込んだせいで、混乱してしまった。
こうした失敗を重ねるうち、文章を基礎から学びたいという思いが増していった。そんな折に松田先生から文演を勧めていただき、速読の効果を実感していた私は、「クリエイトでなら文章の基礎が学べるかもしれない」と考えて受講を決めた。
Q.2 「文演」を受講して文章への印象で変わったことがありますか?
A.2 「文演」を受講する前の私には、文章は感覚的なものという印象があった。例えば、芸術家の人たちは好んで「感性」という言葉を使う。芸術の世界で「君は感性があるね」と言われたらそれは最大級の賛辞だ。文章においても重要なのは感性であって、技巧や論理は枝葉に過ぎないという印象があった。文章はセンスであって、書ける人には書けるし、書けない人には書けない。文章は才能なのだという考えが無意識にまで及んでいた。
「文演」を受講した後の私には、文章は論理的・構造的なものという印象がある。例えば、建築物は論理的・構造的なものだ。東京丸の内の高層ビルから、公園のトイレまでさまざまな建築物があるが、どれも論理的・構造的に組み立てられている。文章においても重要なのは論理構造であって、それなくして文章は組み立てられないという印象がある。文章は建築物であって、だれでもそこそこのものを作れるようになる。文章は建物なのだという考えが新しく生まれた。このように私の文章への印象は大きく変わった。その理由はもちろん文演の講義にある。講義の内容を具体的に述べることは避けるが、文演を通じて文章を読むこと、書くことに対する態度に変化が起こったのは間違いない。
まず、文章の読み方が情緒的なものから論理的なものへと変わった。以前は文章の読み方は感覚的であり、ともすると情緒的であった。今は文章を読むときには文章の構造を把握するよう努めている。文章を読むということは、文章の目的と語や文、段落の役割や関連性を知ることだと考えるようになったからだ。また、文章を読む際に、文章そのものを読むようになった。そんなこと当たり前ではないかと言われてしまうかもしれないが、以前の私には、文章そのものより著者の人格などを読み取ろうとする偏向があったのだ。今は、文章の内容を正面から読むという姿勢で文章に取り組んでいる。一方、文章を書く際には、まず、字数の制限を気にするようになった。試験ではよく「あなたの意見を600字以内で論じなさい」や「あなたにとって芸術とは何かを述べなさい(1200字以内)」といった字数の制限がある。以前は字数の制限を漠然とボリュームとしてしか捉えていなかったが、今ではより厳密に考えている。字数の多寡によって書ける内容が決まってくる場合も多い。そのため、文章の内容を考える前に文字数を細かく計算することが習慣になった。
Q.3 宿題の「要約」はどうでしたか?
A.3-1 「授業前」 文演の2回目に、松田先生から宿題の「要約」について説明がなされ、課題文が配布された。ルールはシンプルで、課題文も魅力的だった。しかし、始めてみるとすぐに手が止まった。課題文のどこを活かしどこを削ればいいのか判断がつかない。自分の文章感覚の頼りなさに改めて直面させられた。要約には30時間以上かけたと思う。外出の際には必ず課題文をもっていき、合間を見つけては読んだ。また、音読も試した。過去の文演受講者の真似をさせてもらったのだが、黙読では気づかない発見が得られて有益だった。一つの文章にこれほど長い時間をかけて取り組んだことはなかった。
A.3-2 「授業後」 気に入った文章を要約するようになった。クリエイトで速読を始めてから、自然と図書館で本を借りるようになり、読書量が増えた。面白い文章や重要と思われる文章と出会うことも多い。そこで、せっかく文演で要約を学んだのだからその感覚をさびつかせないようにと、気軽に文章を要約するようになった。文章の枝葉を落としてみると、必ず新しい発見がある。何度も読んで分かった気になっていた文章であっても、要約を施すと違った表情が現れる。難しいようにみえて実はシンプルな内容であったり、のんきな文章のようにみえて実は厳しいことが書かれていたりと、原文のままでは分からなかったことに気づかされる。まるで文章の正体を見破ったようで楽しい。
もちろん、すべての文章に要約を施すことはできない。要約には時間はかかるし、頭も使う。しかし、これはと思った部分だけでも要約してみると違う。記憶に定着しやすくなるし、ときには自分の文章の材料になってくれたりもする。松田先生は文演の中で「要約は勉強になりますよ」とおっしゃられていた。きっと要約にはまだまだ私の知れない学習効果があるのだと思う。私の要約の技術は未熟だが、今後も機会をみつけては積極的に要約を試みていきたい。