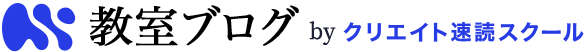2009-11-03
詩、二編
文化の日に寄せて(事寄せて?)、こちらが30年以上前に書いた現代詩なるものを載せてみます
高円寺発赤羽行
松田 真澄
空でも泳ごうよ
とかどわかしにあった女のように
広場の噴水はくぐもり
ぼくたちの会話は滞る
居留守のようにして
いつもひっそりと待っているコーヒーシュガー
さりげない偽善者のあまにがさを
じかに分けてやろうと心づくしするソファー
ぼくたちはコーヒーをすする
しゃれた喫茶店は駅前の二階
打ち気を喪わせるほど屈折するガラスの外に
高円寺発赤羽行のバスは
たったいまも
発車オーライ! いざ
いざ見参! とのぼせている
ぼくたちだって妙にひねこび
辛気ぽいかもしれないけれど
キングコングのような人間味のあるやさしさを
おっかなびっくりで索めて
出発してしまえばよかったのに
KOKUSAIに……それとも
KANTO BUS……
あのひとたちの踏むステップを
ぼくたちも踏むには
たくさんの手続きが必要な気がする
伏線をなで切りして返り血を浴びなければならない気もする
コーヒーカップは拉致され
おひらきへの早すぎたひきでものみたいな
先走った「お水」はいかにも生温く
腹部をたぷたぷふるわせている
ネエ井上
赤羽駅前のいっぱいの
コーヒーの苦さは
ほんとうはどうなんだろう
友人と23のときに創刊した同人誌からです(詳しい発行年月日を確認しようと探したのですが、見つけられませんでした。あることはあるのですが )。
)。
当時は53でしたので、「腹部をたぷたぷふるわせている」などは、まるっきりの暗喩でした
この作品は、幸運にも、思潮社の「現代詩手帖」同人誌推薦作(1977年11月号)となったものです。
月評を担当したのは、当時、気鋭の評論家であった岡庭昇。
「測鉛」創刊号の松田真澄「高円寺発赤羽行」はおもしろい。「舌」のほうがずっと作品的な水準は高いかもしれないが、「高円寺……」の偶発的な肉声が、この世代特有の、一歩退いた視線をよくみせている。
ネエ井上
赤羽駅前のいっぱいの
コーヒーの苦さは
ほんとうはどうなんだろう
すでに詩と、「失恋レストラン」や「横須賀ストーリー」のような上質な「詞」を、特に別なものと考える必要はないのかもしれない。むろんいささかも貶めているわけではない。
と歌謡詞と一緒に取り上げられ、「貶めているわけではない」とあっても、ひそかに顔をしかめた覚えがあります。
いまでは、名誉なことと素直に受けとめられます。77年、「同人誌推薦作」に取り上げられたのはこれを含め三作ですから、やはり名誉なものです(後年、こちらを除く2人は文学賞を受賞しています )。
)。
この詩の一部は、その後奇妙な足跡をたどっていますが、それはまたいつの日にか。
次の「草」は、「肉体言語」という半商業誌に書いたもので、現代詩手帖1981年3月号に転載された作品です。
アンダーラインのリンク先は、振り仮名・ルビです。原文にはありません。
草
松田 真澄
ほとりにそのくにの舟が舫いでおりましょう、わたしは明のふところへわたります。
ふりかえれば夕映えのように紛れてしまうひとことに
たどりついた言問橋のたもとから焼けるわたしの
川面に、藏ったにびいろの空を当てつけた。
(わたしたちは)天翔ける、テンメイを本来の馬体に
雪白を夢想している(トウメイの血のゴールを子が追い駆ける)。
あなたの名を薄命の時刻に呼んだ折りしも
わたしはテンメイであれと霊感したい熟睡の
疾風に賭ける物語りづくりに惑溺していた。
そして、あなたは渡ってしまうが留めようがない。
このひとをどこまでもふさわしいと呼んでいる(呼び交わしている)、突如
闇に湧きあがったひとのこころの切迫に打たれ。
有栖川、その、ひとを紀念した有心。
(わたしたち、と呼べて再び木霊のようにさえ還ってこなかった、そのままに凍結する地)
冬枯れの池のぐるりでひとりふたり少年のようなひとびとが
糸を垂らしている(ほんとうに、どこまで)。
わたしはあなたのいつにない無口からこみあげる
まなざしのようにうるんだ声を
精神の、
ゆたかな歩調の、かげりのように聴き分け
到来した季節に腕を結んで慄えていた。
〈藁かしらん〉
揺曳する島のようにひとびとの内海に
点在するこころを告げるくちを噛み
さあ、現実の晴海埠頭にスカイラインを駆り、それからは潜ってと
欠けているゆめのような澱粉質の亜大陸を夢物語り
ゆめを盛りこめない(テンメイ!)
驕りゆえのまずしい狼狽をわたしは、
しろい息ぐるしさを裸の木々に漏洩する。
綿々と告げられるべき
室町の辻の泥酔のくらいおもむき、それが
十全な現実であって、ひとりのわたしにとってさえ。
想いのあなたは蹴りあげた。稚純なこころを支配する純潔の
にくのくらがりで生まのままの失望をあたためて。
あの闇をかぶってゆく鳥は遠い舟はどこへ戻った。
消失したあまたの夜昼の記憶のような、無彩色に
凝っている未練がすでに溶けかかっている。
経過したものが偸安とも呼べぬ間に消える。
明らかに、ためにしたものだから
この切り岸の先には、なにも、ない。
わたしは周辺のいっしんなこころに付け火して
ほんとうに手を打ち合わせて笑っている。
草のようにしおれて、草のようにしおれて、草のようにしおれて。
いまの仕事をしてからは、初めて披露することになります
「草」以降、詩というものは一行も書いていません。
書き続けられなかったわけですから、詩文の才がなかったことだけは確か、となります。
ただ、不思議なことに、このときの事物への突き詰め方が、その後の身の処し方の土台となっています。目先ばかりに心を奪われてはいけないなどと、たまにエラそうに話してしまうのはこのときの経験からかもです。
また、1997年第13期文演より、初代文演講師KさんからAクラス・Bクラスを何とか引き受けられたのは、この頃の七転八倒があったためです。 真
真
※クリエイト速読スクールHP