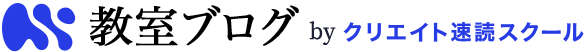2012-07-17
文章の良し悪しをはかる物差しがない
第57期文演(12/4/14~6/23)アンケートです。
きょうは、IT関連企業に勤務するMさんとTさん、20代の2人です。
まず、Mさんから。
Mさんの文演アンケート
Q.1 当講座をどんな目的で受講しましたか?
A.1 分かりやすい文章を書く技術を磨く目的で受講した。
Q.2 「文演」を受講して文章への印象で変わったことがありますか?
A.2 今まで意識していなかったことが多かったので、講義を受けて文章への愛着心みたいのが増した。
Q.3 宿題の「要約」はどうでしたか?
A.3-1 「授業前」 ただでさえ要約することはふだんからやってこなかったので、長文を750字に要約するのは大変だった。どこを切ってどこを切ってはいけないのかいまいちよく分からないまま要約してしまった。
A.3-2 「授業後」 授業前はそれなりにポイントは押さえた要約になっているかなと思っていたが、講義を受けて自分の不完全さや分かりにくさを思い知った。今となっては何でこんな要約をしてしまったのだろうと思う。
Q.4 全体的な感想をお聞かせください。
A.4 他人の書いた文章にダメ出しをするという講義は初めてだったので、とても新鮮だった。一般的には良い文章を読めば良い文章を書く力もつくと言われているため、この講義を受けて必ずしもそうではないことを実感した。ダメ出しをされる文章は自分にも当てはまるような文章の書き方をしていることが多く、まるで自分がダメ出しをされているような気分になったため印象に残った。またこういった講義を受けてみたいし、自分の書いた文章をダメ出ししてもらいたい。
Mさんへの体験レッスンの事務室説明は、こちらでした。どういうわけか、ぜひぜひ入会してくださいと言った記憶があります。
「授業前はそれなりにポイントは押さえた要約~と思っていた」Mさんが、「何でこんな要約をしてしまったのだろうと思」えるようになったわけですから、他人の文章から自身の考え方の不十分さを受け入れるという、宿題の面白さを理解してくれています。
次は、Tさんです。
Tさんの文演アンケート
Q.1 当講座をどんな目的で受講しましたか?
A.1 家族の影響もあり、ジャンルを問わず多読するようになり、そのうち自分でも書くようになりました。とはいえ、書くことの難しさも感じていました。この難しさの原因は、文章の良し悪しをはかる物差しがない、ためです。現在、某NPO団体の記事をボランティアで書いていますが、一人で書いているとどうしても視野が狭くなり、全体を見たときにばらばらまとまりのつかない文章になります。推敲を重ねるうちに、どんどん修正したい箇所がでてきて、途中でどういう方向に行こうか当初の方向性を見失うことがあります。それは地図のないまま歩くような感覚で、途中で何か落ちてないかな、と探すような感覚に似ています。その工程は私個人としてはたのしくもありますが、それは読み手にきちんと伝わっているかという点ではいささか疑問です。
これまでも、文章の書き方の指南書の類を読んできました。けれど、自分で選んだ本の選択が悪かったのか、正直自分の力になるようなことが書かれているものには出合えませんでした。そのため、「文章の書き方のノウハウが簡単に見つかるわけないだろうけど、とりあえず受けてみようかな」というのが、授業前の感想です。
反対に、小説家を目指す人はノウハウを頑として身につけないで自分で模索するという方法を選ぶ人もいるかとは思います。私の場合は、自分の文体を侵食されまい、とするほどにポリシーはありませんので、先に書いたような「何か落ちてないかな」という程度の軽い気持ちです。
Q.2 「文演」を受講して文章への印象で変わったことがありますか?
A.2 感覚的な例えですが、服を着るのは簡単ですが、それを作る作業は大変です。なんとなく見た目に上品だなという印象がもてるのは、一糸一糸がきちんと縫製されているから、です。授業ではその一糸の細やかさと全体の見た目のバランスを見る訓練のようでした。そうすると、著者から差し出された服に対し、その魅力や一糸の精巧さを丁寧に受け止めることができ、その服で毛細血管まで温かくなるように感じるようになりました。
Q.3 宿題の「要約」はどうでしたか?
A.3-1 「授業前」 ・比喩をどこまで入れていいのか、要約だから入れないべきか、迷いました。・要約課題でない文章も読み込むべきか、迷いました。・英語を意訳するように、筆者の言わんとすることに、自分の言葉を付け加えてしまいました。
A.3-2 「授業後」 ・文演の最終回(8回目)は6回目の授業前に提出した課題の添削指導でした。課題の「要約」は、考えぬいて提出したと思っていましたが、6回目の授業から8回目の授業にかけて、私の課題は欠点だらけだったことがわかりました。また、7回目までに提出された他の受講生の要約も、最終回の授業前までは「なるほど、こういうまとめ方もありなんだ」とよい捉え方ばかりをしていたため、授業で受講者一人ひとりに足りない部分を指摘されていても、なかなか見方を変えられませんでした。
・「要約に自分の言葉を使う」という思いこみ。思いこみというより呪縛に近い。これは、原文から言葉を流用するのは、「コピーアンドペーストで楽をした、工夫がないと思われる」という先入観です。筆者の意図ありきで、文脈上やむなく自分の言葉を使うのは仕方ないですが、筆者の意図をふまえず「要約に自分の言葉を使う」を優先事項にしていました。
Q.4 全体的な感想をお聞かせください。
A.4 これからは今まであまり読まなかった古典を読もうと思います。長い間残ってるものは読む価値があると思うからです。源氏物語なんて千年残っていることを考えると、腰を据えて読まないと! という気になります。
ネットのストレートニュースをみていると、おそらくきちんと訓練された記者が書いているのだろうから、読めない自分の知識が足りないのだろう、と思っていましたが、今はこうやって書かないから伝わりにくいんだな、と透明な気持ちで文章そのものを読めます。
さすが、本好きなだけあってQ.2への「感覚的な例えですが」にはじまる一文などうまいものです。
ただ、自分の要約は「欠点だらけ」で他の受講生のものには「よい捉え方ばかりをしていた~」と、まだまだのところもあります。感情的、です。
「はかる物差しがない」なら、自分でつくるしかありません。そのとき、今回の文演が「物差し」の材料の一部になってくれたらありがたいです。
ところで、Tさんの会社には、こちらとしては実に珍しく仕事を依頼しました(「体験記」や「取材」以外で、生徒さんに何かをお願いすることなど10年に一度)。
Tさんの強い個性もありますが、それ以上に縁とか出会いというものを感じざるをえない不思議なものでした。
トントン拍子に進んでいきました。  真
真
※クリエイト速読スクールHP ・関東甲信地方は、きょう梅雨明けしたそうです。水分と睡眠と栄養をたっぷり摂って、夏を愉しみましょう
・関東甲信地方は、きょう梅雨明けしたそうです。水分と睡眠と栄養をたっぷり摂って、夏を愉しみましょう