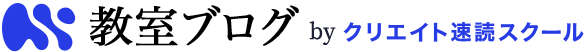2012-07-16
他人の失敗のおかげで、自分にとっては生きた知識となる。素晴らしい互恵関係だったと思う
第57期文演(12/4/14~6/23)アンケートです。
きょうは、12年前SEG生であったDさんです。
SEGがスタートすると、何日かブログに関わる余裕がなくなるかもしれません。
Dさんの下記アンケートが、公式ブログ最上位につかの間放置されます
Dさんの文演アンケート
Q.1 当講座をどんな目的で受講しましたか?
A.1 クリエイトの開講講座をフルコースで受けたい、その一心である。
平成12年、私が高校1年夏、SEGで受けた「速読による能力訓練」の講習時に「文章表現スキルアップ」の紹介を、松田さんから説明され自分も受けたいと思った。別段、自分の文章表現に日頃から問題意識を抱えて、悩んでいたわけではない。ただ過去の受講生の文章の悪例を題材に学び、どのように直すと良くなるのか、それを講習最終日に松田さんからチラリと見せられ、興味を覚えたのがきっかけである。
そもそも「速読による能力訓練」を受講したのは、SEGの高1春期講習で国語担当の先生からすすめられたからだ。
パンフレットの速読の紹介文は、当時も今も変わっていない。
「『何をするのかと思ったらとんでもないことをやった』というアンケートを読み、面白半分で受講を決めた。結果は『マジでとんでもないことをしてくれた。絶対一度受けた方がいい』と思った」(講習受講アンケートより/高2男子)という受講生の声を載せたものである。
春期講習の開講タームを見てみると、ほとんどのタームで速読の訓練が開講されていた。どうやら人気講座らしい。「絶対一度受けた方がいい」ということで、次の夏期講習時に面白半分で受けることにした。
訓練は、「お受験みた〜い」と誰かが言ったらしいロジカルテストが苦手だったが、あとは楽しく受けられた。どれも新鮮だった。特に倍速読書訓練で、用意された本は面白く、十分理解できないままページを繰るのは惜しかった。5日間の訓練時、毎回配布される分厚いプリントも嬉しかった。世界が広がった。当時のプリントは、今でも大切に保管している。
さて、この速読の訓練をきっかけに、SEGの通常授業で開講されている「文章表現スキルアップ」も受講したいと思った。しかし、それは無理な話だった。当時、岡山の高校に通っており長期休暇中のみ横浜の祖父母宅に滞在し、SEGに通わせてもらっていたからだ。
そこで、池袋にある本校で開講されている文章演習講座を大学に入ったら受けようと思い直し、残念に思う自分の心をおさえた。といっても、もともと文章は、読む方が好きで率先して書く性質ではなかった。日記も積極的に書かないし、学生時代、レポートより一発勝負の筆記試験で成績を決められる方が好きだった。作文でもレポートでも書くまでは、億劫で仕方がない。しかし、書き始め興が乗り出すと、筆が勝手に動き始め楽しくなってくるのだ。自分を表現すること、知ってもらうことは快感である。だからといって、作家志望というわけではないし、司法試験等の論述試験がある資格取得を目指しているわけでもない。
ただ大学で卒業論文を執筆した際、指導教授から頻繁に「(文章が)くどい」と指摘を受けていた。書かなくても読み手が、十分わかっていることまで書いているとのことで、よくうんざりさせてしまっていた。性格は、文章に出ると知っていた私は、そんな書き方を改めたい、書き方を直せばひいては性格も改まるかもしれないと考えた。だが、文演はすぐには受けられなかった。大学受験に失敗し、島根大学で学生生活を過ごしていたためだ。受けたくてたまらない想いは、相変わらずであったが文演の体験記やアンケートを読んで気を紛らわしていた。
しかし、それらを読めば読むほど、一体どんな授業が展開されているのか想いは募る一方だった。どんなテキストを使っているのか、受講者は読み方が変わったとあるがどう変わるのか、私は文学部だったため様々な文学理論を学んだが、それを駆使した読み方とどう違うのかなど知りたくてたまらなかった。
実は受講にあたり、具体的な目的を考えたのだが思い浮かばなかった。強いていえば、クリエイト速読スクールで開講されている文演とは、どのようなものかという高校生以来の好奇心を満たすためだったといえるかもしれない。もちろん、文章を上手く書けるようになりたい思いはあるが、なぜ上手く書けるようになりたいと思うのかは、いまだによくわからない。
Q.2 「文演」を受講して文章への印象で変わったことがありますか?
A.2 これといった決まりのなさそうな文章でも、先人たちの築きあげた上に成り立っている書き方というものを知った。例えば、●●●●●●●●●●●●などといった基本的な書き方は、学校では教えてくれない。それを知らずに、今まで書いてきてしまったことに愕然とした。
大学時代、教育学部の教授の依頼で国土交通省からの受託研究の一環として、島根の過疎地域を取材し、地域情報誌を仲間とともに作ったことがある。私は、『出雲国風土記』にも出てくる温泉紹介を担当し、記事にした。確か、6000部発行したはずである。決まりに則った書き方をしていない文章を、不特定多数の読者に読まれるということは、恐ろしいことだと今さらながらに感じる。また、整っていない文章というのは相手に失礼でもある。
今までの文演のアンケートを読むと、もっと文章を書きたくなったとよく書かれている。私の場合、その気持ちはいつ頃湧いてくるだろうと思いつつ受けていた。それは、第6回目ごろにやってきた。なにか、ふつふつと書きたい思いが湧いてきた。文章を書く上での指針を教えていただいたからかもしれない。
正しい書き方、いかに読みやすく書くかを教わるとそれを軸にして、安心して書けるようになる。レポートでも課題を与えられず何でも自由に書けというのは、逆に困ることである。
また、文章を能動的に書くことは、億劫なことであったが教わった留意点を取り入れることで、より書きやすくなった。例えば今まで、これでもかと情報をあれこれ盛り込んで書いていた。書き手としては、詳しく説明すればするほど読み手としては想像しやすいだろうと親切心のつもりだったのだが、まずはいかに必要なことだけ取捨選択して書くかという重要さを認識した。
Q.3 宿題の「要約」はどうでしたか?
A.3-1 「授業前」 私には、詰めが甘いという欠点がある。この宿題が一番大事ということは、受講前から「文演アンケート」を通じて知っていた。そのため、今回は詰めが甘くならないように何度も推敲し、完璧な要約を目指した。
今までの受講生の文演アンケートを読んでいたため、この要約が一番重要視されていることは知っていた。しかし、いくらアンケートを読んでも具体的な要約方法については謎だった。その方法について、やっと学ぶことができる。期待感でいっぱいだった。一生懸命要約に取り組めば、それだけ実りも大きいだろうと考えていた。宿題が課されるまでに、松田さんの要約例を読むとほとんど原文を活かしている文章だったため、安心した。
中学の時に、塾で国語の先生から要約の際はなるべく、自分の言葉で書くようにと教えられた。それ以来、自分の言葉で要約をするものと思いこんでいたため、原文をほとんど活かしてよいことを知りホッとした。
本文を何度も読み込み、それを活かすつもりで、削れる部分は、とにかく削った。要約の宿題が課されるまでに、いただいていた松田さんの要約も参考に段落等を構成した。ただ、要約にあたって、本文の構成を分析し段落構成をどうするかは考えたが●●●●●●●ことまでは思い至らなかった。
A.3-2 「授業後」 最後の最後で、要約文の後半部分が、しっくりした感じでまとまらず気になっていた点を直した。うまくまとめられたと思って提出したが、結果は恥ずかしくてたまらない出来だった。完璧を目指したものの、要約に問題点が全くないと言い切れる自信はなかったが、ふたを開ければ問題点が実に多かった。それまでの授業で、「同じ言葉が何度も出てきて、しつこい」というダメ出しをしていた自分の指摘が、そのまま当てはまる書き方をしていた。くどい書き方を直そうと文演を受けたのに、全然直っていなかったこと、何度も読み返したはずなのに気がつかなかったことに自らの問題の根深さを痛感した。
さらに指摘されたのは、思いもよらない点ばかりだった。必要だと考えて、要約文に入れた文章が、不必要だったり他に大切な言葉が抜けていたりと、著者の伝えたいことをしっかり読み取れていなかった。著者の伝えたいことを読み取れないまま、速読にばかり精を出すのも考えものである。大学の卒業研究までに培った読解力とやらは、何だったのだろう。書き手の意図を明確に読み取る力がないということは、致命的である。
ただ松田さんは、不十分な点を指摘するだけでなく必ず1人数か所は評価してくださった。具体的に説明して、褒めてくださる。私の場合、意識的に修正した部分を褒められたので、そこは救いであった。よく読んでくださったナァとありがたかった。
松田さんによる他の受講者の要約に対する問題点の指摘も、興味深かった。予習の段階で、この人の要約は素晴らしいと思っていても授業では、次々問題点が暴かれていく。他人の失敗のおかげで、自分にとっては生きた知識となる。素晴らしい互恵関係だったと思う。
Q.4 全体的な感想をお聞かせください。
A.4 1分たりとも授業に遅れるわけにはいかなかった。なにしろこの講座を受けるに当たって、約10年間機会を伺い続け、さらに通いやすいように教室から徒歩15分のところに家を借りたのだ。要約提出日は、受講時間直前になっても手直しは続いたため、タクシーで急いで向かったほどだった。
大学受験で失敗した私は今度こそと思い、IT企業への就職を機に、都内に住めるようになった。住まいは教室へ通うことを考慮し、教室まで徒歩15分の池袋に引っ越した。しかし、今度はなかなか受講料を用意できず、さらに土曜日もシフトの関係で夜まで仕事をすることになり、文演を受ける機会に恵まれなかった。私は、引き続きクリエイトのブログに更新される文演受講生のアンケートを羨みながら読む日々が続いた。文演を受けたくてたまらない気持ちは、年に何回か襲来してきた。アンケートをアップされる受講生は、羨望の対象だった。
そんな折、入社して2年目の平成22年10月、会社を退職した。いわゆる職のミスマッチである。コンピュータネットワーク関連の技術職だったのだが、自分には向いていないということがほとほとよくわかり、理系職種には懲りた。
ある時、ハローワークで温泉宿の取材スタッフという職種を見つけ、すぐさま応募した。
温泉情報サイト▼▲▼▲▼というサイトの運営会社である。そこでは、選考過程でトライアル取材というのがあり、私は温泉宿の取材に、社長と社員の2人に同行することとなった。自分が、取材したことを1週間で約1万字程度のレポートにまとめ、会社に提出するという実地試験である。このレポートは、審査を通り文章力や取材する力を認められ、私は無事採用された。しかし、取材に赴くための自動車運転に難があり、3日後にクビとなった。
文章を書くのが主な仕事とするような文系職への転職活動をしながら、アルバイトで得られるお金を貯めてやっと今回文演を受講することができた。
第1回目は、念願の授業を受けられて夢のようだった。受講生は高校生から40代の方まで、背景もSEG生、大学生、司法試験受験生、会社員、私のような転職活動中の者とさまざまだった。こうした年代や経歴の違う人たちと机を並べ、ともに学ぶことにときめきを感じた。学生時代を少し思い出すようだった。
授業の大半は、過去の受講生の作文に対して、ダメ出しをする授業である。ダメ出しなら、得意だ。中学の時に、英和辞書の誤字を出版社に指摘したこともあるぐらいだ。松田さんからダメ出しを求められ、教室の雰囲気を気にすることなく、意見を述べた。毎回述べた。
俺は、この授業を10年間待ち焦がれていたのだ。何を躊躇することがあろうか。浅はかな指摘だということは承知だ。でしゃばりの性格も手伝って、ここはおかしいと思った部分は、遠慮なく全て言わせてもらえた。自分を取り繕っている場合ではないのだ。何より自分が低レベルであれ指摘をすることで、他の受講生にとって言いやすい雰囲気になるのなら本望だ。そういう意図もあった。
他の受講生は、きっと自分には思いもつかないような指摘をするはずだ。どんな考え方を他人はするのか、それをききたかった。自分が誤りだと指摘した箇所が、実は正しいということもあり、その時かいた恥でかえって強く記憶に残ったこともあった。一方、他の受講生の指摘は、マクロ的で第4段落と第7段落は一緒にした方が良いとか段落の順番を逆にしたら良いなど話の全体の流れをつかんだ上での指摘が多かった。私の指摘は、ミクロ的で誤字脱字やこの一文は不要といった指摘が多くなりがちだった。そういう違いには早々に気づき、自分もマクロ的な視点でのダメ出しを心がけるようにしたが難しかった。
また、授業で扱われる題材の最大の問題点には、予習の段階でよく読み込んでも気がつくことはなかった。回を重ねるにつれ、学ぶテーマも変わり題材の文章も良質なものとなり、おかしい点を指摘するような部分がなかなか見つからず焦った。授業で、解説されて初めてわかるという始末だった。自分がいかに他人の文章を読んだつもりになっているか、毎回痛感させられた。松田さんは、私が何も考えず読み飛ばしてしまう文も丁寧に読み取る。題材となる文章を読む際、書き手がもっと詳しく書くことで、読み手は、さらに面白く興味を持って読めるようになる一文や一語に着目するのだ。
「残酷ですよねえ、自分の文章は2回3回と読んでもらいたいのに、他人の文章には実に冷淡。自分のことはわかってもらいたいのに、他人のことには実は無関心」といった授業中の松田さんの言葉が脳裏をよぎる。
題材となった文章には、一読して表面的なことがさらっと書かれているような作品がある。それでも、ある部分を書き手自身がどのように思ったか、どのような体験をしたのかなど掘り下げて、書き直すことで深みのある文章に変わることを目の当たりにした。そのある部分というのを見つけるには、書き手を理解しようという姿勢がないと見つけられない。松田さんは、的確にそれを見つけ指摘していくのだ。そうしたことがわかるにつれ、私も何を伝えたいのか意識して文章から汲み取ろうとするようになった。
精読のための姿勢を学べたことは、今後の社会を生き抜くための即効性ある大きな武器を手に入れたと思っている。手始めに履歴書作成に役立てられるし、会話における話す順序・説明の仕方・相手の話の聞き取り方にも応用できそうである。速読にも好影響をもたらすだろう。
夢が広がる授業であった。
松田さん、病み上がりにもかかわらず、最後までご指導くださりありがとうございました。
どうぞ今後ともご自愛ください。
●●●●●●●は、授業の流れのなかでのものです。いきなり出てくると誤解を受けそうなので伏せ字です

Dさんとは、2010-07-20 「マツダセンセイ マツダセンセイ」の「D君」です。
彼のような想いの強い子に何人も出会えただけでも、もうすでに十分な人生を生きています。  真
真
※クリエイト速読スクールHP