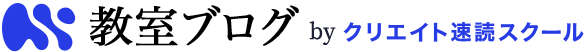2010-04-04
司法試験合格体験記 生徒の目で、講師の目で〈2〉
(2) 中盤のトレーニングは、意識革命を引き起こしてくれた。私は、正確に、丁寧に物事を行うタイプだった。それが災いして、司法試験の短答試験では、第1問から問題を解いて、分からない問題があってもその問題を捨てて、次の問題に移れなかった。だから、最後の方に簡単に解ける問題があっても、時間が足りず解くことが出来ないことがしばしばあった。
そのような性格の私は、まず、イメージ読みのあらすじ書きに手間取った。あらすじ書きは制限時間が決められている。それなのに、私は、読んだあらすじを正確に、丁寧な字で再現しようとしていたので、当然、制限時間内に最後まで内容を書ききることが出来ずに終わっていた。いくら字が丁寧に書かれ、内容が正確に再現されていても、最後まで読めたということを時間内に表現しなければ、たとえ最後まで読んでいたとしても、それを相手に伝えることはできない。そのことに気づいた私は、とにかく時間内に要領よく、多少汚くても最低限読める字で、最後まであらすじを書くようにした。また、イメージ記憶でも、イメージするのが難しければ飛ばして、イメージしやすいものから記憶するようにした。
このように、クリエイトのトレーニングは時間で区切られたものが多いので、時間内に一定の成果を上げるということは、司法試験の勉強においても大いに役立っていった。短答試験でも、分からない問題はすぐに捨てて、次の問題に移ることが出来るようになったし、簡単な問題から解いて点数を稼ぐという意識を持つようになった。
(3)本を隅から隅まで、一度で頭に内容が入らないときは何度も読んでいた私にとって、終盤の倍速読書訓練は苦痛で仕方がなかった。講師の方に相談したら、「ここではトレーニングと割り切って読むことが大切」とアドバイスを頂いた。普段、法律書などを読むときの、いわゆる熟読と、トレーニングでのスピードを重視しながら、内容を必死に読み取る速読を使い分けるようにしていった。トレーニングで、集中して内容を読み取ろうとしていたからか、しばらくすると、法律書を何度も読み返すことがなくなり、一度で頭に入るようになってきた。また、筆者が言いたい重要な文章は、この辺りだろうと読み取れるようになってきた。
3.文演を受けて
クリエイトに通い始め、松田さんやスタッフの方から、「文演を受けるといいですよ」と誘いの言葉を耳にしていたが、ちょうど予備校の講義と重なり、受ける機会を逃していた。ようやく予備校の講義が終わり、文演を申し込んだ。
文演では、駄目な表現方法から、なぜ駄目か、どうしたら良い表現になるのかということを学び、また、読解力も養うことができた。文演を受け始めて数回経ったとき、いつものように新聞を読んでいたら、何回か繰り返して伝える文章の文末が全て異なっていることに気がついた。それまでは、まったく気づかずに読み過ごしていたのである。
文演を受けて、文章に対する心配りができるようになったことを実感した。
また、友人と書いてきた答案を読み合い、批評したりするゼミを行っていた。あるとき、友人に「お互い同じような事実を並べて文章にしているけれども、砂金さんの文章の方が一番強調したいことが読み手に伝わってくるね」と言われたことがあった。司法試験の論文では、問題文の事実を拾ってきて評価することが求められている。友人も私も同じ事実を拾って評価しているのだが、文章の書き方によって、強調したいことが伝わる文章となるか、そうでない文章となるか違いが生じるのである。文演では,伝えたいことをどのように書けば、読み手にきちんと伝わるかを学ぶことができた。それを司法試験の論文でも活かすことができるようになっていた。 ‐〈3〉に続く‐