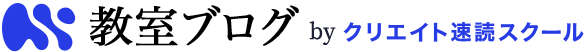2018-07-16
1回ごとの短距離
早稲田の院生Yさんが100回を超えています。
大学院生であると同時に、真言宗僧侶です。
初速818字/分・理解度Aからのスタートです。
以下は、Yさんの受講60回~100目アンケートと最新スコアです。
ただし、受講60回(18/2/26)と90回(18/4/9)アンケートは未提出です。
「Yさんの受講70回目アンケート18/3/22」
マイナス・イメージ読みの書き出しは、同じ単語を2回以上使わないようにという指示がありますが、文章として流れを如実に書き出そうとするとどうしてもきついです。シーンを単語で切り取るより、できるなら文章で物語を描き出せるほうがよいですよね。そうなると固有名詞や人称代名詞は特に2回以上使わざるをえないのですが、そこを何とかという感じなのでしょうか。
・小説を速読したいという心は、精神として貧弱なのではないかと思い始めました。感動や感受性をも倍速できるならいいですが、そこが追いつかないままあらすじだけつかむということに慣れてしまうことがこわいです。とはいえ普段読むときはA読みで読めばいいだけだとは思います。
・たいてい日本語の本は縦書きだと思いますが、本の縦一行が一気に目に入って、さらに内容も入ってくるようにならなければ、横に見る範囲が広くなろうとも読み方はつぎはぎとなりますよね。ということは縦一行を一目で目に入ってくるようにならなければ小説のA読みの速さが劇的に伸びていくことは難しいのでしょうか。そう考えると漢字二行がかなりポイントになってくる気がします。実用書ならばつぎはぎでも言いたいことがわかればそれでいいし、実際わかると思いますが、小説はそうはいかない気がします。速読に対する自分の考えが固いので、他の人の感覚が知りたいです。
・イメージ記憶の成果を一つの区切りとして、これ以降は実用書を倍速の対象としていきたいです。
・イメージボードやイメージ記憶は、問題を見たあと頭の中のスペース(暗闇)でイメージしていますが、できるならば眼前にイメージの場を作るほうがタイムロスは小さいでしょうか。
・イメージボードを目を開けた状態で挑戦してみたいです。
・イメージリスト全部書ききれる気が全くしません。全部は想定していないと思ってよろしいでしょうか。
・カウント呼吸法で色々と思考が跋扈してしまいます。本当は呼吸に集中して無心になるべきなのに。本業なのに。境地が遠すぎます。
・実は60回目のアンケートをバックレているので、それも提出してといわれないか心配です。
・そして次のアンケートもちゃんと書けるか今から心配です。
プラス・生まれ変わるなら本の虫になりたいなと思っていましたが、現世でなれそうなので良かったです。虫干しの憂き目に遭うことがなくなり、心置きなく解脱できます。……プラス面は100回目に期待していてください……
「イメージ読みの書き出し」において「同じ単語を2回以上使わないようにという指示」は、講師のほうに言葉足らずがあります。話の流れなら、何度同じ単語(正確には文節、ですね)が出てきてもかまいません。これは1回書いたからとかの操作をせずにとにかく量を書き出してください。教室は最初は3分から始まり、20個以上が目標。SEGは2分からで、目標はいきなり75個以上です。
「Yさんの受講80回目アンケート18/4/1」
マイナス・そこまで不安には思っていませんが、トレーニング記録の割に読書スピードが伸びません。
プラス・「沸騰」先日SEG授業での松田さんからのアドバイスで世界が一変して、サッケイド中に突如頭が沸騰しだしました。自分の広く見ようという努力は所詮与えられた枠の中でもがいていただけでした。視線の生きようとしていた世界のなんと小さいことか。それを無視し続けてきた時間が惜しいです。
結果、序盤の各トレーニングが有効につながりだした感覚があり、集中の密度が増したように感じます。負荷をかける方向が時間だけではなく空間にもあるということは、序盤のトレーニング全体に通底しています。でもそんなことは分かっていました。ただその負荷の尺度を与えられたものに依拠していては、ブレイクスルーはなかなかおきない。負荷の尺度はもっと自由で、もっと広いほうがよい。なんとなく助言の額面以上に解き放たれた感じがします。これまではとにかく集中して、集中力の底上げができればよいと思っていましたが、トレーニングに慣れてきたらただ集中しようとしているだけではだめなのだと実感しました。最近の文字を追うことに要する集中力たるや、脳が汗をかいてそれが鼻の奥に垂れてくるのを感じます。今のところはサッケイドや漢数字一行等のシンプルなトレーニングで、視野の広がりに如実な効果が表れています。いずれは教室のBGMを聴きながらイメージ記憶15秒に挑戦しているようになれたら最高だと思います。ただ現時点では、いつの間にか視野を狭くしている自分をその度ごとに戒めるので精一杯ですが。
「序盤のトレーニング」序盤のトレーニングの記録は厳密に判定することは難しいはず。ということは参考でしかないからとにかく精度を落としたり、上げたりしながら進んでよいのだと勝手に思っています。精度を決めてしまうとどうしても殻を破れない。球技も、球数をこなす練習と精度ありきの練習を混在させたメニューを組むのが定石ですよね。
終盤のトレーニングは球技でいえばより実践的な試合形式での練習といったところでしょうか。必然的に質が求められ、如実に自分の実力が出るために、記録にこだわらざるをえないと思います。それならばトレーニング全体を通して同じ意識で取り組んだのではもったいない。今のところ序盤はもっと自由に工夫を凝らし、記録にあまりこだわらず、縦横無尽に自分を追い込もうとしています。
本当は中終盤こそ工夫のしがいがあるのでしょうが、難しいので時間より早く終わることに努めています。かなひろいやイメージ記憶のように時間が指定されるものは、指定された時間より早く終わって少し時間が余るぐらいの方がよいのだと、講師の方から聞いて実感しました。与えられたもので無批判に生きているうちは、飛躍的な成長はできない。もはや人生訓ですね。
「イメージの場所」スピードボードの打開策が見つかった気がします。イメージ記憶の方で思っていたことですが、2つの単語のイメージは脳内にイメージの場を作るよりも、その2つの単語の間のスペースをそのままイメージの場として展開していったほうが、訓練すれば速いのではないかと思っていました。しかし、イメージ記憶はそれを試している余裕が全くないので実際にトレーニング中に行ったことはありませんでした。今回スピードボードで気持ちに余裕が出てきたからでしょうか、文字のうえでそのままイメージすることに切り替えたところ、混乱することなく、タイムも早くなりました。イメージボードもできることなら、目を開けたままイメージしたほうが良い訓練になるのではないかと思っています。そのうちイメージ記憶でも試してみたいと思います。
「集中受講」私は未だ学生の身分で、長期休みがあります。3月にかなり集中的に受講して感じたのは、期間を開けてもあまり記録が下がっていることはありませんが、でもなかなか成長にはつながらない。私としてはできれば集中的に通う期間を作るか、週に複数回コンスタントになんだかんだ脳のトレーニングも筋力トレーニングと同じで、1回ごとの受講の間はあまりあけると伸びにくいということです。通い続けるかのほうが良いという結論です。
コンスタントに通えないのであれば、受講を取っておいて一週間ぐらいかそれ以上の集中期間を作るのが良いのではないかなと思っています。もしくは1日2回受講を2日間行うなど。また、集中的に通うとその充実感が他に波及して、しばらくの間モードに入ったようになれる可能性があります。勝負事の前々日までの期間に集中受講ができたらいいパフォーマンスができる気がしています。
「イメージ力に寄与する生活」イメージ力にはある秘密があるようです。3・4年前の「クーリエジャポン」という雑誌の記事によれば、電子機器に3日間全く触れない生活をすると想像力が50%も上昇したという実験結果があるようなのです。私は少し前にすでにこのことに気づいており、テレビを実家に送り、携帯やパソコンをネットがつながらないように設定していたので、この記事を見てまさに門外不出のドヤ顔だったと思います。
また、瞑想を10分でも15分でも毎日行うと集中力や想像力が増すようです。それらの根拠についての私見はちょっとうるさいので、次回に回します。少なくとも私自身は効果がトレーニングに表れているので、やはり本当なのだろうと思います。いつかイメージ強化については密教的見地から少し述べられたらと思っています。でもこの情報は、クリエイトに通う以上のことをしなさいと言っているので、多くの人には残念なお知らせかもしれません。
「球技も」とありますが、Yさんはテニスの国体選手。
「密教的」修行者+全国クラスのひとの言葉は面白いです。
よきことであるなら、「残念なお知らせ」などありません。
「Yさんの受講100回目アンケート18/5/21」
マイナス・ありません。
プラス・100回まで到達できてひとまず嬉しいです。受講69回目と78回目はSEGに参戦させていただいたおかげで、教室でのトレーニングも自然と強迫されました。SEGの教室環境は、池袋のそれとは全く異質です。みんな同じ条件でスタートラインに立たされることで、言い訳のできない実力格差が浮き彫りになります。
また、あれだけの人数がいて時間の読み上げがなされていくと、必然的に追い込まれます。体験等を含めれば70回以上受けている自分がまだ4回目の彼らに圧倒されるとは、なかなか経験できないほどに悲劇的です。今まで無駄にしてきた時間や脳を甘やかしてきた時間を突きつけられました。この時間を埋めるにはあと何回池袋に通えばよいのだろうという気持ちが芽生えた反面、池袋に通い続ければこの時間が埋められるのかと感心しました。
SEGのあとは池袋でも記録が軒並み伸びたことは、とにかくシンプルに焦る、シンプルに追い込むことの重要性の証左だと思います。焦らずにあれこれと試行錯誤するよりも、焦る中で試行錯誤していく。50回や80回を通したマラソンではない。1回ごとの短距離。最近忘れかけていましたが、そう思ってトレーニングしていきます。
・入会からだいたい1年ほど経ちました。安定して定期的に通ったのではなく、長期休みを利用して、なるべく集中的に通うことが多かったように思います。1か月強も通わない期間がありましたが、案外1・2か月のブランクは問題にならないとわかったことはかなり大きいことだと思います。日常様々なことで、一度遠ざかるとまた着手するのが億劫という気持ちがおきます。もちろん定期的に通うのが理想的ではありますが、ただクリエイトに関しては、また暇なとき通おうぐらいのスタンスでも全く問題ない気がします。
実際困難な方もいるでしょう。だから定期的に通えないことに関してあまり神経質にはならない方がよいと今は考えています。その分通える期間はしっかり時間を作って通えば、ちゃんと効果は得られるのだと思います。とはいえ、ああこの時間があればクリエイトに通えたなということはしばしばで、なんとも情けない限りです。
・読み方にグラデーションをつけるということが、なんとなく身についてきたように思います。作家や研究者の読書術に関する本を少し読んだ印象では、たとえ自分の理解の及ばない本にぶつかっても最後まで目を通すことを推奨しています。これは倍速訓練で行っているところのB読みやC読みの感覚が活きるなと思いました。熟読してもわからないような本は、かえって目だけ通して雰囲気や見出しだけ拾って終えてしまっても意外と発見があるようです。いままではそのような読み方に抵抗がありましたが、倍速訓練のおかげでできるようになりました。
「Yさんの受講101回目の主なスコア18/5/23」たてサッケイド54 数字ランダム70・68 数字BP43-6(2分) 漢数字一行〇→6,000、三→3,000 、一→900 たて一行ユニット160・150 スピードチェック34/40(40秒)・36/40(41秒) ロジカルテストDタイプ24/30(3分)・26/29(3分) イメージ記憶15/40(15秒)31/40(15秒) イメージ読み66個(20秒) 倍速読書『街道をゆく10』10,500字/分・理解度A-※スピードチェック・ロジカルは、前回のスコアです。
Yさんには、今春、SEG「速読による能力訓練」にタームをかえて4日目に2回受けてもらいました。
受講回数が69回とまだ少ないかなと心配でしたが、勘のいいひとでした。
彼は、あと899回受けるはずです。
「ひとすぢの道きはむべし」をYさんに
Yさんは、最近忙しいようです。
受講100回目アンケートもメールで届いたのは、7月9日(月)。1週間前でした。  真
真
※クリエイト速読スクールHP