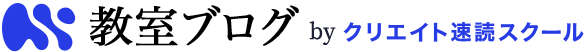2010-01-11
なおしのお薦め本(96)『落語の国からのぞいてみれば』
本日1月11日(月)は成人の日のため、教室はお休みとなります。
どうぞ、よろしくお願いいたします
クリエイト速読スクール文演第1期生の小川なおしさんから、お薦め本が届いています。
『落語の国からのぞいてみれば』
堀井 憲一郎著
おもしろくて、ためになる。その言葉がぴったり当てはまる本です。
あとがきに「江戸時代の気分から見ると、いま、ふつうだとおもってることの多くが、実に特殊な、現代人だけにしか通用しない常識にのっとってることがわかってくる」とあります。
では、第一章「数え年のほうがわかりやすい」から引用します。
「生まれたての赤ん坊は一歳。正月が来ると二歳。正月が来るごとに一つずつ歳を取る。それが数え年だ。
この数え年の説明文を読むと、いつも違和感がのこる。それは満年齢が普通の数えかたで、数え年は昔の不思議な風習のように書かれているからだ。それはちがう。
満年齢は『個人』を中心にした数えかた、数え年は『社会』からみた数えかた、そういう違いでしかない。」
「おとなは一年を区切りとして生きていた。まだ西暦で数えていない時代ですね。西暦ってのは、のべつ数字が増えていくんで、強迫的でいけませんやね。一年で区切る。正月が来るとリセットだ。確定申告の考えと同じだ。その年のものはその年のもの。翌年のものは翌年のもの。
年は干支で記される。もしくは年号プラス干支ですね。」
「子供の年齢は『その子が“社会の一年区切り”で、何回存在していたか』で数える。丑の年に生まれ、寅年になれば、その子はうちの社会の区切りで二年存在していたことになる。だから二歳。社会から見て二歳。一年区切りという社会感覚が先。人の年齢はそれに合わせて数える。
0からは始めない。」
「そういえば、還暦についても、大きな勘違いがある。(中略)還暦。いまでは満六十歳のことですね。もとは数え六十一のことです。」
「還暦は、つまり暦が還るってことだ。
十干と十二支。
甲乙丙丁戊己庚申壬癸。
子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥。
十の干と十二の支が組み合わされてる。10と12の最小公倍数は60。だから六十種類の干と支の組み合わせがある。」
確かに60で一巡りするのですが、ここはどうも説明不足のように思います。
干支の組み合わせは、干の一番目(甲)と支の一番目(子)、干の二番目(乙)と支の二番目(丑)というふうに続きます。その後は次のとおりです。
十一番目は、干の一番目(甲)と支の十一番目(戌)。
二十一番目は、干の一番目(甲)と支の九番目(申)。
三十一番目は、干の一番目(甲)と支の七番目(午)。
四十一番目は、干の一番目(甲)と支の五番目(辰)。
五十一番目は、干の一番目(甲)と支の三番目(寅)。
六十番目は、干の十番目(癸)と支の十二番目(亥)。
干の奇数番目と支の偶数番目の組み合わせ、干の偶数番目と支の奇数番目の組み合わせは存在しません。ですから、百二十種類ではなく、六十種類の組み合わせになります。
ちなみに今年は庚寅で、干の七番目と支の三番目の組み合わせです。
わかっている人には余計な説明でした。では、続きをどうぞ。
「数え年だと無理がなかった。年が明けて暦が還ったときに六十一歳になり、還暦となる。
いまは『還暦=満六十歳の別の言いかた』だとおもっているから、妙なことになる。暦は『ひのえ・いぬ』という自分の生まれた干支の年に還っていながら、誕生日がくるまでは『まだ還暦じゃないよ』、つまり『まだ暦は還ってないよ』と言う。なかなか不思議な風景である。社会の暦は還っているのに、当人としては暦は還っていないことになる。主客転倒してますね。それはどういう暦だってことだ。」
「日本にはかつて誕生日はなかった。少なくとも誕生日の祝いはなかった。庶民にはなかった。庶民、というのが誰をさすのかむずかしい問題だが、落語世界で言うならば、貧乏長屋にはなかった。貧乏人はそんな私的なことで祝いをやる余裕はなかったのだ。」
「もとはといえば、人はすぐ死んじゃうし、という気分が支えてるとおもう。しかも貧乏で、人は寄り添っていかないと生きていけないし、だから社会が先。個人はあと。個人的な誕生日とか、個人情報である満年齢でとか、そんなことにかまってられなかった。年齢を聞くときは個人情報を聞いてるわけではなく、うちの社会に参加して何年になるのだ、と聞いてるばかりである。」
「一九五〇年に『年齢のとなえ方に関する法律』が定められ、満年齢で数えることになった。昭和二十五年のことだ。その時代から庶民にもお誕生祝いがリアルに存在しはじめたのであろう。個人の時代、自由の時代が始まった。それは子供中心の時代の始まりでもあったわけだ。」
数え年。こんな意味があるとは知りませんでした。ぜひ使ってみたいです。  なおし
なおし