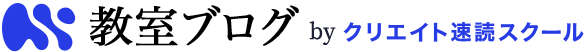2025-07-03
学校で扱った文豪たちの作品を読み返したくなった。今ならもっと作品を味わえそうだ
第88期文演(25/3/29~25/5/31)アンケートです。
きょうは、高3女子のMさんです。
2025-04-02「頭で余計な作業をしなくても答えが出るようになりました」のMさんです。
Mさんの文演アンケート
Q.1 当講座をどんな目的で受講しましたか?
A.1 ・指定校推薦なら小論文と志望理由書が必要で、総合型選抜でも小論文と自己推薦書を書かなきゃいけない。今のうちに、文章力をつけておこうと思ったから。
Q.2 「文演」を受講して文章への印象で変わったことがありますか?
A.2 ・文章を理解するとは、作家の練りあげた「設計図」を自分の頭で再構築することだと気づいた。
選ぶ言葉や表紙の仕方、文章全体としてのまとまりなど、全てが設計図にそって精密に組み立てられている。それが見えると、どこが重要なのかがはっきりとわかり、やっと大意が浮かび上がる。大意をつかむためには、細部を読み込んで、設計図を理解しなくてはならない。
Q.3 宿題の「要約」はどうでしたか?
A.3-1 「授業前」 要約に取りかかる時には、速読の時と同じように緊張した。課題の要約と向き合いたくなくて、ずっと学校の授業が続けば家に帰らなくてすむのにと思った。
家に帰って本文を読み始めると、緊張をほぐすためにカウント呼吸をすることも頭に思い浮かばなかった。
半狂乱になりながら、課題にとりかかった。まずは取り扱った文章を読み返して、文章の書き方をおさらいした。避けた方がいい表現や接続詞の使い方など、考えることがたくさんあった。結局、文章の書き方に気をつけていたつもりだっただけで、2回目の提出で授業中に何度も触れた、避けるべき書き方で文を書き出してしまった。
配布された資料の中には、要約のヒントがたくさん詰まっていた。松田さんの配る資料には全て意味があった。そうだとわかっていて、必要なこと全てを吸収して、使えるかどうかが不安でたまらなかった。
原文を理解するために、1人で現代文の授業をするつもりで原文と向き合った。何度か音読をして、重要なポイントをノートに書き出した。
要約をするときは、文と文をどう繋ぐかに悩んだ。本当にこれでいいのかと考えあぐねた。最後まで書いて違和感はないと思っても、夕食をとると自分の書いた文章のつながりが気に入らなくなった。どう直せばいいのかもわからず、もう投げ出してしまおうかと何回も思った。
A.3-2「授業後」 文と文をつなげる力が足りないことに気づいた。文と文がつながっていないところもあれば、いらないところで接続詞を使っていた。要約したときには、重要なことを抜き出すことに手一杯で、原文から抜き出したことをどうつなげるかに苦労した。そこで思考が止まって、ほぼ無意識で書いたことが最大の反省点だ。完成度を上げることよりも、ひとまず書き終えてタスクを終わらせる安心感を得たかっただけだと今になって気づいた。
文と文を論理的につなげる力が低いのは、数学に触れないからだと思う。私立文系の大学に行くための勉強をするばかりで、まっすぐな筋道をたてて、その上を緻密に考える力を鍛えなかった。今になって、論理を一つひとつ重ねていく数学はやはり私には必要だと気づいた。
ある人たちの要約は美しいとさえ思った。文と文に論理のなめらかなつながりがある。全体としてのバランスを保ちながら、改行することで強調される一文の段落もある。感無量だった。
Q.4 全体的な感想をお聞かせください。
A.4 ・授業が終わるたびに、目の覚める思いがした。知識が深まるにつれて、文章の審美眼が自然と磨かれていった。こんな書き方があったんだと驚いて、文章表現の世界はこんなにおもしろいんだと思った。
今までに学校で扱った文豪たちの作品を読み返したくなった。今ならもっと作品を味わえそうだ。
Mさんの要約は、冒頭はもうひとつでしたが、他は1期にひとりいるかどうかという部分も取られた、よくできたものでした。
「どう直せばいいのかもわからず、もう投げ出してしまおうかと何回も思った」などは、真剣に取り組んだ証し。「投げ出」さなくてよかったですね。これほど大変な経験は、これからもそれほどないはずです。いまは、とりあえず自信をもって受験勉強に打ち込んでください。
文演終了後、速読にも通っています(受講60回。25/6/26)
ICUを目指しているだけあり、視野広く、視点もユニークです。自分の持ち味にいささかも不安がらずに、あと半年突進してください。
Mさんは、8月25日(月)~の第54期平日朝トレ申し込み第1号。
受験生でありながら、このような行動ができることがあなたの特性/天分です。
すでに妹Yさんが入会していています(受講6回。25/6/28)。
先日、お父さんまで「子どもたちが、のめり込んでいる速読とは何?」と体験レッスンを受けにきています(Yさんの出来のよさに驚いていました)。  真
真