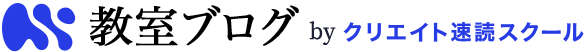2008-11-14
なおしのお薦め本(74)『ずるぱん先生』

『ずるぱん先生』
教師の体験記です。題名に惹かれて手に取りましたが、これは著者本人のことではなく、同僚の先生のニックネームのことでした。「ズボンのバンドがゆるいので、何となくズボンが落ちそうになる」ので、「純心な生徒をして、絶えず、落ちる危険の心配をさせる」のだそうです。
昭和32年に発行された本ですが、内容はもちろん、漢字・ひらがな・カタカナの使い方も、今の時代に通用すると思います。理由はわかりませんが、先へ先へと読ませる力が、この本にはあります。
第一章の「チョークを持つまで」から、二か所引用します。
「はじめて教壇に立つと、マブシイものである。二十四の瞳どころか百のガチャ目、シロ目、ヨリ目の集中看視をうけるからである。その中で平然として、一席ブツということはよほどあつかましい仕業にちがいない。
純情な若人の前で、いかに巧みに自己の弁論をあやつり、彼らをウーンと唸らせるか、そのためのあつかましいテレンテクダを、教授法というのである。
まず、先生教室に入るの場から開幕しよう。
このコツは、教室内が始業直後、ガヤガヤしてうるさい時は、先生たるものはしずかに、いいですか、あくまでも、ゆっくりした歩調ならびに余裕もって、ドアを開けるのである。最初教室にふみ入れる一歩は、かならず自分が生徒全体と相対する姿勢になるように、右足か左足(これ以外に足はございませんからネ)を踏み出す。そしてその瞬間に今、この教室ではどの辺が一番さわがしいか、という場所を、突嗟に見つけなければいけない。もちろんそのためには、ゆっくりと、アッ、先生が来たぞ、という印象づけを与えるためにも、すべてに余裕をもつことである。一口に余裕をもつと言っても、始めての場合は頭がカーッとなるから、なんでもテンポをおそくしてやることが必要である。さて、さわがしい場所を見つけたら、そこをじっと見つめて(つまりガンズケというやつです)ゆっくりと教壇に上り、少なくとも、教卓についてクラス全員と始業の挨拶をかわすまでにはピタリとさわぎを静めるようにする。つまり、その間のマの持たせ方がむずかしい。いうなれば、六代目菊五郎の演技をサンプルにする必要が十分あるわけである。
次に大切なことは、生徒というのは先生が自分の姓名を知っているかどうか、をとても気にするものである。殊に、初めてのクラスの授業にあたっては、必らずそのクラスの氏名を正確に読めるようにしておくことが第一である。それと、あらかじめそのクラスで特に勉強のできる生徒、普通の成績の生徒、できない生徒を各々数人ずつ覚えることが必要である。そのほかには、よくさわいだり、又はクセの悪い要注意人物をマークすることである。もし時間があればそういう生徒の顔まで、写真と首っ引きで知っていれば文句なし、その余裕がないときは、座席表を見て、どの辺に誰がいるということを確認しておくことである。
さて、生徒との始業の挨拶もすんだ。そしたらおもむろに出欠をとり始めるのだが、ゆっくり生徒の名前を呼び上げながら、今注意して区分した人物をそれとなく頭に入れなくてはいけない。
生徒が授業の効果を考えるとき、このことは出来るだけ、速やかにされることが望ましいが、これはあくまでもよりよい教育をするための手段としてで、このこと自体は目的でもなんでもないのである。」
ところどころにクスグリがあります。もう一か所どうぞ。
「……黒板に書く字ははっきりと楷書でするが、一度書いた文字は、生徒のしみじみした批判と鑑賞を一時間中受けるのである。書は人をあらわす。あまり、金釘流や、ゴミタメに棄てるようなキタナイ字、代用食のスイトンみたいな気の抜けた字などは、授業効果を弱めますれば、よくよく字だけは上品にして明快、人をして不快な気持をおこさせないようなものを習得しておく必要がある。黒板に字を書く時は、あまり夢中になって教壇から落っこちないようにすること、私などは、冬のストーブにころげついて、大ヤケドをしてみたり、又はストーブの火を消すためのバケツに、片足を突っこんで、カゼをひいて見たり、油雑巾でふいたばかりの床に足をスベらして、月賦で買った涙ぐましいセビロを油だらけにした、失敗お涙物語がある。
先生の目ツキは、どこを見ているのでもないが、それでいて全体を見つめているような感じを与えるために、いつも教室の中央部に向けていることが大切だ。実際、生徒を見ていようが、見ていまいがそんなことはどっちでもよろしい。ただなんとなく、首をそちらに向けていればよいのである。そして、弁天小僧みたいにスゴんだりしてはいけない。やわらかなまなざしで、微笑をたたえ、(微笑とニヤニヤはちがいます。これを見事に表現するのは、アカデミイ賞くらいの演技力が必要である。)生徒に、生理的な安心感をもたせればよいのである。と、口では至って簡単だが実際はトンとうまくゆきません。身ナリはさっぱりとし、Yシャツはいつも清潔にしないとダメ。ネクタイも時折は、季節の来訪を思わせる風情をただよわせて、変えなければいけない。なぜこんなことまで言うのか、というわけは、先生たるもの、一歩教室に入ったが最後、完全に罐詰めにされるのである。いわばサラシモノである。まして女学生はコマカイからよれよれのズボンや、文化財として指定されるような古めかしい靴、それに、首にぶら下げているだけと言ったネクタイ(二年間同じネクタイをしていた豪傑がいましたナ)を特別陳列するならば、その上、顔にヒゲが繁茂していようものなら、善良にして想像力ゆたかな彼女たちは、この先生はいかなる原因で、かかるスサマジキ風体をしているのか、と考え、遂には、先生の月給や、奥さんの耐乏生活などを空想し、とんだ授業効果をあげてしまうに至るのである。
と言って、先生がイカれた格好をしてはいけない。虚にして虚にあらず、実にして実にあらず、近松の虚実皮膜論ではないけれど、地味にして貧ならず、上品にして華美ならざる、小ざっぱりした身ナリこそ、教授の前提になろうというものだ。」
オススメしたところで入手がむずかしいかもしれません。でも、こういう面白い本が埋もれている、ということを知っていただきたく、紹介することにしました。  なおし
なおし
 オマケ
オマケ
―なおしのメール―
松田さん、こんにちは。
ひさしぶりのおすすめ本です。
所沢古本まつりで見つけました。日焼けのせいか茶色くて甘いニオイがする本ですが、中身をちらりと読んでみたら、なかなか読ませるものでした。
150円。買って帰りました。
古本まつりの最終日まで残っていたのですから、人気がないのですね。
知られていないのでしょうか。こんなにいいのに。
明日クリエイトに持っていきます。
それではまた。