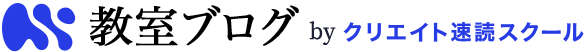2024-02-08
「全体の中の部分」を意識すること
2月11日(日・祝)・12日(月・振)は、休校となります どうぞよろしくお願いします
どうぞよろしくお願いします
2023-08-17「教室は基本的に負荷をかける場所である」のTさんについて。
公認会計士試験受験生です。
まず、Tさんの体験レッスンスコアと入会時アンケートコピーです。
「Tさんの体験レッスンの主なスコア19/8/29」たてサッケイド25 数字ランダム20・24 漢数字一行〇→450、三→111、一88 たて一行ユニット31・36 スピードチェック26・26 ロジカルテストAタイプ15/16(3分)・18/18(3分) イメージ記憶24/40(2分)36/40(1分30秒 )初速766字/分・理解度B
「Tさんの入会時アンケート19/8/29」 ・「体験感想」とても集中力が必要だと思った。続けていけば力が伸びそうだと思った。・「入会を決めた理由」資格試験に役立てようと思って。・読解力を上げようと思って。
以下は、Tさんの受講100回目アンケートと、最新スコアです(受講90回(23/8/18)は未提出です)。
「Tさんの受講100回目アンケート23/12/27」
・トレーニングを通して気づいたこと 視野を広くしようと意識すると、今までよりもトレーニングがスムーズにできるようになってきた。ロジカルテスト、スピードボード、イメージ記憶も、イメージを最優先で解いているが、視野を広くとったときの方が数値がいい。
・クリエイトの速読について とうとう100回目まで受講することができた。今までお世話になった松田さんをはじめ、教室のスタッフのみなさん、ブログでヒントをくださる生徒の皆さんに感謝します。最初のころは、ブログで圧倒的な数値を見るたびに「こんなの無理だろ」と思った。しかし、その途方もないと思えた数値に近づくうちに、自分の成長を実感することができた。クリエイトのトレーニングは、生徒からのフィードバックを受け、より確かなものに進化してきた。そのトレーニングに素直に従うことができれば、だんだんと文字を速く読める実感がわいてくる。また、自分の頭でもしっかりと考えて普段の読み方に生かそうと試行錯誤することも大切だ。また、講師がトレーニングの合間に挟むアドバイスをしっかりと聞いたほうがいい。講師はトレーニングの全体像を理解して、アドバイスを言うからだ。私も講師からのアドバイスを受けて成長することができた。
受講を重ねるたびに何を意識すれば、理解力と速度を両立しながら速読できるようになるのかと考え、ある程度考えが確立した。速読の基本は、リラックスして、視野を広げた状態で文字の形を捉え、しっかりとイメージすることだ。文字から直接イメージできるようになれば、いちいち頭の中で音読せずとも内容を理解できるようになる。ただし、音読を否定しているわけではなく、実際には頭の中で音読していることも多い。あくまで、イメージを優先させたほうが音読にこだわらなくなり、結果として理解力を保ったまま速度を出すことができるということだ。
私は、サッケイドシートをはじめとして、全てのトレーニングが有機的に結びついて日常の読むという行為に生かすことができてきた。読書経験が浅い私にとっては、一つのきっかけを得ることができた。まず、サッケイドシートは全てのトレーニングの基本であり、根幹と言ってもいい。「結局、サッケイドシートが一番大切である」とUさんのブログに書いてあったが、正直半信半疑だった。私はサッケイドシートを見るときに、生長さんのブログに書いてあるように「両端▼▲を視野の端に置き、連結する点線をはっきりと見るように」取り組んでいる。普段、私が文章を読むときもこの見え方に近づいてきた。松田さんをはじめ、講師の方もこのアドバイスを頻繁にしている。トレーニングを受けていくほど、サッケイドシートは文章を読む上での基本であり、根幹であると気づいた。
松田さんは、サッケイドシートと数字ランダムシートが大切だと言っていた。最初のころは意味が分からなかったが、最近理解できつつある。基本であり根幹はサッケイドシートだが、数字ランダムシートでページ全体に視野を広げて、文字の形をイメージして捉える必要がある。その後のトレーニングでは、ブロックごとに分け、実際の文章を読むときと同じ感覚のトレーニングが展開される。私はおもに、サッケイドシート、数字ランダムシート、よこサッケイドシートの見え方を試すと数値が上がることに気づいたスピードチェックが結びついて、文字をどのように捉えればいいか分かってきた。序盤の認知視野拡大で体得したものと、中盤のイメージ記憶を中心としたイメージトレーニングを組み合わせることにより、文章を読むときの基本的なスタイルが確立した。そして最後に、これまでのトレーニングを生かすように倍速読書トレーニングを行う。倍速読書では、文字をかたまりで見ることが大切だ。それを理解度B以下にしてコツをつかむ。そして、理解度A以上で読むときの感覚に生かしていく。教室では負荷をかけて、日常の仕事、勉強、読書に生かしていく。どのトレーニングも、視野を広げて「全体の中の部分」を意識することが大切だ。クリエイトの一連のトレーニングで、今までよりも文字を認識できる幅が広くなり、そこにイメージの精度、速度がかけ合わさることにより、理解度を保ったまま速く読めるようになる。
以下は、荒木健友さんの体験記(2005年)の一部を抜粋したものである。
速読なのだから速ければ速いほどいいだろうと思うかもしれません。確かに、初めはそういった意識で臨んだほうがいいようです。それまで本はゆっくりと読むものという固定観念が刷り込まれています。クリエイト速読スクールでは自分に上限を定めないで、常に限界以上の読書スピードで読んでいくような訓練をするといいと思います。また、そのための場所として速読スクールがあるといえます。
この1年間でぼくの読書スピードは1分間に1200文字から2万文字まで上がってきました。この数字を1ページ650字の250頁の新書で換算すると6~10分で1冊読めることになります。だからといって、普段からこの速度で読んでいるわけではありません。1分間に2万文字という記録はそれほど当てになるものではありません。
正確に理解できているかどうかの基準を試験の問題文に置くと、初めの3倍ぐらいで読めれば十分だと思います。ただし、自分の限界が3倍であって、3倍の速度で読むのと、自分の限界が初めの十数倍まで上がっていて、3倍で読むのではずいぶんと違うと思います。試験というミスの許されない状況では、限界の3倍では通用しません。余裕を持った3倍である必要があります。試験は運が左右するとはよく聞きますが、そうした運に振り回される部分を削っていくことが大切です。速読でスピードを追求していくと、時間に対して厳しくなります。厳しい時間感覚を持って、はじめて余裕も生まれてくるものだと思います。
私はこの文章に、クリエイト速読スクールの本質を見た。この文章は、負荷をかけて取り組むことで自分の限界を引き上げ、日常での文章を読むという行為を楽にしようというものだ。負荷をかけるということは、普段の教室でよく言われることだ。教室でのトレーニングは、嫌でも自分と向き合わなければならない。数値は日進月歩、じりじりと上がっていく。停滞する時期も訪れるが、あきらめずに取り組むことで必ず前に進むことができる。数値が向上していくなかで、日常の仕事、勉強、読書への効果が実感できるようになるだろう。
クリエイトの速読トレーニングによって、これからどのように成長できるのかを、最近は霧が晴れたようにはっきりとイメージできてきた。あとはそこに向かって、果てなき荒野を歩いていくだけである。最初は、「本当にこんなので速読できるようになるのかな」と疑り深い私は思った。しかし、トレーニングを受けるほどにBTRメソッドの確かさを確認することになった。これからも引き続き、楽しんで取り組みたい。
「Tさんの受講103回目の主なスコア24/2/7」たてサッケイド119 かなランダム54・43 数字ランダム104・100 漢数字一行〇→20,412、三→17,334、九→1,088 たて一行ユニット169・204 スピードチェック35/40(49秒)・36/40(48秒)かなひろい59/85(45秒)ロジカルテストDタイプ29/30(2分40秒)・27/30(2分31秒)スピードボード5×525/30(2分51秒)・25/30(2分48秒)イメージ記憶8/40(20秒)19/40(20秒)倍速読書『ツナグ』4,200字/分・理解度A-「ユウさんと1vs.1で非常に集中することができた。ユウさんなりのイメージを教えてくれてとても参考になった。イメージすることを大切にして、これからのトレーニングに励みたい⑨⑧⑧」
2005年体験記である荒木健友(あらきけんすけ)さんの体験記が出てきて驚きました。
熱心な生徒さんは、参考になるものならどこまでも調べます。貪欲です。
むかしは、この体験記だけでした。
いまは、18年弱の教室ブログがあり、初級朝トレが用意され、最近は速読ナビまで登場しましたから相当な量です。
ユウさんとの「1vs.1」とは、お得でしたね。
Tさんは、短答式合格ラインまであと数%と聞きました(公認会計士試験は超難関)。
勉強法に間違いなさそうですから、ラストスパート、しっかり通ってほしいです。  真
真
※クリエイト速読スクールHP